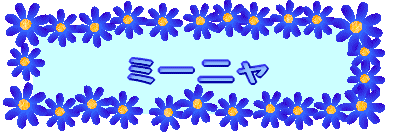
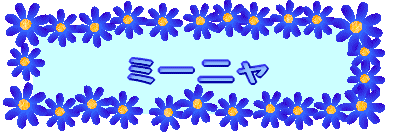
3月9日、40回目の結婚記念日に、ミーニャが死んだ。
18年前、庭の片隅に迷い込んだ真っ白な仔猫を妻が抱き上げた。手のひらに載るほど小さかった。子供たちが仔猫を囲むように覗き込んだ。仔猫は顔中を口にしてニャーと鳴いた。子供たちから一斉に歓声が上がった。長い尻尾を器用に動かしながら、縁側に置かれた小皿の牛乳をむさぼるように飲んだ。その瞬間、子供たちは我が家に家族が増えたことを、仔猫は漸く安住の地にたどり着いたことを確信した。
ネコは家につくというが、ミーニャは5度の引越しにも決して迷うことはなかった。アメリカまでもついてきた。子供たちが独立して、家族が一人減り、二人減り、だんだん淋しくなっても、ミーニャだけは、我が家に君臨していた。
潔癖症の妻は生来あまり動物が好きではなかったが、病に倒れてからは、ミーニャをとても可愛がるようになった。ミーニャも妻になついた。
妻が食事をするときには、ミーニャは当然のように食卓に上がって、妻のお皿の直ぐ横に正座した。妻が魚の切り身を少し分けてくれるのを大人しく待つのだった。以前の妻なら、テーブルに登って来ようものならこっぴどく叱ったものだが、今は頗る寛大になっていた。
昼間、家族が出かけてしまうと、一人残された妻にとってミーニャだけが話し相手だった。それどころか、ミーニャこそが、障害者となった妻の精神的空白を埋める存在であったかもしれない。
4年前、妻が入院して以来、ミーニャは空になった妻のベッドに寝るようになった。寒い夜も顔を埋めるように丸くなって、妻の香りが残るフトンの上にうずくまった。
今年の正月を過ぎた頃からミーニャの元気が少しずつなくなっていった。好物の白身魚のネコ缶も殆ど残してしまう。水ばかり欲しがった。駅の近くにある獣医に連れていって診てもらった。
血液検査の結果、肝臓と腎臓の機能を表わすマーカーのGPTとBUNが基準値の4倍もあるという。
「これは厳しいなあ。」
小太りの女医は思わずもらした。
「取りあえず脱水症状だけは防ぎましょう。」
ミーニャの腕よりも太い注射を背中に刺した。信じられないほどの大声でミーニャが鳴いた。
皮肉にも、その翌日からミーニャの容態は目に見えて悪くなっていった。エサは全く食べなくなった。水だけは、蛇口から新鮮なものを茶碗に入れておくと少し飲んだ。
やがて、歩行困難となり水も自分から飲みに行けなくなった。台所に行く途中で座り込んでしまう。持ち上げると驚くほど軽い。まるで仔猫に戻ったようだ。
今年の暖冬も3月に入るとカレンダーが逆転したかのように寒くなった。ミーニャは終日床暖房の効いたリビングのソファに寝ていた。さすがに妻のベッドに飛び上がる力は残っていない。
飲まず喰わずで2日ほど経った。
「ミーニャ」と呼びかけると、尻尾を僅かに動かして返事をする。が、眼は閉じたままで耳も動かない。もちろん寝返りもできない。
3月8日は妻の誕生日。
私は、小さな鉢植えの花とお祝いのカードをもって病院を訪れた。ベッドの妻に励ましの言葉を贈り、ミーニャが危ないことを報告した。
その夜、ソファの上で昏々と眠り続けるミーニャを末娘と二人で見ていた。私はミーニャの旅立ちが近いことを予感した。できることなら妻の誕生日を避けてもらいたいと思った。夜中の12時が過ぎたとき、娘の呼びかけに白い尻尾が悲しげに少しだけ動くのを確認した。ミーニャに私の気持ちが伝わったように感じた。
ミーニャは昔の夢を見ているように思えた。18年前、我が家の全員が仔猫を取り囲んで暖かく迎え入れる。仔猫は自慢の尻尾を大きく動かしてそれに応える。
午前3時15分、ミーニャは二、三度小さく痙攣した。
「ミーニャ!」
娘が号泣した。だが、ふさふさの白い尻尾はもう動かなかった。
[2007年3月記 原稿用紙 約5枚 課題「囲む」]