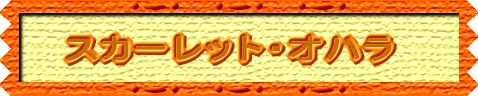
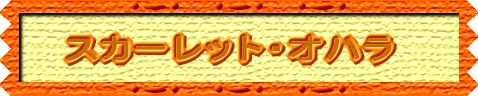
アメリカに駐在することが決まったとき、私は妻と約束をした。それは、『風とともに去りぬ』の舞台になったタラの町に妻をつれていくというものだった。妻は若い頃からこの小説の大ファン。スカーレット・オハラのたくましい生きざまに深く共鳴していた。
ところが、赴任直後に妻が病に倒れたため、この約束は反故になったものと思われた。
4年の駐在任期がもう直ぐ終わろうとする頃、妻が身体を壊したのを口実に約束を破ってはいけないのではないか、と思い直した。どうしても、妻にタラの町を見せてやりたかった。私は妻を車椅子に乗せて、デトロイト空港からアトランタに飛んだ。
オリンピックを翌年に控えたアトランタは活気に溢れていた。その夜、私はホテルの一室で、買ったばかりの地図の束を広げた。妻は長旅で疲れたのか、洋服をつけたままベッドで眠っていた。
小説の舞台となったタラというのは、実在の町でないことは知っていた。が、私には確かな心当たりがあった。1年ほど前、アトランタに出張したときに見た地図の上に、偶々、Gone with wind(風とともに去りぬ)と書かれた文字を見かけたからだ。
私は、そのときのものと同じ地図を丹念に探していった。その文字は直ぐに見つかった。アトランタの市街地から南に80マイルほど下がった所に、点線で四角に囲まれた地区がある。その文字は点線部分の説明として書かれていた。地図の上に赤で印をつけ、そこに行くための道路を調べた。
![]()
翌朝、レンタカーに妻を乗せ、ハイウェーを快調に走った。睡眠十分の妻は、アトランタ郊外の平野を窓から眺めながら何やら興奮気味であった。
2時間足らずで目的地の近くに来た。ハイウェーから出て、住宅街に車を進めた。スピードを落とし、地図のマークと外の道路標識を見ながら、特別な建物を探した。
そこは、何の変哲もない住宅街で、私たちの興味を惹くようなものは何処にも見当たらなかった。だが、注意深く車を進めていくうちに、一つの道路標識が目に入った。私は思わずアッと叫んで車を停めた。そこには『タラ・ストリート』と書かれていたのだ。
私は道端に車を寄せて駐車し、外に出た。何処までも住宅街のようだった。取りあえず、トランクから出した車椅子に妻を乗せて暫く歩いてみることにした。
通りに人影はなく、昼前の静寂が漂っていた。道の両側には、決して豪華ではないが前庭のある小奇麗な建物が並んでいた。
一軒の家の庭先で、老婦人が花の手入れをしているのを見かけて、声をかけた。
「ちょっとお尋ねします。この点線で囲まれた部分は、この辺りでしょうか?」
私は赤で囲まれた区画の地図を示した。
「あぁ、これね。この点線は計画中という意味ですよ。」
「というと、未だ出来ていないということですか。」
「いえいえ。以前、この辺にそういうイベントの設備を作ろうという計画があったそうですよ。だけど、プロモーターが倒産しましてね。それで、計画は中止になったと聞いています。」

お礼もそこそこに、私は車椅子を押してタラ・ストリートを引き返した。落胆の様子を隠せないでいる妻を再び車に乗せて、アトランタに戻ることにした。
「残念だったね。間違いなくあそこに何かあると思ったんだけどね。」
私は自分の早合点を弁解しながら、元来た道を走った。緊張が落胆に転じて、忘れていた空腹を思い出した。妻も何か食べたいというので、ドライブインを探しながら野原の道を走った。暫くすると、ジョーンズボロという名の小さな町に出た。
『インフォーメーション』と書かれた案内所に車を停めた。隣にレストランがあったので、そこに入った。注文を済ませ、店内を見渡すと客は半分程度の入りで、中には観光客らしい姿もあった。視線が、何気なく壁に貼られたポスターに向かい、そこに凍りついた。
『マーガレット・ミッチェル記念館』とあった。
「あれは何だろう。ちょっと隣の案内所で訊いてくるよ。」
案内所の若い女性はとても親切だった。彼女の説明によると、ジョーンズボロはマーガレット・ミッチェル女史ゆかりの町らしく、女史の通った学校や教会が当時の姿のまま保存されているという。しかも、その場所は案内所の直ぐ裏手だと!
「おいおい、えらいことになったぞ! 御飯どこじゃないよ。」
パンフレットをごっそり抱えて帰ってきた私を妻は訝しげに見た。注文した食事はテーブルに運ばれていたが、妻は私の帰りを待っていたようだ。
「此処に車を停めたのは大正解だよ。此処はマーガレット・ミッチェルの生まれた町らしいぞ。」
私は案内所で聞いたことに尾ひれをつけて妻に説明した。妻は鳩が豆鉄砲を食らったように聞いていたが、やがて驚きの表情がニッコリした微笑に変わった。
じっくり味わう余裕もなく食事を済ませ、レストランを出ると妻の車椅子を押して案内所の裏手に回った。
「オー、あるぞ、あるぞ!」
目の前の広場では、古い教会や学校の木造の建物が当時のままの姿で私たちを迎えてくれた。
先ず、学校に入ってゆっくり中を見学した。ミッチェル女史の書いた手紙やノートが硝子ケースに納められていた。粗末な木の長机に同じく木製の椅子。正面には古い大きな黒板が架かっていた。
次に教会に入ってみた。シンプルな造りで装飾が殆どなかった。その時、祭壇の横の扉が開いて一人の女性が入ってきた。
「スカーレット・オハラ!」
思わず小さく叫んだ。少し年を取っているが、服装はまさにスカーレット。
コルセットで締め付けた、くびれた腰から床に届くほどのゆったりしたロングスカート。頭には羽のついた帽子を斜めにかぶっている。それに、その後に居るのは、レッド・バトラーではないか。こちらは細身のズボンにジャンバー。頭にはツバ広の帽子。二人は笑みを浮かべてこちらにやってきた。
「ウェルカム!」
スカーレットがレースの手袋をはめた右手を妻の方に差し出した。妻は興奮の余り口もきけない。自由の利く左手でスカーレットの手を取り、大きく上下に振った。
どうやら、先ほどの案内所の女性が、気を利かせてガイドの二人を我々に差し向けたらしい。
私たちは、とんだハプニングのお陰で、小説の主人公二人に案内してもらって広場の建物をくまなく見学することができた。別れ際に、スカーレットは、腰をかがめ、車椅子の妻の肩を抱いて頬擦りをした。身体の不自由な妻を励ます積もりなのだろう。
妻の興奮は最高潮に達し、オー、オーと、言葉にならない声を出して満面の笑顔で応えた。両の目からは大粒の涙がこぼれ落ちた。
(了)
[2007年1月記、課題『涙』]