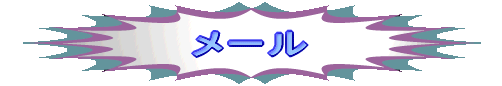
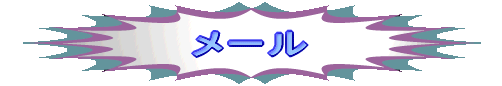
3年前の春、妻が脳出血の再発で倒れた。意識もなく病院のベッドに寝ていたが、1年半後に肺炎をこじらせた。
高熱に加え喉にタンが絡まって、苦しそうに喘ぐ病室の妻との対面を済ませ、ナース・ステーションで主治医と向かい合って座った。
「ほら、今日の写真ではここの部分が白く見えるでしょ。こちらは2日前の写真ですが、それほどではありませんね。肺の炎症が進んでいる証拠です。」
医師は二枚のレントゲン写真を私に見せて説明した。
「更に進むと危険です。この数日が山と思われます。」
「それで、病院としてはどういう処置をされているのですか。」
私は、言葉に窮してありきたりの質問をした。
「基本的には、抗生物質の投与以外に方法はありません。もちろん、身体中に氷嚢を巻いて熱を下げるようにはしていますが・・・・」
「今のところ、抗生物質は効果を示さないということですか。」
「この病院にある抗生物質の種類は限られています。代わる代わるトライしていますが、菌にも抗生物質に対する抗体が出来てきます。どうしても、効果は限定されてくるのです。」
「それでは、率直に言って容態は極めて危険だということですか。」
「その可能性はあります。御親戚の方々にも連絡されておかれた方がいいでしょう。」
「・・・・・・」
「御主人に一つ確認しておきたいのですが、気管内挿管はやられないということで宜しいのですか。これをやると、本人の呼吸は楽になるし、タンの吸引も簡単になります。此処の患者さんは、殆んどが気管内挿管をしています。」
気管内挿管とは、俗にいう気管切開のこと。喉に穴をあけて気管支内にチューブを挿入し、そこから呼吸する。また、気管支に溜まったタンを吸入するのにも、チューブ内に吸入用の細い管を入れて行うので、タンが取りやすい。
この病院に入院するときにも説明があり、延命策は取らないという観点からお断りした経緯がある。
本来、こうした手術を行う場合、患者本人の意思確認が大原則だが、意識のない妻に確認のしようがない。
「私は必要ないと考えますが、一応、娘たちにも再確認して明日返事します。」
そう答えて病院を出た。
妻に意識がない以上、妻の意思は夫に委ねられるのは当然かもしれないが、生命に係わる決定を一任されるのは、矢張り、辛い。
帰りの車の中で、私は、以前横浜のホスピス医から聞いたことを漠然と思い出していた。
「奥さんに意識がない場合、最も身近な存在である中村さんが、奥さんなら、きっとこのように判断するだろう、と考えられることが、即ち奥さんの判断になります。」
その夜、私は4人の娘にメールで手紙を書き、最後の部分を次のように結んだ。
『病院の患者さんの多くは気管切開しています。だけど、一旦これをやると、二度と自分で呼吸することはできません。生きているというより生かされている状態に近くなります。
お母さんも、決して、そのような姿になることを望んでいないだろうと判断し、お父さんとしては気管切開をお断りしようと思います。しかし、最悪の場合、気管内にタンが詰まって窒息死したり、肺炎が更に進行することがあるのは覚悟しなければなりません。
仮にそのような最悪の事態が訪れたとしても、お母さんは最後まで自分の力で頑張ったわけですから、拍手をもって見送ってやりたいと思うのです。
だけど、恐らくは、ビッグ・ファイターのお母さんのことだから、今回も自力で乗り越えてくれるものと信じています。皆の意見も知らせて下さい。』
娘たちからは、賛同する旨のメールを貰い、病院には確認の返事を伝えた。

1週間後。
3枚のレントゲン写真を前に、再び主治医と向かい合った。
「これが昨日撮った写真です。炎症がきれいになくなっています。正直、私も些か驚きました。恐らく、抗生物質が効いたのでしょう。」
「というより、私は妻がビッグ・ファイターだから治ったのだ、と思います。
クスリよりも妻のファイトが肺炎を克服したのです。」
主治医は苦笑いをかみ殺すように言った。
「確かに、奥さんは、すごい生命力です。」
私は、医師と看護婦にお礼を言って病院を出た。
フレッシュな空気を胸一杯吸い込んで、見上げると、雲一点ない秋の空が広がっていた。
(了)
[2006年9月記、 原稿用紙 約6枚、 課題「手紙」]