

夕食の支度ができていても、母と私は父の帰りをじっと待っていた。父より先に箸をつけることは許されなかった。
玄関のベルが鳴ると、母はバタバタと廊下を走って迎えにいき、上がり口に三つ指をついて、「お帰りなさいませ。」と頭を下げた。
私の記憶では、父が台所に立つ姿は見たことがなかった。『男子厨房に入るべからず』を徹底的に実践する明治生まれの典型的な亭主関白であった。
ある意味では、父は私にとって反面教師だったように思う。その所為か、私は小さい頃から台所で母の料理の手伝いをした。手間のかかるゴマ摺りや大根おろしは私の仕事だった。見よう見まねで、少しずつ母の作る料理の手順を覚えていった。
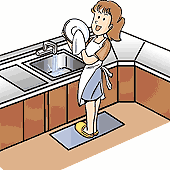
学生時代、私は下宿生活をしたが、台所での経験が役に立った。四畳半の下宿部屋の片隅にある、小さな流し台の古いガスコンロで脂の滴るビフテキを焼いて、友人たちに御馳走した。自分の作った料理を「美味しい」と言ってくれると、とても嬉しかった。
家庭を持っても、休日には夕食を作った。子供たちに「お父さんのカレーが食べたい。」とねだられると、ついついその気になってしまう。家内も子供たちを誘導して、私に食事を作らせるコツを覚えたようだった。
カレーは、私のレパートリーの中でも子供たちに最も人気のあるメニューとなっている。だが、私には特別のレシピがあるわけではない。ただ、ひたすら時間をかけて煮込むだけだ。
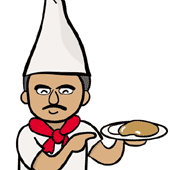
料理は、時間をかければ美味しいものができる、というのが私の持論だ。料理に限らず、ものごとの価値はそれにかけた時間の合計で決まる。
今の時代は、殆んどのものがお金で買えるが、モノの値段はどうして決まるのだろうか。
例えば、腕時計と電気釜といった全く用途の異なるものが同じ値段で売られていたりする。一体、どのような尺度で同じ値段がつくのか。
実は、細かく積算していくと、腕時計も電気釜も、それを作るのに要した時間がほぼ同じなのだ。能率や熟練といったものを捨象すれば、すべての商品の価値は、それを作るために必要となる時間で決まる。

品物の価値は、それを作るために必要となる時間で決まる。マルクスは、『資本論』の中で、「商品の価値は、それをつくるのに要した社会的必要労働時間の総和である。」としている。
学生時代、私は外国語の学習には人一倍時間をかけた。また、サラリーマン時代には、海外生活が長かったこともあって、いくつかの外国語を喋ることができる。
「どうすれば、英会話が上達するのですか。コツがあるのですか。」といった質問を受けることがある。
私の答えは、いつも決まっている。
「コツなどはありません。英会話の習得にどのくらいの時間をかけたかで決まるのです。」
「そんなことはないでしょう。いくら勉強しても、できない人はできないのじゃないですか。」
質問者は更に食い下がる。
確かに、才能や要領といったものを全面的に否定するものではない。が、芸術活動ならいざしらず、暗記がベースとなる外国語の習得が天賦の才能に左右されるとは思わない。
英語に限らず、外国語を学ぶ上で、二千時間かけた人は、千時間かけた人に較べると、二倍だけ上達するのは、ごく当たり前のことなのだ。逆にいえば、千時間の努力で二千時間分の結果を求めるのは、欲張りということになる。
![]()
料理も同じこと。
偶の日曜日、とろ火の上でクツクツと煮える鍋の肉汁を覗き込んで、私は黙々と玉杓子で灰汁をすくっている。
(了)
[2006年8月記 原稿用紙約4.5枚 課題「家事」]