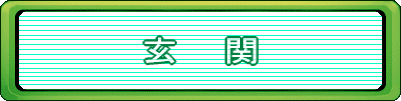
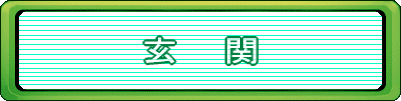
鉄平石の門柱に朽ちかけた木の表札がかかっている。その横にある呼び鈴を押して暫く待つ。冠り松の向こうで、門灯に照らされた玄関の扉が開いて、年老いた母が石段を降りてくるのが見える。背中が曲がっているのでバランスを取るのであろう、腹を突き出して不恰好な姿で歩く。
やがて門扉の閂の滑る音がして、扉が開く。
「お帰り。遅かったね。」
いつもの母の第一声だ。

 玄関に入ると懐かしい犬の臭いが鼻をつく。上がり框では、
玄関に入ると懐かしい犬の臭いが鼻をつく。上がり框では、
柴犬のカロがちぎれるほど尻尾を振って待っている。
大きく口を開けているのに鳴き声は小さい。きっと、
大声で鳴くと叱られるのであろう。
靴を脱いでスリッパに履き替えると、先ず、カロが
カタカタと廊下に爪音を立てて走り出す。私を案内して
くれるらしい。振り向くと、危なっかしい足取りで母が
ついてくる。少しゆっくり歩いてほしいと懇願するかのように、声がかかる。
「ご飯にする?」
掘りごたつの食卓の席は決まっていて、亡くなった父の席は正面にあり、今でも座椅子に厚手の座布団が敷かれている。四角い食卓の火鉢を挟んだ右隣が私の席だ。
上着を脱ぎ、席について夕刊に目を通す。タバコを1本吸い終えた頃、母が暖かい夕食をお盆に載せて運んでくる。横から見ると、歩く姿はS字型に近い。
メニューは、ロールキャベツと大根煮。それに、油揚げとネギの味噌汁や私の好物の柴漬けもある。何時だったか、美味しいと褒めたことがあって以来、何時帰っても同じものが出るようになった。
私は、大学を卒業すると同時に神戸の実家を出た。父が74歳で他界してからの母は、広い家に一人暮らしとなった。毎日、犬だけが母の話し相手だった。時折、思い出したように帰ってくる一人息子に手料理を御馳走することは、母の最大の楽しみだったかもしれない。
その実家も阪神大震災で完全に倒壊してしまった。父の自慢であった陶磁器のコレクションや母が描いた趣味の油絵は殆んどが失われた。カロも行方が知れなかった。
不幸中の幸いと言おうか、母は直前に大腿骨骨折で山の手の病院に入院していたため難を逃れた。だが、震災後は、すっかり弱ってしまった。帰る家もなく、歩行困難になった母を東京に引取り、体の不自由な家内と、車椅子2台の生活が始まった。が、子供たちの協力を得てもなお、限界に近かった。母には納得づくで千葉の老人ホームに入ってもらった。

ロマンチストで、社交性の乏しい母にとって、ホームでの生活は辛かっただろう。私が見舞いに行くたびに、神戸に帰りたい、と訴えた。現実を逃避しようとするプレッシャーからか、頭の方も段々怪しくなっていった。
ある時、母は、お願いがあると言った。
「わたし、神戸の家に眼鏡を忘れてきた。テレビの下の引き出しにあるはずやから、あんた、今度帰ったときに取って来てくれへんか。」
その母も、7年前に亡くなった。東京で葬式を済ませたが、お骨は、神戸に持ち帰った。六甲山の麓にある父と同じ墓に眠っている。
墓参に帰るたびに、私は、更地になってしまった神戸の実家に立ち寄る。松の木は枯れてしまったが、石の外塀と鉄製の門だけは当時のままだ。そこに立つと、玄関の扉を開けて石段を降りてくる、背中の曲がった母に会える気がする。
(了)
[ 2006年7月記、原稿用紙 約4.5枚、課題「玄関」]