![]()
13年前の今日、妻が脳出血でミシガンの雪の上に倒れた。6時間に及ぶ大手術で一命はとりとめたものの、右半身不随と失語症が残った。それ以来、私の主夫としての仕事が続いている。その妻も、3年前、脳出血の再発で入院してしまったので、今年は3度目の妻の居ない正月となった。
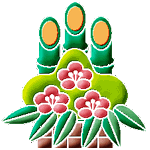
おせち料理の支度は、主夫にとって一大イベントである。主だったものは出来合いを購入するが、最低5品は自家製のものを作ることにしている。私の得意は、厚焼き玉子とブリの照り焼きだ。
家族4人とお客様の分を合わせて、10個の卵をボールに割り込む。掻き混ぜるときに少量の牛乳を入れるのが、滑らかに焼くためのコツだ。それに、別に用意した特製のだし汁を加える。銀色のボールの中で琥珀色に輝く膠質状の液体を指先で舐めてみる。よし、上出来だ。
次に、玉子焼き器。最近では、熱伝導率の高い銅製が流行りだが、我が家では未だに鉄製のものを使っている。鉄製では十分に予熱しておくのがポイントとなる。頃はよし。琥珀色の液体を玉杓子ですくって入れる。ジューッと音がして芳醇な香りが鼻を刺激する。早速、フライ返しで丸めていくのだが、これまた、アルミ製で相当な年代モノ。柄はひん曲がっているし、取っ手は外れたままなので直ぐに手が熱くなる。来年は新しいものを買おうと心に決める。が、恐らく1年後に、また、同じ決意をしなければならないような気もする。
5重に巻き上がった厚焼き玉子が4本、きれいにまな板の上に並んだとき、長女と次女がやってきた。長女の分担はお煮しめ作りだ。彼女のお煮しめは私からみれば、極めて乱暴な作り方だが、出来上がったものは、何故か、私が作るより格段に美味しい。出戻り娘だが、数年間の主婦稼業でお煮しめだけは上手になったようだ。
狭いキッチンに二人が入ると急に窮屈になる。私は、今度はブリの照り焼きにかかる。照り焼き用のタレには、先ほどの厚焼き玉子のダシに酒と醤油を少し加えたものを使う。同じものを数の子にも使う。だから、だし汁は大目に作っておくと手間が省ける。オーブンの魚焼き器の受け皿には、水ではなく、アルミフォイルの上に備長炭を砕いたものを敷く。備長炭から出る遠赤外線の効果で、内部までふっくらと焼けるからだ。しかも、焼いた後、受け皿を洗う必要がない。何度か使って、魚油のしみこんだ備長炭を捨てずに植木鉢に入れると、格好の肥料になる。
美味しそうな匂いがキッチンに立ちこめて、こんがり焼きあがったブリが大皿に盛り上がった頃、紅白歌合戦も終盤に入っている。リビングでテレビを見ていた次女が、長女と一緒にお節を重箱に詰め始める。主夫は、煙草に一服つけた後、今度は年越し蕎麦とお雑煮の準備だ。年越し蕎麦には、今年は、新潟・小千谷名物のヘギ蕎麦というのを使った。薬味は、おせちの残りのかまぼこ、稲荷揚げ、それにトロロ昆布とネギ。ツユは昼間スーパーで買った。とても蕎麦ツユまで手が回らない。
年越し蕎麦が出来上がると、テレビでは、もう、除夜の鐘が始まっていた。
翌朝、末娘も加わり、一家4人が食卓に着く。両親が残してくれた漆塗りの屠蘇器からお神酒を少しだけ皿型の杯に注ぎ、全員で「明けましておめでとうございます」と乾杯する。次に、白味噌ベースの京風お雑煮に、オーブントースターで焼きあがったモチを入れる。これも、主夫の自信作だ。
最後に、お節の詰まった五段の重箱のフタを取ると、一斉に歓声が上がった。長女は、早速、デジカメで写真を撮る。自分のブログで紹介する積もりらしい。
皆が思い思いの料理に箸をつけたとき、私が先ほどから心の中で思っていたことを長女が口に出した。
「お母さんが居れば喜ぶのにネ。」

[了]
[2006年1月14日記 原稿用紙約5枚 課題 「私のお正月」]