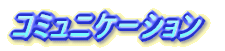
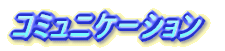
近年、医学の進歩によって人間の寿命は著しく延びた。自分が年をとったから言うわけではないが、60代、70代は未だ壮年期だ。昔なら、隠居生活を余儀なくされた年代が、今や人生の充実期だといってもいい。
人は必ず死ぬ。生まれたときは無限の可能性を秘めていても、年齢とともにその幅が狭められ、死をもって遂に固定する。
さて、一生を終えるに当たって、自分の人生の価値はどの程度だったのか、スコアーカードの提出を求められたとしたら、どうだろうか。百点満点をつける人は先ずいないだろう。
医者の世界では、QОL(Quality of Life=生活の質)という治療のベースが一般的になってきた。つまり、病気を克服するだけではなく、患者のQOLが改善されなければ、十分な治療とはいえない。同じように、私たちの人生も、QOLを高めなければ高得点をつけるわけにはいかない。
ところで、生活の質を高めるといっても、基準は様々だ。学者なら優れた研究を発表することで、また芸術家なら秀でた作品を残すことで人生の充実を実感するだろう。
しかし、私たち凡人は、残念ながら、そのような才能を持ち合わせていない。日常生活の中で、各人が自分の人生の質を高めるための価値判断の基準というものを設定しておかなければならない。
私の考える基準を敢えて披露すれば、私は人間の価値はその人が生前どれだけの人と真のコミュニケーションを持ったかで決まると思う。
コミュニケーションの詳細な定義については別の機会に譲るが、要は他人と自分が理解しあえるということがコミュニケーションの基礎だろう。そのための方法は決して簡単ではない。
十年も前の話だが、山口県・小野田市の市会議員たちとの宴会の席に、スペイン人のシスターを招待したことがある。彼女は、小野田のサビエル高校の校長だが、日本語はペラペラで、日本文化への造詣が深く、書の道でも並みの日本人書家に引けを取らない。今や、小野田市の重鎮的存在で、国際文化に関する市の知恵袋となっている。
私は彼女のファンの一人で、彼女も、多分、私のファンだと勝手に思っているのだが、宴もたけなわの頃、突然、彼女が宴席の議員たちに質問した。
「あなたの心は何処にありますか。」
面食らった男どもがキョトンとしていると、もう一度、はっきりした口調で「あなたの心は何処にありますか?」と訊いた。
男どもも一応は名士のはしくれ。「分かりません」というわけにはいかない。それぞれ思い思いの答えを出した。私も、質問の真意を掴めないまま、「此処です。」と自分の胸を指して答えた。『心臓』という単語が頭に浮かんだ以外に特に根拠はなかった。
全員から回答を得て、満足げな笑みを浮かべた彼女は、「流石に皆さん、立派な答えです。」と、お世辞としか思えない前置きをした後で、全く意外な“正解”を披露したのだ。
彼女は、ゆっくりと全員の眼を見回したあと、極めて断定的に、且つ諭すように言った。
「心は、人と人の間にあるのです。」
私は、幾分白けた表情でこの正解を聞いていたが、内心では眼からウロコが落ちるのを感じていた。
その時以来、コミュニケーションの原点は『心の架け橋』であると確信している。
[ 2005年11月記、原稿用紙 4.5枚、 課題 『橋』]