![]()
第6回の寄稿で「大人になるということ」というのを書いたが、これについて色々と御意見を頂戴している。社内誌の新年号に紹介されたように、先ず、若手エリートのM氏が噛みついてきた。彼のいうには、「あの文章を読む限り、大人になってしまうと仕事の面でも伸びていかないのではないか。」つまり、大人になるということは前進を阻害することではないのか、との御指摘である。実は、ある意味では確かにM氏の意見は正解であり、「大人になること」は好ましいことではない場合が多いかもしれない。だから、私は必ずしも大人になることを推奨しているわけではない。しかし、精神医学の観点からすると、大人になりきっていない人たちの精神構造は甚だ不安定で、時としてバランスを崩すことにもなりかねない。今回は、「大人になること」の意味を精神分析学の見地から少し勉強してみたいと思う。このアプローチのナビゲーターは、前回紹介した内田樹という神戸女学院大学の教授だが、内田氏の代表作は、私の知る限り3冊あり、私は、今般、漸くそれらを読み終えた。「おじさん的思考」「寝ながら学べる構造主義」「期間限定の思想」がその3冊の書物だが、興味深いのは、内田教授が「期間限定の思想」のあとがきで「私は期間限定の物書きである。そう宣言して物書きとしての営業期間を2002年末までと決めた。」と“物書き廃業宣言”をしていることで、華々しいデビューで観客の注目を惹きつけておいて、突然、自分から勝手に幕を引いてしまう気紛れともいえる引退宣言にある種の魅力を感じる。
さて、内田教授は東大の仏文科卒業だけあって近代西洋哲学の代表的作品を殆ど読破されたようだ。だから、「大人になること」の説明をマルクス→ヘーゲル→カントにまで遡って解きあかそうとされている。内田教授によれば、マルクスの後、ハイデッカー、サルトルと続く実存主義に対抗して、フロイド、ラカンという精神分析学派が構造主義なる論理を構築するわけだが、ラカンまでたどりついて、漸く、「大人になること」の本当の意味が理解できることになる。私はここで君たちに西洋の思想家たちの主張を紹介する積りは全くない。そんなことをしても、先ず、読んでもらえないだろうし、それよりも私にはその力もない。ここでは、内田教授の解説による西洋思想家のサワリに触れながら、大人になることの意味を考えていきたい。 私たちは日本人なので、日本語でものごとを表現する。日本語は日本民族という限られた民族の中で形成された言語なので、他の言語に較べると制約が多い。例えば、今年の干支である「ヒツジ」を取り上げてみよう。英語ではヒツジ=Sheep だ。しかし、ヒツジの肉となると
Mutton、ヒツジの毛は Wool と、ヒツジの特定の部分に全く別の名前がある。日本語的発想からは、羊肉は Meat of
sheepであり羊毛は Hair of Sheep となる。逆に、日本文化の主食であるコメについては日本語は実に多彩な表現を有している。総称はコメだが、刈り取る以前は「稲」と呼ばれ、脱穀すると「コメ」「ヌカ」「もみがら」と3種類の言葉に分けられる。もう一つ例をあげると、Swan を日本語では「白鳥」という。考えてみると、実にいい加減な命名で「白い鳥」と表現したに過ぎない。だから、近年、Black Swan が外国から入ってきたとき「黒い白鳥」と呼ぶわけにはいかずに、「黒鳥」と命名したが、これをそのまま英語に翻訳したら、人は「からす」だと思うだろう。ついでながら、白鳥のヒナを英語では Cygnet という。全日空のラウンジを「シグネット」と改名したときには素晴らしい名前だと思ったが、Signet というスペルをみてガッカリした。 人間の行動様式のもう一つの原点として、人類の進化の過程で人間が原始的な自然人からルールに基づく社会的な生活を営むように変化(進化)した時点を考えると分りやすい。法律やルールやそれに違反したときの制裁もない時代では、人間は自然からありとあらゆるものを収奪することに専念していたはずだ。しかし、私有財産の概念が発達してくると、それを守りたいという気持ちがはたらき、そのために止む無く私権の一部を制限されることを受け入れるようになる。こうして、他人のものを奪うことは「してはいけないこと」になり、「なすべきこと、してはいけないこと」という善悪の規範が成立する。この規範はやがてその社会の中でのルールへと進化し、人間がその社会の中で他者と共生していくための共通のルールとして人間の行動様式を制限するようになる。このルールは時代や環境とともに絶えず変化するのだが、ひとつだけ人類の歴史の中で変化しなかったルールがある、と文化人類学者は主張している。それは「近親相姦禁止」のルールで、これが人類の進化のベースにあるという。ギリシャ神話のオイディプス(Oidipous)王は父を殺害して母を自分の妻とする。これは近親相姦の典型だが、精神分析学では男児が父親に反感をもち母親に強い愛情を抱くことをオイディプス王の名前をドイツ語読みにして、エディプスコンプレックス(Oedipus Complex)と呼んでいる。逆に、女児が父親に愛情を母親には反感を抱くのをエレクトラコンプレックス(Elektra Complex)というが、今回のナビゲーターである内田教授の解説はすべて男児が主人公となっており、ヒロインについては触れていない。女性の読者にはもの足りないかもしれないが、それはナビゲーターの所為であることをお断りしておく。 さて、男児に「近親相姦禁止」のルールを教えるのは父親の重要な役目で、母親との癒着を父親から有無を言わさず禁止されて、男児は「世の中には無条件に受け入れなければならないルールがある。」ことを学ぶ。この学習のプロセスを精神分析学では「エディプス」と呼んでいる。逆にいえば、このエディプスの過程で学ぶのは「自分の思いどおりにならないのは父親の所為だ。」という正当化を身につけることにもなる。ここでは、父親という表現を用いだが、実は、この父親は他の絶対的な存在であってもよい。鬼、神、暴君でもよいし、ワンマン社長であってもよい。要するに、この世の中には自分の力ではどうしようもない、ただ服従するしか方法のないルールがあるということに気付くことが重要なのだ。例えば、先の日本語の制約について思いだしてみると、日本語が形成されたのはずっと昔の先人が世界のあらゆる部分を細切れにして、それに単語という名前をつけたことに始まるわけで、その部分の切り取り方というものは現在では既に出来上がっている。日本語の発音に関して、日本人は Love(愛する)と Rub(こする)の区別がつかないといわれるが、それは日本語がそういう音声学的な機能をもっていないから仕方がない。どう気張ってみても、日本語で r と l の区別を説明することはできない。つまり、日本語はそういう構造になっていることを受け入れざるをえない。考えてみると、私たちの社会では、多くのことが暗黙のルールとして社会の中に組み込まれている。つまり、そういう構造になっている。それは、自分の意志とは関係のない何か絶対的なものが定めたように見えるが、実は、そのルールを定めたのは他ならぬ私たちなのだ。私たちのマジョリティがそう考えれば、それがルールを形成する。だから、ルールは時代とともに、当然、変わっていくし、変えていかなければ進歩がない。しかし、現状においては、私たちの社会にビルトインされたルールは自分ひとりで変えられるものではない。だが、ルールとして組み入れられたものでなければ、勿論、変えることは可能だ。それでは、何がルールで何がルールではないのかという区別はどうしてつけるのか。内田教授はそのことには触れていないが、私はこの点がエディプスというプロセスの本質に係わっていると思う。 話が少しややこしくなったので、ここで、私の例をあげて間違っているかもしれないが、私流の理解を説明してみたい。私は学生時代にロシア語を学んだこともあって、思想的には相当左翼がかっていたと思う。つまり、自分の“内なる声”は左側を向いていた。しかし、宇部興産に入社してみると、その限られた社会では左翼思想はタブーともいえるルールがあるのに気付いた。これは自分の力ではとても抗しきれない先人たちが会社という社会の中にビルトインしてしまったルールであるといえる。そうなると、自分の行動様式を変える必要がある。というより、先ず自分の中の“虚像”が自分の発言をチェックし、左を向いた“内なる声”は映倫の検査のようにモザイク模様でぼかされてしまう。加えて、社内に構造的にビルトインされたルールが“内なる声”はこの社会では通用しないことを教えてくれる。というより、自分で学んだ結果“内なる声”は何処かに消えてしまった。私の“内なる変化”は、左翼用語でいうところの「日和見主義」や「修正主義」の典型かもしれない。しかし、精神分析学的には立派なエディプスの学習過程であったはずだ。 (2003年1月 記)
私たち人間の行動様式がどのように形成されたかを知るためには、先ず、原点から出発する必要がある。一人の人間のスタートは“誕生”という赤ちゃんの状態で、生後間もない赤ん坊は行動も自由にならず、栄養摂取も他人に依存している。生後6ヶ月くらいになると人間の幼児は鏡に映る自分の姿に興味を抱くようになる。ラカンはこれを「鏡像段階」と名付けでいるが、それは幼児が鏡の中の自分の姿に強烈な喜悦の感情を表す段階で、生まれて初めて自分の「主体」というものを意識するのがこの鏡の中の自分に対してなのだ。それまで、幼児は自分の身体の中にさまざまな「運動のざわめき」を感知してはいるものの、それらは未だ統一にいたることはなく、原始的な混沌のうちにあるわけで、この統一を欠いた身体的不調和感は幼児に無力感なり不快感を与えている。
ところが、ある日、鏡の中に自分を発見して、「おお、これが《私》なのか。」と、周囲の景色の中に自分を見出し、これまでのバラバラの感覚が一挙に統一され、「私という存在」を自覚することになる。
ところが、実は、「鏡の中の私」は「本当の私」ではない。物理学でもそれを虚像と呼ぶように、「私でないもの」を「私」とみたてることにしたのだ。つまり、「私」の起源は「私ならざるもの」によって担保されており、「私」の原点は「私の内部」にはない。これは極めて危うい事態で、人間は誰でも、鏡像段階を経過することで、ある種の「誤魔化し」を自分の中で正当化しているということになる。このことは、その人が成長して自分の主張を吐露する場合においても、その人の口から発せられる言葉は必ずしもその人の「内なる自分」の主張ではないということにつながる。何故なら、自分の原点は「内なる自分」ではなく「虚像としての自分」なので、「内なる自分」が自己主張しようとしても、その虚像がチェックしOKを与えた言葉のみに発言許可が与えられるからだ。私たちが自分の内なる声をそのまま表現する上で、もう一つの障害となっているのが「言語の問題」である。
言語とは、上に述べたように、それを話す民族の文化や習慣に応じて全体の中から部分的に引き裂いてそれに名前という記号をつけていったもので、いわばジグゾーパズルの断片が単語といわれるものだ。引き裂く方法の出鱈目加減の良い例が星座だ。適当な星だけをマークし、その輪郭をたどることで「熊」とか「さそり」とか命名しているが、どんなに無理をしても私にはあの多数の星が熊やさそりには見えない。つまり、「言語活動」というものは、満天の星を星座に分かつように、ある観念が先に存在しそれに名前がつくのではなく、名前がつくことによってある観念が私たちの思考の中に存在するようになるのだ。ここでは、日本人として生まれた私たちは日本語という言語制約の中で自分を表現していくことが運命づけられていると理解していただきたい。従って、私たちが鏡像段階を経過し言語を覚える段階になっても、自分の内なる声の表現は自分の虚像からチェックを受け、更に、言語の制約をも甘受しなければならないことになる。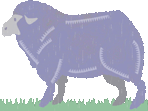

![]()
結論として、人間は二つの“欺瞞”を通じて大人になるということができる。最初の欺瞞は鏡像段階における鏡の中の虚像を自分にみたてること。更に、もう一つの欺瞞は成長とともにエディプスの過程を経て自分を変化させていくことだが、後者の欺瞞は一度きりのプロセスではなく、何度となく経験するプロセスであるはずだ。“構造主義”という立場からの内田教授の表現を最後に紹介したい。
「私たちはつねにある時代、ある地域、ある社会集団に属しており、その条件が私たちのものの見方、感じ方、考え方を基本的なところで決定している。だから、私たちは自分が思っているほど、自由に、あるいは主体的にものを見ているわけではない。むしろ私たちは、ほとんどの場合、自分の属する社会集団が受け容れたものだけを選択的に『見せられ』『感じさせられ』『考えさせられている』。そして自分の属する社会集団が無意識的に排除してしまったものは、そもそも私たちの視界に入ることがなく、それゆえ、私たちの感受性に触れることも、私たちの思索の主題になることもない。」
「私たちは自分では判断や行動の『自律的な主体』であると信じているけれども、実は、その自由や自律性はかなり限定的なものである。」