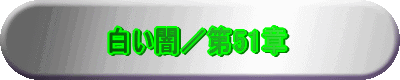
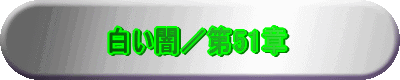
�@���̈�e���g���Ẵh���X�f���ʂ�K��͏I������B����́A���̗��s�̍ő�̖ړI���I���Ĉ��g���o�����B
�@�����A����̓z�e���̑����獷�����ތ��Ŗڊo�߂��B���v���݂�Ɩ���6���B����q�Ɩ������H�̎��Ԃ�8���B�����f���b�Z���h���t�̊X������Ă݂����Ȃ����B
�@�T�{�C�E�z�e���̓I�X�g�ʂ�ɂ���B�����s���ƃx�������ʂ�A���̐�ɃP�[�j�q�X�E�A���[������B���̊X�̖ڔ����ʂ肾�B�}���j�G�̊X�H���ɕ����Ǝԓ����d��ꂽ��ʂ�́A����50���͂��낤���A�ʏ́g�P�[�h�ƌĂ��B�ʂ�̗����ɂ��n���ȓX���������ԁB�P�[�̓h�C�c�̃t�@�b�V�����̃��b�J�ł�����B
�@���̑������ԁA�ǂ̓X�������͕�����Ă��邪�A�E�B���h�[�̃V���b�^�[�͊J���Ă���B����Ȃ��ŁA�̂�т�ƃE�B���h�[�E�V���b�s���O���y���ޘV�v�w�̎p������ɂ�ῂ��������B
�@���̓��A����ƈ���q�͒��̕ւŃ~�����w���ɔ������B�~�����w���̓o�C�G�����B�̎�s�B�o�C�G�����̓h�C�c�ő�̏B�ŁA�p��ł̓o�o���A�ƌĂ��B�m�َq�̃o�o���A�̓t�����X��Łu�o�C�G�����́v�Ƃ����Ӗ��ł���B
�@���j�I�ɂ̓f���b�Z���h���t�̂���k�h�C�c�̓v���C�Z�������A�~�����w���̓�h�C�c�̓o�C�G���������ƁA���S�ɕʂ̍��ł������B���n��������������h�C�c�́A�c�Ɏ҂̖k�h�C�c���y�̂��Ă����Ƃ���邪�A���̕����͍����c���Ă��āA�k�h�C�c�Ƃ͈�������͋C������B
�@�܂��A�Y�Ƃ̖ʂł��k�Ɠ�ł͑傫�ȈႢ������B�k�h�C�c�͑f�ރ��[�J�[��̂ŁA�f���b�Z���h���t�̎��ӂ́A�N���b�v��e�B�b�Z���Ƃ������S�|��Ђ������B��͉��H�A�g���ă��[�J�[�������A�x���c��a�l�v�ȂǁA�h�C�c�̖��Ԃ͓�ō���Ă���B�a�l�v�i�p�ꎮ�ɂ́u�o�C�G�����E���[�^�[�E���[�N�v�̓������j�̖{�����~�����w���ɂ���B
�@�~�����w���ɂ͊ό������������B����͒��݈�����ɉ��x���d���Ń~�����w����K�ꂽ���Ƃ����邪�A�w�ǂ������Ԃ̂a�l�v���A�R���H�ƂƋZ�p��g�����Ă��������f�Ђւ̏o���ŁA�s���ό����������Ƃ͂Ȃ������B
�@����q�͎��O�ɂ悭���������Ƃ݂��āA�~�����w���̖����Ɋւ��Ă͗�������͂邩�ɏڂ����A����q���K�C�h�����ďo���B
�@���̓��͒����w�ɋ߂����h�ɔ��܂������A���̃z�e�������͈���q�Ɠ����������B����̓C�r�L�������Ă͂����Ȃ��ƋC�������B�T���āA�C�r�L�������̂͋����ɖ������Ƃ��������悤���B����͉E�ɍ��ɐQ�Ԃ��ł��Ă͉������̎p���Ŗ��邱�Ƃɓw�߂��B
�@�����̒��A�����^�J�[��Ђŏ��^�̃x���c���肽�B���n���h���Ȃ̂ő����͌˘f�����������Ɋ��ꂽ�B�����A��������点���̂̓J�[�i�r�������B���{���̃i�r��z�����Ă������A�����ɂ��f�B�X�v���[��ʂ��Ȃ��B�ړI�n����͂��邽�߂̏����ȉ�ʂ����邾���ŁA�����̎w���͉����ł��悤�ɂȂ��Ă���B
�@����q��2�l�ł��ꂱ�ꑀ�삵�āA���Ƃ������ē����p��łɁA�ړI�n�������Y�u���O�ɐݒ肷�邱�Ƃ��ł����B
�@�~�����w������A�E�g�o�[���`96�����𐼂�30��������ƃ��}���`�b�N�X���ƌ�������B�����������Y�u���O���B���܂�m���ĂȂ��������A�Ԃ��~��ď����U���B
�@����h�䂷�邩�̂悤�ɑ傫�Ȑ삪����Ă���B���q��Ƃ����炵���B�������ʂ����A���ꂢ�Ȑ��B�ƂĂ��������������͋C�ŁA�X���݂��G�{�ɂłĂ���悤�ʼn����B
�@���}���`�b�N�X���ɂ͉Ƒ��ň�x�������Ƃ�����B30�N���O�̘b�����A���̎��́A�m�C�V���o���V���^�C���A���B�[�Y����A���[�e���u���O�A�f�B���P���X�r���[���Ȃǂ����ĉ�����B����q�͓������w�Z�ɏオ��������ŁA�w�NJo���Ă��Ȃ��Ƃ����B
�@�ό��n�Ƃ��Ă̓m�C�V���o���V���^�C�����ł��m���Ă���B�f�B�Y�j�[�����h�̃V���f������̃��f���ƂȂ��������̏�͓��{�ł��l�C�������B������݂����Ȗ��O�����A�h�C�c�ꕗ�ɒP�����Ĕ�������Ɗo���₷���B�u�m�C�E�V�����@���E�V���^�C���v�Ƃ́u�V���������̐i��j�v�Ƃ����Ӗ����B
�@�����A���炽���́u�V���������̏�v��������B���܂�ɂ����{�l�ό��q�������̂ƁA�Ԃ��߂�ꏊ�ɋ�J���邩�炾�B����́A�i�r�Ƀ��B�[�Y�����o�^���悤�Ƃ������A��ʂɂ́u���B�[�Y�v�Ƃ������̖��O�����\������Ȃ��B�������Ƃ��낤�ƎԂ̃G���W�����n���������B
�@���}���`�b�N�X������1���Ԃ��܂葖��ƁA����炵���ꏊ�ɂ���Ă����B���A����̌����͂Ȃ��B����͌Â��L���𗊂�ɋ߂����G�Ȃ��T�������A����Ɍ�����Ȃ��B30��������������A�ׂ��_���̘e���Ɂu���B�[�Y����v�Ə����ꂽ�����ȗ��ĎD���������B�i�r���g���Ȃ��ƂȂ�ƁA����Ȃ��獶�E�ɖڂ�z�邵���Ȃ��B
�@�e��������Ă����ƁA�������쌴�̒����Ɍ��o���̂��鋳��̌��������ꂽ�B���ӂɂ͂�������̎Ԃ����Ԃ��Ă����B
�@���B�[�Y����ɂ͖ʔ����G�s�\�[�h������B18���I�̏��߁A�_�Ƃ̕v�l���C���m����L���X�g�̖ؑ���Ⴂ���B�Ƃ��낪�A���̖ؑ��̃C�G�X������Ƃ��܂𗬂����B���̉\���āA�����̏���҂������_�ƂɏW�܂�悤�ɂȂ����B�����ŁA10�N������Ō��݂����̂����݂̃��B�[�Y����Ƃ����B
�@����͏H�c���̏C���@�ł������悤�ȁg��Ձh���������ƕ��������Ƃ�����B������͐���}���A���B�ǂ�����ؑ��Ȃ̂ŁA���t���܂Ɍ������̂ł͂Ȃ����Ɗ����������A���ۂ͂���ȒP���Ȃ��Ƃł͂Ȃ��炵���B
�@���B�[�Y����̌����͊O���猩��ƕ��ʂ̋�����A���ɓ���Ǝv�킸�ڂ�������B���R�R���̑����̓��[���b�p����Ƃ����A�V��ɕ`���ꂽ�t���X�R��́g�V����~������h�ƌĂ�Ă��āA���E��Y�ɂ��o�^���ꂽ�B
�@����ƈ���q�͎b���V��̃t���X�R��Ɍ��Ƃ�Ă������A�ɂ��Ȃ��ĊO�ɏo���B����̎��͖͂q��ɂȂ��Ă���B������������̉Ԃŏ������_�Ƃ��_�݂��A������������������Ƒ���H��ł���B���ɂ̂ǂ��ȕ��͋C�B�x�[�g�[�x���̌�����6�Ԃ͂��������Ƃ���ō�Ȃ��ꂽ�̂�������Ȃ��A�Ɨ���͏���ɑz�������B
�@���B�[�Y������o���Q�l�́A�Ԃ���H�k�Ɍ����đ��点���B�����̏h���n�̓��[�e���u���O�B200�����ȏ゠��B���}���`�b�N�X���͍������H�ł͂Ȃ��̂ŕ��ώ�����60�����B�܂Ƃ��ɍs���Ă��R�Ԉȏォ����B
�@���[�e���u���O��30�q��O�Ƀf�B���P���X�r���[��������B12���I���Ɍ��݂��ꂽ�Ƃ����ƂĂ��Â����B30�N�O�̉Ƒ����s�Ŏq���������ƂĂ���̂�z���o���āA��������Ă݂邱�Ƃɂ����B
�@�f�B���P���X�r���[���ɂ͐̂̏�ǂ����̂܂c���Ă��āA���ɓ�����͂S�ӏ������Ȃ��B�Ԃœ����̂͂��̂����̂P�ӏ������B����͈���q�̍L�����n�}�����Ȃ���T�d�ɎԂ����̒��ɐi�߂��B
�@����������ƁA�����͂܂��ɒ����B���b�̍��ɗ����悤�ȍ��o���o����B�Ώ�̓��H�̗����ɂ́A�Â�����̉ƁX������A�ˁA���ɂ͗�O�Ȃ��Ԃ┒�̉Ԃ������Ă���B���̂Ȃ��ǂɂ͑傫���R�m��n�̊G���`����Ă���B���ꂼ��̌����ɂ͓����̂������肪�����āA���ꂪ�\�D�̑�������Ă���炵���B
�@���̒��͐�Ђꂽ���A�ŁA�����̊X���݂���������c���Ă���B�ʂ�̌���������n�ɏ�����Z�̋R�m������Ă��Ă��s�v�c�͂Ȃ��B����q�͂������苻�����āA�J������Ў�ɍׂ��H�n�����������B����͘H��̃J�t�F�ŏ��x�~�B30�N�O�A�q�����������������ɑ������Ă������i��z���o���Ă����B�����ɂ́A�����悤�ɂ͂��Ⴂ�ł��鏽�̎p���������B
�@���̖�A���炽���̓��[�e���u���O�̌Â��z�e���ɔ��܂����B���̃z�e���ɂ͂Q�����邱�ƂɂȂ��Ă���B
�@���[�e���u���O�̓f�B���P���X�r���[����傫�������悤�Ȓ����̒��B����ǂɈ͂܂�Ă���B�����A�����͐�ЂŏĎ����A�̂̃f�U�C�����̂܂܂ɍČ����ꂽ�B���ɂ́A�����Ȕ��p�ق┎���فA�M�t�g�V���b�v�Ȃǂ��������сA���}���`�b�N�X���ł͊ό��q�̃��b�J�̗l����悵�Ă����B
�@�Q���ԁA����͈���q�̃��N�G�X�g�ŁA�l�`�����ق⍉�┎���قȂǒ������Ƃ�������ĉ�����B�܂��A�N���X�}�X�E�V���b�v��e�f�B�x�A�E�V���b�v�Ȃǂ��`���Ă݂��B����͂���Ŗʔ����͂��������A���S�̂̕��͋C�Ƃ��ẮA�f�p�ł�����܂肵���f�B���P���X�r���[���̕��ɗ���͂��傫�Ȗ��͂��������B
�@���[�e���u���O�ƃ��}���`�b�N�X���ɕʂ�������A�Q�l�͍Ō�̖ړI�n�ł���Ï�X���Ɍ��������B�l�b�J�[��ɉ����ČÏ�X���ƌĂ��ό����H�����邪�A���̖��̒ʂ�Â����邪�X�������ɓ_�݂��Ă���B���̒��̃q���V���z�[���Ƃ����Ï邪�z�e���ɂȂ��Ă��āA����������q����z���Ă����B
�@���[�e���u���O���璼�������ɂ����70�����قǂ����A�Ȃ��肭�˂����R���𑖂�̂Ŏ��ۂ̑��s�����͂R�{�߂�����B�i�r���q���V���z�[���ɐݒ肵�����A���x�����ɖ������������S���ԋ߂����������āA�ړI�̌Ï�ɒ������B
�@�q���V���z�[����̓l�b�J�[��������낷�������R�̒������J���Č��Ă��Ă����B�����猩�グ��ƌÂ��邾���A���ɓ���Ə���̕����͋q���ɉ�������ăz�e���̑̍ق𐮂��Ă���B�������A�Ï�̃��C�A�E�g���Ȃ��悤�ɍ���Ă���̂ŁA���፷���傫���A�������烌�X�g�����ɍs���ɂ́A��U�O�ɏo�Đ̊K�i���r���̂R�K���قǓo��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�G���x�[�^�[�͂Ȃ��B
�@��������̒��]�͑f���炵�������B�ቺ�Ƀl�b�J�[��������낵�A�Ί݂ɂ͎R�������L����B�����ɂ́A�Ԃ������ɔ��ǂ̏����ȏZ���������ł���̂��}�b�`������ׂ��悤�Ɍ�����B������ʂɂ͔������̔�Ԏp�⏬�D���������ƍs��������l���A�ӂ�̐Â����Ƒ��܂��ĕs�v�c�Ȓ��a�������o���Ă���B
�@�����ň�x�݂�����A����͒�ɏo�Ă݂��B�����ɂ�����̒�炵���A�Â��u�����Y���̑�C��̒e�ۂ��̖X�̊ԂŊi�D�̃A�N�Z���g�ɂȂ��Ă���B
�@����q�͔���m��Ȃ��B�����A��̓W�]��ɓo���Ă݂����Ƃ����������B����ɂ͌��グ�������ŁA�ƂĂ����̗E�C�͗N���Ă��Ȃ��B������ʐ^���B�邱�Ƃɂ����B����q�͂��Ȃ葬���y�[�X�Ő̊K�i��o��n�߁A10���قǂŒ���ɒ������B���b�z�[�Ƃ������͂悭�������邪�A���U�鈟��q�̎p�̓S�}���̂悤���B
�@����͈���q���߂�܂ŁA�u�����Y�̑�C�̖C�g�ɂ܂������đ҂����B�������q���ɕԂ����C���������B
�u���������L���C�B����������o���Ă݂���H�v
�@�~��Ă�������q������e�܂��Ȃ��猾�����B
�u��������́A��ɓo��܂łɎ��Ⴄ��B�r����10�K���炢���邾�낤�B�v
�u���̂��炢�͂��邩���ˁB��������ʐ^�B����������{�ɋA�����瑗���Ă�����B�v
�u����͗L��B���������Ȃ�ƂĂ��B��Ȃ��ʐ^������ˁB�v
�@���̖�A����ƈ���q�͂���̃e���X�ɂ��郌�X�g�����̃e�[�u���Ɍ����������č������B
�u�[�H�͍������Ōゾ��ˁB�������A�Ƃ��Ă��y���������B��������́H�v
�u����������y����������B����ȂƂ���ւ͂������邱�Ƃ͂Ȃ����낤�ˁB�v
�u��������ƂQ�l�Ńh�C�c���s�Ȃ�āA�l�������Ȃ������B���ꂳ��̂��A���ȁB�v
�@����͋��̃|�P�b�g����^�o�R�����o���ă��C�^�[�ʼn�_����ƁA�x�̉��܂ŋz��������Â��ɋ�Ɍ������ēf�����B���͂��敗�ɏ���Đ�̏㗬�ւƗ���Ă������B���̐�ɂ́A�Ԃ����܂����傫�ȑ��z���������ƎR�̒[�ɒ������Ƃ��Ă����B
�u�����́A�n�C�f���x���O�Ɋ���Ă���t�����N�t���g��`�ɍs�����B�v
�u�����ˁA�t���C�g�͖�̂W�������玞�Ԃ̓^�b�v�������ˁB�v
�u�n�C�f���x���O�ɂ͈���q����x�s�������Ƃ�����̂����ǁA�o���Ă��邩�ȁH�v
�u�S�R�o���ĂȂ����B�����ǁA�Ƃ̃A���o���ő傫�ȋ��̂����ƂŎB�����ʐ^���������̂͊o���Ă�����B���ꂪ�n�C�f���x���O�Ȃ́H�v
�u���������B����̓e�I�h�[�����Ƃ����ĂˁB�n�C�f���x���O�̖����̂P����B�����͎��ۂɌ��邱�Ƃ��o�����B�v
�u�P�T�Ԃ̗��s�Ȃ�āA��w�̎��ɂ͖��̂܂������������ǁA�I����Ă݂�Ƃ����Ƃ����Ԃ���ˁB�v
�u�������ˁB�����ǁA���x�̗��s�͂�������ɂ��A���Ƃ������A���ꂳ�S���Ȃ������Ƃɑ���S�̋��ɂȂ�����B�U���Ă���ėL��B�v
�u�������̕����������������B����q�ɂƂ��Ă��ō��̃��t���b�V����������B�v
�@�����A�Q�l�͌Ï����ɂ��āA�n�C�f���x���O�Ɍ��������B�n�C�f���x���O�͑�w�̒��B
�@�n�C�f���x���O��w���ł����̂�1386�N�Ƃ�������A���{�ł͖�����������B���傤�Ǒ������{�̍��ł���B�n�C�f���x���O��w��ɂ��������u�A���g�E�n�C�f���x���q�v�͓��{�ł��L�����B
�@���炽���͑�w�����ڂɌ��ăP�[�u���J�[�ŎR��̃n�C�f���x���O��ɏオ�����B���̏��15���I�ɏo�����Ƃ���邪�A17���I�̂Q�x�̐푈�Ŕp�ЂƂȂ�A���́A�p�Ђ̂܂ܕۑ�����Ă���B��̃e���X����̓e�I�h�[�������悭�������B�����o�b�N�Ɉ���q�𗧂����A�������ʐ^���B�����B
�@�n�C�f���x���O�̊X�ŁA����q�͂��y�Y�̔������ɖZ���������B�X�\���̗ǂ������ȂƂ���ɂ͕K�����荞��ŁA���ꂱ��ƕi��߂ɗ]�O���Ȃ��B����͑҂������т�āA�X�̑O�Ă��Ȃ������Ă݂��B
�@�哹�|�l�Ƃ����̂��낤���A�S�g�������œh��Ԃ������N�������E���O�ɏo�����܂ܐg���났�����������Ă����B�̍L���X�q�����Ԃ�A�t���A�̃X�J�[�g�𒅂��Ă��邪�A�ߗނɂ����ׂċ������h���Ă���B�O�ɒu���ꂽ���ɒʍs�l�����K�𓊂������Ƃ������A���Ȃ₩�ɍ��������߂Ċ��ӂ�\�킵���B�ʔ����p�t�H�[�}���X�������B
�@����͍Q�ĂăJ�������������B�ʐ^���B�邾���ł����炪�v�邩������Ȃ��B����̓|�P�b�g����P���[���̃R�C�����o���Ĕ��ɓ������ꂽ�B�����́A������荘�������߂ė���Ɍ������ċ��F�̊�ɔ���������B
�@�����̊Ԃɗ����̂��A�傫�Ȏ��܂�����Ɏ���������q���E��ŃJ�������\���Ă����B
�@�p���g�}�C���̏����͗���e�q�ɔ��݂������̂�������Ȃ��B����ɂ͏�������ł���悤�Ɏv���āA���x�͂Q���[���̃R�C���ɓ������ꂽ�B
�@�n�C�f���x���O����t�����N�t���g��`�Ɍ������r���A������Ƃ����������������B�Ԃ̃K�\�������ꂽ�̂��B�~�����w���Ŏ�Ă����x���������Ă��Ȃ��B��قǂ���ԃ����v���_�ł��Ă���B���A����̌o�����炷��ƁA�����v�_�ł���50�����قǂ͑���͂����B
�@����͎Ԃ̑��x���������Ƃ��ăA�E�g�o�[���̘H���ɂ���K�\�����E�X�^���h�̕W����T�����B�₪�Ėڂɂ����W���ɂ́u���̃K�\�����E�X�^���h�܂�60�����v�Ƃ������B
�@����͂܂����B�������H�̏�ŃK�X�����N���������ςȂ��ƂɂȂ�B����͎��́g�A�E�X�t�@�[���g�h�ƕW�����ꂽ�o������A�E�g�o�[�������肽�B�����́A�V���̏��ƒc�n�̂悤�ȂƂ��낾�����B
�u�����Ȃ�ǂ����ɃK�X�����E�X�^���h������͂����B�v
�@����͓Ƃ茾�̂悤�əꂢ�āA�Ԃ�1���̓X�̒��ԏ�ɓ��ꂽ�B��^�̃V���b�s���O�E���[���̂悤���B�X���ɐu���Ă邱�Ƃɂ����B�����A�K�����Ƃ����X���ɂ͋q�̎p�͖w�ǂȂ��A�X���̐��������قǏ��Ȃ��B
�u���̕ӂ�ɃK�\�����E�X�^���h�͂���܂��H�v
�@����̓��W�ɂ��������̓X���ɐu�����B
�u���̋߂��ɂ͂Ȃ���˂��B10���قǑ�����邯�ǁc�B�v
�@��肠�����A���̏ꏊ�������Ă��炤���Ƃɂ����B���A�����̃h�C�c��̐����ł͓��������ɓ���Ȃ��B�߂��܂ōs���āA�܂��u���������B����͂���������ƁA�u�����h�̃W���[�W�[��i��߂��Ă��鈟��q�ɐ����|���ēX���o���B
�@10����A���炽�����悹���x���c�́A�Ƃ���X�[�p�[�̒��ԏ�ɒ�܂��Ă����B����ɂ�����q�ɂ��S�����p��������Ȃ��Ȃ��Ă����B
�@���̎��A���������I��������̒��N�̕w�l���A�܂���ɉ����Ă�����Ɍ������Ă���̂��������B����͎Ԃ��~��Đ����|�����B
�u���݂܂���B���̕ӂ�ɃK�\�����E�X�^���h�͂Ȃ��ł��傤���B�v
�u�K�\�����E�X�^���h�˂��B�߂��ɂ͂Ȃ������Ǝv�����B�v
�@�w�l�͖ʓ|���������ɓ����āA�����̎Ԃɏ�荞��ł��܂����B
�@���҂͂���̉ɃK�b�J����������́A���̐l��T�����B���������Ƃ��́A�Z�J���h�E�I�s�j�I����u���Ă݂�K�v������B
�@���ɒʂ肩�����������Ⴂ�w�l�ɓ�����������Ă݂��B
�u�K�\�����E�X�^���h�Ȃ璼�������ɂ�����B�������������^���ɂ��Ă����������B�v
�@�w�l�͋��������Ƃɉp��œ������B
�u�T���L���[�E�x���[�E�}�b�`�I�v
�@����ƈ���q�͎v�킸�������낦�ċ��B
�@�Q���Ԍ�A����ƈ���q�͑S����@�̃G�R�m�~�[�E�N���X�̃V�[�g�ɕ���ŁA�P�T�Ԃ̗������Ă����B
�u�����͂�����������ˁB�v
�u���̗��s�́A��������ɂ͑f���炵���Z���`�����^���E�W���j�[��������B�v
�i����͍ŏI�͂ł��B�j�@
![]()
�u�����L�[���̌�v�ɂ��ǂ�
![]()
�u�����Łv��52�́i�I�́j�ɐi��
![]()
�g�b�v�y�[�W�֖߂�