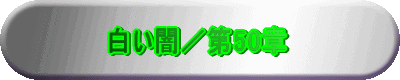
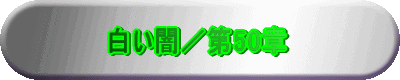
翌朝、竜也は6時に目が覚めた。喉が痛むし、頭もスッキリしない。どうやら昨夜の野外コンサートで風邪を引いたらしい。早めの朝食を済ませ、外に出てみた。
空はどんよりと厚い雲に覆われて、今にも雨が降り出しそうだ。竜也は折り畳み傘をもってこなかったことを後悔した。
此処のドイツ人はあまり傘を持たない。デユッセルドルフはドゥリズルドルフ(英語で drizzleは霧雨のこと)と異名をとるように、小雨が多い。だが、少々の雨なら濡れても平気ということだろうか。デパートにも折り畳み傘は殆ど見かけない。
そもそも、折り畳み傘は日本の発明だ、と何かの本で読んだことがある。日本人は平安時代にウチワを折りたたむことで扇子を発明した。洋傘は大正年間にドイツから輸入されたが、番傘と同じように既に折りたたんだもの。それを更に半分に折るという発想はヨーロッパ人には到底思い浮かばない。日本では1950年代に折り畳み傘を量産して、ドイツに逆輸出した。1980年代になると、3段傘が登場した。長さ18cm。ハンドバッグにも入る。これも日本人の縮み志向が生み出した発明品に他ならない。そんなことが書いてあった。
亜希子は朝から日本人学校に出かけてしまった。デュッセルドルフ日本人学校は1971年に教会の建物を間借りしてスタートしたが、73年には立派な校舎が完成した。竜也の上3人の娘はこの学校にお世話になった。特に亜希子は小学校1年から通ったので友だちも想い出も多いようだ。
午後、亜希子の帰りを待って一緒にホテルを出た。行き先はオストラートのドレスデン通り。昔の我が家である。竜也と亜希子はタクシーではなく市電に乗った。以前はKバーンというクレフェルド行きの赤い電車だった。今は普通の市電と同じ電車が走っている。ガランとした車内の窓際の席から2人は窓の外を注意深く眺めた。
電車は町から郊外に出て、畑の中を走り、30分ほどでカンパー・ウェグという小さな駅に着いた。駅といっても野原の真ん中に小さなプラットフォームがあるだけで周囲には何もない。殺伐とした景色は昔のままだった。
電車を降りた途端、先ほどからの小雨が本降りに変わった。竜也たちは、プラットフォームの中央にある小さな屋根の下で雨宿りした。竜也たちと一緒に1人のドイツ人が降りたが、こちらは土砂降りの中を平然と傘も差さずに駅から出て行った。
10分ほどで雨脚が弱まったので、竜也たちも亜希子の折り畳み傘を頼りに駅を離れた。
“Kamperweg”と標示のある通りに出ると急に懐かしさがこみ上げてきた。竜也は背広の内ポケットから1枚の写真を取り出した。梢の遺影だった。竜也は胸元に写真を掲げ、ゆっくりと歩き出した。
「梢、分かるか? カンパーウェグだよ。30年前と少しも変わっていないよね。」
「お母さん、懐かしいでしょ。」
亜希子も涙声で写真の梢に話しかけた。
2人は古い記憶を辿りながら小雨の中を歩いた。10分ほどでドレスデン通りに来た。この通りの23番地に竜也たちは住んでいた。昼下がりのドレスデン通りには人影もなくひっそりと静まり返っていた。
30年前の夏、この辺りは大騒ぎだった。道路にガーデンチェアが並び、バーベキューの煙が立ち込めていた。ドレスドナー・フェストと名づけられた夏祭り。梢はフェストの主役だった。紺の浴衣に赤い帯。俄か作りの提灯の下で近所のドイツ人たちに盆踊りの指導をした。小さかった4人娘はわけも分からずに走り回っていた。
閑散としたドレスデン通りを歩きながら、竜也は再び梢の遺影を取り出した。
「梢、憶えているかい? お前は此処で盆踊りを踊ったんだよ。」
竜也は写真の梢に辺りが見えるよう、胸元に写真を持ったままその場でゆっくりと回れ右をした。本当なら梢の車椅子を押しながらこの通りを歩きたかった。だが、それは今は無いものねだりでしかなかった。
23番地の家は竜也たちの想像とは違っていた。家の前面には、生垣のようにビッシリと木が植えられて、玄関のドアが見えない。ただ、横手にある大木は当時のままであった。
竜也は1軒おいた27番地のニーツォルトさん宅の呼び鈴を押した。年老いたエリカが顔を覗かせた。
「ハーイ、ヘル・ナカーノ、ヴィルコーメン!」
竜也はエリカのしわだらけの手を固く握った。
竜也たちが此処に住んでいたときは、隣にはシュテマーさんという銀行員の若夫婦が居たが、今は空き家らしい。その隣がニーツォルトさんだった。当時、御主人は50代後半でティッセンという製鉄会社の技師だった。その奥さんがエリカ。梢とは親しく付き合っていた。夫婦には双子の息子と娘が1人居た。双子の弟の方はデュークといったが、兄の名前は忘れてしまった。しかも、兄弟は全く同じ顔だったので当時から区別がつかなかった。
エリカは殆ど英語を喋らないが、双子の兄弟は当時から上手な英語を喋った。竜也は旅行に先立って、エリカ宛に英語で手紙を書いておいた。手紙の内容は、当然、息子たちがエリカのために翻訳してくれるだろうと想定した。
竜也と亜希子はリビングに案内された。テーブルにはエリカが作ったのだろう、典型的なドイツのクーヘンが皿に盛られていた。3人がソファに座ると、片言のドイツ語での怪しげな会話が始まった。
「コズエが亡くなったと聞いてとても残念だわ。」
「私もです。ところで、御主人はどうされたのですか?」
竜也は御主人の姿が見えないのが気になっていた。息子や娘たちは独立して家を出て行ったのだろう。
「夫は5年前に死にました。もう年でしたから。」
そういえば、クリスマスカードにそのようなことが書かれていた記憶がある。エリカからのカードは読めない筆跡のドイツ語だったので、竜也には極めて難解だった。
「それは失礼しました。ところで、エリカさん、お元気そうですね。お幾つになられましたか?」
「82歳です。もう年寄りですわ。」
竜也にはドイツ語の会話が苦痛に感じられてきた。ありきたりの話が終わると次のステップに進めない。亜希子は30年前にはドイツの幼稚園で流暢な子供のドイツ語を喋っていたが、今は黙っている。完全に忘れてしまったようだ。
会話が途切れたままなので、竜也は庭を見せてもらおうと立ち上がった。そのとき、玄関のチャイムがなった。
「息子が帰ってきたらしいわ。あの子なら英語を喋るのでもっと話ができるわよ。」
エリカは竜也の胸中を見透かしたように言って、玄関に向かった。ドアが開いて、長身の男が夫人らしき女性と小さな女の子を連れて現れた。
「デュークだったかな。」
竜也は差し出された手を握り返し、英語で尋ねた。
「デュークは私の弟ですよ。私はエルフ。」
「ごめん、前から区別がつかなかったから。」
竜也は喋りながら相手の名前が分かってホッとした。今まで黙っていた亜希子も英語が共通語だと知って、俄然喋り始めた。
エルフは奥さんと娘を紹介した。今はミュンヘンに住んでいて、休暇の帰りだという。竜也たちが来るというので、時間を合わせてくれたらしい。
「ところで、エルフ。随分立派な頭だね。」
エルフの頭は日本の僧侶のように全くのスキンヘッド。しかもツルツルに光っている。
「先年、病気をしましてね。薬の副作用でこうなってしまったのです。デュークは未だフサフサしていますから、今なら簡単に区別できますよ。」
「で、そのデュークは何処に住んでいるの。」
「彼もミュンヘンの近くに居ます。」
「妹さんはどうしたの。」
「彼女は看護学校を卒業したのですが、まだ独身ですよ。いい年をして。」
「ウチも亜希子以外は3人とも独身だから・・・」
一息ついたところで、竜也たちは庭に出てみた。竜也たちの家は4軒長屋のテラスハウスの東の端にあった。入口は別々だが、庭は4軒とも共通で自由に行き来できる。竜也と亜希子は芝生の庭を23番地の方へ進んだ。隣のシュテマーさん宅は、誰も住んでいないのが庭からでも見て取れた。が、肝心の昔の我が家は、庭にもテラスを覆い隠すように高い木の生垣があって、庭からも中は見えなかった。
「この家には、どなたが住んでいるの?」
竜也はエルフに小声で訊いてみた。
「変った人が住んでいるのですよ。私たちにも殆ど顔を見せないのです。近所とは全く遮断されています。母も挨拶すらしたことはないそうですよ。」
「ドイツ人なの?」
「それも分かりません。」
「そうですか。出来れば中を見せてもらおうと思っていたのに。残念だな。」
亜希子は家の中を見ることが出来ないと知って、庭から生垣に向かって写真を撮っていた。竜也は内ポケットから梢の遺影を取り出して、23番地の家の方に向けた。
「梢、残念ながら中には入れないけど、お前の住んでいた家をよく見ておきなさい。」
エルフはその様子を眺めていたが、竜也のもっていた写真を手に取った。
「きれいな人でしたね。残念です。」
竜也は、たくさん持ってきたからと言って、エルフに梢の写真を2枚渡した。
「シュテマーさんは何処かへ引っ越したの?」
芝生の庭をニーツォルト家に引き返しながら、竜也はエルフに質問した。
「いえ、亡くなったのですよ。奥さんと離婚して暫く此処に住んでいたのですが、ガンにかかって。」
「えっ、まだ若かったでしょ。」
「52歳でした。とてもいい人だったので残念です。コズエもそうですが、いい人は若くして亡くなりますね。」
リビングではエリカがコーヒーを入れて待っていた。お手製のクーヘンを御馳走しようと張り切っていた。竜也は勧められるままに1切を手に取り口に入れた。想像していた通り、とても甘かった。亜希子も1つ摘んだが、2つ目には手を出さない。
竜也は成田で買ってきた手土産を渡した。日本の風景や人形がデザインされた煎餅だった。駐在時代の経験から、竜也はドイツ人が日本の煎餅やおかきを好むのを知っていた。
ニーツォルト家を1時間ほどで辞去した2人はホテルに帰った。亜希子は昔の友人と夕食の約束があると出て行った。竜也はホテルでアレックス・リーを待った。竜也がドイツに駐在したとき最初に雇ったアメリカ人のアドバイザーである。竜也は駐在員としての要諦をリーから学んだ。
「日本人駐在員はいつも東京の本社に顔を向けているが、それは間違いだよ。駐在員は会社を代表する存在だから、いつもカストマーに顔を向けていなければならない。駐在員はカストマーの味方で、敵は東京本社だと心得よ。」
リーは、ことあるごとに竜也に説いた。竜也が駐在員として本社とは距離を置くように心がけたのはリーの影響からであった。
約束の時間に少し遅れてリーがやってきた。
「イッツ・ユアー・タイム!」(キミの時間に来たよ。)
十数年振りに会ったリーは、腕時計を指しながら第1声を放った。
1924年生まれのリーは、今年84歳になったはずだ。頭髪が少し薄くなったのと、以前より少し太った以外は昔のままであった。
「オクサン、とっても気の毒でした。コズエはホントにナイス・レディーだったのに。」
リーは英語と日本語をチャンポンにして梢の話から切り出した。
竜也は梢の遺影の1枚を取り出してリーに渡した。
「記念に差し上げます。」
「素晴らしい写真だ。少し微笑んでいるところが梢らしい。有難う、大切にするよ。」
リーは写真の梢に愛おしそうに口づけをしてからジャケットの胸にしまった。
その夜、リーは竜也の好きだったという中華レストランに竜也を案内した。リーは竜也との再会がよほど嬉しかったとみえて、以前にも増して饒舌だった。運ばれてくる料理に1皿ずつコメントを加えるのも以前と変わらなかった。
リーは2度結婚したが、2度とも離婚している。最初の奥さんとの間に5人の子供がある。別れた奥さんのこと、子供たちのこと、今の生活などを竜也に語って聞かせた。竜也も問われるままに会社のこと、娘たちのこと、学習塾のことなどを率直に話した。
他の客が誰も居なくなって、2人は店をでた。亜希子にも是非会いたいとリーがいうので、サボイ・ホテルに帰り、ロビーで亜希子の戻るのを待った。11時ごろになって亜希子が現れた。2人は初対面同然のはずだが、古くからの知己のように挨拶した。握手に続いて抱き合ってハグ。アメリカ式の挨拶は日本人には馴染まないが、亜希子はアメリカでの経験からスムースにこなした。
リーはミシガン大学を卒業しているので、亜希子の先輩に当たる。そのことも2人の会話がはずむ要因になったようだ。竜也は暫く黙って2人が喋るのを聴いていた。
「リーさんって、面白いお爺ちゃんだわね。」
リーの車が走り出したのを見届けて、亜希子がつぶやいた。
「明日は早いからもう寝るか。」
竜也は亜希子と別れて自室に戻った。今日1日で梢の想い出の場所にも行ったし、懐かしい人とも会えた。竜也は、残った梢の写真の1枚を枕元に置いてベッドに入った。
![]()
「介護日記ーその後」にもどる
![]()
「白い闇」第51章に進む
![]()
トップページへ戻る