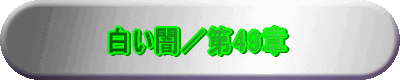
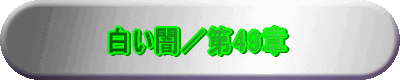
出発の日、竜也は成田空港で亜希子と待ち合わせた。今まで、美佐子と2人で神戸に旅行したことはあるが、自分の娘と2人で長期旅行に出かけるのは竜也にとって始めての経験であった。
亜希子が大きなスーツケースを転がしながらやってきた。2人は全日空のカウンターに並んだ。現役時代はビジネス・クラスだが、引退した身では当然エコノミー。だが、竜也は、スーパー・フライヤーズ・カードを持っていたので、空いているファースト・クラスのカウンターに並んだ。
係員に航空券とカードを渡すと、意外にも嬉しい対応があった。
「本日は、エコノミーは満席ですが、ビジネスにはかなり空席があります。宜しければ、お連れ様と御一緒にビジネス・クラスにアップ・グレードさせて頂きますが。」
「わーい、ラッキー! お父さんと一緒だとこういうことがあるのね。」
横から覗き込んでいた亜希子が大声を出した。竜也は、スーパー・フライヤーズの思いがけない威力に少なからず満足した。
10分後、竜也は全日空のシグネット・ラウンジにゆったりと腰を下ろし、コーヒーを飲みながら新聞に目を通していた。横では、亜希子が興奮気味に辺りを見回していた。
「あたし、国際線のラウンジなんて初めてだもんね。お父さん、そのカードがあれば帰りもビジネスなの?」
「そんなわけには行かないよ。偶々ビジネスに空席があったからサービスしてくれたけど、帰りはダメだろうよ。」
「片道だけでもいいや。機内の食事が楽しみだな。」
「これで、タバコが吸えると申し分ないのだけどね。」
「海外旅行はスモーカーにとっては試練だわね。ホテルも禁煙かもよ。」
「ホテルの部屋は、亜希子と一緒なの?」
「経費節約のためにそうしようと思ったけど、お父さんはタバコは吸うし、イビキもかくからミュンヘン以外は2部屋にしてあるわよ。ミュンヘンはとても高いから1部屋。」
飛行機以外の手配はすべてお任せだったので、竜也はどんなホテルに泊まるのかも知らなかった。
「デュッセルのホテルは、お父さんが頼んだのよね。」
「そうそう、会社のドイツ支社に頼んだから立派なホテルかもしれないよ。2部屋手配したと連絡があったよ。」
「レンタカー、大丈夫かな。ミュンヘンのホテルの近くで手配したのだけど。」
「ナビはついているの?」
「一応、ナビ付きとは言ってあるんだけど・・・ ナビがないと何処にも行けないから。お父さん、左ハンドルは平気なの? あたしは自信ないからね。」
「最初は少しまごつくかもしれないけど、慣れれば大丈夫だよ。ドイツでもアメリカでも運転してたし・・・」
出発時刻が来て2人はジャンボ機に乗り込んだ。流石にシートはゆったりしていた。離陸後、暫くして食事が出た。竜也も亜希子も和食を頼んだ。亜希子は、運ばれてきたトレイを珍しそうに眺めていたが、思い出したようにバッグからカメラを取り出して写真を撮った。
「そんなもの、写してどうするんだい?」
「食事は主婦の最大の関心事ですからね。出てくるものは全部撮っておこうと思って・・・」
食後、竜也はシートに備え付けのビデオで映画を見ていたが、やがて眠くなって眠ってしまった。タバコが吸えないので、大脳から早く眠るように指令が出されるらしい。
夏場は、日本とドイツの時差は7時間。日本時間の昼前に成田を出発し12時間かけてフランクフルトに着いたが、現地ではまだ同じ日の夕方であった。その日は、フランクフルト中央駅の近くに泊まり、翌朝、列車でデュッセルドルフに行くことになっていた。
竜也は20年以上も昔の記憶を辿りながら、フランクフルト空港の地下に降りて電車に乗った。そこから中央駅までは1本で行ける。電車は1時間足らずで中央駅についたが、ホテルを探すのに手間取った。特に、亜希子は石畳の道路を大型のスーツケースを転がしていくので容易ではない。途中、雨が降りだして慌てたが、小雨だったので何とか濡れずにホテルについた。
ドイツの夏は昼が長い。外は9時ごろまで明るい。ホテルで一休みしてから、竜也と亜希子は街に出てみた。レーマーと呼ばれる中心部には多くの観光客の姿があった。広場にはたくさんの雨よけテントが張られ、中は、オープン・レストランになっている。ドイツに限らず、ヨーロッパでは夏場は外で食事をするのが好きらしい。
その中の1軒に入って、ソーセージとパンの軽い食事を取った。竜也が嬉しかったのは、オープン・レストランでは自由にタバコが吸えることであった。
「食事は、毎日、外がいいな。」
竜也は冗談半分に言ったつもりだったが、実際に旅行期間中は朝食以外すべて屋外レストランで食事することになる。
翌朝、中央駅からICと呼ばれる特急列車に乗った。亜希子がデュッセルドルフまで飛行機ではなく列車を手配したのは、ライン河畔の景色を楽しむためであった。竜也が駐在していた頃は、列車はライン河に沿ったルートしかなかった。ところが、竜也たちを乗せたICは一路山の中を走った。新しい幹線が出来たらしい。2時間あまりで着いたものの、殆どがトンネルで外の景色は全く期待はずれに終わった。
「こんなことなら飛行機で行けばよかったね。」
「だって、こんな幹線があるなんて知らなかったもの。」
亜希子も些か不満げな表情であった。
デユッセルドルフの初日、亜希子と竜也は別行動を取ることにしていた。手配してもらったサボイ・ホテルは町の中心部にあった。ホテルに着いた後、亜希子は昔の友人と会うために出かけていった。竜也は山口工業の駐在員と昼食をともにすることになっていた。
竜也の頃は駐在員事務所だったが、今は現地法人化され、GmbHと呼ばれる株式会社組織になっていた。社長の広末と部下の星山が竜也をサボイ・ホテルに出迎え、別のホテルにある日本食レストラン『弁慶』のテーブルを挟んで向かい合った。
広末と星山を前にして、“2人とも若い”と思った。だが、考えてみれば竜也も当時は40の手前だった。恐らく今の広末よりは下だったはずだ。70に手が届きそうな竜也から見ると40代はとても若い。その分、どうしても頼りなさそうに思えるのだが、それが会社の新陳代謝なのだろう。老兵は消え去るのみ。次々に若い人が支えていくのが会社のあるべき姿なのだ。竜也は真剣に2人の話に耳を傾けた。
午後、昔からの友人・高村と会った。高村は竜也がデュッセルドルフ駐在時代、S産業の駐在員だった。高村の話は理屈が通っていて面白いので、よく一緒に食事をした。その時、高村は既に駐在暦10年を超えていた。ドイツ人の奥さんとの間に2人の娘がいた。
その後、高村は定年でS産業を退職して、自分でコンサルタント会社を開いた。長年のドイツでの経験を活かして、ドイツ企業と日本企業の仲立ちをする仕事である。
商社のOBは、メーカーの人間をよく知っているのだが、意外に同業の商社マンを知らない。竜也は高村の依頼で、日本商事の機械部の何人かを紹介したことがある。トルコのラクタムプラント以降、日本商事の機械部門では竜也は有名人になっていた。
高村は大きな仕事はS産業ではなく日本商事と組んだ。弱小のS産業では十分なフォローができないと判断したらしい。
「日本商事さんは、やはり、S産業とは全然違いますね。商社のプロという感じがします。」
ことあるごとに高村は竜也にそう漏らしていた。
久し振りに再会した高村は、竜也を自分の車に乗せてデュッセルドルフ郊外に連れ出した。行き先はメアブッシュ・オストラート。意外にも、竜也の住んでいた家の近くである。高村はそこに1軒の家を持っていた。高村の本拠は横浜だが、ドイツには度々出張するので、奥さんの名義で家を買ったという。夫婦の寝室とリビングだけの家だが、高村はそこを仕事場に使っていた。いわゆるSOHOである。
高村は竜也に自分のSOHOを見せたかったようだ。パソコンと電話だけが置かれたリビングは、情報化時代に入った現在では立派にオフィスとして機能する。高村は年に数ヶ月は、こちらで仕事をするという。まさに、日本とドイツを股にかける活躍だ。
高村の家を出てから、竜也たちは車でオストラートの林の道を奥に入っていった。竜也の知らない場所であった。30分ほど北に走ると、車はライン河のほとりに出た。河の西岸になる。
林を切り開いた草原には瀟洒なホテルがあり、たくさんの車が停まっていた。ホテルの看板にはドイツ語で「フィア・ヤーレス・ツァイテン」と書かれていた。フォーシーズン・ホテルの経営らしい。
「へえー、こんなとこ全然しらなかった。前からあったの。」
「中野さんの居られたときからありましたよ。」
高村は竜也がこの場所を知らなかったのが意外だという顔をした。
2人はホテルの石段を上がり、庭を一望できる、テラスの食道に座った。
庭ではガーデン・パーティがあるのか、緑の芝生の上に通路の赤いじゅうたんが敷かれ、あちらこちらにビール樽が置かれていた。幾つかのテーブルの間を白いシャツに黒ズボン、蝶ネクタイをつけたボーイさんたちが、グラスを載せたトレーを片手で運びながら忙しそうに動き回っていた。空は青く澄み渡り、鳥のさえずりが聞こえた。暑くもなく、寒くもなく頬を撫でる風が心地よかった。空気が美味しい、と竜也は思った。
「結婚式でもあるのかもしれませんね。」
高村が、メニューからをそらした目を庭の方に向けて言った。
「オストラートにこんなところがあったとはね。流石は高村さんだね。ところで、高村さん、娘さんたちはどうしているの。」
「2人ともドイツにいますよ。最初は一緒に住んでいたのですが、今は別々です。1人は北、1人は南です。」
「で、何をしているの。」
「2人ともデザイナーです。雑誌のデザインや本の装丁をやっています。上の娘はドイツ語の本も出していますよ。」
竜也は末娘の悦子を想い出した。悦子も雑誌の制作の仕事をしている。趣味の切手コレクター用の雑誌だった。一度、高村の娘さんに引き合わせてやりたい、と竜也は思った。
「食事の後、フェリーで対岸に渡ってみましょうか。」
突然の提案に竜也は怪訝な表情を見せた。
「フェリー? こんなところにフェリーがあるの?」
「ありますよ。ここの客の殆どは対岸のカイザースベアートから来ています。あちらのレストランは値段が高いですから。」
「そうか、ここはカイザースベアートの対岸になるんだ。」
竜也は驚きの声をあげた。
カイザースベアートはデュッセルドルフ郊外の古い町で、竜也も何度か行ったことがある。ライン河の東岸を北上して行くと雄大な草原に囲まれた、古い城跡のある小さな町に出る。そこがカイザースベアート。城は12世紀にフリードリッヒ大帝が建てたものだと聞いた。
そんなところにフェリーの渡しが運行していることを竜也は全く知らなかった。
高村との楽しい夕食を終え、高村の車でそのままフェリーに乗り込んだ。フェリーは10分足らずで対岸についた。車が走り出すと、カイザースベアートの小奇麗な町並みが左右に広がった。竜也は古い記憶の一端を引きずり出されたような気分で窓の外を眺めていた。
サボイ・ホテルまで送ってくれた高村に竜也は丁寧にお礼を言い、車を降りてホテルに入った。その日の夜は亜希子と2人で野外コンサートに行くことになっていたが、亜希子はまだ戻っていなかった。竜也は自室のベッドに横になって昼間のことを思い出していた。
8時頃ベッドサイドの電話が鳴った。亜希子からだった。
「帰ったわよ。コンサートは9時半からだから、そろそろ出発した方がいいと思う。」
「そうだね。ロビーに降りていくよ。寒いかもしれないから暖かい格好で行く方がいいよ。」
「そんなこと言ったって、上はジャージしかないわよ。」
竜也は電話を切って、自分の着ていくものを考えた。だが、夏物スーツに薄手のベスト。うだるような日本から来るのに、それ以上のものは持ってこなかった。
野外コンサートは、市の南にあるベンラート城の噴水庭園で行われる。「真夏の夜の夢」とタイトルがついているだけに、日が暮れてから花火や照明でファンタジックな雰囲気を出すらしい。
竜也と亜希子は市の中央から市電に乗った。ベンラート城までは約30分かかる。竜也はこの城には以前何度も日本からの客を案内したことがあった。デュッセルドルフは歴史的にはそれほど古くない。もっとも、先史時代には市の東10kmにあるネアンデルタールで原始人が住んでいたとされるが、デュッセルドルフの町づくりが始まるのは12世紀以降のこと。ベンラート城は18世紀の建築だが、ロマネスク調の外壁と広大な噴水庭園はデュッセルドルフの貴重な観光資源になっていた。
コンサート会場に着いたときは未だ周囲は明るかったが、気温は急速に下がり始めた。
驚いたことに、集まったたくさんの観客は例外なく防寒具に身を固めている。竜也たちのように夏服で来ている人の姿はなかった。噴水池の周囲には無数のパイプ椅子が置かれ、それぞれに座席指定の番号が貼ってある。竜也たちは震えながら所定の席に腰をかけた。
9時半、特設テントの中のオーケストラが演奏を始め、花火が打ち上げられる。同時に薄暗くなった空に向かって4本の大噴水が一斉に吹き上げると、5色のライトが水を照らした。確かに「夜の夢」ではあったが、真夏というにはあまりにも寒い。
10時を過ぎる頃には竜也の身体は完全に冷え切っていた。体感温度は10℃以下。昼間とは20℃近い差がある。竜也の隣でジャージ姿の亜希子も震えていた。
「こう寒くてはどうしようもない。帰ろうか。」
竜也が提案すると亜希子も二つ返事で同意した。2人は始まったばかりの会場を後にしてホテルへと急いだ。
明日は、センチメンタル・ジャニーの本番、30年前の我が家を訪問する予定になっている。風邪を引いてはいけないと、竜也は早めにベッドにもぐりこんだ。
![]()
「介護日記ーその後」にもどる
![]()
「白い闇」第50章に進む
![]()
トップページへ戻る