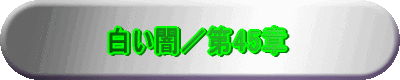
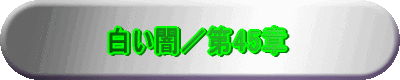
2007年後半、梢の容態は比較的安定していたが、竜也には梢の気力が徐々に失われていくように思われた。病院のベッドから竜也を見上げる目には以前のようにキラリと光るものはなく、何時も弱々しくどんよりと曇っていた。
枕元のラジカセで琴の名曲をかけても、梢の大好きだった『タラのテーマ』を聞かせてやっても殆ど反応を示すことはなかった。
9月初めに竜也は美佐子を連れて神戸に帰省した。六甲山の麓には両親の眠る墓がある。母が健在だった時分、墓参は母の仕事と決めていた。が、その母も8年前に他界し、今は父と同じ墓の下に居る。1人息子の竜也には、墓を守る責任があった。
梢も自分も、いずれ、この墓に入ることになる。竜也は墓参にはなるべく娘たちと一緒に来ることにしていた。
毎年、お盆の前後に里帰りすると、霊園を訪れて墓にお参りし、一泊して翌日東京に帰るというスケジュールだった。美佐子と一緒のときには、これに甲子園でのナイター見物が追加された。
竜也も美佐子も大のタイガース・ファン。縦縞のユニフォームに着替えて、虎バットと呼ばれる黄色いメガホンを手に声援を送る。
甲子園の熱気には独特のものがある。4万の大観衆の9割以上がトラキチ。応援団のリーダーに合わせて一糸乱れぬ声援を送る。竜也は大観衆の興奮との一体感が好きだった。学生時代、安保反対のデモに参加したときの昂ぶりと似たような高揚感を覚えた。
帰省とはいえ、実家は先の震災で倒壊して既にない。いつもは大阪市内に宿を取るのだが、今回は、三宮駅構内にあるホテルに宿泊した。
竜也は朝5時ごろに目を覚ました。昨夜のタイガース勝利に酔いしれた美佐子は未だグッスリ眠っているようだった。早起きの苦手な竜也には珍しいことなので、早朝の神戸の街を少し散策することを思い立った。
ホテルを出ると、足は結婚前に梢とよく歩いた北野町の方向へと自然に向かっていた。震災の後、街並みはすっかり変ってしまって、まるでエトランゼのようだ。おぼろげな記憶だけを頼りに、山に向かって歩き出す。街には殆ど人通りがない。くすんだ色のゴミ収集車だけが忙しそうに動いていた。
『東門街』という表示が見えた。この通りの名前はよく憶えている。だが、周囲は知らない店ばかりだ。よく通った喫茶店やスナックは見当たらず、代わりに、今では何処にでもある外食店や消費者金融のビルが軒をつらねている。
東門街を北上すると中山手通りに行き当たる。その角に『フロインドリーブ』という看板を見つけた。古くからあるドイツ人のパン屋さんだ。
記憶の正しかったことを確信して坂道を上っていく。以前は何ということもない坂道だったが、今では『ハンター坂』という立派な名前がついている。坂を上りきると『山本通り』だ。此処も『異人館通り』と仰々しく名付けられている。
以前、NHKの朝のドラマで北野町から山本通りにかけての異人館が取り上げられて以来、この辺りは神戸の新名所になっているらしい。そういえば、外見の立派な洋館はよく手入れされていて、『○○邸』と表示が出ている。
竜也は無意識のうちに、ある建物を求めて異人館通りから左に折れる細い路地に入った。
高校を卒業して、竜也はロシア語を学んだ。会話を習得するためロシア人の先生を求めて、山本通りを歩き回った。そこで、『白系ロシア人組合』という建物を見つけ、そこの物置で暮らす孤独なお婆さんに先生をお願いした。
名前をマリヤ・マカロヴァという。学生最後の年に、レニングラード旅行で出会ったジプシーの老婆に似た、あのマカロヴァさんである。2年間ほど通った。
マカロヴァさんは元・白系ロシアの貴族だが、ロシア革命で追われて家族とは離れ離れになり、命からがら日本に逃げてきたという。当時、既に80歳を過ぎていて、孫の齢の竜也を自分の息子ように可愛がってくれた。が、彼女はやがて淋しく世を去る。40年以上も前の話だ。
その彼女が、突然、記憶の中に現れて竜也を呼んでいるような気がした。竜也は、白系ロシア人組合の白い異人館を探そうと、この路地に入ったのだ。古い記憶をたどりながら行き着いたその場所に異人館の跡はなく、新しいマンションが立ち並んでいた。
『入居者募集』と書かれた立て札に記憶をさえぎられ、竜也はハンター坂をホテルへと引き返した。
三宮駅では、7時前なのにラッシュが始まっていた。大勢の人がそれぞれの方向に急ぎ足で歩いていく。竜也は、何故か40年前のともだちの姿を探そうとして暫くその場に立ち尽くした。白い異人館を発見できなかった代償を昔のともだちの姿に求めたのかもしれない。
当然ながら、駅の群集の中にともだちの顔はなかった。足早に過ぎ去る大勢の見知らぬ人たちの中に取り残され、神戸が自分の郷里ではなかったような錯覚に捕らわれた。矢張り、故郷は「遠くにありて思うもの」なのだろうか。だとすれば、昔のともだちも心の中だけに留めておくのがよいのかもしれない、と竜也は思った。
ホテルを出た竜也は美佐子を連れて、東灘にある実家跡へ向かった。震災の後、竜也は、一時、ここにバリアフリーの家を建てて障害者となった梢と2人で暮らすことを真剣に考えた。だが、梢が再び倒れて入院してしまうと、その計画も消えた。
神戸に帰るという選択肢がなくなった以上、90坪近い土地を保有していても仕方がない。父が折角残してくれた財産だが、この土地を売りに出すことに決めていた。だから、人手に渡る前に、もう一度、この場所をしっかり脳裏に焼き付けておきたかった。
家は更地になってしまったが、石塀と玄関は残っている。玄関の前に立つと、年老いた母の姿が脳裏に浮かんだ。
鉄平石の門柱に朽ちかけた木の表札がかかっている。その横にある呼び鈴を押して暫く待つ。冠り松の向こうで、門灯に照らされた玄関の扉が開いて、年老いた母が石段を降りてくるのが見える。背中が曲がっているのでバランスを取るのであろう、腹を突き出して不恰好な姿で歩く。
やがて門扉の閂の滑る音がして、扉が開く。
「お帰り。遅かったね。」
いつもの母の第一声だ。
玄関に入ると懐かしい犬の臭いが鼻をつく。上がり框では、柴犬のカロがちぎれるほど尻尾を振って待っている。大きく口を開けているのに鳴き声は小さい。きっと、大声で鳴くと叱られるのであろう。
靴を脱いでスリッパに履き替えると、先ず、カロがカタカタと廊下に爪音を立てて走り出す。竜也を案内してくれるらしい。振り向くと、危なっかしい足取りで母がついてくる。少しゆっくり歩いてほしいと懇願するかのように、声がかかる。
「ご飯にする?」
掘りごたつの食卓の席は決まっていて、亡くなった父の席が正面にあり、今でも座椅子に厚手の座布団が敷かれている。四角い食卓の火鉢を挟んだ右隣が竜也の席だ。
上着を脱ぎ、席について夕刊に目を通す。タバコを1本吸い終えた頃、母が暖かい夕食をお盆に載せて運んでくる。横から見ると、歩く姿はS字型に近い。
メニューは、ロールキャベツと大根煮。それに、油揚げとネギの味噌汁や好物の柴漬けもある。以前、美味しいと褒めたことがあって以来、いつ帰っても同じものが出るようになった。
竜也は大学を卒業すると同時に神戸の実家を出た。父が74歳で他界してからの母は、広い家に1人暮らしとなった。毎日、犬だけが母の話し相手だった。時折、思い出したように帰ってくる1人息子に手料理を御馳走することは、母の最大の楽しみだったかもしれない。
その実家も阪神大震災で倒壊してしまった。父の自慢であった陶磁器のコレクションや母が描いた趣味の油絵などは殆んど失われた。カロも行方が知れなかった。
不幸中の幸いと言おうか、母は直前に大腿骨骨折で入院していたため難を逃れた。だが、震災後は、すっかり弱ってしまった。
歩行困難になった母を東京に引取り、体の不自由な梢と、車椅子2台の生活が始まった。が、子供たちの協力を得てもなお、限界に近かった。母には納得づくで千葉の老人ホームに入ってもらった。
ロマンチストで、社交性の乏しい母にとって、ホームでの生活は辛かっただろう。竜也が見舞いに行くたびに、神戸に帰りたい、と訴えた。
その母も、8年前に亡くなった。東京で葬式を済ませたが、お骨は、神戸に持ち帰った。
墓参に帰るたびに、竜也は、更地になってしまった神戸の実家に立ち寄る。松の木は枯れてしまったが、石の外塀と鉄製の門扉だけは当時のままだ。そこに立つと、玄関を開けて石段を降りてくる背中の曲がった母に会える気がする。
東京に帰って間もなく、台風9号が近づいているという。この年は台風が少なく、関東地方に上陸したものはなかった。だが、今回は違っていた。
9月6日、東京地方では横殴りの豪雨。病院に行く途中、車のワイパーを最大速度にしても水しぶきを拭い切れず、前方が殆ど見えない。まるで、滝の下を走っているようだ。
病室の窓ガラスにも激しい音を立てて雨が襲いかかっていたが、梢はわれ関せずと眠っていた。梢は夢を見ることができるのだろうか。夢の中なら自由に飛びまわることができる。4年半もベッドから離れられない梢にとっては、夢の中が幸せの世界かもしれない。梢の夢に竜也は登場するのだろうか。その日は、梢を起こさないようにして病院を後にした。
翌朝、竜也はリビングの窓のカーテンを開けて驚いた。多摩川の河川敷が見えない。こちら側は窓の直ぐ下の堤防まで水が来ている。川崎側も河川敷の上を濁流が凄い速さで流れている。川幅は一挙に1kmほどに広がった。多摩川が一夜にして揚子江になったような錯覚にとらわれた。
梢が居なくてよかった、と竜也は思った。幼い頃、ジェーン台風が神戸地方を襲い、住吉川が決壊した。濁流は竜也たちの住む住宅街にまで流れ込んだ。そのことが梢のトラウマになっていた。もし、意識のある梢がこの場に居合わせたら、恐怖のあまり泣き出したかもしれない。
台風が通過すると雨は上がり、午後には河川敷の水も引き始めた。やがて、西の空は素晴らしい夕焼けに変わった。赤く染まった太陽が河川敷に残った水に映えて、ゆっくりと山の端に沈んでいく。竜也はベランダに出て、デジカメのシャッターを何度も押しながら、今度は、梢が居ればよかった、と思った。
![]()
「介護日記ーその後」にもどる
![]()
「白い闇」第46章に進む
![]()
トップページへ戻る