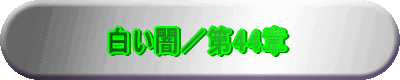
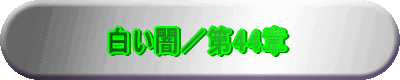
2007年6月、竜也は8年間住み慣れた南雪谷のマンションから転居することにした。特に不満があったわけではない。逆に、マンションの環境、雪谷の街並み、駅からの距離など、すべてにおいて竜也は大いに満足していた。それでも転居を決めたのには、幾つかの理由がある。
第1は経済的な理由だった。山口工業を引退して年金生活者となった以上、贅沢な生活は望めない。梢が入院してしまうと、悦子と2人で4LDKの広いマンションは無駄のように思われた。しかも、2,000万円以上のローンが残っている。
現在のマンションが新しいうちに売却し、安い物件を捜して、住み替えの差益でローンを返済してしまいたい。
阪神大震災で倒壊した神戸の実家からサルベージしてきた家財を運送会社のトランクルームに預けたままになっていた。10年以上も毎月2万円余りの保管料を支払っている。これも無駄な出費だ。この機会に、家財道具を大整理してトランクルームのものも引き取るか、処分するか白黒をつけてしまいたい。
第2の理由は、末娘の悦子に自立を促すことにあった。美術大学を卒業し、一応、デザイナーの卵として働いている。このまま一緒に生活していては、何時まで経っても親離れできないのではないか。悦子としては、独立することを望んではいたが、年老いた父をケアするのは自分の責任だという意識があった。だから、竜也が1人で暮らすことに反対した。
一方、隣のワンルーム・マンションに居た長女の恵子は、前年、既にマンションを出て、蒲田で次女の美佐子と一緒に暮らしていた。だが、恵子は従来からアメリカで独り立ちしたいという強い願望があり、単身アメリカに渡る計画を着々と進めていた。
転居は娘たちの希望をかなえるためにも有効であった。つまり、長女の恵子はアメリカへ、次女の美佐子は竜也と同居、末娘の悦子は1人暮らしするということで、問題は一挙に解決できる。
転居に際して、竜也は梢が戻ってくるケースも考慮に入れた。少なくとも梢のベッドを置く1室だけは確保しておきたかった。梢が回復するという可能性を信じたわけではないが、このまま死ぬまで病院のベッドから離れられないというのは如何にも不憫に思われた。
竜也と美佐子は学習塾の近くに適当なマンションを探したが、なかなか見つからなかった。羽田に気に入った物件があったが、先約に取られてしまった。仕方なく、少し半径を拡げて探すことにした。
ある日、下丸子の多摩川べりの古いマンションに空室があるというので、不動産屋につれられて内見に出かけた。
リビングに足を踏み入れた途端、竜也は思わず息をのんだ。
7階のベランダから見下ろす雄大な景色。視界を遮るものは何もない。眼下には悠々と流れる多摩川。河川敷では子供たちが野球をしている様子が胡麻ツブのように見える。川向こうは川崎市だろう。夕陽を受けた白いビル群がマシュマロのように輝いている。
これこそ終の棲家ではないのか!
案内の不動産屋が並べる宣伝文句を聞き流しながら、竜也は全く別のことを想像していた。リビングの揺り椅子に深々と身体を沈め、コーヒーカップを手に、ぼんやりと窓の外を眺める。BGМにはベートーベンの交響曲6番が流れる・・・・
70歳が近づいてくると、視力は落ちるし聴力も衰える。できることなら、残る人生、本物を見、本物を聴く機会を増やしたいと思う。クラシックのCDなら今のマンションでも聴けるが、窓を開けると隣の軒先が目の前に迫ってくる環境では本物を見ることはできない。
眼下を流れる多摩川はまさに本物だ。あの悠久の流れは本物に違いない。
もし梢がこの景色を見れば、あの笑顔を取り戻してくれるかもしれない。
交通の便は悪く、生活の快適さも失われるだろう。だが、窓の外には1年365日、本物の眺望が待っている。
人は「老い」を避けることはできない。それでも、可能ならば美しく老いたい。そのための条件は、本物を見、本物を聴くこと、ではないだろうか。
あのマンションで、毎日窓の外を眺めていると美しく老いることができるような気がする。
帰路、不動産屋の車の中で竜也の決心は既に固まっていた。竜也は隣のシートの美佐子の耳元で囁いた。
「あそこに決めよう。」
美佐子も大きく頷いた。
下丸子のマンションに引越しを終えて、竜也は快適な住まいにするため、これまでダンボールにしまってあった装飾品を取り出した。幸い、リビングが広いので、ドイツ時代に集めた絵皿や磁器の置物をバランスよく配置した。
トランクルームから引き上げた、神戸の実家の家財からは、多くの小物家具が出てきた。その中に父の集めていた土鈴があった。土鈴は父の晩年のコレクション。各地の神社で買い求めたものが、実家の応接間にところ狭しと、並べてあった。だが、大半は震災のときに割れてしまった。竜也は破損のないものを掘り出して、いくつかをトランクルームの荷物に入れておいた。
10年振りに陽の目をみた土鈴を眺めていると、懐かしさがこみあげてきた。竜也は父に対する敬意の気持ちを込めて、いくつかの土鈴を和室に飾ることにした。
インテリアを決める上で竜也が最も迷ったのは、玄関の正面に掛ける額を何にするかであった。当初は安井曽太郎のバラのリトグラフを飾ってみた。が、結局、母の描いた油絵を掛けることにした。
100号のキャンパスのほぼ下半分に、真っ白な雪が描かれている。上半分は青空だが、淡い色調だ。中央には、空と雪を結ぶかのように一本の大樹が葉を落とした枝を四方に伸ばしている。
後の雪原では、小さな潅木がところどころに集まって、遠慮がちに枝を空に向け、自分たちが脇役であることを自認しているかのようだ。
大樹の左には、ガーデンチェアが置かれ、鉄の背もたれの上に、私こそが主役ですといわんばかりの格好で1羽の鳥が中央にクチバシを向けて止まっている。雪を背景にシルエットで描かれているのでよくは分からないが、青みがかった大型の鳩のような鳥だ。
静まりかえった雪原に舞い降りた1羽の青い鳥が、夕のしじまを破って、森のメルヘンでも語っているのだろうか。
『冬の詩』とタイトルがつけられた油絵は、亡くなった母の遺作だが、ここに来るまで様々なところを渡り歩いた。
20年ほど前、藤代から小平の家に転居した機会に、たくさんある中で、竜也が1番好きだったこの画を母がプレゼントしてくれた。
その後海外勤務などで移動の多い時期が重なり、『冬の詩』は朝霞の美佐子のアパートの物置や恵子の嫁ぎ先など点々と場所を変えた。阪神大震災で神戸の実家は無残にも倒壊。母の油絵もすべて泥の中に埋もれてしまったが、既に持ち出されていた『冬の詩』だけは難を逃れた。
母の晩年には、入居先の老人施設に寄贈され、食堂に架けられていた。だが、母の死後、恵子が祖母の形見にとこの画を引き取って、自分のアパートの狭い部屋に無理やり飾っていた。
しかし、アメリカに移住することになった恵子は、流石に100号の画を持っていく訳にはいかないと、竜也のもとに返されてきた。
生来ロマンチストの母は、少女時代に当時まだ珍しかったピアノを始めた。女学校の卒業式では皆の前で『月光』を弾いたと聞く。女専では国文科に進み、文学に興味を向けるようになる。
自分の想いとは裏腹に平凡な見合い結婚をしてからは、内に秘めたロマンを短歌や俳句に吐露していたようだ。が、限られた文字では物足りなかったのか、竜也が小学校3年のときに画を始めた。40の手習いだったが意外に長続きし、竜也が大学に入った年の秋、二科展に初入選した。
母は実家の8畳の和室に続いた縁側をアトリエ代わりにしていて、ところ構わず絵の具のチューブが散らばっていた。その頃から家に帰ると、いつも油絵の具の匂いがしていたのを想い出す。
『冬の詩』は1985年の作品で、某美術出版社から賞を受けたものの、母としては必ずしも自信作ではなかったようだ。この画の話になると、「あんまり上手に描けてないやろ。」と、本心からか照れからか、決まってそう言うのだった。
竜也は、この画を玄関の入口の壁に掛けることにした。今度のマンションは、竜也にとって終の棲家だが、『冬の詩』も漸く安住の地をみつけたことになる。ついでに、引越しの際の廃棄荷物の中から油絵の具のこびりついた母のパレットを拾い上げ、自室の壁に飾った。そのためか、美佐子と2人暮らしの生活を母が見守ってくれるような気がする。
今度のマンションに移ってから、竜也には毎日の楽しみが1つ増えた。それは、多摩川の向こうに沈む夕陽。天気のよい日には丹沢の山々がくっきりと見え、その中央に富士山がそびえる。真紅の日輪がゆっくりと山の端に沈んでいくと、赤く染まった空に黄金の雲が輝く。大自然の織りなすドラマを一度でいいから梢にも見せてやりたい、と思うようになった。
テラスの椅子に腰を下ろした梢は、「すげえなぁ!」を連発し、沈み行く夕陽に照らされた顔を竜也に向け、ニッコリと微笑む。4年前、竜也の幸せの構図は、梢の車椅子を押しながらスイスの山を散策することであった。だが、今では、それは自宅のベランダから梢と一緒に夕陽を眺めることに替わっていた。
![]()
「介護日記ーその後」にもどる
![]()
「白い闇」第45章に進む
![]()
トップページへ戻る