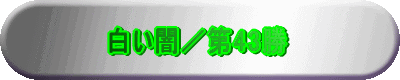
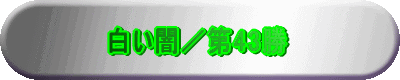
3月に入ると、竜也の周辺は慌しくなった。梢はその後小康を保っているので一安心だが、自宅で飼っている老猫のミーニャが危なくなってきた。たかがネコという気もするが、ミーニャは梢の1番の友だちだった。
18歳というのは人間にすれば100歳近いかもしれない。だが、ミーニャは5番目の娘として、梢の帰りをずっと待っているように思われた。
18年前、庭の片隅に迷い込んだ真っ白な仔猫を梢が抱き上げた。手のひらに載るほど小さかった。子供たちが仔猫を囲むように覗き込んだ。仔猫は顔中を口にしてニャーと鳴いた。
子供たちから一斉に歓声が上がった。長い尻尾を器用に動かしながら、縁側に置かれた小皿の牛乳をむさぼるように飲んだ。その瞬間、子供たちは自分の家に家族が増えたことを、仔猫は漸く安住の地にたどり着いたことを確信した。
ネコは家につくというが、ミーニャは5度の引越しにも決して迷うことはなかった。アメリカまでもついてきた。子供たちが独立して、家族が1人減り、2人減り、だんだん淋しくなっても、ミーニャだけは、中野家に君臨していた。
潔癖症の梢は生来あまり動物が好きではなかったが、病に倒れてからは、ミーニャをとても可愛がるようになった。ミーニャも梢になついた。
梢が食事をするときには、ミーニャは当然のように食卓に上がって、梢の皿の直ぐ横に正座した。御主人が魚の切り身を少し分けてくれるのを大人しく待つのだった。梢は、意味不明の言葉を並べながら、自分の皿から左手のフォークを器用に動かしてミーニャの前に少し分け前を置いてやる。
以前の梢なら、テーブルに登って来ようものならこっぴどく叱ったものだが、今は頗る寛大になっていた。
昼間、家族が出かけてしまうと、1人残された梢にとってミーニャだけが話し相手だった。それどころか、ミーニャこそが、障害者となった梢の精神的空白を埋める存在であったかもしれない。
4年前、梢が入院して以来、ミーニャは空になった梢のベッドに寝るようになった。寒い夜も顔を埋めるように丸くなって、梢の香りが残るフトンの上にうずくまった。
正月を過ぎた頃からミーニャの元気が少しずつなくなっていった。好物の白身魚のネコ缶も殆ど残してしまう。水ばかり欲しがった。駅の近くにある獣医に連れていって診てもらった。
血液検査の結果、肝臓と腎臓の機能を表わすマーカーのGPTとBUNが基準値の4倍もあるという。
「これは厳しいなあ。」
小太りの女医は思わずもらした。
「取りあえず脱水症状だけは防ぎましょう。」
ミーニャの腕よりも太い注射を背中に刺した。信じられないほどの大声でミーニャが鳴いた。
皮肉にも、その翌日からミーニャの容態は目に見えて悪くなっていった。エサは全く食べなくなった。水だけは、蛇口から新鮮なものを茶碗に入れておくと少し飲んだ。
やがて、歩行困難となり水も自分から飲みに行けなくなった。台所に行く途中で座り込んでしまう。持ち上げると驚くほど軽い。まるで仔猫に戻ったようだ。
この年の暖冬も3月に入るとカレンダーが逆転したかのように寒くなった。ミーニャは終日床暖房の効いたリビングのソファに寝ていた。さすがに梢のベッドに飛び上がる力は残っていない。
飲まず喰わずで、2日ほど経った。
「ミーニャ」と呼びかけると、尻尾を僅かに動かして返事をする。が、眼は閉じたままで耳も動かない。もちろん寝返りも打てない。
3月8日は梢の誕生日。
朝早く、竜也は小さな鉢植えの花とお祝いのカードをもって病院を訪れた。ベッドの梢に励ましの言葉を贈り、ミーニャが危ないことを報告した。
その夜、竜也は、ソファの上で昏々と眠り続けるミーニャを悦子で2人で看た。竜也はミーニャの旅立ちが近いことを予感した。できることなら梢の誕生日を避けてもらいたいと思った。
夜中の12時が過ぎたとき、悦子の呼びかけに白い尻尾が悲しげに少しだけ動くのを確認した。ミーニャに竜也の気持ちが伝わったように感じた。
ミーニャは昔の夢を見ているように思えた。18年前、家族全員が仔猫を取り囲んで暖かく迎え入れる。仔猫は自慢の尻尾を大きく動かしてそれに応える。
午前3時15分、ミーニャは2、3度小さく痙攣した。
「ミーニャ!」
悦子が号泣した。だが、ふさふさの白い尻尾はもう動かなかった。
竜也には、ミーニャが梢の身代わりになったように思われた。
3月8日、竜也にはもう1つの大仕事があった。ポーランドのワレサ元・大統領の来訪である。
半年ほど前、小島真理子から突然相談を受けた。
「ワレサさんを日本に招待しようと思うの。」
「招待って、誰が?」
「あたしがやるの。竜也さん、一肌脱いで下さるかしら。」
「ワレサといえば、元・大統領でしょ。外務省のやることじゃないのですか。」
「外務省は過去の人には見向きもしないわ。だから、民間外交で私たちが招聘するの。」
とんでもないことを考えている、と竜也は身構えた。だが、小島真理子は、一旦言い出したら後へは引かないこともよく知っていた。
取りあえず、真理子のアイデアを聴くことにした。
真理子は、メモ用紙に大きく『ワレサ元・大統領招聘組織委員会』と書き、委員長・中野竜也と続けた。
「ちょっと待ってください。私には何もできませんよ。それにお金も出せません。」
「総予算は2000万円よ。あたしが寄付を集めるわ。竜也さんは講演会の入場券を売ってくださればいいの。」
「警備なんかはどうするのですか。」
「そのくらいのことは警察がやってくれるわよ。だって、万一のことがあれば日本の恥でしょ。」
「一行の足はどうするのですか。ハイヤーというわけにもいかないでしょ。」
「大使館に車を出してもらうの。それも竜也さんが頼んで頂戴。」
「ワレサは英語を話しますか。それともロシア語?」
「英語は全くダメ。ロシア語はソ連嫌いだから話さないんじゃないの。ポーランド語の通訳を雇えばいいのよ。ボランティアで。」
この人は強情に加えて極端なオプティミストだ、と竜也は内心で少し呆れてきた。
そのことがあって以来、竜也は小島真理子のお供でポーランド大使館に足しげく通うようになった。大使館は目黒にあるので、竜也の雪谷のマンションからは遠くなかった。
小島真理子はポーランドには何度も演奏に行っているので、大使のリビツキーも真理子には一目置いているようだった。竜也が真理子の名前を言って面会を申し込むと直ぐにOKが出た。
パイプオルガンの奏者は日本では少ない。しかも演奏家としてはマイナーで、ピアニストやバイオリニストに較べると数段評価が低い。だが、カトリックの世界では違っていた。
パイプオルガンの原点はカトリック教会。オルガンの音色は神の声でもあった。カトリック教国のポーランドでは、オルガン奏者には敬意が払われるようだ。真理子によると、グダンスクでの真理子の演奏会には、大統領時代のワレサも必ず顔を見せたという。
ポーランド大使館を何度も訪問するうちに、小島真理子がオルガン奏者としてではなく、カトリック教徒として大使館に接近しているように思われた。
「カトリックの世界ではね、ローマ法王も小島真理子も神の前に平等なのよ。」
真理子は口癖のように言っていたが、竜也は、漸く、その意味が分りかけてきたように感じた。
当初は全くの夢物語だと思われたワレサの招聘が徐々に現実味を帯びてきた。そして、新年の挨拶に大使館を訪れた竜也と真理子に、リビツキー大使がグッド・ニュースを伝えた。竜也の作った英文の契約書にワレサがサインした、という。
竜也は、児島真理子の無謀とも思える行動力に脱帽せざるをえなかった。
3月7日、ポーランド『連帯』の旗手、元・大統領のワレサが3名の随行者と共に来日した。翌8日には、大使館で第1回目の講演とレセプションが催された。
レセプションでは、小島真理子が壇上から挨拶した。
「神様が私にワレサさんを呼ぶように囁かれました。リビツキー大使初め、皆様のご協力のお陰でそれが実現しました。とても嬉しいです。」
大きな拍手があった。
会場には大勢の招待客が集まっていた。政治家や外交官も多数来ていた。その中に黒田康夫元・大使の顔もあった。長身の黒田康夫は外国人の中に入っても目立つが、夫人の久美子は小柄なのでよく探さないと分からない。黒田久美子の方が先に竜也を見つけると、近寄ってきた。
「凄い盛会ですね。小島さん、よくここまでなさいましたわ。彼女の行動力は大したものですわね。これも、中野さんの御尽力のお陰でしょ。」
「いいえ、私には大したことはできません。ホンのお手伝いです。私も最初に話を聞いたときには冗談だろうと思いました。まさか、実現するとは正直驚きました。」
久美子との会話を簡単に切り上げると、竜也は来客を掻き分けながら児島真理子を捜そうとした。
「中野さん。」
聞き覚えのある声に振り向くと、カメラを片手にもった堀田美恵子の顔があった。
「ワレサさんとツーショットを撮ってほしいの。」
「来てくれたんだ。いいよ。ひな壇に居ると思うから。」
洋画家の堀田美恵子は竜也が招待したゲストの1人だった。
美恵子は東京の女子大を卒業して山口工業に入社した。配属された先が機械営業部・輸出課で、竜也が山口から転勤してきた部署だった。40年近く前の話だ。
美恵子は画が好きで、会社勤めの傍ら絵画教室に通っていた。2年で退社すると、本格的に画の勉強をするため美術大に入った。竜也は、その後すっかり美恵子のことを忘れていたが、美恵子の家が荻窪にあり、父が都内でも珍しい能面師だということだけは不思議に覚えていた。
30年後、竜也はアメリカから帰国し、善福寺の借上げ社宅に移り住んだ。あるとき、杉並区から配布される区報を何気なく見ていて、“杉並区の誇る能面師”というコラムが眼に留まった。更に、略歴の紹介欄には、“長女は洋画家の堀田美恵子氏”とあった。
「ほう、あの美恵子が洋画家と言われるようになったのか。」
懐かしくなった竜也は、早速、美恵子の実家宛に手紙を書いた。
『憶えておられますか。』から始まって、『会社は、現在、天王洲のウォーター・フロントにあります。立派な本社ビルを建てました。一度遊びに来ませんか。昔仲間も居ます。』で結んだ。
2週間後、美恵子は天王洲の本社にやってきた。竜也は立川と2人で美恵子を迎えた。
立川は、美恵子が山口工業に勤めていたときの同僚で、最近バンコク駐在から帰国し、今はプラント事業部で竜也の配下にあった。美恵子は立川の案内で興味深げに本社ビルを観て回った。
特に、18階の社員食堂に入ったときは、感嘆の声を上げた。
「こんなところでお昼を食べるなんて、いいわね。」
広いガラス窓からは、東京湾が一望に見下ろせる。正面のレインボー・ブリッジが格好のアクセント。橋のこちら側には特徴ある三角のビルがあり、向こう側は台場のビルが立ち並ぶ。観覧車もみえる。静かな海面には観光ボートがチラホラ浮かんでいる。
美恵子は大理石を敷き詰めた1階の玄関ロビーにも興味を示した。磨かれた石の感触を確かめるように、広いロビーを何度か往復すると、だしぬけに言った。
「中野さん、偉くなったのでしょ。私の画を買って下さらない? このロビーと食道に飾るのに丁度いい画があるの。どなたに言えばいいのかしら。紹介して下さる?」
小島真理子にしろ、堀田美恵子にしろ、熟女のビジネス・マインドに竜也はいつも感心させられる。早速、宣伝課の南田を紹介した。
美恵子は、バッグから自分の作品のアルバムを取り出して南田に説明を始めた。わずかなチャンスを見逃さないところがセールス・ウーマンの心得なのだろう。
話はとんとん拍子に進んで、数日後、3枚屏風のような巨大な画が山口工業の本社ロビーに納まった。
堀田美恵子の画は抽象画とは少し違う。コンテンポラリー・アートと名づけられた彼女の作品は、どれもブルーの基調で波のような線が幾重にも描かれている。画壇では、「青の画家」とか「魂の画家」と呼ばれているらしいが、竜也にはどの画も死後の世界をイメージして描いたように思われた。
美恵子が何処に行くにも持ち歩く、分厚いアルバムには美恵子の描いた殆どの作品の写真が入っていた。その中に、フィンランドの日本大使館に飾ってあるものや、東京のポーランド大使館に寄贈した画が含まれていた。それを竜也が憶えていたことが、今日のワレサ招聘パーティに美恵子を招待するきっかけになった。
ポーランド大使館のホールで、招待客をかき分けるようにして、竜也と美恵子はひな壇に進んだ。ワレサは、ひな壇の中央に空になったグラスを右手に持って立っていた。御満悦の様子だった。ワレサの前には、一緒にスナップを撮ろうと長い列ができていた。
ワレサは竜也の姿を認めると、片目でウィンクを送り早く来いと合図した。竜也は美恵子を促し、ワレサの横に立たせてシャッターを切った。
「ありがとう。」
美恵子は笑顔でワレサに握手を求めた。ワレサの太い手が美恵子の細い手を覆い隠した。
美恵子は意気揚々と帰っていった。
翌日、ワレサは総理官邸を訪問した。現職の総理大臣への表敬訪問はワレサ側が強く希望したもので、小島真理子がアポイントを取り付けた。小島の祖父・児玉源太郎が山口県出身で、同じ山口県出身のA総理も断りきれなかったのだろう。国会の合間を縫って、会見に応じた。
会見には、A外相も同席した。その昔、梢と婦人雑誌で対談した九州出身のA代議士は、このとき外務大臣に昇格していた。
A外相がワレサとの会見に同席したのには理由があった。
A氏が外務大臣に就任して直ぐに打ち出した外交方針に『自由と繁栄の弧』というのがある。日本を円周上に取り巻く諸国を北欧から始まって、バルト諸国、中欧、東欧、中央アジア、コーカサス、中東、インド亜大陸、さらに東南アジアを通り北東アジアに至るまで、弧を描くようにつながる諸国から日本の友好国を特定し、それらの友好国との協力関係を強化しようというもの。
東欧諸国の中ではポーランドが具体的国名としてあがっていた。そのポーランドの元・元首が来訪したからには、『自由と繁栄の弧』の提唱者であるA氏としては顔を出さないわけにはいかない。
会談では首相よりも外相の方が雄弁であった。だが、6ヵ月後に総理大臣が、突然、辞任するとは誰も予想しなかった。ましてや、A外相が1年半後に総理の座に着くことなど想像すらできなかった。
その日の午後、ワレサは、新宿のB学園で講演会を持った。広い講堂に補助椅子を置いても座りきれないほどの入場者があった。竜也が入場券を買ってもらった人たちの顔も見えた。
ワレサは雄弁に語った。質問にも答えたが、その殆どが自説の押し売りで質問に対する回答には、ほど遠いものであった。竜也は、通訳をお願いしたTG大の久野講師に深く同情した。質問に対してピント外れの回答が返ってくると、何故か通訳の責任のように受け取られることを、竜也は自分の経験を通じて知っていた。
週末にワレサ一行は意気揚々と引揚げていった。まさに台風一過の感があった。
![]()
「介護日記ーその後」にもどる
![]()
「白い闇」第44章に進む
![]()
トップページへ戻る