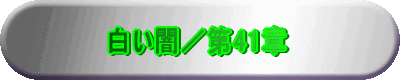
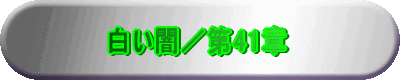
2006年は平穏に過ぎていった。竜也は梢が落ち着いた状態で新しい年を迎えることに感謝したかった。感謝の対象は何でもよい。竜也は特に信仰を持たなかったので、何か絶対的なものとして、天に感謝した。
年末の主夫は多忙だ。正月には、小島真理子が3人のVIPをつれて年賀に訪れることになっていた。彼らの目的は、竜也が作るおせち料理。梢が入院してからも、竜也は、毎年、正月を迎えるのにそれなりの準備をした。
おせち料理の支度は、主夫にとって一大イベントである。主だったものは出来合いを購入するが、最低5品は自家製のものを作るのが竜也の決めたルールだった。竜也の得意は、厚焼き玉子とブリの照り焼き。
家族4人とお客様の分を合わせて、10個の卵をボールに割り込む。掻き混ぜるときに少量の牛乳を入れるのが、滑らかに焼くためのコツだ。それに、別に用意した特製のだし汁を加える。銀色のボールの中で琥珀色に輝く膠質状の液体を指先で舐めてみる。よし、上出来だ。
次に、玉子焼き器。最近では、熱伝導率の高い銅製が流行りだが、竜也は未だに鉄製のものを使っていた。鉄製では十分に予熱しておくのがポイントとなる。
頃はよし。琥珀色の液体を玉杓子ですくって入れる。ジューッと音がして芳醇な香りが鼻を刺激する。早速、フライ返しで丸めていくのだが、これまた、アルミ製で相当な年代モノ。柄はひん曲がっているし、取っ手は外れたままなので直ぐに手が熱くなる。来年は新しいものを買おうと心に決める。が、恐らく1年後に、また、同じ決意をしなければならないような気もする。
5重に巻き上がった厚焼き玉子が4本、きれいにまな板の上に並んだとき、長女の恵子と次女の美佐子がやってきた。恵子の分担はお煮しめ作り。彼女のお煮しめは竜也からみれば、はなはだ乱暴な作り方だが、出来上がったものは、何故か、竜也が作るより格段に美味しい。出戻り娘だが、数年間の主婦稼業でお煮しめだけは上手になったようだ。
狭いキッチンに2人が入ると急に窮屈になる。竜也は、ブリの照り焼きにかかる。照り焼き用のタレには、先ほどの厚焼き玉子のダシに酒と醤油を少し加えたものを使う。同じものを数の子にも使う。だから、だし汁は大目に作っておくと手間が省ける。
オーブンの魚焼き器の受け皿には、水ではなく、アルミフォイルの上に備長炭を砕いたものを敷く。備長炭から出る遠赤外線の効果で、内部までふっくらと焼けるからだ。
しかも、焼いた後、受け皿を洗う必要がない。何度か使って、魚油のしみこんだ備長炭を捨てずに植木鉢に入れると、格好の肥料になる。
美味しそうな匂いがキッチンに立ちこめて、こんがり焼きあがったブリが大皿に盛り上がった頃、紅白歌合戦も終盤に入っている。リビングでテレビを見ていた美佐子が、恵子と一緒にお節を重箱に詰め始める。
主夫は、煙草に一服つけた後、今度は年越し蕎麦とお雑煮の準備だ。年越し蕎麦には、今年は、新潟・小千谷名物のヘギ蕎麦というのを使った。
薬味は、おせちの残りのかまぼこ、稲荷揚げ、それにトロロ昆布とネギ。ツユは昼間スーパーで買った。とても蕎麦ツユまで手が回らない。
年越し蕎麦が出来上がると、テレビでは、もう、除夜の鐘が始まっていた。
2007年元旦の朝、末娘の悦子も加わって一家4人が食卓に着く。両親が残してくれた漆塗りの屠蘇器からお神酒を少しだけ皿型の杯に注ぎ、全員で「明けましておめでとうございます」と乾杯する。
次に、白味噌ベースの京風お雑煮に、オーブントースターで焼きあがったモチを入れる。これも、竜也の自信作だ。
最後に、おせちの詰まった5段の重箱のフタを取ると、一斉に歓声が上がった。恵子は、早速、デジカメで写真を撮る。自分のブログで紹介する積もりらしい。
皆が思い思いの料理に箸をつけたとき、竜也が先ほどから心の中で思っていたことを恵子が口に出した。
「お母さんが居れば喜ぶのにネ。」
この年の恵方は北北西。こちらの方角は竜也には不案内なので、地図で調べて東玉川神社に初詣に行った。神社の神殿はとても古く、450年前建設されたものをこの地に移設した。
向拝殿の天井には火焔龍神像が水墨で書かれていて、この龍神が悪霊を祓う守り神となっている。あまり知られていない神社のようで、初詣客は比較的少なかった。参拝の後、梢の好きな破魔矢を買い、おみくじを引いた。「吉」とあった。
昼頃、病院に着いた。未だ早い所為か見舞い客は殆どなくガランとしていた。梢は年が改まったのも知らないで悠々と眠っていた。
枕元のCDで琴の名曲をかけた。ベッドの柵に猪の絵が描かれた破魔矢を取り付けたので、病室の中が少しだけお正月らしい雰囲気に変わった。娘たちと一緒に梢に「明けましておめでとう」の挨拶をした。竜也は心の中で、「今年も Big fight だね。」と語りかけていた。
2日には、VIP4人の来訪があった。小島真理子とその仲間だが、うち2人はユーモア・スピーチの会のメンバーで、元・大使夫妻。夫婦ともに大使だった。夫人の黒田久美子は、外務省初の女性大使としてフィンランドに勤務した。その後、亭主の黒田康夫がスイス大使に任命されると、久美子夫人も国連大使としてジュネーブに派遣され、同じ国に夫婦で大使を務め、オシドリ大使として評判になった。
久美子は外務省を退官した後も公正取引委員会の委員として活躍したが、今はすべての公職を離れボランティア活動に専念していた。
黒田久美子は竜也の作ったおせち料理を「美味しいわ」と言いながら食べた。半分お世辞としても竜也には光栄だった。
3日は、3女の亜希子一家がやってきた。亭主の香山哲夫との間には2人の男の子がいた。6歳になる上の孫を梢は可愛がっていたが、2歳の孫は梢が意識を失ってから生まれたので知らない。
香山一家は松戸在住だが、哲夫の実家が三島にあり、年末から一家でそちらに滞在していた。帰りに竜也の家に立ち寄ったものだが、途中、第一京浜で、偶々、箱根駅伝に出くわして孫たちは車の中で大騒ぎだったらしい。
孫たちはじっとしていない。兄弟で仲良く遊んでいたかと思うと、おもちゃの奪い合いでケンカを始める。老猫のミーニャの姿を見ると追い回すので、ミーニャは孫たちが苦手だ。隙をみて物陰に隠れる。
ミーニャとは、以前はビビと呼んでいた白猫のことで、5度の転居にも迷子にならずアメリカまでもついてきた。竜也の付けた”ビビ”という名前は、いつの間にか梢が勝手に”ミーニャ”と替えてしまっていた。
ネコ捜しを諦めた2人は、自分のバッグから何やら取り出した。汽車のおもちゃだ。2人とも乗り物が大好き。
子供たちが遊び疲れた頃、全員で夕食におせち料理を囲む。子供たちよりも親の方が食欲旺盛だ。孫の2人には、実は別の狙いがある。それは、食後のデザート。
2人ともフルーツ大好き。何時も竜也の家に来ると、竜也の用意した大皿のフルーツを楽しみにしている。というわけで、竜也も手抜きは許されない。
フルーツの盛り合わせは、見た目が大切。季節の果物から色合いのバランスを考えて選ぶ。この時季の主役は、リンゴ、オレンジ、それにイチゴ。他に、キューイとパイナップルを添える。
ガラスの大皿の外側には、8つに切ったオレンジを奇麗に外皮を取り除き、菊の花のように並べていく。大皿の半分まで、半円状にオレンジの花びらが並ぶと、残り半分をリンゴの花びらで埋める。この時、リンゴの上下端を少し切り落としておき、オレンジと大きさを揃えると見た目が良い。
黄色と白の花びらで出来た大きな円の中に、イチゴとキューイを置く。中央に一口大に切ったパイナップルを載せると、大輪のフルーツ皿の完成だ。これに、ラップをかけて冷蔵庫に入れておく。
フルーツの大皿をテーブルに置きラップを外すと、歓声とともに2人の争奪戦が始まる。先ず、イチゴを手で掴んで口に放り込む。フォークを出してあるのだが、素早く確保するには手の方が早い。お互いに相手を意識しながら、次々に手を伸ばす。口の中には未だ前のものが入っているのだが、お構い無しに新しいイチゴをギュウギュウ詰め込む。果汁が周辺に飛び散る。
あっという間にイチゴがなくなっていき、残り1つとなったとき、手を伸ばしかけた上の子が、ハッとして母親の亜希子に顔を向ける。
「お母さん、イチゴほしい?」
「要るわよ。」と返事が返ってきて、2人は休戦協定。
「これは、お母さんの。」と、上の子が宣言して、1つだけイチゴを残した。
今度はオレンジの早食い競争だ。フォークこそ使っているが口に運ぶスピードはイチゴの時と変らない。
争奪戦は5分も経たないで終わる。大皿には、1切れのオレンジ、1粒のイチゴ、それにリンゴがたくさん、無残な姿で残っている。
「この子たち、リンゴは家で何時もあげているから、他のものから食べるのよ。」
些か呆れ顔の亜希子が、残されたイチゴに手を伸ばす。残る大人たちも遠慮がちにリンゴを口に運ぶ。
2人の孫は、もう汽車を手に走り回っている。
1時間後。下の子がそろそろ疲れてきた。
「今帰れば、クルマの中で眠ってくれそうだわ。」
潮時とみた亜希子が亭主の哲夫に声をかける。
「そうだね。」
家では制限の厳しい喫煙をゆっくり楽しんでいた哲夫が腰をあげる。
4人が帰ってしまうと、嵐の後の静けさがやってくる。
「やっと、帰ったか!」と言いたげなミーニャが、そろりと現れた。
3が日はアッという間に過ぎた。竜也は、翌日、病院を訪ねて梢に3が日の報告をした。賑やかなことが好きだった梢が、もし家に居れば嬉々として来客の相手をしたはずだ。
![]()
「介護日記ーその後」にもどる
![]()
「白い闇」第42章に進む
![]()
トップページへ戻る