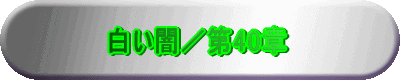
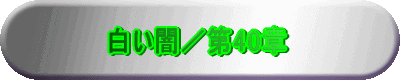
病院での梢は一進一退で、安定した状態が続くかと思えば、突然、熱が出ることがある。病状のバロメーターは体温と血中酸素濃度。酸素濃度が下がれば、肺の機能が低下していることの証拠である。
肺から取り入れる空気中の酸素はヘモグロビンと結合して血液中に溶け込む。血液中の酸素濃度を測ることによって、十分な酸素が摂取できているか、どうかが分かる。
簡単な計測器具を手の指に取り付けると表示窓に数字が現れる。健康体なら100が標準。梢の場合は95〜100の間にあるが、この数字が95を切ると酸素吸入が行われる。
寝たきり患者は、身体の抵抗力がなくなっているので肺炎に罹りやすい。肺炎になると、タンの量が増える。タンが気管支に絡まると窒息死することがあるので、頻繁にタンの吸引をしてやらなければならない。
タン吸引は簡単なようにみえて難しい。枕元に設置してあるエアーポンプにプラスチックのチューブの根元を装着し、先端を患者の鼻や喉からピンセットの助けを借りて差し込む。チューブの先端が上手くタンの集まっている場所に届けば、音を立ててタンが吸引される。が、タンのある場所は手探りで探さなければならない。無理をすると気管支の内面に傷をつける。
竜也は病院に梢を訪ねると、先ず、梢の顔と手足をホット・タオルで拭く。寝たきりでも分泌物は少なくない。梢は入院直後に眼の病気に感染したらしく、右目からの目やにがひどかった。
顔と手足の清掃が終わると、両手のタオルを交換する。両手とも指を固く折り曲げたまま硬直しているので、手のひらに汗が溜まる。それを防ぐために、両方の手にハンドタオルを握らせているのだが、それを新しいものに取り替えてやるのだ。
この作業が簡単ではない。指の硬直は日によってまちまちだが、ひどい時には指を拡げようとすると折れるのではないかと思うほど固い。それを無理にこじ開けて、予め筒状にしておいたタオルを小指側から入れていき、親指側に抜くようにして握らせる。
時には伸びた爪をつんでやるのも竜也の仕事だった。手の爪は親指が大変だった。親指を中にして握り締めているので、他の指をこじ開けて親指を外に出さなければならない。
どういうわけか、親指の爪は非常に肉が厚くなっていて爪が2枚重なって生えているように見える。それを普通の爪切りを使ってつんでいくのだから時間がかかる。
足の爪は更にひどい。まるで貝殻のように硬い。爪切りに力を入れると、2枚の刃の間で割れてしまう。足の爪は入浴直後でなければとても無理だった。
入浴は週に一度ヘルパーが4人がかりでやる。病室のベッドから移動用台車に移し、そのまま浴室に運ぶ。入浴といっても実際に湯の中に入るわけではない。寝たままの姿で低温スチームを浴びせる。
そんな入浴でも、風呂好きの梢には快適だったようで、入浴の後は何時も熟睡した。
当初、竜也にはタン吸引は怖くてできなかった。が、少し慣れてくると見よう見まねでやってみた。
消毒液に浸かった細いチューブをピンセットで摘み出し、根元をエアーポンプに差し込むとシューッと音がする。チューブの先端をそっと口から挿入する。梢は無意識のうちにチューブを噛んで中に入れさせまいと抵抗する。
身体は硬直して動かないが、眼の開閉と口だけは動く。時に欠伸をしたり、口の中のもの噛んだりするのは、ひょっとすると生存本能が身体の運動を要求しているのかもしれない、と後になって竜也は思った。
竜也がタン吸引しても、なかなか上手く行かない。だが、時にはジュルジュルと音がして、大量のタンがチューブを通って、収集ビンに取れることがある。そんなときは、今日は梢のために少しは貢献することができた、とビンの中のタンを眺めながら満足感を覚えるのだった。
2006年3月8日、梢は65歳の誕生日をベッドの上で迎えた。植物状態になって3年が過ぎた。この年、梢の状態は非常に安定していた。高熱の出ることは殆どなく、顔色もよかった。
竜也は小型のフラワー・アレンジメントを持って病院を訪ねた。病室に入ると、梢は眼を開けていた。話しかけると、竜也の方に視線を向ける。その瞬間、竜也は梢がニッコリと微笑んでくれることを期待したが、いつものように裏切られた。
「これ、誕生日のプレゼントだよ。ケーキがなくてごめんね。」
無表情な梢の枕元に花かごを置き、『70歳まで頑張ろうね。』と書かれたカードを添えた。
3年前、この病院に来たときには、梢がここまで頑張るとは竜也も想像していなかった。だが、病状が安定してくると、本当に70歳まで生きるかもしれない、と思い始めた。
意識もなくベッドに寝たきりの梢の生きる力を支えているのは、『どうしても回復するのだ。』という執念かもしれない。
最初にアメリカで倒れたときも、懸命のリハビリで退院することができた。梢の唯一の心の支えは竜也の存在だった。竜也に恩返しするためにはどうしても元気な身体に戻らなければならない。その一念からリハビリに励んだ。
植物状態になってしまっても、その執念だけは何処かに残っているのではないか。そして、それが梢のはかない生命の原動力になっているのではないか。
竜也は、梢のベッドサイドの椅子に腰をかけ、ぼんやり天上に視線をやっている梢の顔を暫く眺めていた。
完全に自由を奪われ、何の楽しみもなく、3年間もベッドの上で頑張り続けた妻の姿に、竜也はある種の感動を覚えた。梢は何もできないが、存在することだけで竜也の心の支えになっているのかもしれない。それが梢の恩返しだろう、と竜也は思う。
竜也は奇跡というものを信じなかった。梢が意識を取り戻すことはあり得ないだろうとあきらめていた。だが、心の何処かで、もう一度梢の笑顔を見たいという願望が渦巻いているのを感じていた。その願望は、竜也のあきらめとは裏腹に、竜也の“奇跡を信じない”という理性を覆そうと懸命に戦っているように思われた。まるで、梢の心の奥に秘められた“回復への執念”に励まされるかのように。
![]()
「介護日記ーその後」にもどる
![]()
「白い闇」第41章に進む
![]()
トップページへ戻る