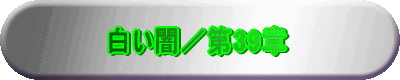
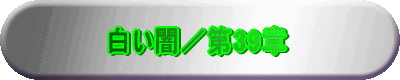
学習塾を開設する傍ら、竜也は人的交流に努めた。山口工業に在職していた間は組織の中の人間として、会社関係の人たちとの接触が絶えなかった。だが、組織を離れてしまうと彼らとの交流は疎遠になる。
竜也は、自分の生活の質を高めるには、できるだけ多くの人とコミュニケーションを持つことが必要だと考えていた。
会社の元部下たちを、毎年、自宅に招いて、忘年会や新年会のスキ焼パーティを持った。
また、異業種交流にも積極的に参加した。手始めに、近くの文化センターの体操教室や文章教室に参加した。同時に、『ユーモア・スピーチの会』という集まりにも加わった。
ユーモア・スピーチの会は、以前から交際のあった小島真理子の勧めで参加することになったもの。この会の本部は秋葉原にあり、自称・ユーモア共和国・大統領と副大統領が主催して、月に1度40人ほどのメンバーを集めて開かれる。
参加者は順番に前に出てスピーチをするのだが、制限時間は3分。その間にユーモアとウィットを交え、起承転結をつけてスピーチを終えなければならない。話し方のトレーニングには打ってつけであった。
当初、秋葉原本部の集会に顔を出す程度だったが、そのうちに中野にある小島邸にメンバーを集めて支部を作ろうということになった。竜也は中野支部の幹事を仰せつかることになる。メンバーの大半は小島真理子が集めてきた。その顔ぶれは多彩で、元大使、現役の弁護士、作家、音楽家、画家、議員など様々な分野の人が集まる。小島真理子の交友の広さをうかがわせた。
真理子は、日露戦争で活躍した児玉源太郎の孫にあたる。名門の出身で、日本では数少ないパイプオルガンの奏者。毎年、数ヶ月は海外に演奏旅行に出かける。竜也とは同世代だが、そのバイタリティは年齢を感じさせなかった。ポーランドの演奏会から帰国したその日に、ユーモア・スピーチの会をやり、翌日には長崎に出張するといったスケジュールを平気でこなした。
竜也はドイツ駐在時代の自分を見ているようで、彼女のバイタリティには共感するものがあった。
梢が植物状態になってしまった現状では、以前イメージしていた引退後の幸せの構図は成り立たない。竜也は多くの人との交流で梢と語ることのできない寂しさを紛らわそうとしたのかもしれない。
2005年4月最初の日曜日、竜也は小島真理子のオルガン・コンサートを聴くために近江八幡に来ていた。コンサートは隣町・安土の「文芸セミナリヨ」で開催される。滋賀県の片田舎、安土にパイプオルガンとは些か奇異な感じがするが、実は、日本初のパイプオルガンは安土に設置された。400年以上も前のことだ。
当時、天下を治めようとしていた織田信長は安土を「国際自由都市」と位置づけ、欧州文化の導入に積極的であった。信長の目的は、近代的な武器、特に鉄砲の調達にあったが、スペインやポルトガルの宣教師たちは、武器を餌にキリスト教を日本に広めたいとする下心があった。
信長とイエズス会の宣教師たちとの接触は歴史的にも重要だが、中でもフロイスとの会談は安土を西洋化させる上で大きな役割を果たした。というのは、この会談で信長は安土にセミナリヨ(神学校)を建設することを許可したのだ。
それを契機に、安土は異人さんの闊歩する街へと変貌し、セミナリヨにはパイプオルガンが設置された。
そのパイプオルガンは焼失してしまったが、10年ほど前、当時の安土町長が、セミナリヨのパイプオルガンを是非とも再現したいとの強い希望から、ウェストミンスター寺院のものと同じ、英国・マンター社のオルガンを購入する。オルガンの調達に力を貸したのが小島真理子で、竜也はこの話を彼女から聞いた。
その日の朝、ホテルの自室で観たテレビでローマ法王の逝去を知った。竜也はキリスト教とはあまり縁がなかったが、パイプオルガンはカトリック教会とは切っても切れない関係にある。これから始まるコンサートに影響があるかもしれないとの思いでホテルを後にした。
古い町には不似合いなモダンなホールでコンサートは始まった。お目当ての小島真理子作曲・演奏の「世界の輪と光」は、パイプオルガンとお神楽の共演により、西洋文化と日本文化の融合を狙ったもの。視覚と聴覚に訴える新しい試みとして興味深いものがあった。
しかし、竜也の心を強く打ったのは、ゲスト出演したジョルジオ・カルニーニのバッハ作品の演奏であった。
カルニーニはローマのカトリック教会のオルガニスト。世界のカトリック教会の最高位に君臨するローマ法王は、彼にとっては神に近い存在といっても過言ではない。初めての訪日。しかも、滋賀の片田舎での演奏会の初日の朝、ローマ法王の逝去を知る。彼の心は、大きく動揺していたはずだ。
竜也は真理子との付き合いで、パイプオルガンの演奏会には何度か足を運んだが、あまり好きになれなかった。一言でいえば、”退屈”に近いものがあった。だが、この日のカルニーニのバッハは全く違っていた。
「トッカータとフーガ・ニ短調」のお馴染みの旋律は、激しいインパクトで竜也の心に迫った。カルニーニは、恐らく、法王の死に対する深い悲しみと心の動揺を、直接、鍵盤にぶっつけたのではないだろうか。そのことが、強烈な迫力となって感動を与えたのかもしれない。
遠く離れた異国の地で弾く彼のバッハが、ローマ法王逝去への悲愴なレクイエムではなかったのか。帰りの新幹線の中で、パイプオルガンの鋭い金属音が、竜也の耳の奥を何時までも占領していた。
竜也は文章教室にも力を注いだ。学生時代から書くことが好きで、会社に入ってからも竜也は文章を書くことを自分の武器として使った。特に、駐在員時代は毎月のレポート作成には細心の注意を払った。お陰で、竜也のレポートは社内でも非常に評判が良かった。
文章教室は、竜也を含めて5人ほどの集まりで、毎月、与えられた課題で原稿用紙4〜5枚のエッセイを作る。それを教室で読み合わせるのだが、竜也以外は全員家庭の主婦。エッセイの内容は自ずと家庭での出来事になる。
その点、竜也の書くものはスケールが大きかった。現役時代の海外での経験や妻の介護をテーマに次々と異色のエッセイを発表した。安土でのオルガン・コンサートも、早速、エッセイのテーマになったことは言うまでもない。
自分の書いたものを文章教室で発表するだけでは飽き足りず、竜也はミニコミ誌にも応募した。洋菓子・W社のミニコミ誌「風の詩」には何度か採用され、謝礼金を貰った。
この頃、著名な月刊誌・B誌に山口工業が掲載する企業広告頁のライターの話が舞い込んだ。これまで担当していたプロのライターが引退するので後任を捜しているとのことであった。竜也は二つ返事で引き受けた。
この頁は広告というより、山口工業の社員が海外で経験したカルチャーショックや珍しい話をエピソード形式で紹介するもの。B誌の企業広告としては30年以上続いており、読者からも好評を得ていた。
竜也の仕事は、海外で面白い経験をした社員にインタビューし、それを750字の記事にまとめることにあった。短い文章だけに、最後のオチを工夫するのがポイントとなる。実際の記事はインタビューを受けた社員の名前で掲載されるので、竜也の役割は、いわばゴースト・ライターである。
この仕事は竜也には楽しかった。インタビューのため山口工業の本社を訪問する機会が増えた上に、時には、昔の職場を訪ねて雑談に興じることもできる。
自分の書いた記事が、毎月80万部の発行部数を誇る雑誌の1頁を飾ることにも満たされたものを感じた。しかも、会社からはそれなりの原稿料が支払われた。
今や年金生活者となった竜也には、書くことで生活費の一部を補うことができる。まるで、一端の物書きになったような錯覚さえ覚えた。
![]()
「介護日記ーその後」にもどる
![]()
「白い闇」第40章に進む
![]()
トップページへ戻る