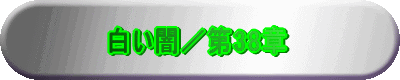
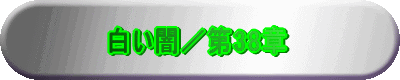
2004年元旦、竜也は娘たちと毎年参拝する御嶽山に初詣に出かけた。梢のために絵馬とおみくじを買った。おみくじは「吉」で、「病は治る」とあった。
早速、それを持って早速病院を訪ねた。だが、梢の体調はよくなかった。竜也たちは絵馬のついた矢を枕もとのビンに挿して梢に見えるように置いた。
3日後、梢の口には酸素吸入器が当てられていた。肺炎にかかったのだ。抵抗力が弱ると肺炎にかかることはよくあるらしい。
翌日、医師から特別に面会を求められ、X線写真を前に説明を聞いた。3枚の写真の中では今朝撮ったとされるものの右肺に多少白い部分が認められた。
「この白い部分が肺炎です。3枚並べると徐々に進行しているのが判ります。患者は抵抗力が弱っているので、このまま肺炎が進行すれば、危険な状態になることが考えられます。その覚悟をしておいて頂きたい。」
この病院に梢を入院させたとき、医師は梢の状態を診て「長くて1年くらいかもしれない。」と言っていた。いよいよ、そのときが近づいているのかもしれない、と竜也は思った。
「それで、最悪のケースは、最短でいつ頃になるのでしょうか。」
竜也は動揺を抑えて訊いたが、医師はまともに答えなかった。
「それは判りません。健康体でも翌日に亡くなることもある。何が起こるかは予想できません。」
「それでは、現状でどの程度持ちこたえれば、峠を越したと判断できるのですか。」
「それも難しい質問だが、この進行状況からすると長くて1週間が山でしょう。」
竜也は梢の頑張りを信じた。S大学病院では、それを信じることができずに神戸から梢の弟たちを呼んだが、今度は連絡しなかった。
1週間がとても長く感じられた。梢は非常に苦しそうだった。呼びかけても目を開けることはなく、口を開いたまま荒い息遣いで横たわっていた。3日目には体温が39度に達した。看護婦が座薬と全身に水枕を当てて体温を下げた。
その効果があったのか、4日目からは体温が下がりだし、呼吸も少しずつ穏やかになった。1週間後にはすっかり元の状態に戻った。
『梢は肺炎に勝った!』
竜也は梢のファイト振りに心の中で快哉を叫んだ。
撮影したばかりのX線写真を前に医師が呟いた。
「肺炎の影が消えていますね。薬が利いたのでしょう。」
「いいえ、そうではなく、妻がビッグ・ファイターなのです。」
医師は苦笑いを浮かべた。
梢の容態が安定してくると、竜也は毎日の病院通いに疑問を感じるようになった。往復2時間近くかかる。車で行けば精々片道10kmの距離なので30分もあれば着くはずだが、途中、悪名高い“開かずの踏み切り”で待たされる。
環状8号線が第1京浜と交差する南蒲田の交差点では、蒲田駅を発着する京急電車と第1京浜の信号待ちが重なり、10分待ちは毎日のこと。運が悪いと30分近く待たなければならなかった。立体交差が計画されていると聞くが、いつのことか分からない。
病室を訪ねても梢には意識がない。時々目を開けて竜也の顔を見つめるが、目の前に竜也が居ることに気づく様子はない。仮に気づいたとしても、どんより曇った、物憂げな梢の眼差しは竜也に感謝するというより負担に感じているようにも見える。
「あなた、近所に用事があるなら別だけど、こんなところまで毎日わざわざ来ないでいいわよ。私のことはいいから、もっと有意義なことに時間を使いなさい。」
元気なときの梢なら、恐らく、そう言ったに違いない。
『よし、それなら、近所に用事を作ろう。その方が、梢が感じるかもしれない心の負担を減らすことができるなら。』
竜也は昨年から考えていた計画を実行に移すことを決心した。
次女の美佐子は、D大を卒業後、大学受験予備校のTハイスクールを運営する会社に勤めていた。事務職として入社して10年を超えた。だが、昇進の壁と社内の人間関係に嫌気をさして退職を心に決めていた。
美佐子の学習塾運営のノウハウを利用できないか。竜也は美佐子と組んで学習塾を立ち上げるアイデアを思いついた。
調べてみると、梢の病院の半径1.5kmの中には8,000人の小・中学生が居ることが分かった。しかも、少子化時代というのに、家計のうちに占める教育費は年々増加傾向にある。
高校生相手の予備校は無理だが、小・中学生相手なら自分にも教えられる。竜也は以前から教師という仕事に魅力を感じていた。将来日本を支えていく子供たちに自分の考え方を多少なりともインプットできるなら、それは社会的にも意義のあることだ。
加えて、教えることは自分が勉強することをも意味していた。サラリーマンを退職して、何もせずにブラブラしている姿は自分には相応しくないとも思った。
計画は着々と進行した。4月には梢の病院の近くに10坪ほどの事務所を借りた。また、学習プログラムの基礎データを得るために、九州に本社のあるP社とフランチャイズ契約を結んだ。
P社の特徴はコンピューターを利用したCAI学習にあった。早速、パソコン9台を購入し、CAI教育に備えた。講師は、竜也を塾長に、インストラクターとして美佐子、それに美佐子の友人の久子の3名とした。
学習塾の立ち上げで最も難しいのは生徒の募集。新聞のチラシ、ポスティング、口コミなどあらゆる手を使った。新たに塾のホームページも開設した。
事前の計算では12名の生徒を集めれば、何とか経済的に成り立つ。8,000人の中の12人なら比較的簡単だろうとタカをくくっていたが、そう甘くはなかった。
7月、梢の病院の近くに、新装なった学習塾を6人の生徒を集めて開校した。塾生の人数に関して不満が残ったが、竜也には1つの大きな期待があった。
日本最大の新聞A紙の金曜朝刊の生活面に「職場BBS」というコラムがあった。普通の職場でよく見かけるちょっとした悩みを題材にして、それに読者がウィットとユーモアで「悩みに答える」式の回答を出すという読者参加型のコラムである。
竜也はこれに度々応募して採用され、賞品の図書券を何枚か獲得していた。
テーマの連絡も回答もメールで行われるため、このコラムを担当する高田美子記者とは何度もメール交換して“メル友”の間柄になっていた。
ある日、高田記者から竜也に一度インタビューさせてほしいとの申し入れが来た。『ニュー・金の卵』という特集を組むという。竜也のホームページを見て、竜也の経歴に興味をもったらしい。
学習塾の格好のPRになりそうなので、竜也は二つ返事で了解した。
教室でのインタビュー、電話でのやりとりが何度も行われ、その年の9月、竜也の学習塾が朝刊の全国版に紹介された。『人生語る先生を目指して』というタイトルで、写真入り5段抜きの大きな記事であった。
「新聞見ました。」という電話が学習塾にジャンジャンかかってくることを竜也は期待したが、電話は殆どなかった。高田記者も応援してくれていたのだが、記事の反響はサッパリであった。理由として2つのことが考えられた。
1つは、高田記者の原稿には明記されていたはずの学習塾の電話番号が、直前になってデスクの一言で削除されたこと。もう1つは、後に判ったことだが、学習塾に設置した電話がKDDI登録のため、NTTの番号案内では調べられないことにあった。
特に後者は致命的で、連絡の取りようがなければどうしようもない。念のため、竜也は104に電話して、自分の学習時塾の電話番号を問い合わせてみた。
「そのお名前では登録はありません。」と、冷たい答えが返ってきた。
一方、竜也の自宅にはたくさんのメールや電話があった。学生時代の友人、会社時代の知人、神戸の親戚などから「新聞見たよ。」と言ってきた。流石は750万部発行の大新聞だと驚いたが、肝心の塾に問い合わせがなければ意味がない。竜也の期待は完全に裏切られた。
それでも、学習塾は少しずつではあるが、塾生の数も増えていった。昼の早い時間には小学生がやってくるが、そちらは次女の美佐子に任せた。また、午前中には不登校の生徒を数人受け入れた。
竜也の出番は中学生が来る夕方からだった。先に病院で梢を見舞い、その足で塾に行く。帰りは夜の10時頃になるが、生来遅寝遅起きの竜也にはピッタリで、徐々に生活のパターンが出来上がっていった。
家では、雪谷の広いマンションで末娘の悦子と2人暮らしだが、家事は悦子と分担していた。掃除と洗濯は悦子がやり、食事の支度は竜也の仕事だった。
朝食は、前日の夜、家に戻ってから作った。隣のマンションに暮らす長女の恵子が朝食を食べに来るので3人分を用意する必要がある。
竜也は3人分の朝食を時間をかけて作った。どうしても食事が不規則になるので、朝食だけは野菜をたっぷり使ったサラダにした。少なくとも12種類の野菜、果物、ハムなどを彩りよく皿に盛り、ピッタリとラップをかけて冷蔵庫に入れておく。
朝の早い恵子と悦子は竜也が眠っている間に竜也の用意したサラダを食べて出かける。竜也がゆっくり起きて、冷蔵庫を開けると1人分のサラダ・プレートが残っている。時間をかけて朝食を取る。
竜也は、朝、のんびりと過ごすことが好きだった。梢が居ないのは淋しいが、1人で食後のコーヒーをすすりながら新聞にゆっくりと目を通す。その間に1日分のエネルギーが蓄積されていくように感じた。
夕食は不規則だった。悦子の夕食用に簡単なものを作っておくが食べないことが多い。
竜也も外食が多かった。塾の帰り、近くのファミリー・レストランで美佐子と夕食を取ることは1つの楽しみでもあった。
しかし、竜也にとって何よりの楽しみは、塾で真剣に学習してきた生徒の成績が徐々に上がっていくのを見ることにあった。
先日も、中学2年生のK君が教室に入ってくるなり、「先生、また上がったよ。」と期末試験の結果を嬉しそうに示した。
8月に入塾した当時、K君の成績は学年で120番だった。それが、80番台、60番台と上昇してきた。
竜也は彼の成績表を眺めて、こみ上げてくる嬉しさを必死に抑えながら、
「よく頑張ったが、こんなところで満足していては駄目だ。3年生になれば20番台を目指そう。」と、ニコリともせずに成績表を返す。
「無理、無理!」といいながらも、K君は密かに次の目標を定めようとしているようだった。
美佐子は朝から塾に出ている。終わるのは、早くても、夜の9時過ぎ。その年の5月、塾の開校に合わせて、教室の近くに引っ越してきたので通勤上のハンディはないが、連日の10時間を越える勤務は彼女にとっても負担に違いない。
塾が終わると彼女を近くのファミリーレストランに連れて行って遅めの夕食を共にする。竜也の気持ちとしては、彼女のハードワークに対するささやかな感謝の表現でもあった。
美佐子は嬉しそうに、「今日は何を食べようかな。」と、メニューを覗き込む。 運ばれてきた大好物の鰻丼を口に頬張りながら、その日の総括が始まる。
「今日のK君は嬉しそうだったね。塾長先生に感謝・感謝じゃないかなぁ。」
「お父さんも嬉しかったよ。K君には言えなかったけどね。今度は、美佐子先生のみているMちゃんも上げなきゃいけないね。」
「あの娘は大丈夫だよ。お喋り娘だけど、やるときはやるんだから。」
大いに食べ、大いに語る。最後は、竜也には歯が泣き出しそうな甘いデザートに目を細める。
昨今の新聞紙上では、父と娘の断絶を憂いた記事が目に付くが、毎日のように娘と2人きりで夕食を楽しむことができるというのは、学習塾のもう1つの効用かもしれない、と竜也は思った。
![]()
「介護日記ーその後」にもどる
![]()
「白い闇」第39章に進む
![]()
トップページへ戻る