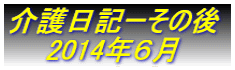
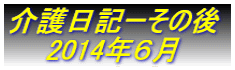
2003年3月を迎え、竜也の実質的な任期は後1ヶ月となった。実際は6月の株主総会で退任するのだが、4月からは新体制となるため竜也は自分のポジションを後任に譲ることになる。
後任には竹中が任命された。竹中をどうこういう積もりはないが、自分の後任が鴨田ではなかったことに竜也は大きな不満を感じていた。それに、竹中が全く違う部署から来たため引継ぎにも手間取った。客先、役所、関係団体などに竹中を紹介してまわる必要があった。
3月4日、竜也は出張先のU市に来ていた。家では梢と悦子が留守番をしているはずだった。長女の恵子は既に家を出て、隣のマンションに引っ越していたので、家には梢と悦子しかいなかった。
悦子も渋谷でデザイナーの助手のような仕事をしていて何時も帰りが遅かった。実質的には梢1人が留守番していたことになる。だが、梢は1人で過ごすことには慣れていた。
食事は竜也が出張前に作って冷蔵庫に入れておいた物を適当に食べているはずだった。ただ、入浴だけは梢1人ではできないので、隣のマンションから恵子が来て1日おきに入浴させることになっていた。
夜10時半、竜也がそろそろホテルのバスに入ろうかと考えていたときに携帯電話が鳴った。悦子からだった。
「お父さん、大変。今会社から帰って来たらお母さんが台所で倒れてるの。」
梢は多点杖で上手に歩くが時々無理をして転ぶことがある。側に掴まるものがあれば、何とか苦労して自分で起き上がるのだが、掴まるものがないと、まるで亀を裏返したようにもがくばかりで立ち上がれないことがある。
「お母さんを起こしてやれるだろ。」
「そうしようと思ったの。だけど意識がないの。このまま寝かしておいた方がいいのかもしれないと思って。」
「意識がない?」
「叩いても起きないの。側に猫の餌がちらばっているから、猫に餌をあげようとして転んだのかもしれない。お茶碗が流しに出たままだから、倒れてから相当時間が経っているかもしれない。」
受話器を耳に当てたまま、竜也は頭の中が混乱していた。
「ちょっとこの電話をお母さんの耳もとに当てて頂戴。」
梢は痙性発作を起こすと意識を失うことがあった。そんなときは5分もすれば目を覚ますはずだ。夕食は7時ごろに食べるので3時間も寝たままというのはあり得ない。竜也は背中に冷や汗が流れるのを感じた。
「梢!梢!どうした。起きなさい。」
竜也が電話越しに叫んでも目を覚ます様子はなかった。
「悦子、すぐに恵子を呼びなさい。そして119番に電話して救急車を呼びなさい。結果を直ぐに連絡しなさい。」
竜也は一旦悦子の電話を切ると、ホテルの部屋の便箋にファックスの原稿を書き始めた。宛先は糸川だった。
『家内にトラブルがあったようなので、明日朝1番で東京に帰る。明日のアポイントは勝手ながらすべてキャンセルするので、宜しく手配願う・・・』
そこまで書いたところで電話が鳴った。恵子の声が響いた。
「救急車を呼んだの。もう直ぐ来るわ。行き先はS大学病院でいいのね。」
「それでいい。お父さんの机の引き出しに保険証と診察券があるから、お前がそれをもってついていってほしい。」
「判ったわ。で、お父さんはどうするの。何時帰ってくるの。」
「お父さんは明日1番の飛行機に乗る。羽田着は9時半ごろだから病院には10時過ぎには着けると思う。」
その夜は恵子との電話連絡や糸川へのメッセージを作るのに忙殺された。恵子からの連絡では梢の状態はかなり危険だとの医師の判断らしい。
竜也は糸川へのメッセージにそのことを付け加えた。竜也はどんな緊急事態にも他人のプライバシーを侵すことを避けていた。ましてや、この状況で糸川を電話口に呼び出しても心配を押し売りするだけの結果になるのは明白だった。
竜也はできるかぎり詳細にファックスを書き、ロビーに下りて送信を頼んだ。時計は既に4時をまわっていた。
竜也は少し仮眠することにして、電話器のアラームを6時半にセットし、念のためにフロントにもモーニングコールを頼んだ。しかし殆ど眠れなかった。
小学校の教室で机を雑巾がけするお下げの少女、蓼科の高原で黄色のニッコウキスゲに顔を寄せる溌剌とした娘、更には車椅子の上から竜也を見上げて微笑む梢の笑顔が走馬灯のように竜也の頭の中を駆け巡った。
3月5日午前10時、竜也はS大学病院に着いた。緊急治療室には恵子、美佐子、亜希子、悦子の4人娘が顔をそろえていた。梢は遮断された奥の治療室のベッドの上で、身体中に管を差し込まれ、口には大きな酸素吸入マスクをはめられて寝かされていた。
意識は全くなかった。全員で医師の話を聴いた。医師は脳の断層を示したCTスキャンの画像を何枚か示して、声を殺して話し出した。
「この部分に出血が認められます。右脳視床部です。出血の規模はかなり大きい。」
竜也は軽い目眩に似たものを感じた。前回は左脳をやられて右半身が麻痺した。今回右脳に出血を起こしたとなると左半身も駄目だ。
医師は竜也の心配を見透かしたように淡々と説明を続けた。
「前回は開頭術をやられてますが、今回は手術はやりません。血塊の除去もやりません。リハビリもやりません。しても意味がないからです。この規模の出血だと、回復の見込みは殆どありません。仮に回復されたとしても、左半身の機能は難しいでしょう。右半身は既に機能を喪失されているのでリハビリをしても本人に苦痛を与えるだけで意味がありません。」
竜也は医師の口元を見ることができなくなりCTスキャンの画像に視線を移した。
「本人の容態も極めて危険です。通常ではこの規模の出血があると脳内圧が上がって死に至るケースが多いのですが、幸いというか、本人は以前左脳出血の手術をしたときに脳内部に空洞ができていました。そこに出血した血液が流れ込んで脳内圧は思ったほど上がっていません。我々としては、当面は酸素吸入に加えて血圧と脳内圧のコントロールをやりますが、もし小康状態に入れば脳外科ではそれ以上できることがありません。」
要は、このまま死ぬか、持ちこたえても放っておくしかないと言っているのだ。理屈の上では理解できても、他に何か方法はないのか。竜也は苛立ちを覚えた。
「それで、本人の容態が急激に悪くなる心配はあるのですか。家内の兄弟は神戸に居るものですから呼び寄せておく必要があるかと思いまして・・・」
竜也は内心自分が意味のない質問をしていることに気付きながら尋ねた。
「それは、何とも申し上げられません。しかし、御心配なら呼んでおかれた方がいいでしょう。」
医師の方も意味のない答えだった。竜也は一応梢の弟たちに連絡することにした。
梢は生来の頑張り屋だ。元気なときも身体が言うことをきかなくなるまで頑張った。アメリカで最初に倒れてからもそうだった。毎日の日課としてリハビリ体操を続けていた。
頑張り屋は本能的なものらしく、医師や竜也たちの心配をよそに翌日にはかなり安定してきた。とはいえ、意識は戻らなかった。3日目には緊急治療室から病室に移った。
S大学病院では一般病室の空きが殆どなく、梢は1日5万円の個室に入った。竜也の従兄や梢の弟たちが代わる代わる訪ねてきて、広い個室も花で一杯になった。
だが、梢は大きなイビキをかきながら眠り続けた。顔には酸素マスクが当てられ、腕には点滴、心臓には心電図、指には血中酸素計がつけられて、まるで完全武装した宇宙飛行士のような姿だった。
5日後、部屋を換えてもらった。いくら何でも1日5万円は高い。今度の部屋も個室で、1日3万円だった。一般病室に空きができたら転室させてほしいと竜也が頼んだとき、医師が意外なことを言った。
「奥さんは予想以上に体力がおありです。ひょっとすると、このまま病状が安定するかもしれない。そうなると、この病院では引き受けられなくなります。ここは緊急病院ですから長期入院はできないのです。転院先の病院はこちらで探します。」
医師のいう安定状態が続いて1ヶ月が過ぎた。今では梢の重装備も殆ど取り去られ、鼻腔に装入された流動食用のチューブだけが残っていた。梢は眠り続けていたがイビキはかかなくなった。そして時々目を開いた。
虚ろな表情で天井を見たり、時にはこちらを見たりしたが、呼びかけには反応せず意識はないようだった。
4月17日、S大学病院から羽田空港近くのT病院に転院した。竜也は会社があるので、恵子が救急車に同乗してT病院まで付き添った。
T病院は長期入院患者用の病院らしく、入院時の説明でも「何年でも居て下さい。」と貸し別荘に入るようなことを言われた。
医師はさかんに気官内装管を勧めた。これは喉に孔をあけて肺と食道に直接チューブを装入し、酸素と食事を確実に与えるようにすること。そこまでやると「生きる」というよりは「生かされる」ニュアンスが強くなり、竜也は同意しなかった。
梢の状態は俗に言う植物人間だが、それにしても少しは人間らしい生命維持をしてほしかった。
梢は機械の助けを借りることなく自分で呼吸している。間違いなく、生きているのだ。竜也としては、できることなら車椅子に乗れる程度に回復してほしかったが、それは無理だろうとあきらめていた。意識が戻る可能性は1%以下だと医師は言ったが、せめてもう一度あの素晴らしい笑顔を見せてほしいと思った。
T病院に転院してからも竜也は会社の帰りに梢を訪ねたが、毎日というわけにはいかなかった。だが、6月末の株主総会で退職が決まってからは殆ど毎日ように病院を訪ねた。
退職後にはあり余る時間ができる。妻の車椅子を押しながら、昔訪ねたヨーロッパの各地を旅行する。それは、竜也にとって漠然とした幸せの構図として頭の中にイメージされていた。
折角、会社生活から解放されたというのに、梢のために何もしてやることができない。せめて、傍に居てやれば梢に勇気を与えることができるのではないか、と感じた。
12月に入っても梢の意識は戻らなかった。竜也が一方的に話しかけても梢の反応はない。竜也は”妻と語る”ことができる日を夢に見た。竜也はせめて自分が手の届くところに居ることを何とか梢に認めてもらいたかった。
年の瀬も押し迫ったある日、梢が音に反応するようだと医師がいうので、竜也は梢の大好きだった琴のCDを買ってきて枕元でかけた。確かに梢は琴の音に少し反応を示した。少なくとも竜也にはそう思われた。竜也はそのときの喜びを介護日記の中で次のように書き記している。
x x x x
xx月xx日
病院に行く途中、蒲田駅の構内露店で琴のCDを見つけて購入した。名曲12点が入って980円はお買い得だ。
病院に着くと、妻は左横向きの姿勢で眠っていた。買ったばかりのケースからCDを取り出し、レコーダーに挿入した。ベッドの枕元でスイッチを入れ、少しボリュームを上げた。
『千鳥』の演奏が始まった。妻はうっすらと眼を開ける。自分の耳に入ってくるのが何の音なのか確かめているように見えた。私はそっと右手を妻の額に当て、琴のリズムに合わせて人差指で軽くこめかみを叩いた。
何曲かの演奏が終わり、妻が元気なときに何時も練習していた『六段の調べ』が始まった。妻は視線を忙しく動かしたかと思うと、じっと遠くに目をやった。何かを思い出そうとしているようだ。
私は人差指のビートを少し強くした。妻は視線を遠くに据えたまま何かを感じているように見えた。横向きの妻の左目にウッスラと涙が浮かび、やがて一滴のシズクとなって目じりからベッドにこぼれ落ちた。
何かを感じ取ったのだ!
琴の演奏とこめかみを打つ私の指のリズムを通じて私のアクセスに妻が反応を示したことに私は感動を覚えた。同時に、私の目からも涙があふれ出た。
今日は、妻に小さな幸せを与えることができたと確信する。また、私もほんの少しではあるが、妻と語ることができたように思う。
x x x x
![]()
「介護日記ーその後」にもどる
![]()
「白い闇」第38章に進む
![]()
トップページへ戻る