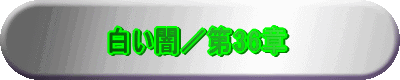
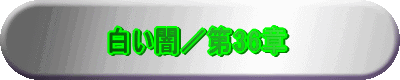
2002年4月、竜也はS大学病院で前立腺ガンの宣告を受けた。偶々測定した前立腺ガンのマーカーであるPSAの値が異常に高く、梢の通院で通いなれたS大学病院で精密検査を受けた結果、ガンが分かった。
少し前には、今上天皇が矢張り前立腺ガンの手術をされたとの報道があったが、竜也の場合は天皇陛下のケースよりも少し進んでいて、左リンパ節に転移が見られることから、「D1」レベルと判定された。
Dレベルだと手術をしても根治しないので、ホルモン療法でガンと共生することを勧められた。前立腺ガンは男性ホルモンを栄養にして増殖するため、男性ホルモンをブロックする目的から女性ホルモンを投与することでガンを休眠させておくという療法だ。
しかし、女性ホルモン投与には当然ながら女性化の副作用がある。それを嫌って投与を止めると、意外に早く進行するらしい。三波春雄や深作欣二のケースがそのようだった。
竜也には選択の余地はなかった。梢を残して先に死ぬわけにはいかない。竜也はガンと共生することを決心した。
幸い、病院が処方した薬が竜也に合ったのか、投薬後すぐにガンのマーカーであるPSAの値が下がりはじめた。医師はこの調子なら十分共生できると太鼓判を押した。
一方、竜也としてはこのまま3K生活を続けていく自信はなく、会社・家事・介護の3Kの中で最も負担の大きい”会社”を辞めることを考えた。山口工業の役員定年は常務が62歳。来年62歳を迎える竜也が退任することは決して不自然ではない。
竜也は糸川に自分の決心を告げた。アメリカの機械販社でサービス部門のマネジャーをしていた、あの糸川である。
糸川は竜也より2年後に帰国し機械部門に配属されていたが、数ヶ月前、竜也が自分のスタッフに引き抜いてきた。それ以来、竜也の最も信頼する部下となっていた。
糸川は竜也の決心を聞いて大いに残念がった。糸川は今までと違った仕事を覚えるのに忙しかったが、竜也をサポートし、竜也を通じで自分の考えを新しい職場に反映させることに喜びを感じていた。
また竜也が折に触れて糸川を引き立ててくれることも心強かった。糸川にとって、竜也の居なくなった事業部の運営は想像できなかった。
しかし、同時に糸川は竜也の家庭事情についても最もよき理解者だった。竜也の妻の状況をよく知っていたし、加えて竜也にガンが見つかった以上、慰留を強要することはできないと判断した。
「仕方ないですね。」
糸川が力なく言うのを確認して、次に竜也は筒井社長に面会を求めた。筒井は永田の後任の社長で、従来の山口工業の社長とはかなり違ったタイプだった。
竜也よりは2歳年上だが、入社後はずっと技術畑で、外部との接触は竜也に較べるとはるかに少なかった。外見も小柄で酒も飲まず、丁寧な言葉遣いはいっそう生真面目な印象を与えていた。
竜也の大学時代の親友の石川が何かのパーティの席で一緒だったらしく、竜也に筒井の印象を話したことがあった。
「今度のお宅の社長はエライ紳士やな。山口工業の社長というたらゴッツイおっさんかと思とったけど。」
石川は大学卒業後に入社した会社が1年後に他社に吸収されたことに嫌気をさし、当時できたばかりのリース会社のO社に転職した。その後、会社の成長とともにとんとん拍子に出世して、今では金融トップとなったO社の副社長の要職にあった。
竜也と石川は学生時代から馬が合い、山口工業の本社移転により同じ港区・芝に勤務するようになってからは交流を深めていた。2人が喋るときはお互い神戸弁丸出しなので、余計に親近感が感じられた。
社長室に入ると、筒井はデスクで書類に目を通していた。竜也を見ると、煙草をくわえて立ち上がり、前のテーブル席を勧めた。昨年から、オフィス内禁煙は常識となっていた。が、筒井は愛煙家なので、社長室に入ると煙草を吸えるのが1つのメリットだった。竜也も愛用のチェリーに火をつけた。
「実は、私の進退のことで相談に参りました。」
筒井は一瞬意外な表情を見せたが、竜也は続けた。
「先般、S医大から前立腺ガンの告知を受けました。病気の方はホルモン投与で落ち着いているのですが、何時どうなるかは予測できません。」
竜也は病院の診断書のコピーを筒井に渡した。筒井がそれに目を転じたのを確認して、更に言葉を続けた。
「来年6月で常務の定年を迎えます。その機会に降りる決心をしました。関係会社への出向も御配慮いただく必要はありません。」
診断書を見ながら竜也の話を聞いていた筒井は顔を上げて静かに言った。
「そうですか。潔い決断ですね。お宅は奥さんのこともあるし、なかなか大変ですね。判りました。来年の6月までは頑張ってください。」
竜也は慰留の言葉が全くないのに軽い失望を覚えたが、石川のいう細面の紳士らしい発言かもしれないと思った。
実はこのとき筒井が、既に、肺がんに犯されていることは全く知らなかった。筒井の言った”潔い決断”には、自分はガンでも辞めないぞ、という意味が含まれていたのかもしれない。
「私の後任ですが、後継者指名制度に基づいて鴨田くんをお願いします。」
「鴨田くんねえ。一応、お考えは承っておきましょう。だけど、保証はできないよ。」
山口工業には後継者指名制度というものがあり、自分の後継者を指名できるようになっている。筒井は保証できないと言ったが、竜也はこれで鴨田に決まった、受けとめた。
また、他に竜也の仕事を引き継げる人物は考えられなかった。糸川ならやれるかも知れないが、何といっても竜也とは10歳以上違う。此処は4歳年下の鴨田に任せる以外にはないと決めていた。
だが、結果的にはこの判断は裏切られることになる。これが竜也の経験する山口工業での最後の人事の裏切りになるのだが、竜也は迂闊にも全くそれには気づいていなかった。
通常、サラリーマン重役が常務に昇進すると、1段上の専務を目指してミスをしないよう慎重になる。だが、竜也の場合は自分からその道を閉ざしたことで気が楽になった。竜也は積極的に筒井に新しい提案をぶっつけていった。
折から、二酸化炭素の排出によって地球の温暖化が進むと騒がれ始めた時期で、山口工業でも二酸化炭素排出を削減するために各種の施策が検討されていた。
しかし、空気中に0.5%しか含まれていない二酸化炭素が、温室効果ガスとして地球温暖化の犯人だと決めつけることに竜也は合点がいかなかった。竜也はこの分野の専門書を何冊が読み、日本でも多くの専門家が地球温暖化や二酸化炭素犯人説に懐疑的な見解をもっていることを知った。
特に、京都議定書に定められた日本の削減義務は、数字の決め方がフェアでないばかりか、ジャパン・バッシングそのもののように思われた。
竜也はこのことをレポートにまとめ、筒井に上申した。筒井は部下の話をよく聴くが、根は頑固なところがあった。
「中野クンのレポートはよくできているし、言うことも判るが、だからといって当社が時代の趨勢に逆行することはできないでしょう。」
筒井らしい判断だと竜也は思った。筒井は1年後に肺がんの手術を受けるが、病状は回復せず現役の会長のまま他界することになる。
一方で、竜也は山口工業での自分の仕事が後1年で終わると思うと限りない寂しさを憶えた。だが、同時に有り余る自由時間をどのように過ごすかを想像すると楽しかった。
梢を旅行に連れて行ってやろうと考えた。10年近くも車椅子での生活を余儀なくされ、人並みの楽しみを奪われてしまった梢を最大限に喜ばせることが自分の残された使命であるとさえ思った。
竜也は日本に帰ってから梢を何度も国内旅行に連れていった。夏には北海道、冬には沖縄。昨年の冬は鹿児島に行った。
指宿まで足を伸ばして、新婚旅行で植樹したワシントニアを見に行ったのだ。指宿での1日は今も忘れることはできない。
35年振りの鹿児島は殊のほか寒かった。桜島は雪で覆われていた。地元の人に聞くと18年ぶりのことらしい。空港でレンタカーを借りた。2人だけのドライブなので小さなクルマでも良いのだが、車椅子を入れるためトランクの大きな中型車にした。
国道226号線を真直ぐに南下する。指宿は薩摩半島の最南端に位置する。60㎞ほどの道のりだが、片側1車線の道路なので早くは走れない。
助手席の梢は、窓の外を見ながら大きな声をあげていたが、30分もすると静かになった。大脳に障害があって直ぐに疲れて眠ってしまう。
左手の海は、風が強い所為か白波を立てている。渋滞の中を2時間ほど走ると、前方に開聞岳が見えてきた。薩摩富士と呼ばれる山の形だけは記憶に残っている。
指宿市内に入った頃、梢は眼を覚ました。突然、何やら大きな声で喋りだしたが、よく分からない。適当に相槌を打って、こちらから話しかける。その方が会話の的を絞りやすい。
「あの山の形は覚えているよね。」
「そうやねぇ。」
今度は梢が相槌を打つ。簡単な言葉は自然に出てくる。
市内を少し迷った後、今夜の宿泊先・指宿観光ホテルに着いた。大きなホテルで、当時は新婚旅行の客で満員だったが、今は閑散としている。
ホテルの駐車場に車を停めた。トランクから荷物と車椅子を取り出して、取りあえずチェックインを済ませると、妻を車椅子に乗せて外に出た。
ホテルの庭は公園のようになっていて、少し行くと見晴らしのよいところに出る。そこからは、錦江湾が一望に見下ろせる。
竜也は車椅子を停め、コートのポケットから1枚の古びた写真を取り出した。35年前、錦江湾をバックに2人で肩を組んで写っている写真だ。同じところでもう1度記念のスナップを撮ろうと計画していたのだ。
その場所からの景色は写真のままだった。なだらかな弧を描いた海岸線が眼下に広がっていた。
竜也は、誰かシャッターを押してくれる人を探した。が、視界には人影はない。あの時はハネムーンのメッカ。若いカップルで混み合っていた。記念の1枚を撮るのに場所が空くのを暫く待たなければならなかったほどだ。
しかし、今は寂れ果てた公園を訪れる人もない。今どきの新婚さんは殆どが海外に出かけるらしい。
その時、公園の入口近くに親子連れが現れた。
「スミマセーン。」と叫んで手を振った。妻も何か叫んだ。
小学生くらいの女の子の手を引きながら中年の婦人が近づいてきた。
「あのー。すみませんが、この写真と同じアングルでシャッターを押して貰えないでしょうか。」
写真を手にした婦人は、そこに写っている若いカップルと、今、自分の横に居る私たちを見較べて、「まあ!」と小さく叫んだ。
娘さんも写真を覗きこんで表情をゆるめた。
あれこれと被写体の私たちに注文をつけながら、婦人は慎重に3枚のスナップを撮った。
「ありがとうございました。」
カメラを受け取って、その場を離れようとする私に、婦人は話しかけてきた。
「これ、新婚旅行でしょ。何時の写真ですか。」
「はぁ。35年前です。」
「素晴らしいですわ。ウチでは新婚旅行の写真なんて何処へいってしまったか、分からないです。」
今度は、少し腰を屈めて車椅子の梢に顔を向けた。
「奥さん、幸せね。羨ましいわ。」
梢はニッコリ笑って頷いた。
「そうよ。私は幸せよ。」
笑顔の目が語っていた。
![]()
「介護日記ーその後」にもどる
![]()
「白い闇」第37章に進む
![]()
トップページへ戻る