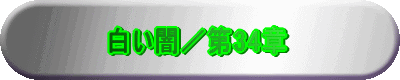
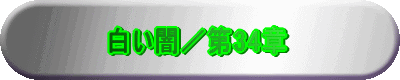
1997年6月の株主総会で竜也は取締役に昇進した。専務の新田が強く推してくれたに違いなかった。しかし、皮肉にも新田自身は本社役員から外され、子会社の会長に転出となった。
取締役就任直後、竜也は挨拶を兼ねてテキサコ社を訪問した。竜也には営業部長の古川が同行した。竜也のアメリカ時代にアルミホイールのビジネスで一緒に仕事をした京都のボンボンである。同期入社の竜也と古川は同じ職場に配属されることが多かった。トルコ・ラクタムプラント、ミシガンの機械販社、そして今度は本社の環境・エンジニアリング事業部。2人は何となく互いに因縁めいたものを感じていた。
テキサコ本社はニューヨーク郊外のホワイトプレーンにあった。白亜のビルの一室で竜也と古川は3人のテキサコ社員と向かい合った。中央には、ジム・ファルセッティ。
ファルセッティはガス化部門の副社長。営業のトップとして何度も来日していて、竜也とはファーストネームで呼び合う関係にあった。
簡単な挨拶の後、古川が山口工業の石炭ガス化プラントのビジネスプランについて説明した。古川は、社内では疑問符のついたプロジェクトも有望案件として熱弁を振るったので、ファルセッティは満足そうに聴いていた。
それぞれの案件についての両者の意見交換も終わり、両者が席を立つころを見計らって、竜也はおもむろにゴミのガス化の概念図を取り出して説明した。
テキサコから反対されると今後の開発が上手く進まないので、先ずテキサコの了解を取っておきたかった。テキサコからは特にコメントはなく、ゴミのガス化は採算が難しいという一般論としての意見が出た。
当時、テキサコはオランダのロッテルダムで試験的にゴミのガス化に着手していた。しかし、オランダではゴミの再商品化に支払われる処理費はトン当たり1万円前後。それでは、採算的に合わないとのことだった。
竜也は容器包装リサイクル法の下では7万円の処理費が期待できることは伏せた。ただ、自分たちはこの技術の開発を続けていくことだけは伝えた。
「テキサコは何も言わなかったですな。」
帰りの車の中で古川が言った。山口工業が新しく開発する技術をテキサコが容認したと理解したようだ。
「そう断定するのは未だ早いが、一応、伝えることは伝えたよね。」
古川は常に楽天的に考えるが、今日のミーティングでテキサコが了解したというには、一抹の不安が竜也には残った。
新技術の開発をスタートするに当たって、山口工業の役員会では『テキサコの事前了解を得ること』という条件がついていた。
テキサコのガス化部門はライセンス収入だけで成り立っていた。ライセンサーとして世界中のライセンシーに技術の実施権を与え、見返りにローヤルティを受け取る。技術が唯一の収入源なので、ライセンシーが開発する新しい技術もテキサコの技術だと主張するケースが多かった。
開発が進むにつれて、新技術は極めて高い将来性を秘めていることが判ってきた。その第1はドライフィードと呼ばれる乾式の原料投入にあった。
テキサコのガス化炉は石炭を微粉にして水に混ぜ、スラリー状にしたものをバーナーから吹き込むので、ウェットフィード(湿式)と呼ばれていた。この方式ではガス化に必要な熱量が水を飛ばすのに消費されるため、折角の石炭の熱量が無駄遣いされてしまう欠点がある。
日本では、T電力が中心となって勿来で実証中のIGCCと呼ばれる国家プロジェクトには最初から湿式プロセスは除外された。
竜也たちが開発を進めるプロジェクトでは、E社の2段炉をベースにするとドライフィードが可能となる。このプロセスは、発電所の高効率ボイラーとしても利用できる見通しが出てきた。山口工業とE社の技術陣は新技術の開発に没頭した。その過程では多くの特許が申請され、業界紙や学術誌にも華やかに紹介された。
ラボ・レベルの技術開発が終わり、実証プラントの完成が近づいた頃、丁度、柿の実が熟すのを待っていたサルかに合戦のサルのように、テキサコからクレームがついた。
新技術はテキサコ技術の模倣であり、山口工業はテキサコ技術を他目的に転用している、という内容だった。
テキサコの狙いは明白で、山口工業とE社が共同開発した技術をタダで手に入れようというのだ。竜也は弁護士と相談したが、テキサコからのクレームレターは法律面で厳重に武装されおり、訴訟の前段のような体裁を整えていることがわかった。
アメリカの特許裁判では、射出成形機のレメルソン特許の苦い経験があった。何としても訴訟は避けなければならなかった。
早速、竜也はテキサコのジム・ファルセッティに電話した。ジムも訴訟は避けたいとの意見だった。
その日から、ジムと竜也の目まぐるしい交渉が始まる。未だEメールが十分普及していない段階だったので、ファックスや電話だけでは足りず、時には片方が相手側に出張して交渉をもった。最後は、東京のTホテルのジムの部屋で、明け方まで2人で話し合った。
ジムは竜也の立場を理解してくれた。何とか社内を説得してみる、と約束して別れた。が、テキサコ社の法務部の態度は強硬だった。
1999年7月、テキサコはニューヨーク連邦地裁に山口工業をライセンスの不当流用という理由で提訴した。訴状は山口工業の実証プラントの即時仮差押さえをも請求していた。
竜也たちは正面から受けて立つ以外になかった。日本側の弁護士に加え、ワシントンの法律事務所とも契約を結び、早速防御体制を敷いた。テキサコとのガス化プロセスのライセンス契約に基づき、裁判はアメリカの法律に則り行われる。対応には大変な精力を割く必要があった。
先ず、ディスカバリーと呼ばれる予備調査があり、テキサコ側の弁護士に対して関係書類をすべて提出することが要求された。
次に、予審の段階に進むと、竜也たちは米国領事館に呼び出され証人喚問を受けた。厳重なボディーチェックの後、ビデオカメラの前に座らされ、テキサコ側の訴追弁護士からの尋問に答えるのだ。不用意な発言は一切許されない。
竜也たちはワシントンから呼び寄せたアメリカ人弁護士たちの前で何度も何度もリハーサルを繰り返した。
争点は、テキサコのガス化プロセスと、新しく日本側が開発したゴミのガス化プロセスが、内容的に同じものか異質のものか、という極めて技術的な問題である。竜也たちは、アメリカ人弁護士たちに2つのプロセスの差異を丁寧に説明した。
主任弁護士のベールは、小柄で禿げ上がった風采からは想像できないほどシャープで、技術的なポイントをよく理解し、鋭い指摘で竜也たちの防御を指導した。竜也はベール弁護士がレーニンに似ていると思った。
テキサコとの裁判は意外に早く進み、2000年3月には予審の最終段階を迎えた。竜也を筆頭に新技術の開発に関係した山口工業の5人の社員は、ニューヨークの連邦地方裁判所に出頭した。荘重な趣の建物に入ると、中は厳粛な空気に包まれていた。
テキサコの関係者も来ていた。ジム・ファルセッティの顔もあった。竜也は目だけで挨拶を交わすと、被告側の席についた。
裁判長は女性だった。ベールによると辣腕の判事らしく、クリントン内閣に勤務したこともあるという。
この裁判に備えて、竜也たちは第一級の通訳を雇った。翻訳が上手なだけではなく、声の通りや真摯で誠実な喋り方が要求される。裁判長が女性なので尚のこと印象が大切だった。
テキサコ側の弁護士による尋問、ベール弁護士の反対尋問、裁判長の質問などが続いた。竜也も証人席に招かれ尋問を受けた。
映画でしか見たことのない裁判所の証人席で証言するときは流石に気持ちの昂ぶりを抑えることができなかったが、ベール弁護士の笑顔を頭に浮かべながら、努めて冷静かつ慎重に答えた。
法廷が3日目に入ったとき、裁判長が全員に対して厳かに宣言した。
「本件は極めて専門的な技術の色彩が濃い内容である。私は専門家ではないが、私の判断では2つの技術が同一であるとするテキサコ側の論拠は十分であるとは認めがたい。従って、テキサコ側の仮差押さえの請求は却下する。」
ベール弁護士の口元が一瞬ゆるんだように見えた。
「また、仮に本件を本裁判に持ち込んだとしても、技術の専門家ではない陪審員たちが本件の問題点を正確に判断できるとは思えない。従って、両者に和解を強く勧告する。裁判所が和解調停人を選定するので、その調停人の調停の下、3ヶ月以内に和解することを勧告する。山口工業側も有能な社員をこんな場所に滞在させずに早く帰国して、本業に復帰することを勧告する。」
竜也たちは意外なほど好意的な裁判長の言葉に興奮を隠せなかった。テキサコ側の弁護士たちは口惜しそうに唇を噛み、ベール弁護士は小声でビクトリーだと囁いた。
3ヵ月後、和解契約書に双方の弁護士がサインして訴訟問題は解決した。テキサコが提訴してから丁度1年が経過していた。山口工業はテキサコに和解金を支払ったが、その金額は予定の半分以下で、テキサコ側としては弁護士費用もカバーしきれなかった。
一方、山口工業としても大きな痛手を蒙った。それは、テキサコのライセンシーとして石炭ガス化プラントのエンジニアリングが、継続中のものを除いて、できなくなったことである。
プラントビジネス再生の切り札として考えていた石炭ガス化プラントを切られては、もはやプラントビジネス存続の道はなかった。
結果的には自らの手でプラント事業の幕引きをしなければならなくなったことに竜也は強い責任を感じた。海外でのプラント建設に憧れて山口工業に入社した若い社員たちの夢を自分が打ち砕いたのだ。同時に、25年前、プラント事業部を華々しく立ち上げた故・塩川社長に詫びなければならないと思った。
後年、プラント部隊の手で最後のテキサコ石炭ガス化プラントが完成した折に、竜也は、プラント事業撤退のことを懐古して、社内イントラネットの『若き技術者に贈る』シリーズに懺悔録を書き、その最後の部分を次のように結んだ。
* * * *
テキサコとの裁判が結審した2000年の7月、私は1人で山口県のU市にある故・塩川社長の墓を訪ねた。
墓前には数日前に供えられたとみられる菊の花が、炎天下に元気なく首をたれていた。私はそっと半ばしおれかかった菊の花を抜き、用意したバラとカーネーションの花束を供えた。故人の性格からして華やかな方が喜ばれるだろうと考えた。
静かに手を合わせ、頭をたれて、声に出して詫びた。
「赦して下さい。私があなたの創られたプラント事業部を潰しました。」
これで、少しは精神的に楽になったとはいえ、ガス化プラントやセメントプラントからの撤退は当時の私自身を苛め続けたことを告白しておきたい。
海外でのプラント建設に男の生き甲斐を求めて当社に入社した若き技術者も多く居たと思う。その夢を私自身の所為ではないとはいえ、自分の手でもぎ取ってしまった。
プラント事業からの撤退は、プラントが過去に積み上げた恐ろしいほどの赤字の山からすれば当然の帰結ではあったとは思うが、君たちの幾人か、いや、多くの人が今も心の片隅にしまいこんだわだかまりの一部になっているのではないかと思う。
今般、当社にとっては、恐らく、最後のテキサコプラントとなるIGCCプラントが完成した。赤々と燃えるフレヤースタックの炎の中に、私は君たちの達成感と同時に無念さを見ることができる。
私の中でも、既に灰になったはずの自責の念がこの炎によって再び燃え上がるような気がしてならない。出来ることなら、君たちのわだかまりも私の自責の念もすべてこの炎が焼き尽くしてくれることを願ってやまない。
(2003年1月記)
* * * *
![]()
「介護日記ーその後」にもどる
![]()
「白い闇」第35章に進む
![]()
トップページへ戻る