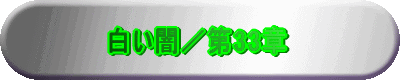
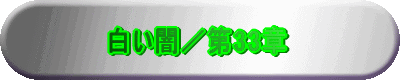
亜希子と悦子を家探しのために先に返して、竜也と梢はゴールデンウィークに2人で帰国する予定を立てた。が、猫のビビを置いていくわけにはいかない。たくさんの荷物を抱えて、竜也1人ではとても無理。長女の恵子を日本から呼び寄せることにした。
恵子は二つ返事でやってきた。学生時代ミシガンに留学経験のある恵子にとって、往復航空券付きの旅行は魅力だったらしい。早めにやってきて、昔の友達と旧交を温めるのに忙しかった。
出発の日、梢の車椅子を恵子に任せ、竜也はスーツケースと猫のビビが入った篭を持って車に乗り込んだ。空港までは、会社の河田が送ってくれた。
成田行きのノースウェスト機の中で、梢は体調を崩したのか、苦しんで食事をもどした。スチュアーデスの手厚い看護もあって、何とか成田に着いたものの、梢は救急車で空港のクリニックに直行となった。
帰国早々のハプニングに竜也は前途多難を感じたが、その場は恵子の協力もあって何とか無事におさまった。空港のホテルで一泊すると、朝には梢はすっかり回復したようだった。
恵子は富里の家に帰ったが、竜也と梢はこのホテルにしばらく滞在し、ミシガンから発送した家財道具が新しい家に到着するのを待った。
新居は亜希子が選んだ家賃20万円の戸建で、杉並区の善福寺にあった。竜也は翌日梢をホテルに残して新居の視察に出かけた。家賃はミシガンの家より高いが、広さと内容は比較にならなかった。
40坪足らずの敷地一杯に建てられた2階家で、1階にLDKと6畳1間。梢はこの狭い空間で生活しなければならない。竜也は少し心配になった。しかも、朝霞の母を引取れば、母も2階には上がれないから、狭い6畳にベッド2つを置くことになる。それに車椅子が2台要る。
2階には3部屋あるが、亜希子と悦子が既に自分たちの部屋を確保していた。残る1つが竜也の書斎兼寝室となる。
数日後、ミシガンからの大量の家財が到着すると、たちまち家の中はモノで溢れてしまった。
恵子の夫の青田が富里の家から車をもって来て、竜也と梢はホテルから我が家に向かった。梢は窓の外の車の洪水を珍しそうに眺めていた。
善福寺の我が家に到着して、早速問題が出た。玄関の門から上がり口までほんの数歩の距離だが、飛び石になっていた。車椅子が通れないし、梢も歩けない。青田が近くで大きな板を買ってきてそれを敷き、その上を梢に歩かせた。
「よいしょ。よいしょ。」と自分を励ましながら梢は多点杖を使って板の上を上手に歩いた。上がり口も段差があったが、梢を靴のまま押し上げた。梢の靴は右足首の曲がりを矯正するための深い靴で、脱がせると上手く歩けないため、梢は靴のまま上がることにした。
梢は何度も「すげえなあ。」とため息まじりに荷物の山を眺めていたが、疲れたのか自分のベッドに横になった。梢には、毎日、午後に数時間の昼寝が不可欠で、そのために梢のベッドだけは真っ先に準備してあった。
竜也は荷物の山に埋もれて、これで何回目の引越しだろうか、とため息をついた。数えてみると結婚後10度目の転居だった。これまでは、梢が張り切って殆ど片付けてくれたが、今回は梢を当てに出来ない。少しずつ片付ければいいか、と竜也は長期戦を覚悟した。
1週間後、竜也は朝霞の母を引取った。案の定、梢と母のベッドで6畳間はほぼ埋まってしまった。
亜希子は前年の夏にミシガン大学を卒業していて、4月から赤坂の日本商事に勤務していた。
悦子はサリーン・ハイスクールの2年終了のまま帰国したが、3学年への編入は何処の高校も難しかった。帰国子女受入れ校を捜し歩いて、漸く中央線の高尾にあるE高校へ2学年からの転入がかなった。1年遅れることになるがやむを得ない。
竜也の日本での新たな3K生活がスタートした。
竜也の新しい職場は、以前勤めたことのある旧・プラント事業部で、現在は『環境・エンジニアリング事業部』と名称変更し、従来の海外向けプラントビジネスから環境ビジネスへの転換を図っていた。
海外向けプラント事業は、発展途上国が自国の経済発展のために建設する各種の工場設備を受注し、エンジニアリング(設計)、プロキュアメント(機器調達)、コンストラクション(建設)を経て最終的に客先に引渡しを行う。英語の頭文字をとって、EPC契約と呼ばれる受注形態である。
受注から引渡しまでの期間が長いため、必然的に、様々なリスクに直面する。1件あたりの受注金額が数百億円に上るセメントプラントの大型商談では、48ヵ月納期というのが一般的。この間に相手の国で経済変動が発生すれば、折角完成したプラントで製造するセメントが市場で売れない。そうなると、客先はプラントの受取りを拒否する。一方的な受取り拒否は契約違反となるから、細かな難癖をつけてプラントが完成していないことを主張するのだ。こうなると、コントラクター(受注者)側では売上を計上することができず、代金回収も著しく遅延し、泥沼に入ってしまう。
一般的に、欧米のコントラクターは契約書を前面に出して手切れよく引渡しをおこなうが、日本のコントラクターはそうはいかない。特に、山口工業は会社の成り立ちがプラント専業メーカーではなく、モノ造りから発展した企業なので、どうしてもプラントのユーザーの立場に立ってしまう。
“ユーザー志向のプラントメーカー”というのが山口工業の“売り”だったが、これが両刃のヤイバで、客先にプラントを引渡す際の手切れが悪い。その結果、月単位で何億もの追加原価が発生する。
プラント事業部の誕生から15年を経過した時点で、累積損失は数百億円に達していた。社内では、プラント事業からの早期撤退を唱える声が次第に高まりつつあった。
竜也は、そこの事業部長を任命された。決して易しい仕事ではないが、昔の懐かしい顔ぶれが竜也を迎えてくれた。
ボスは新田専務で、彼が機械と環境・エンジニアリングの両方の事業部をみていた。新田は、早速、竜也を自室に招いて将来への自分の抱負を語った。
「プラントの仕事は、現在はセメント関係で何とか食いつないでいるが、いずれは駄目になる。プラントに代わる新しい分野が環境ビジネスだ。環境は裾野が広く、ビジネス規模は途方もなく大きい。セメントプラントで稼いだ利益を環境に注ぎ込んでこれを育ててほしい。」
新田の話は一応筋が通っていたが、竜也にはセメントプラントが果たしてどの程度利益を上げているのか疑問が残った。竜也はセメントプラント営業部長・富田の話を聞くことにした。
富田は竜也よりも1年先輩で、以前トルコ向けのラクタムプラントで竜也と一緒に仕事をしたことがある。10年前、竜也がプラント事業部を去るときに、既に、現職についていた。当時は机を並べる同僚の部長だったが、今は明確に上下の差がついていた。
富田は何でも割り切って考えるタイプで、自分のやる仕事のストライクゾーンを狭く設定していた。そこに入らない案件はすべてゴミ箱に捨てられるので、商社連中からは「折角、案件を持ち込んでも相手にしてくれない。」と、けむたがられていた。
事実、富田のデスクの上には何時見ても電話機以外何も見当たらず、ゴミの山のような竜也のデスクとは大違いだった。竜也は富田に対して肌合いの違いを感じていたので、幾分改まって質問した。
「今度、偶々、セメントプラントも見る立場になったが、この分野は私にはよく判らないので全面的にお任せしたい。新田専務によると、セメントプラントで稼いだ利益を新分野の環境に注ぎ込んで環境ビジネスを育てろということだった。」
竜也は一旦言葉を切り、富田の顔を窺いながら続けた。
「富田部長の立場からは、他所のために稼いでいるんじゃない、という反論があるかもしれない。だが、その議論の前にセメントプラントでは、この先どの程度の利益を見込んでいるのかお聞かせ願いたい。」
「新田専務に何を吹き込まれたかは知らないが、セメントの利益を当てにするなんて全くのお門違いだよ。」
富田は、上司に対するというより以前の同僚に対する言葉遣いで説明を続けた。竜也には富田の話し方は不遜ではなく、むしろ親しみを込めているように感じられた。
「セメントの生産量は世界的に過剰で、新しいプラントの引き合いは激減している。しかも、受注済みの案件の採算も悪い。このままだと、セメントプラントからは早晩撤退すべきだと思う。」
「今期の受注予定に上がっている2件についての採算はどうなの。」
「この2件については、ボクは受注できるなんて考えてもいないよ。他に有望案件がないから無理やり上げさせられたようなもので、こんなものを当てにしていたら経営を間違えるよ。」
竜也は資料をベースに詳細な説明を富田から受けたが、その中身は惨憺たるものだった。今期受注予定の2百億円近い案件が消えることも重大な問題だが、それ以上に既に受注した案件に種々のクレームが発生しており、その解決には今年度以降に相当な額の追加コストが発生する見込みだった。
竜也はこのようなセメントプラント部隊の現実が新田に正確に報告されているとは、とても信じられなかった。
エンジニアリングのもう1つの柱は化学プラントであった。特に、山口工業の石炭ガス化プラントは世界に知られていた。
石炭をガス化する技術は、大きくドイツ系とアメリカ系に分けられるが、最近ではアメリカのテキサコ社のプロセスの普及が顕著だった。実は、その裏には、エンジニアリングを担当する山口工業のノウハウが隠れていた。
山口工業では、石油ショックの直後に自社のアンモニア工場の原料を世界に先駆けて、石油から石炭に切り替えることに成功していた。アンモニアは化学工業の重要な基礎原料だが、その組成は単に水素と窒素を合成させたもの。窒素は空気中に大量に含まれているので原料としては無尽蔵だが、水素はナフサと呼ばれる石油を分解して製造するのが一般的であった。
山口工業では、水素の原料をいち早く石炭に切り替え、テキサコ・プロセスで石炭をガス化分解して水素を取り出すことに成功。1980年代の初頭にこの技術を商業化してオーストラリア炭をベースにアンモニアを製造していた。
実は、この石炭ガス化計画が表面化したとき、竜也は間接的にこれに関与した。それも竜也には珍しい否定的な関与の仕方であった。
当時、会長の中田は石炭ガス化計画の積極的な推進者だったが、社長の水沼はこの計画に不安を感じていた。中東では石油を採掘するときに出てくる随伴ガスを原料に水素を製造し、アンモニアを生産していた。随伴ガスは100万BTU当たり50セントというタダ同然の価格。オーストラリアからわざわざ高い石炭を運んでそれをガス化しても、中東の随伴ガスと競争できるとはとても思えなかった。
水沼は、当時化学監理部長だった幸田に中東のアンモニア生産の現状を密かに調査するよう特命を出した。同時に、デュッセルドルフに居た竜也に幸田をサポートするよう依頼がきた。
社長の特命により、幸田と竜也はクエートからサウジを回り、アンモニア製造コストを詳細に調査した。この調査を基に幸田が報告書をまとめたが、それには石炭ガス化はコスト的に成り立たないと結論付けられていた。
水沼は報告書を満足げに眺めると、おもむろに口を開いた。
「この報告書を基に、中田会長に反論することはしない。ボクはこの報告書を机の中にしまっておいて、ガス化プロジェクトが失敗したら、その時にこれを取り出して『最初から判っていた。』という積もりだ。」
水沼のこの発言には幸田も竜也も唖然としたが、結局、この報告書が陽の目を見ることはなかった。石炭ガス化プロジェクトは大方の予想に反して見事な成功を収めたのだ。その陰には、EPCを担当した当時のプラント事業部の果たした役割が大きかった。
プロセスオーナーのテキサコも山口工業のEPC能力には一目置かざるを得なかった。これを契機として、プロセスはテキサコ、EPCは山口工業という評判が世界中に広まり、両社の蜜月時代が続いた。
竜也が事業部長に就任したときには、化学部隊は中国向けに2百億円に上るガス化プラントの大口商談を決めていた。しかも、このプロジェクトは中国向けには珍しく採算も良かった。セメントプラントの将来に明るさが見えないことが確実になり、竜也はガス化プラントに期待をかけた。
しかし、90年代後半から始まる東南アジアの不況のため、ガス化プロジェクト自体の具体化が進まず、他方ではテキサコとの間に決定的な亀裂を生じる事態が発生することになる。その引き金となったのは、皮肉にも竜也たちが環境事業の目玉として開発を進めてきた”新技術”であった。
竜也が帰国して新職場に赴任したときに最も喜んだのは福井だった。福井はソ連にジェットコースターのプラントを売り込んで以来営業マンとして自信をつけていた。
同時に、化学屋としての技術的背景から、環境ビジネスに進出するに当たって1つのアイデアを持っていた。それはテキサコの石炭ガス化技術からヒントを得たゴミのガス化であった。
当時の世の中は大量消費社会から循環型社会へと大きく変わろうとしていた。このトレンドを先取りして、廃棄物をガス化し水素を取り出すことを福井は考えた。
特に、容器包装リサイクル法が施行されると、カロリーの高いプラスチック類が大量にゴミとして出てくる。プラスチックは元々石油から作られているので、化学成分からいえば石炭よりも利用価値の高い炭化水素であるはずだ。
石炭がガス化できるのにプラスチックのゴミがガス化できないはずはない。福井の着眼点はここにあった。
しかも、プラスチックのゴミを再商品化(つまり、リサイクル)すれば、処理費として、トン当たり7万円近い収入が期待できた。
これまでは、トン6,000円の石炭を購入して、これをガス化することで水素を得ていたが、原料の石炭をゴミに切り替えれば材料費はマイナス7万円になる。机上の計算では、水素の製造コストはゼロ以下になるかもしれない。
更に、21世紀は水素の時代といわれるように、燃料電池を初めとして水素の用途はアンモニア以外にも大きく広がることが予想された。
福井はこのアイデアを熱心に竜也に語った。竜也は福井の話を聴くうちに、このアイデアが既に具体化に向けて相当進んでいることを知った。福井は、技術開発のパートナーとして環境のトップメーカーのE社と既にコンタクトを進めていたのだ。
当時、E社は地方自治体向けに新しいタイプのゴミ焼却炉を売り込んでいた。ガス化溶融炉と呼ばれる新型焼却炉は、従来使われていたストーカー炉と異なり、ダイオキシン発生のリスクが極端に低い。E社はこれを次世代型焼却炉と呼び、次期戦略商品に位置づけていた。
E社のガス化溶融炉は2段の炉からなり、1段目の低温炉で先ずゴミを蒸し焼きにし、発生するガスを熱源として2段目の高温炉で完全燃焼する構造だ。福井はE社の高温炉を不完全燃焼炉に変えれば、ゴミから水素がとれるはずだと考えた。
例えば、マッチ棒に火をつけると完全燃焼して水蒸気(水)と炭酸ガスが発生し燃えカスが残る。これは空気中の酸素が十分にあるため、H2OとCO2になってしまうわけだが、酸素がない状態つまり酸欠状態で燃やせば不完全燃焼して、H2とCO、つまりO(酸素)が1つ足りない状態のH2(水素)とCO(一酸化炭素)の段階で化学反応が停止する。テキサコはこれを部分酸化と名づけ、炭化水素を部分酸化するために特殊な炉を開発していた。
酸化してしまうと価値はないが、部分酸化状態の水素や一酸化炭素は大きな価値がある。ということは、E社のガス化溶融炉を雛形にすれば、1段目の低温炉はすでに完成しているので、2段目の高温炉だけをテキサコとは異なる部分酸化炉にすればよい。開発の雛形をE社のガス化溶融炉に置くことで、テキサコ技術とは異質のものができるはずだ。
竜也は福井のアイデアに乗った。先ず社内でオーソライズしてもらうために、E社の藤山会長に御足労願い、山口工業の新任社長の永田とのミーティングをアレンジした。
藤山は業界ではミスター・ゼロエミッションの名で知られた名物会長で、藤山が熱心に呼びかける共同開発に労務屋上がりの永田は反対する理由もなく、竜也に本件を取りまとめるよう指示が出た。
喜んで応じた竜也は、福井に共同開発契約書のドラフトを作成するよう命じた。
新しいプロセスを開発するためには、ラボテストやコンピュータを使ったシミュレーションが重要だが、どうしてもセミコマーシャル規模の実証プラントを建設する必要がある。
試算では30t/dの能力の設備でも30億円の建設費がかかる。福井は当時の通産省に日参して、9億円の補助金を確保してきた。
不足分をE社と山口工業が9億ずつ出し、総額27億円の予算で実証プラントを建設する計画を立てた。
この計画を経営会議に上申したとき、真っ先に反対したのは、意外にも前社長で今は会長職にある東山だった。東山はО大学・化学工学の出身でE社の藤山の先輩に当たる。しかも藤山は溶接の出身だった。東山にしてみれば、溶接屋に化学のことが分かるはずがないという一種の自負のようなものがあった。
ゴミのように品質の不安定なものをガス化するのは容易ではないと感覚的に判断したのだ。東山の発言につられて他の役員連中が反対意見に傾きかけたとき、それまで沈黙していた社長の永田が発言した。
「要するに、10億円をドブに捨てると思えばいいのか。」
「そうです。」
案件の説明者だった竜也は、嬉しさの余り些か上ずった声で答えた。永田の一声でこの案件は採決された。
![]()
「介護日記ーその後」にもどる
![]()
「白い闇」第34章に進む
![]()
トップページへ戻る