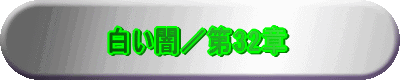
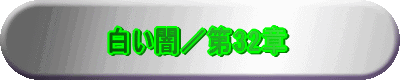
日本に帰国するまでに、竜也にはどうしてもやらなければならないことがあった。それは、梢をアトランタに連れて行き、一緒にタラの町を探すことだった。
学生時代からスカーレット・オハラを自分の理想像にしてきた梢にとって、『風と共に去りぬ』の舞台となったアトランタを見ずに帰国するわけにはいかない。
留守を亜希子と悦子に頼んで、竜也と梢はアトランタに飛んだ。96年春のアトランタは、目前に迫ったオリンピック開催の準備で街中はいたるところで工事中。その日は市内観光を簡単に済ませ、翌朝レンタカーで南に向け走った。
タラは架空の町なので実際には存在しないはずだが、竜也には目算があった。前夜、アトランタで買い込んだ沢山の地図を調べていて、市の南方に「ゴーン・ウィズ・ウィンド」と小さく書かれた地区を発見していた。
竜也は、そこに行けば何かがあるはずだと考えて、地図を片手にタラ探しに出かけることにした。梢は助手席で眠っていた。昨日の市内見学で興奮して疲れたのだろう。竜也は梢を起こさないよう静かに運転した。
2時間も走ると、地図に示された場所にやってきた。だが、そこは何の変哲もない新興住宅地。日本流にいえば、郊外のサツキ台とか青葉台といった名前で呼ばれる中流クラスの住宅が立ち並んでいて、特に目ぼしい建物はなかった。
竜也は車を道端に止めて地元の人に訊いてみることにした。車が停止すると、梢が目を覚まし、「そうか?」と言って、窓の外を眺め始めた。
「此処がタラの町なのか?」と訊いているのだ。
「地図では此処が『風と共に去りぬ』に関係があるとなっているので、近所の人に訊いてみるよ。」
「そうか?」
梢は真剣な顔つきで、自分のイメージと少しでも合致するものがないか、車の窓を開けて周囲の観察に余念がない。竜也は梢を助手席に残したまま車を降りて歩き出した。
昼前の住宅街には人通りは殆どなかった。竜也はなるべく年配の人を探して歩いた。ある家の庭先で、花に水をやっている老婦人を見つけて声をかけた。
地図を片手に叫んでいる東洋人を見て、てっきり道に迷ったらしいと判断した老婦人は、竜也の方に近づいてくると、竜也の質問を聞くより先に話しかけてきた。
「日本の方ですか?」
「はい、そうです。」
「道に迷いなさったかね。」
「いいえ、私は妻に『風と共に去りぬ』のタラの町を見せたくて此処まできたのです。この地図によると、この辺がどうもそれに関係があるように描かれているのですが。」
竜也は地図を示した。老婦人は首に吊るした老眼鏡を手にすると、地図に見入った。
「ははぁ、なるほど。この『ゴーン・ウィズ・ウィンド』と書かれた部分ね。この地図は古いわね。10年以上も前の話だけど、あるお金持ちがこの地域を『風と共に去りぬ』ゆかりの地として観光資源にする計画をもっていたのよ。」
上品な感じのする老婦人は、昔のことを思い出そうとするかのように、一瞬、老眼鏡を外し目を細めて遠くを見るような仕草を見せた。
「開発計画は地区の行政委員会で承認されたのだけれど、結局、資金が続かなくてね。計画は途中で中断されたの。この地図は行政委員会で承認されたときの計画をそのまま表示しているのよ。」
「そうなんですか。がっかりですね。此処に来れば何か手がかりが見つかるかと思ったのですが。」
「日本からわざわざこんなところまでタラを探しに来られてご苦労さんだわね。此処は御覧の通りただの住宅街よ。でもね、名前だけでよければ、タラという名前の通りは直ぐその先にあるわ。スカーレットは居ないけれど行って見られたらどうかしら。」
竜也は丁寧にお礼を言うと、車に引き返した。梢は目を丸くして竜也のニュースを待っていた。竜也が老婦人の説明を伝えると、「あかんわ。」と言って笑った。
竜也は無言で少し車を走らせて老婦人の教えてくれた通りに入った。そこも特に変わったものがあるわけでない、普通の住宅街だった。が、確かに青地に白く『タラ・ストリート』と書かれた道路標識が立っていた。
竜也は黙ってその標識を指差した。梢は標識に目をやり、一瞬こわばった表情に変わった。英文でも一応は読めるようだった。
「この標識はね。名前だけで何の関係もないそうだよ。」
「あぁ、そうか。すげえね。」
梢は表情をゆるめ、一瞬落胆の色を見せたが、次の瞬間には左手を目のところにもって行き、中指と人差指で何かをを押すジェスチャーをした。
「写真だけでも撮って帰ろう。」と言っているのだ。
竜也は車を降りてトランクを開け車椅子を取り出して、助手席のドアまで運んだ。梢は手馴れた動きで器用に車椅子に乗りこんで、道路標識を指差した。竜也は車椅子を標識の下に押して行って、梢のバックに標識が入るように構図を定めて、カメラのシャッターを押した。
目的達成には程遠かったが、一応はタラの標識に出会ったことを成果として、2人は帰途についた。来た道を逆に北に向けて1時間ほど走った頃、梢は「お父さん」と竜也に声をかけた。
竜也は車のスピードを落として、助手席の梢を見た。梢は、左手を口元に持っていき、さかんに指を動かしてみせる。
「お腹が空いたのか。」
「そうや。」
「もうチョット待って。この先にジョーンズボロという町があるみたいだから、そこまで行けばレストランがあると思うよ。」
「ハイ、ハイ。」
ジョーンズボロの町に入った竜也は『インフォメーション』を示す”I”の字のある建物の前に車を停めた。一応この町の案内書をみてレストランを探そうと思ったのだ。
中には観光客らしき人影はなかった。竜也は、何となく、壁に貼られたポスターに目をやった。その途端、釘付けになったように、その場に立ちすくんだ。
そこには、日本でもお馴染みのクラーク・ゲーブルとヴィヴィアン・リーのポスターが貼られていた。更に、その横には当時の学校、教会、厩などの写真が大きく展示されていた。竜也はカウンターの女性に急いで質問した。
「この写真は何ですか。この町にこういうものがあるのですか。」
「そうよ。此処はマーガレット・ミッチェルのゆかりの地です。ミッチェルが通った学校や教会が当時のままの姿で、そっくり保存されています。」
「そ、それは何処にあるのですか。」
「この建物の裏にあります。」
案内嬢は事務的に答えたが、竜也は興奮していた。お礼もそこそこに、カウンターにあったパンフレットをかき集めると、車に走った。
「梢、大発見だ。食事は後だ。降りた、降りた。此処がタラの町みたいだよ。」
呆気にとられた梢の前に車椅子を下ろした。
梢は何のことか判らないまま車椅子に座った。竜也は車椅子を押して、案内所の裏手に回ってみた。
そこには、昔、映画で見たことのある西部劇の街角のような風景があった。
舗装のない土の道路。右手には、太い木の柱でできた厩。中には2頭の馬がゆっくりと口を動かしている。正面には、古い木造の教会が見える。
梢は一挙に100年前にタイムスリップしたような光景に驚いた様子だった。
2人は恐る恐る木造の教会に入った。見物客は2人の他には殆ど居らず、教会の中はガランとしていた。ドイツやフランスの大きな石造りの教会を知っている竜也たちにはステンドグラスもない木造の教会は質素に映った。
壁には展示ケースがあり、その中にはマーガレット・ミッチェルの書いたものと思われる手紙が展示されていた。
梢が多点杖を使って立ち上がり、ケースを覗き込もうとしたとき、祭壇の横の扉が開いて1人の女性が現れた。彼女は映画で見るスカーレット・オハラの服装をしていた。
「ハーイ、ウェルカム」と言いながら、彼女は手を差し出して2人の方に近づいてきた。40代の半ばだろうか、小柄で美しい女性と握手を交わしながら、此処のガイドさんだろうと、竜也は思った。恐らく、案内所の女性が気を利かせてガイド嬢を差し向けたのだろう。
突然出現したスカーレットに梢は興奮していた。例によって「すげえな。」を繰り返し、スカーレットの衣服を左手で触り、感触を確かめる仕草をした。顔はすっかり上気していた。
モニカと名乗るガイド嬢は梢の車椅子を押しながら、顔は竜也に向けて教会の建物の説明を始めた。南部の英語は十分に聴き取れなかったが、竜也は推測も交えて梢に翻訳して伝えた。失語症の梢には、日本語は殆ど理解できても、英語を聞き取ることは出来なかった。
教会を出ると、次に学校の建物に向かった。学校の中では、驚いたことに、レッド・バトラーが竜也たちを出迎えた。梢は大きな叫び声を上げると、バトラーの衣服の袖を左手で掴んで頬擦りをした。余程嬉しかったとみえる。
案内所の粋な計らいに、2人は時の経つのも忘れて『風とともに去りぬ』の世界をさまよった。
梢は小説のヒーローとヒロインの案内に空腹すらも忘れた様子だった。最後に記念写真を撮り、モニカの住所を聞いて、別れた。
レストランのテーブルについてからも、梢は興奮覚めやらぬ様子で「すげえな。」を連発した。
「梢があそこでお腹がすいたと言ったから、偶然あの場所が見つかった。梢がタラの町を発見したようなものだね。」
竜也が言うと、梢は嬉しそうにニッコリ笑った。素敵な笑顔だった。
![]()
「介護日記ーその後」にもどる
![]()
「白い闇」第33章に進む
![]()
トップページへ戻る