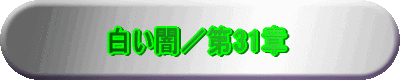
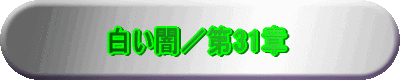
4月には雪がなくなり、5月には春がやってくる。ドイツでもそうだったが、最初に咲くのは連翹(れんぎょう)の黄色い花。その後でチェリーのピンクが咲き、白いリンゴの花が咲くと、草花も一斉に顔を出し、周囲は花と緑の世界に変わる。1年で最も美しい季節の到来となる。
梢は我が家での生活が気に入ったらしく、とても快活で元気になった。東洋医学的な療法に回復への希望を捨てていなかった。
悦子が土曜日に通っているデトロイト日本人学校の友人・高橋さんの父親がミシガン大学病院の外科医で鍼治療を研究していると聞き、早速、高橋医師の自宅で週に1度、電気鍼の治療を受けることにした。また、東洋医学を取り入れたカイロプラクティックの治療にも通った。
梢は自分の部屋のカレンダーに毎週これらの予定を竜也が教えた文字で書き込み、治療の日が来るのを楽しみにしていた。こうして、梢の生活にも一定のリズムが出来てきた。
梢は外出が大好きで、スーパーへの買い物にも必ずついてきた。アメリカのスーパーは殆どが24時間営業で、竜也が会社から帰ると、どんなに遅くなっても買い物に行きたいとねだった。
スーパーの中では、車椅子を自由に操って棚から次々に商品を取り竜也のバスケットに入れた。梢は元気なときから生活用品のストックをたくさん備えておきたい性分だった。「何時地震が来てもいいように」が口癖だったが、アメリカでも、石鹸、歯ブラシ、トイレットペーパー、台所洗剤などを山のように買い込んだので、自宅の物入れは小さな商店の倉庫のようになっていた。
梢は外食することも大好きで、お気に入りはサリーンの街外れにある小さな中華料理店『ウォック』。幾分くたびれた内装で、お世辞にも高級店とはいえなかったが、料理の方は悪くなく、特にゴールデン・セサミ・チキンはとても美味しくボリュームも満点で、梢の大好物だった。
竜也はできるだけ梢を外の風に当てるようにした。近郊へのドライブだけでなく、時にはナイヤガラの滝まで足を伸ばした。ナイヤガラでは、案の定、梢は「すげえな。」を連発した。
夏休みには、亜希子と悦子を連れて4人でカナダのケベックを旅行した。この時は、流石に車では行けないので飛行機を利用した。梢は飛行機に乗ると子供のようにはしゃいだ。
ケベックは坂道が多く、竜也は車椅子を押すのに骨が折れた。だが、反面、梢の車椅子が威力を発揮することもあった。
フロリダのオーランドにあるデズニーワールドを訪ねたときは、各種イベントの行列に並ぶ必要はなかった。車椅子をみただけで、係員がハンディキャップ用の別の入り口から付き添いも含めて入れてくれるので、待つことはなかった。アメリカではハンディキャップ用の施設が充実していて、殆ど不便を感じなかった。遊園地の乗り物にも車椅子用の場所が確保されていて、車椅子ごと乗りこんで固定金具に車椅子を固定すればよかった。梢の生活は徐々に充実していった。
亜希子はミシガン大学での授業にも慣れてきたようで、課外活動のビオラにも精を出していた。あるとき、地方紙のアンナーバーニュースの1面に亜希子がビオラを弾いている写真が大きく掲載され、竜也は街の売店を回って新聞を買い集めた。
悦子は亜希子が来てからは少し落ちついてきた。矢張り、日本語で話し合える相手が必要だったようだ。亜希子と悦子は2人でよく出かけた。梢が使えなくなったフォード・トーラスは亜希子の車に替っていた。
自動車王国アメリカでは運転免許証は16歳から取得できるので、悦子にも運転の特訓をして免許を取らせ、マツダの中古車を買い与えた。社有車のタウンカーと合わせると1家に3台となるが、アメリカでは平均的な台数であった。
亜希子はその頃奇妙な病気に取り付かれていた。血小板が少なくなるという病気で、正式な病名を突発性血小板減少性紫斑病、英語ではITPという。
これは、血小板に正体不明の物体”X”が取り付く病気で、物体”X”自体は無害なのだが、血液が脾臓を通過して浄化される際に、脾臓が物体”X”を外敵と判断してこれを攻撃し、血小板もろとも破壊してしまう。このため、血小板がどんどん少なくなっていくらしい。
血小板が少なくなると、出血が止まらなくなる。実際、亜希子は蚊に刺されただけで血が止まらず、刺された個所が大きく腫れ上がり紫斑ができた。この病気は、当時、日本の厚生省の難病指定を受けており、これを治すには、脾臓を摘出してしまうしかない。
脾臓は機能的には大した役割をもっておらず、摘出しても支障はないが、何しろ脾臓自体が血の塊なので摘出手術が難しい。ミシガン大学病院の若いベトナム人医師はこの手術を内視鏡による最新の方法でやりたいと主張した。
ラパラスコーピック・スプレネクトミーと書かれた難しい医学用語を辞書で調べながら竜也は途方にくれた。梢のときもそうだったが、医学の専門用語は竜也の判断力を超えていた。医者に任せるしかないかと思ったが、念のために日本に問い合わせることにした。
竜也のデュッセルドルフ駐在の前任者だった浅田正俊は当時の浅田専務の長男だが、次男の浅田隆二はT大医学部を卒業し、現在は日本血液学会の重鎮として活躍していた。竜也は長男の正俊に頼まれて、浅田隆二をイスタンブール観光に案内したことがあった。
竜也は思いきってT大病院の浅田隆二に電話した。偉い先生らしく捕まえるのに苦労したが、漸く電話口に出た浅田隆二はぶっきらぼうに言った。
「やめなさい。それは単なる売名行為です。日本で内視鏡による脾臓摘出手術なんて実施例がない。」
竜也は浅田隆二の話を聞いてから益々心配になった。あのベトナム人医師は功名心から難しい手術を勧めているのではないのか。翌日、竜也は再度ミシガン大学病院を訪ねた。
「私は、昨日、日本血液学界の権威の意見を訊いたが、彼はラパラスコーピック・スプレネクトミーには反対でした。日本では、未だ実施例がないと言っていましたよ。」
「日本で実施例がないとは驚きです。アメリカでは極めてポピュラーな手術です。」
「で、あなた御自身はどのくらい経験をお持ちなのですか。」
「10回以上はやっているでしょう。すべて成功です。」
「10回ねえ。いずれにしても、私は反対です。」
「亜希子はもう大人です。これは親が決める問題ではない。亜希子自身に決めてもらいましょう。」
心配していたはずの亜希子が、何故か賛成に回った。恐らく、腹部に傷がつかないというのが大きな魅力だったのだろう。本人がやると言うのだから仕方がない。竜也は渋々了承した。
手術の当日、竜也が病院を訪ねたときは既に手術は終わっていた。亜希子は病室のベッドで明るい表情で竜也を向かえた。
「ちっとも痛くなかったわ。明日には退院できるらしいわよ。」
竜也は少なからず驚いた。自分が学生時代に受けた盲腸の手術でさえ1週間入院した記憶がある。日本の外科手術は患者に過保護なのかもしれない。ベッド数の不足を嘆く前に、手術後の入院期間を大幅に短縮する必要があるのではないか、と竜也は思った。
亜希子は96年の夏、無事にミシガン大学を卒業した。本来ならアメリカで就職活動をすることになるが、竜也はグリーンカードを持っていなかった。永住権のない外国人にとってアメリカでの就職は難しい。かといって、就職活動のために日本に帰ることもできなかった。
竜也は自分の会社に娘を入れることには気が向かず、日本商事のニューヨーク支社長の草田に電話をかけた。
草田とはイスタンブール時代からの付き合いだった。草田は当時日本商事のロンドン駐在で、化学品の営業をしていた。竜也たちがトルコに新設した工場で生産されるカプロラクタムを欧州市場で販売したいとの思惑から何度もトルコにやってきた。
ある年のクリスマスイブをヤリムジャの工場の宿舎で、花札をして過ごしたことは2人にとって共通の想い出となっていた。
竜也は亜希子の就職を草田に頼んだ。草田は快く引き受けてくれ、東京本社に連絡してくれた。但し、東京サイドでの引受人が必要とのことで、竜也はこれを機械の関山に頼んだ。
関山とはデュッセルドルフ時代からの付き合いで、彼は日本商事のパリ駐在員だった。パリ駐在とはいってもフランス語はからきし駄目で、自動車の『ルノー』というフランス語が読めなかったという逸話がある。
関山は、昨年までシカゴに駐在していたので、竜也とは密に交流していた。関山も亜希子の引受人を快諾してくれた。こうして、亜希子は面接のために一度日本に帰国しただけで日本商事への就職が内定した。
後日、草田が日本商事の社長に、関山が専務に昇格することになるが、竜也にはこの時点では想像もつかなかった。
1996年の決算で、山口工業のデトロイト販社は6万ドルの黒字を計上した。これで、竜也のアメリカでの目的は一応達せられた。本社の新田専務からは、早速、帰国の打診が寄せられた。
竜也は帰国辞令を4月まで待ってもらい、最後の課題の仕上げに入った。それは、アンナーバーに組立工場を建設する計画だった。竜也たちが販売する射出成形機とダイカストマシンには短納期が要求された。日本から運んでいたのではアメリカの競合先に勝てない。現地生産は次の飛躍のためのステップとしてどうしても避けられない課題だった。
主要部品は日本から運ぶとしても、電気品や一般部品はアメリカ市場から調達し、マシンを現地で組立てる必要があった。
竜也は組立工場建設のプロジェクトを糸川に一任した。幸い、販社に隣接する3万坪の土地が売りに出たので、95年の10月に土地の手配は済んでいた。
土地の購入についても本社との間で摩擦があった。日本なら数十億円もする3万坪の土地の値段は4千万円相当で、坪単価にすれば1000円強。大した金額ではなかったが、本社からは3万坪は贅沢なので半分にしろと言ってきた。地主にかけあったところ、3万坪はパッケージとして売り出したものだから、半分買っても値段は同じ4千万円で安くならないとの返事が返ってきた。
竜也はデュッセルドルフでのボールペン発注のことを思い出して苦笑いしたが、そのままの情報を本部に伝えた。
「それなら3万坪を購入すること。」というのが本部からの回答だった。土地神話の浸透した日本人的感覚からは当然の反応だが、アメリカの田舎では土地にはそれほど価値がない。現実に、竜也の住んでいるような戸建住宅では、2エーカーの敷地よりも1エーカーの敷地の物件の方が高いことがある。土地が半分しかないのに、価格が高いのは変だと思うが、実際は敷地が広いと芝刈りや手入れに経費がかかり、購入者から敬遠されることが少なくない。
竜也はアメリカ生活で物価の安いことを享受したが、日本の物価高のベースが土地の価格にあることを痛感せずにはいられなかった。
95年10月16日、GMやフォードの関係者を招待して新工場の起工式を催した。デトロイトの鏡総領事をも招待した起工式では、竜也はホスト役として活躍した。竜也は前夜準備したスピーチを原稿を見ずに流暢に話した。
オチは鏡開きだった。総領事の名前が鏡さんであることをもじって、「ミスター・ミラーがミラーをブレークします。」とやって喝采をあびた。
一方、本社側の対応の遅れもあり、工場の建設はその年12月のスタートとなった。ミシガンでの冬の工事は難航する。地盤が凍りついていて基礎工事をするのにパワーショベルでも歯が立たないからだ。このため、予定以上の爆薬を使用しコストも跳ね上がる。
だが、糸川は予算を修正することはしなかった。通常、日本のトランスプラントが現地に工場を建設する場合には、日本のゼネコンに一括発注するのだが、竜也たちはこの方法を避けた。ローカルの個人コンサルタントを雇い、すべての工事を糸川が直接発注した。
それで浮いた金を冬場のエクストラ・コストに回した。96年4月に建屋が完成した。竜也は建屋の完成を確認し、後は糸川に任せて帰国を決心した。
![]()
「介護日記ーその後」にもどる
![]()
「白い闇」第32章に進む
![]()
トップページへ戻る