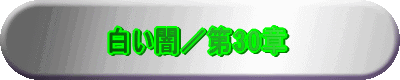
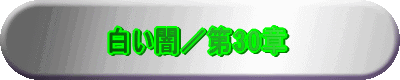
1996年の新年を迎えた。ミシガン地方は例年通り大雪で、竜也は正月の支度を簡単に済ませた。第一、日本からの家財道具は未だ全部開梱できておらず、正月の重箱やお屠蘇セットなども箱に入ったままだった。
1月14日、梢が倒れてから2年を迎えた日、夜の8時半に梢は玄関を開けるよう、竜也に手まねで伝えた。膝の上には、何時の間に用意したのか塩を盛った小皿をのせていた。竜也は、梢の意図を直ぐに理解して、雪の中をガレージに通じる坂道まで車椅子を押した。
外は、梢が倒れたときと同じように強風が粉雪を吹きつけていた。梢は自分が倒れた場所まで来ると、皿の塩を雪の上に撒いた。左手で手刀を作り、頭を深く垂れて車椅子に座ったまま無言で祈った。長い時間だった。
竜也も思わず、両手を合わせて梢の回復を祈った。心から祈った。こんなに真剣に祈るのは竜也には初めてのことだった。寒さを忘れていた。梢は泣いていた。悔し涙に違いなかった。竜也も貰い泣きした。
昨年は梢が神戸の病院に居たためできなかったが、1月14日の清めの儀式は、この日以来、梢と竜也の毎年の恒例行事となる。
3日後、日本時間17日の朝、東京の恵子から突然電話がかかった。
「お父さん、大変なことが起こっている。神戸が大地震よ。」
「日本では地震は珍しくないよ。」
「いや違うの。大変な地震なの。テレビで中継してるわ。大きなビルが殆ど倒れてるの。しかも、震源地はお祖母ちゃんの家の近くらしいのよ。お祖母ちゃんの病院に電話してみたけど全然つながらないの。アメリカのテレビでもやってるはずよ。一度、CNNのニュースを見て。」
恵子は、竜也がアメリカに赴任する2年前にミシガン州ホランダにあるホープ・カレッジに1年間留学していたので、アメリカのテレビ放送にも詳しかった。竜也は日本で起こった地震をわざわざアメリカで報道することなど考えられないと直感したが、恵子が熱心に言うので、テレビを点けた。驚いたことに、テレビは激震の様子を放映していた。
竜也は電話を切って、テレビの画面に見入った。見覚えのあるビルが倒壊している様子が映されていた。何よりも衝撃的だったのは、阪神高速道路が横倒しになっている映像だった。しかも、その場所は竜也の実家から数百メートルと離れていない。
竜也は慌てて神戸の親戚に片端から電話をかけた。山口工業の大阪支店や京都の親戚にもかけた。どこもつながらなかった。竜也には、漸くことの重大性が伝わってきた。竜也はその夜殆ど一睡もせずにテレビを見ていた。
梢と2人の娘も心配そうに画面を覗き込んだ。梢は盛んに「すげえなあ。」を連発した。感激したときにも同じ表現を使うが、心配したときの「すげえなあ。」はまるでニュアンスが違っていた。
竜也は、テレビの画面から見るかぎり神戸の実家も倒壊している恐れは十分にあると感じた。それにしても、母が甲南病院に入院していたのは幸運だった。ニュースでは、山の手は殆ど被害を受けていないと報じていた。
翌日、会社でも地震の話題で持ちきりだった。河田によれば、山口工業の大阪支店から東京本社への社内電話は専用回線なので、情報が東京経由入ってくるとのことだった。それによると、神戸地方は大変な惨状らしい。
「中野さんも大変ですな。奥さんやお母さんの事故に加えて、今度は実家が大地震ですか。早く様子を見に帰られた方がいいでしょうよ。」
河田が言うと、何となく冷やかし半分に聞こえるのだが、この時ばかりは真面目な忠告だと竜也は受け止めた。竜也は2日後の関西空港への直行便を予約し、東京経由大阪支店に緊急車輌の準備を依頼した。大阪支店には、竜也と同期の岡本や綿貫が居る。2人とも竜也とは親しくしていたので、協力してくれるはずだ。
その夜、梢の末弟の浩から電話があった。
「お義兄さんところも被害に遭ってます。家の形は残っていますが・・・」
浩は遠慮からか被害の状況を詳しくは語らなかった。しかし、浩の話からも、道路という道路には家屋や樹木が倒れていて車の通行がままならないらしい。
3日後、竜也は大阪のホテルで早朝から岡本を待っていた。交通規制が厳しく、緊急車輌でなければ神戸方面には行けないとのことだった。幸い、庶務課長をしている綿貫が、手を回して緊急車輌の手配をしてくれていた。
朝の7時、岡本の部下に当たる若い社員・三橋の運転する緊急車輌で岡本がホテルにやってきた。通常なら竜也の実家のある魚崎まで1時間もかからないが、今は8時間ほどかかるだろうという。竜也を乗せた車は快調に走り出した。
竜也は案外早く着くのではないかと思った。しかし、車が尼崎を過ぎる頃から、混雑が激しくなった。西宮辺りで殆ど動かなくなった。左右の倒壊家屋が道路の上に倒れこんでいるからだ。
西宮を過ぎると周囲の惨状はどんどん酷くなった。芦屋の辺りまで来ると、竜也の実家と同じような古い木造家屋は軒並みに倒壊していた。竜也は地獄絵のような周囲の惨状を眺めながら用意されていた握り飯をほお張ったが、なかなか喉に通らなかった。
魚崎にある竜也の実家にたどり着いた時は午後3時を回っていた。浩が電話で言ったように、確かに形は残っていた。しかし、それは2階部分だけで、1階部分は完全になくなっていて、最初から平屋建ての家のように見えた。
竜也は崩れ落ちた玄関の脇から庭に入った。庭には石灯籠や父が大切にしていた石の狛犬が砕けて散らばっていた。玄関の松の木は殆ど折れていた。竜也は池のある表庭に回った。池には大きな鯉が何匹か居たはずだった。だが、池には水がなかった。鯉の姿もなかった。野良猫がくわえていったらしい。
家屋の方は無茶苦茶な状況だった。竜也は先ず写真を撮った。1階部分は完全に押し拉げられて中に入る隙間もなかったが、所々にたんすや家具に支えられた空隙があった。竜也は危険を覚悟で空隙に身をこじ入れた。あらゆるものが散乱していた。
ふとみると、居間にあったはずの金庫が見えた。扉は衝撃のお陰か開いていた。竜也は思わず中にあったものを次々に取り出し、岡本に渡した。仏壇からも位牌を取り出した。
「泥棒みたいだね。」
岡本が言った。
後日談だが、ホンモノの泥棒が大挙して関東から出張してきて倒壊家屋から目ぼしいものを持ち出した、と報道された。竜也の家の空の金庫を見て、さぞやホンモノの泥棒は口惜しい想いをしたに違いない。
竜也は更に目ぼしいものを捜しに奥へ進んだ。だが、洋服ダンスの扉を開けるとガタガタと何かが崩れる音がした。
「危ないからそのくらいにしておこう。」という岡本の忠告に従って、竜也はサルベージを断念した。
竜也は少し近所を歩いてみた。道路を隔てた向かいのマンションはピサの斜塔のように傾いていた。竜也の家の裏にあった西福寺は屋根瓦の重みに耐えかねたのか、完全に倒壊していた。
西福寺の住職は竜也の小学校時代の友人の井上正一だった。僅かに倒れずに残っている玄関の柱には張り紙があり、そこには、『住職他界しました。』との走り書きがあった。小学校時代の腕白少年だった井上を思い出して、竜也は思わず頭を垂れた。
竜也は陽が落ちる前に甲南病院を訪れた。
外見上は病院の建物に被害はないようだったが、中の壁はあちらこちら大きくひび割れていた。停電から回復していない院内は薄暗く、廊下には沢山の負傷者が毛布に包まって横たわっていた。竜也は縫うようにして母の病室に入った。岡本も会社からの差し入れの品を抱えてついてきた。
暖房の止まった部屋は異常に寒かった。母はベッドの上で目を閉じていた。眠ってはいなかったらしく、竜也たちがベッドの脇に近づくと目を開けた。
「あんたかいな。どないなったの。何が起こったのかさっぱり分からへん。」
「まあ、元気そうやね。ものすごく大きな地震があって、下の方は大変な状況や。殆どの家が倒れていて、ウチの家もペチャンコや。ここも揺れたんと違う?」
「ものすごく揺れたわよ。これからどなえなるの」
「廊下は怪我人だらけや。多分、お母さんは病院から追い出されるやろう。しょうがないから、朝霞の美佐子のところへ行くか。」
「そんなん嫌や。ウチへ帰る。」
「そのウチがペシャンコになって、もうあらへんのよ。」
「あらへんて、どういうこと。火事で焼けたんと違うやろ。」
母は事態が呑み込めず、精神的にもかなり動揺しているようだった。取りあえず、岡本のもってきた毛布や寝巻きの差し入れを母に渡し、竜也はナースステーションに向かった。看護婦たちは忙しそうに走り回っていたが、竜也は机で書きものをしている年配の看護婦に話しかけた。婦長らしかった。
「中野さんですか。丁度よかった。ご覧のように負傷者が次々に運ばれてきます。ベッドが絶対的に不足しています。中野さんのような軽症の患者さんは直ぐにでも退院してもらわないといけない状況です。」
「状況はよく分かります。けれど、退院しても行くところがない。家は完全に潰れました。しかも、本人は未だ歩けそうにない。」
「お宅の大変な事情は分かりますが、もっと大変な方が沢山おられるということです。」
竜也は1週間の猶予をもらって病院を出た。
外はすっかり暗くなっていた。停電で街路灯はなく、車のライトがまぶしかった。
思案の挙句、母をひとまず恵子の嫁ぎ先に預かってもらうことを考えた。恵子の夫の青田は成田で乗馬クラブのインストラクターをしていて、住居は富里にあった。恵子と連絡をとり、1ヶ月以内という条件で引取ってもらうことにした。母は4人の孫の中でも恵子を一番可愛がっていたので、恵子のところなら反対しないだろうと思った。
しかし、夫の青田と同居なので長くは置いてもらえないだろう。一息ついたところで、美佐子の朝霞のアパートに移ってもらう心積だった。美佐子のアパートなら亜希子の部屋が空いている筈だ。アメリカに連れて行くことも打診したが、母は全く耳を貸さなかった。
1週間後、竜也は車椅子の母を連れて、大阪伊丹空港に居た。成田に向かうことにしていた。恵子の家は成田空港から近い。空港から直接恵子の家に母を連れて行く段取りをつけていた。
伊丹空港に向かう車中で母は空襲の跡のような外の景色を見ながら、「何でこんなことになったんやろね。」と何度もつぶやいた。飛行機に乗ってからも、地震が実際にあったことが、未だ信じられない様子だった。
「私、テレビの上に眼鏡を忘れてきたわ。今度、あれを取ってきて頂戴。ついでに、テレビ台の引き出しに住所録が入ってるはずやから、あれも取ってきてほしいなあ。」
「そんなもん、あるわけないやないか。家はペシャンコになっとるんや。テレビなんかあるわけないやないか。」
「なんでそんなことになったんやろ。」
竜也は母の相手に疲れて、窓の外に目をやった。雲間から大阪湾が遠ざかっていくのがみえた。外の景色の動きをぼんやり眺めながら、慌しかった1週間のことを思い出していた。
先ず、倒壊した家屋を撤去する必要があった。区役所で訊いたが、神戸市が倒壊家屋をすべて撤去するとなると、1年先になるだろうとのことだった。だから、民間の業者に自発的に頼んでほしい。補助金が神戸市から支給される、と説明を受けた。近くの業者を何軒か訪ねた。
「何しろ、何十万という家が倒れてるんだからね。お宅の順番が何時になるかわからないよ。」
どの業者も、皆おなじ台詞を口にした。その中でも、夏までには何とかしましょうと前向きな姿勢をみせた業者に竜也は解体と撤去を頼んだ。竜也の家のケースでは、450万円が神戸市から支給されるとのことだった。だが、それを上回る撤去費については、直接業者に支払う必要があると聞かされた。
また、解体・撤去にあわせて、少しでも回収できるものは回収する必要があった。父が集めていた陶磁器のコレクションは殆どが壊れているだろうと思った。絵画のコレクションなら少しは助かるかもしれない。それに、竜也は2階の自分の部屋の本棚にしまってあった古い辞書のことが気になった。
それは、父の友人から入学祝いに貰ったものだが、江戸時代の英和辞書で、「袖珍英和辞典」と古い書体で書かれていた。木版刷りの和紙を綴じたものだが、電話帳ほどの大きさだった。英文でコンサイス・ポケット・ディクショナリーという文字も書かれていた。恐らく、「コンサイス・ポケット」の部分を「袖珍」と訳したものと思われた。
次に、何故か、ジプシーの老婆が結んだハンカチのことが気になった。あのハンカチは何処にしまったのか。多分、押入れの何処かにあったはずだが、結び目はどうなっただろうか。ぼんやり想像しながら、梢のことが気になった。
ミシガンの家はちゃんと暖房が働いているだろうか。亜希子は母親の面倒をみてくれているだろうか。悦子との間はうまく行ってるだろうか。
![]()
「介護日記ーその後」にもどる
![]()
「白い闇」第31章に進む
![]()
トップページへ戻る