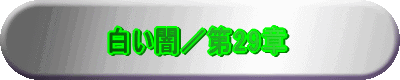
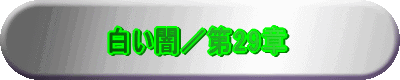
年が明けて1995年、竜也は猛烈に仕事に打ち込んだ。河田や木谷と一緒に客先を積極的に歩いた。
また、サービス・マネジャーの糸川とも真剣にサービス体制の拡充について議論した。竜也はドイツでの経験から、日本製の機械を販売する上でサービスが如何に大切かを十分に理解していた。アルキャン・バンバリーのベネット氏が竜也に示した『ディスタンス』という単語が今でも竜也の脳裏からは離れなかった。
糸川も最初は竜也に遠慮していたようだが、今では積極的に自分の抱えている問題を竜也に話すようになっていた。竜也は糸川とともに考え、糸川の納得できる解決策をアドバイスした。
童顔の糸川は、実際よりもはるかに若く見えた。日本人から見てもそうだから、アメリカ人には実際の年齢よりも20歳も若く見られることもあった。しかし、サービス部門のアメリカ人スタッフは一様に糸川を尊敬していた。
大阪出身の糸川は、日本語は典型的な関西弁だが、英語にも関西弁訛りがあるように竜也には思われた。童顔で関西弁の英語を喋って、どうして部下のアメリカ人たちの信頼を得ることができるのか、竜也は不思議に思った。しかし、糸川の号令一下アメリカ人スタッフは実によく動いた。サービス部門の充実をベースにアンナーバーの販社は徐々に成績を伸ばしていった。
会社の戦力を集中するためには、日本人スタッフだけがいくら頑張ってみても効果は薄い。アメリカでのビジネスはアメリカ人従業員が先頭に立たなければならない。
竜也はこの年から毎年1月に50人ほどの全従業員に1人ずつに直接インタビューすることにした。時間は日本人、アメリカ人を問わず、1人30分。社長室に招き入れて1対1で話す。特にアメリカ人スタッフに対しては、不平、不満を含め何でも率直に話して貰うことにした。
彼らは、普段は口にしないプライベートな事情まで詳細に竜也に話した。特定の個人に対する不満の声も聞こえてきた。意外だったが、日本人スタッフではなく同僚のアメリカ人スタッフに対する不満が少なくなかった。特に、給料の額について、少しの格差を問題にした。
ローカル・スタッフの多くは年俸制だが、同僚と較べて年に100ドルの格差でも真剣に説明を求めた。
アメリカ人スタッフは途中転職が多い。折角仕事を覚えても他社に移ってしまう。それは会社にとって大きな痛手だが、アメリカ人のマインドとしてある程度理解しなければならないと竜也は思う。
あるとき、ダイカスト・マシンのセールスマン、スティーブンが辞めたいと行って来た。競合他社からオファーが来たのだ。竜也は一応慰留にかかった。
「スティーブン、この会社に不満があるなら言ってほしい。キミの主張がリーズナブルなら、キミの意見を尊重したい。」
「いいえ、ボス。」
今で言う”イケメン”の好男子スティーブンは、2m近い長身を折るようにして腰をかけていたが、おもむろに顔をあげてキッパリと言った。
「私はこの会社に何の不満もありません。今でも山口工業を愛しています。だけど、目の前にベター・チャンスをぶら下げられたら、それを掴むためにジャンプしなければならない。それが、フロンティア・スピリットです。」
アルミホイール部門についても、竜也は積極的に動いた。ホイールのアメリカ会社の販売担当副社長をしている古川と一緒にフォードやクライスラーを訪ね、新規の売り込みに奔走した。日本のトランス・プラント向けには星田と協力した。
また、メイソンの工場にも出来るだけ顔を出し、工場サイドとの連絡を緊密に取るようにした。というのは、販売担当の古川と工場の間が必ずしもしっくりいっていないと思われたからだ。特に、メイソンの総務担当重役の宇田との折り合いがわるかった。
古川は竜也とは同期の入社だが、京都の下町育ちで新入社員の時から何処となく“エエシのぼんぼん”特有のわがままなところがあった。仕事はよくできるのだが、周囲からはあまり評価されていなかった。古川が宇田との間でトラブルを起こすと、竜也は古川の肩をもった。それが工場の連中から反感を買うかもしれないと知りながら、竜也が古川の味方をしたのは、同期入社の親しさもあったが、宇田に対してある種の先入観を持っていたからかもしれない。
宇田は知らないが、実は竜也が25年前に内定していたはずの国際貿易大学への派遣を取り消されたとき、竜也に代わって派遣されたのが宇田であった。宇田はT大法学部卒の秀才肌の男で頭もシャープだが、ロジックの立て方に一種独特のクセがあり、それには竜也はついていけなかった。
宇田の最大の仕事はメイソン工場を悪名高き全米自動車労組のUAWから護ることにあった。だが、宇田はそれを総務部長のアメリカ人に一任していたため、後にUAWの侵略に屈することになる。
工場がUAWの傘下に落ちたときでさえも、宇田は独自のロジックを持ち出して、心配することはないと主張したが、竜也は糸川と2人で『あの工場は潰した方がいい。』との危機感を共有していた。後に、このUAWが山口工業のホイール事業の足を大きく引っ張り、メイソン工場は清算されることになる。
機械以外の分野でも、竜也は積極的に動いた。竜也が初めて東京の機械輸出課に転勤したときの上司だった末村は、今はマグネシウム関係の子会社の社長に転出していた。
末村はピッツバーグのリマコー社との技術提携を計画しており、その関係で再三アメリカに来訪した。竜也は恩返しの意味からも末村ミッションには優先的にアテンドした。
リマコーのジョー・ジャックマン社長は、スクオッシュの趣味が高じてシニアー世界選手権出場のためしばしば日本を訪問しており、なかなかの日本通で、竜也の日米比較文化論に興味深く耳を傾けた。
竜也は海外での経験が長いこともあって、日本と外国の文化の比較に興味があった。アメリカでは、アンソロポロジーという学問が発達しており、亜希子もミシガン大学でアンソロポロジーを専攻していた。これは、日本語でいえば文化人類学に相当するが、日本ではそれほどポピュラーではない。
この学問が日本では何故普及しなかったのか、竜也はいろいろと文献を当たってみたが、竜也の得た結論は次のようなものであった。
植民地時代には、欧米の先進国が植民地の現地人を完全に支配するために、文化の違いを研究する必要があった。その目的から、植民地に派遣されたスペシャリストが、フィールドワークを通じて、その国の文化を体系立てて本国にレポートする。このレポートが文化人類学の基礎になった。
「菊と刀」を書いたルース・ベネディクトなどは、アメリカが派遣した一種の諜報員で、日本文化の研究成果を本国に情報提供するために本を書いたのだろう、と竜也は理解した。従って、短い時期を除いて植民地を持たなかった日本ではアンソロポロジーは普及しなかった。
リマコー社はマグネの屑を集めてきて再生地金を作る、今でいうリサイクルビジネスがメインの仕事だった。ジャックマンは、自分たちの仕事を『鯉』に例えて、『水の底に住み、たまった泥を喰う底辺の仕事(マッド・イーター)』だと言った。竜也は、この発言に文化人類学的な興味をもった。というのは、日本では『鯉の滝登り』と言われるように、鯉は勢いのよいことからむしろ高級魚に分類されるからだ。竜也はこのことをジャックマンに伝えた。
「日本では、鯉は『上昇』を意味する魚で、カープという名の野球のチームもあるくらいですよ。」
「それは驚きだね。アメリカでは、鯉は最も低位の魚で、球団名にカープなどつけたら忽ち最下位だよ。」
マグネシウムの分野では、竜也はアメリカやカナダで行われた国際会議にも出席した。
山口工業は当時ピジョン法と呼ばれるプロセスを使って純度の高いマグネシウムを日本で生産していた。本社の会長となった中田道夫は、IMA(国際マグネシウム会議)の理事だったので、総会には毎年出席した。中田道夫は、実弟の英男が山口工業のニューヨークに駐在しているにもかかわらず、アテンドにはデトロイトの竜也を指名した。竜也には気楽に何でも話せるようだった。
中田が会長職を退任することが決まった最後のIMA総会が95年5月にサンフランシスコであり、竜也もこれに参加した。総会が終わった日の夜、竜也は中田のホテルの自室に呼ばれた。
既に相当酒が入っていたが、バーボンの水割りを手にした中田は、竜也と中田に同行した数人を前に大演説を始めた。父親からの特訓による帝王学に基づいた会社経営に自信満々の中田は、会長職を退任することがよほど口惜しかったとみえて、最後は激昂してグラスをテーブルに叩きつけた。
「名村の社長が内定していたとき、名村を下ろして東山を社長にしたのはオレじゃないか。オレが東山を社長にしたんだぞ。それが、今回、東山はオレに降りろと言う。一体、どういうことか。これは!」
夜中の1時を過ぎても中田の独演会は続いた。誰もが席を立つことが出来ずに困惑していたが、最後に中田を抑えたのは同行の静子夫人だった。静子は元社長の水沼の娘だが、風流人の父親に較べると現実派で、夫の中田道夫に対しても抑えるべきところはしっかり抑えていた。
「あなた、もう遅いし皆さんにも迷惑です。そろそろ終わりにしましょう。」
静子夫人に言われると中田は渋々腰を上げた。竜也を含めて同席の4人は救われたと感じた。
中田は、その後、相談役に落ち着くが持病の喉頭ガンが悪化して71歳で亡くなる。
プライベート面では、竜也の周辺は騒がしかった。先ず、94年1月、竜也の母が大怪我をしたとの連絡が入った。
足腰の弱った母は殆ど外出しなかったが、この日は画の集まりで三宮に出たらしい。その帰路、阪神三宮のホームで電車を待っていた。電車が着いて、中から中学生らしき一団が勢いよく飛び出してきた。そのうちの一人が母に接触し、母はホームに転倒、大腿骨を骨折した。駅員の機転で、直ぐに最寄の病院に運ばれ、直ちに手術を受けたのでリハビリさえきちんとやれば回復は可能だという。
竜也は仕事で多忙を極めていたが、週末を利用してデトロイトから新しくできた関西新空港に飛んだ。神戸の海岸病院で、母は意外に元気だった。病院の先生が親切なので、病院生活が楽しいと竜也に言った。外科手術では、大腿骨をつなぐのに鉄片を右足の太ももに埋め込んだらしく、母は裾をはぐって竜也に手術した場所を示した。
「此処に鉄の棒が埋まってるんよ。」
母は何処となく誇らしげだった。孤独な生活を送っていた母は、病院で医師や看護婦に話しかけられるのが楽しいらしく、竜也は安心した。医師と看護婦に宜しくお願いする旨を頼み、とんぼ返りでミシガンに帰った。
3月には、心配していた神戸しあわせの村のリハビリ病院から梢の入院期間が満了するので退院してほしいとの督促が来た。神戸の友人・山口省二は、その頃既に神戸市助役への昇進が決まっていた。竜也は山口に電話をかけ、梢の入院の延長を依頼したが、通常の3ヶ月を6ヶ月に延長したので、それ以上は出来ない、と山口は電話の向こうで申し訳なさそうに答えた。
偶々、長女・恵子の結婚話がまとまり、4月の初めに北海道で式を挙げることになっていたので、竜也は梢を式に出席させることにして、退院を覚悟した。3月末、竜也は亜希子と悦子をつれて日本に一時帰国した。
日本から連れてきたネコのビビは自宅周辺でリスやウサギを追跡するのに多忙だったので、隣家のダールベルグ夫人に預けた。
神戸の病院では、梢が張り切って待っていた。恵子の結婚式に参加できることになったのが嬉しかったとみえる。竜也は病院の関係者に簡単な挨拶を済ませると、梢の末弟・浩の車で病院を出た。浩には、帰国の都度お世話をかけ気の毒だったが浩の方は気軽に引き受けてくれた。
竜也は恵子の結婚式に出かけるまでの数日を神戸市内のホテルに泊まることにした。海岸病院の母の見舞いにも行く必要があったからだ。翌日、竜也は梢の車椅子を押して海岸病院を訪ねた。
母は元気だった。梢は少し増えたボキャブラリーを駆使して母を励まそうとしたが、母は耳の遠い所為もあって「なんや判らへん。」と悪気からではなく、素直に言った。
「オシとツンボの会話だから判るわけないよ。」
竜也が言うと、2人は同時に笑った。
4月の北海道は未だ寒く、雪が残っていた。札幌・千歳空港から竜也一家を乗せたワゴン車は、広い平野の中を一路苫小牧に向かった。恵子の結婚相手の青田がハンドルを握っていた。久し振りに姉妹4人が顔をそろえ、娘どもはお喋りに余念がなかったが、竜也と梢は黙って窓の外を眺めながら、2人ともミシガンの平野を頭に浮かべていた。
1時間も走ると車は目的地のホテル・ニドムに着いた。ニドムはゴルフ場を併設した大規模なホテルで、500万㎡の雄大な敷地に各種の施設が点在していた。
『北国の大自然にはばたくテクノフロンティア』とのキャッチフレーズで近年開発された新名所だ。結婚式は北欧風のチャペルで、パーティは湖に面したコテッジで行われた。
梢には、ワゴン車の乗降からコテッジの階段まで、左手の多点杖を頼りに苦労の連続だったが、娘の晴れ姿に接して頬は上気していた。新郎側の青田の父親から、近くに別荘があるのでゆっくりしていくように勧められたが、竜也一家はホテルに一泊しただけで、恵子を残して東京に帰った。竜也には時間的余裕もなかったが、それよりも青田の父親を何となく好きになれなかった。長女を嫁に取られたからというより、何かにつけて自慢したがる舅の態度に好感がもてなかった。
羽田で次女の美佐子と別れ、しばらく東京に滞在したいという亜希子と悦子を残して、竜也と梢は、翌日、成田からデトロイト行きのノースウェストに乗り込んだ。
梢は日本に来た時よりも数段元気になっていたので、機中はトイレ以外に特に心配はなかった。
問題はミシガンに帰ってからにあった。サリーンの病院では、既に引受けを拒否されているので、梢を自宅に引取る以外になかったが、十分なケアができるかどうか、竜也は少なからず心配だった。
竜也は梢を自宅に引取るために、必要な改造を大家の許可を得て、既に済ませていた。浴室は2階にあったため、階下に簡単なシャワー室を設けた。梢には階段を登るのは無理で、1階が生活空間となった。ところが、1階はオープンな構造で部屋の間仕切りがない。1階の1室を梢の部屋にして、カーテンで間仕切りを作った。また、各部屋の移動は車椅子で出来るように段差のあるところにはスロープを設けた。
最大の課題はトイレで、当初はコモードと呼ばれる西洋オマルを梢の部屋に準備した。
が、梢自身もコモードでの用足しには抵抗があるらしく、1週間後には何とか自分でトイレに入れるようになり、問題は解決した。
準備万端整ったところで梢を引取ったので、梢の方も大したトラブルもなく自宅で生活を始めることになった。しかし、昼間は竜也も娘たちも家に居ないのでヘルパーをつけた。
ヘルパーにも多少の看護知識が必要なので、サリーン病院の看護婦をしていたフィリピン国籍の中国人リサに来てもらうことにした。リサは病院時代から梢のことをよく承知していたので、ヘルパーとしては最適任だった。だが、リサが夏にフィリピンに帰ってしまい、その後は複数のヘルパーが交替でやってきた。竜也は、梢の状態をその都度説明するのに骨が折れた。
曲がりなりにも梢をメンバーに加えた家族の生活パターンが出来あがった。梢と悦子の関係は以前ほどではなくなったものの、相変わらずしっくりは行かなかった。悦子は、その後も学校に親しみがもてず、遅刻、早退が多いことから、竜也にはしばしば学校から呼び出しがかかった。
竜也たちは、3度目のミシガンの冬を迎えた。駐在員の家族はクリスマスには一家で南方に出かけるのだが、竜也は梢の介護でとてもその余裕がなかった。亜希子と悦子は折角の冬休みを家に篭っているのは不満だった。
事情を察した糸川が2人をスキー旅行に誘ってくれた。久しぶりに、梢と2人でのんびり新年を迎えようとしていた大晦日の日に、日本の従姉から突然電話がかかった。神戸の母が自宅で転倒して救急車で病院に運ばれたという。
母は大腿骨骨折の手術から回復して夏に海岸病院を退院し、自宅に戻っていた。竜也は、時々母に電話をかけて元気にしていることを確認していた。もし、また怪我をしたら歩けなくなるから注意するようにと電話で念押ししてはいたが、その矢先の出来事だった。
今度の入院先は母の家からは遠くない六甲山の麓にある甲南病院だった。電話をかけてきた従姉が、母は元気だから特に帰国する必要はないと言ったので、竜也はその言葉に甘えて、年が明けてから一時帰国することにした。だが、本来なら1人息子の竜也が老母の世話をすべきなのに、緊急事態をすべて従姉に任せてしまうことに後ろめたさを感じた。同時に、年末の慌しい時にじっとしていればいいのに、と母をとがめたい気持ちもあった。しかし、母の入院が結果的には幸運だったことをこの時点では知る由もなかった。
![]()
「介護日記ーその後」にもどる
![]()
「白い闇」第30章に進む
![]()
トップページへ戻る