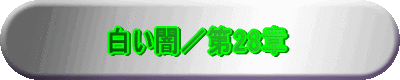
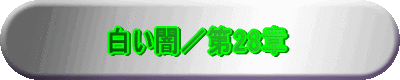
9月の終わりに竜也は再び休暇をとり、梢を神戸に連れて帰った。倒れてから最初の旅行が日本行きということで心配したが、飛行機の中では梢は殆ど眠っていたので大きなトラブルはなかった。
ただ、問題はトイレで、多点杖の助けを借りて10 歩程度しかあるけない梢をトイレまで連れて行き、狭い機内のトイレの中で体の向きを代えて便器に座らせるのは大変な仕事だった。
アメリカの空港では、身障者用のトイレが完備していて車椅子でも簡単に用を済ませることができたが、当時の日本ではそうはいかなかった。
先ず竜也が迷ったのは、男性用と女性用のどちらに入るか。梢の気持ちからは女性トイレを望んだかもしれないが、竜也としては車椅子の介護者とはいえ女性トイレに入る勇気はなかった。
仕方なく男性トイレに入るのだが、総じて男性用の大便トイレは汚い。しかも、中には掴まるところがないので、梢1人で用を足すことはできなかった。比較的広いトイレなら、竜也は自分も中に入ってドアを内から閉めることができるが、残念ながら日本の公衆トイレは2人が入れるようなスペースがない。止む無く、ドアを開けたまま車椅子でドアの空間を塞ぎ、竜也は車椅子の前に立つようにして、用足しに来た男どもの好奇な視線から梢を護るようにした。
もし、洋式トイレがないようなときは、まさに悲劇だった。右足が硬直したまま麻痺している梢にはしゃがむことは無論不可能だった。また、用が済めば梢のためにトイレットペーパーを適当に千切って渡すこともしなければならなかった。普通何でもなく出来ることが左手1本では非常に難しいことが判った。そんなわけで、日本で梢をトイレに連れて入ることは竜也にとって大きな苦痛となった。
ホテルの一室に入ってもトイレは問題だった。日本のホテルは一流ホテルでもユニットバスを設置したところが多い。高々10㎝のユニットバスの敷居が梢には大きなバリアーになる。夜中に梢がトイレに立つときには、竜也も起きてバリアーを越えるために梢の重い右足を持ち上げてやる必要があった。
しあわせの村のリハビリ病院は、梢にとっては超一流ホテルも比較にならないほどの楽園だった。廊下は広く、何処に行くにも車椅子で自由に動ける。壁には必ずしっかりした手すりが設置されているので、杖がなくても伝い歩きができる。何といってもトイレが安心だ。車椅子のまま中に入れて、便器の周囲には十分な手すりがある。トイレットペーパーも片手で千切れるような仕掛けが施されている。誰の助けも借りずに自分ひとりでトイレに行けることは梢にとっては大きな喜びだった。
それに、同室の患者や看護婦たちは、以前慣れ親しんだ関西弁で梢に話しかけてくれる。更に、自分の弟たちが毎日のように病院を訪ねてくれる。梢は、忽ちこの病院を好きになったようだ。
竜也はその足で山口省二にお礼を言うために、神戸市庁に立ち寄った。高層ビルの立派な応接室で竜也は山口と向かい合った。ガラス越に神戸港に停泊中の外国船が一望できた。
「家内があの病院をとても気に入ったようで、本当に助かったよ。」
「日本の福祉行政は65歳以上の老人向けには比較的施設も整っているんだが、もっと若い世代の障害者は殆ど考慮されていない。これが問題だな。君んとこも余り長居はできないと思うよ。」
「そんなこと言わずに。本人も気に入ってるし、僕も梢をあそこに入れておくと安心だから、何とか御配慮をお願いするよ。ところで、和歌子さんはどうしているんだい。」
竜也は以前訊き漏らしたテーマに到達したことで、ある種の余裕を感じた。
「何とかやってるみたいだが、俺んとこもなかなか大変でね。兄貴が死んでからウチの母親も引き取ったもんだから、婆さん2人が同居で、これがうまく合わないよね。」
和歌子は母1人娘1人だったので、山口夫婦が和歌子の母親を引き取るのは当然だった。和歌子の母は、竜也も何度か会ったことがあるが、先生一筋の教育者でなかなかさばけた人だった。
山口の母は、竜也が一度会ったときの印象では下町のおかみさんといった感じで、和歌子の母親とはかなり肌合いが違っていた。だから、山口の話はその通りだろうと思った。和歌子も実の母と義理の母の間に入って苦労しているようだ。一度、和歌子に会ってみたい衝動に駆られたが、このことは山口には言わずに、仕事の話を少しして、神戸市庁を後にした。
その日、竜也は久しぶりに神戸の実家に泊まった。父は9年前に他界し、今は母が1人で大きな屋敷に住んでいた。家には父の可愛がっていた柴犬のカロが健在だった。
竜也が居間に入ると、覚えているはずもないのに飛びついてきて腕を舐めた。竜也は犬も好きだが、こうして媚びへつらうところには少し抵抗があった。その点、猫のビビは竜也の顔をチラッと見ただけで、しらぬ顔で寝ていたが、そちらの方に何となく威厳を感じる。
だが、カロは未亡人となった母にとっては貴重な友達だった。半分腰が曲がってしまった母は、それでも竜也のために竜也の好物のロールキャベツと大根の煮付けを作って待っていてくれた。
久方振りの『中野家の味』に舌鼓を打ちながら、竜也は梢の様子を話した。
「何で、そんなことになってしもたんやろね。」
母はどうしようもない口惜しさを独特の表現で伝えた。竜也の母は物静かだが、内に秘めた情熱は何時も若々しい炎に包まれていた。
女学校時代には、当時未だ珍しかったピアノを習い、卒業式にはベートーベンの月光のソナタを弾いたという。その後、京都の女専に進み、国文学を修めた。和歌、俳句に秀でたが、今では30年ほど前から始めた油絵に打ち込んでいた。
小さな身体で、毎年100号の作品を数点画いた。二科展には連続入選していて、会友になる日も近いように思われた。だが、母は派手なことは好まず、自分の情熱を傾ける対象がありさえすれば満足している風だった。
生前、父との夫婦仲は決して良くなく、一人息子の竜也に父の悪行を随分こぼしていたが、今ではその父が懐かしく、晩年重度のアルツハイマーにかかり病院で死んだ父を愛おしがった。
「可愛そうなことをした。この家で死なせてあげたらよかったのに。何で病院なんかに入れたんやろ。」
母1人ではどうしようもなくなった父を病院に入れたときは、「ほっとしたわ。」と喜んでいたのをすっかり忘れてしまったようだ。そして、最後には竜也が最も恐れていた台詞をこともなげに口に出した。
「あんた、この家にはもう帰ってこやへん積もりやろ。」
その年の年末、竜也は再度一時帰国した。しあわせの村の梢は見違えるほど元気になっていた。アメリカでは食事を受けつけず、痩せ細っていたが、今は丸々と太り、元気で車椅子を乗り回していた。2ヶ月振りの竜也の来訪に大張り切りの梢は、車椅子で竜也の先を進んで、しあわせの村の庭を案内して回った。
「すげえな。すげえな。」を連発して、自分の周囲の環境が素晴らしいことを竜也に自慢しているようだった。竜也もアメリカでは見たことがなかった妻の元気な姿に幾分興奮して、車椅子を押しながら、
「きれいだね。すばらしいね。」と、梢の自慢に一々相槌を打った。梢はその度に竜也を振り返ってにっこり笑いかけるのだった。
素晴らしい笑顔だった。
リハビリの方も進歩が見られた。物理療法では多点杖での歩行距離が相当伸びた。今では、10m近く歩けるようになっている。左手の使い方も上手になった。梢は新しく覚えた漢字を左手でたくさん竜也に書いて見せた。
言語の方は著しい進歩はなかったが、それでも以前に比べると少しはボキャブラリーも増えたようだ。食事のときに「おいしい。」と言ったり、竜也のことを「お父さん。」と呼べるようになっていた。
主治医の東谷先生は小柄だが、スタイルの良い女医さんで、リハビリの効果を盛んにPRした。東谷医師によると、最も力を入れた点は梢のトーンズ(痙性)を除去することで、そのためにアメリカで身につけていた装具をすべて取り外してしまった。
右脚の踵部分につけていた足型をしたプラスチックのサポート、右膝を固定するためのギブス状の装具、右手を亜脱臼から保護するための三角巾、更に右手指の曲がりを矯正するため手首に固定していた装具。梢が几帳面に毎朝身に着けていたものをすべて取り去った。
梢は最初は不安がったが、その内に装具なしの自然体に慣れ、歩行距離も急速に進歩したという。だが、何よりも大切なのはトーンズが下がって、梢が明るくなったことだった。
今は、明らかに生きる喜びを感じている様子に竜也も感動に近いものを覚えていた。竜也は東谷先生の許可を得て、梢を1日外出させることにした。
先ず、梢の元気な姿を竜也は母に見せたかった。身体の衰えた母は、殆ど外出することはなく、梢の病院に訪ねることもなかったからだ。梢の末の弟、浩の運転で梢を病院から連れ出し、最初に竜也の実家を訪ねた。
梢は、久しく会わなかった竜也の母の痩せた手を自分の左手でしっかり握りしめて、声を出して泣き出した。竜也の母の衰えた姿に驚くと同時に、自分がこんな姿になってしまったことを詫びる気持ちが交錯したようだった。
梢の大げさな感情表現に母は一瞬たじろいだ様子を見せたが、直ぐに自分から梢の手を握り返した。梢は自分の回復振りを見せたいらしく、畳の上を靴をはいたまま杖を使って歩いて見せた。
「梢さん、強いわねえ。」
竜也の母は、梢が絶望の淵にあったことを竜也から聞いていただけに、梢の前向きな姿勢に心を動かされたようだ。梢は返事の代わりに例の笑顔で竜也の母に答えた。
竜也は、梢を弟の浩に預け、自分は病院に引き返した。先生やセラピストに訊いておくことが残っていた。
浩は梢を自分たちの母親に会わせるために有馬に向かった。梢の父は6年前に亡くなり、母は夫の死後急速に衰えて、今では有馬温泉病院に長期入院していた。
竜也が梢の母の惨めな姿を見るのは気が進まず、遠方を理由に有馬温泉病院を訪問したことはなかった。
しあわせの村に引き返した竜也は、梢のベッドを整理した。そのとき、見舞いにきた人たちの励ましの言葉を記したノートが見つかった。パラパラとめくってみると、矢張り親戚の人たちが多かったが、その中に山口と和歌子の名前を見つけた。
梢と和歌子は学生時代に竜也の実家で会ったことがあるが、果たして和歌子は梢のことを覚えていただろうか、と竜也は気になった。ベッドの整理を終え、竜也はセラピストの控え室を訪ねた。
言語療法士の西田恵美子は梢の現状を丁寧に説明した。発病後かなり時間が経過しているため、以前に蓄積された言葉を思い出すのは不可能に近く、今は新しく右脳で言葉を覚えていく以外にない。その方法も、同じ言葉や文章を何度も何度も反復する地道な練習を積み重ねていくしかない、とのことだった。
理学療法士の薮田は、梢の歩行の進歩は本来の機能回復ではなく、本人の意欲が無理やりに歩行距離を伸ばしているのだ、と説明した。つまり、歩行に必要な右足の筋肉は全く働いていないが、身体のバランスを杖にかけて右足を浮かせて前方に進んでいるもので、薮田はこれを『骨的に歩く』と表現した。つまりは、筋肉で歩いているのではないという意味だろうと竜也は理解した。
医局では、東谷医師から話を聞いた。東谷は、竜也に退院後の生活について話し始めたので、竜也は慌てて口を挟んだ。
「もう、退院しなきゃいけないのでしょうか。」
「そう、ここは一応3ヶ月単位のリハビリコースになっているの。だから、梢さんは、この年末で本当は退院していただかなきゃいけないの。中野さんの場合は神戸市の偉い方からの推薦状があるから、少しは延ばせるかもしれないけど、それでも来年3月までだわね。」
「そうなんですか。」
「本人にとっては、病院なんかに居るよりも家族と一緒に居る方が生活は充実するはずですよ。だから、周囲が暖かく見守ってあげる必要があるわね。」
「梢は、この病院がとても気に入っているし、此処でも十分充実しているように見えますけどね。それにウチに帰っても、病院のように色んな設備もないし、第一、平日の昼間は誰もケアできませんよ。」
「それは、アメリカの話でしょ。日本に帰れば娘さんたちが居るのでしょ。あっ、そうそう。梢さんの身障者手帳を申請しておくといいわね。日本ではあれがあると何かと便宜が図ってもらえるわ。」
「身障者? 梢が、ですか?」
「もちろんよ。梢さんなら立派に1級がもらえるわ。」
竜也は『身障者』という言葉のもつ語感に大きな抵抗があった。身体障害者は障害が固定してしまって回復の見込みがないというニュアンスが強いからだ。
『ひょっとすると梢は回復するかもしれない。』竜也はかすかな期待を抱き続けただけに、東谷医師の身障者手帳を申請するようにとのアドバイスは竜也を谷底に突き落とすような冷酷な響きをもっていた。
「ということは、梢の機能回復の見込みはゼロということですか。」
「そうよ。完全にゼロよ。アメリカではどう言われたか知れないけれど、この現実は旦那さんがしっかり受け止めなければいけないわ。これからは、障害を前提にした生活設計を考える必要があるのよ。」
「そう言われても、私には会社の仕事があるし・・・。」
「男の方はすぐそう仰言いますけどね。会社と奥さんのどちらが大切か、よく考えてみられた方がいいんじゃないですか。」
東谷医師はそういうと、後ろを向いて部屋から出て行った。患者を診るのが医師の仕事だとすれば、東谷の言うことは正しい。患者を第一優先に考えるからだ。しかし、それでは竜也の立場はどうなるのだ。東谷は竜也の立場も少しくらい考慮してくれてもいいじゃないか。竜也は割り切れない気持ちで病院を出た。
ミシガンの豪邸に戻った竜也を3女の亜希子と悦子が出迎えた。亜希子は首尾よくミシガン大学の編入試験に合格し、10月からソフォマー(2回生)として大学に通っていた。
亜希子が来てくれたお陰で、竜也は随分と楽になった。夕食の支度に悩まされることもなくなった。おまけに、梢が日本に帰ったことで負担は激減した。竜也は仕事に打ち込めることに喜びを感じた。
![]()
「介護日記ーその後」にもどる
![]()
「白い闇」第29章に進む
![]()
トップページへ戻る