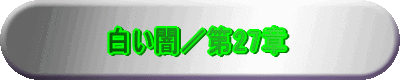
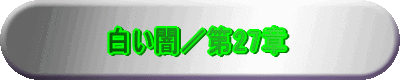
竜也は、セントジョセフ病院の待合室で悦子と2人、梢の手術の終わるのを待っていた。何の装飾もない白い壁を見つめていると、梢との出会いからミシガンに赴任するまでの40年余りの出来事が走馬灯のように頭の中を駆け巡っていた。
梢は死んでしまうのだろうか、そう考えると、ずっと昔、蓼科高原を旅行したとき、白樺湖のボートの上で竜也に向って微笑んだ梢の笑顔が浮かんできた。
『美しい。失いたくない。』竜也は、梢との意見の衝突や梢と悦子とのいざこざなどすっかり忘れていた。梢の魅力ばかりが誇張されて脳裏に焼きついていた。
ふと傍らに目をやると、悦子が目を閉じて椅子にもたれていた。眠っているのだろうか。それとも、梢に反抗してきた自分を反省しているのだろうか。悦子も確かにストレスが多いはずだ。ドイツで生まれた関係で、幼稚園から中学校まで転校の連続。しかも今度はアメリカ。学校では英語が理解できないだろうし、日本のテレビもない。この子は梢に辛くあたることでストレスを解消しているのだろうか。そんなことを考えているうちに、何時の間にか眠ってしまったようだ。
「お父さん、先生がみえたわよ。」
悦子が腕を揺り動かして、竜也は目が覚めた。慌てて立ち上がった竜也の前には、笑顔のストラックナー医師が白衣をはだけて立っていた。
「手術は終わりました。大成功です。奥さんは一命を取りとめました。但し、2日間はICUで絶対安静です。」
早口でそれだけ言うと、竜也に軽く握手をして、くるりと背中を向け早足に部屋を出て行った。部屋に残った看護婦が竜也と悦子に手招きしながら、梢に会せるから一緒にくるように言った。
2人は長い廊下を看護婦について歩いた。ICUと書かれた部屋のドアを開けると、幾つかの移動ベッドに患者が横たわっていた。梢のベッドは左手の奥にあった。頭には白い包帯が巻かれ、口には酸素吸入のマスクが当てられ、顔は殆ど覆われていたが、硬く閉じられた目は梢のものに違いなかった。
「未だ麻酔から醒めていないの。3時間もすれば意識は戻るわ。」
看護婦が優しく説明した。
「それじゃ、我々は一旦家に帰ります。昼からまた来ます。」
竜也と悦子は病院を出た。外は暗かったが雪明りで周囲を見渡すことができた。時計を見ると午前7時だった。冬のミシガンは夜明けが遅い。竜也はタウンカーをサリーンに向けて走らせた。途中、終夜営業のスーパーに立ち寄り、簡単な食事の材料を買った。
「これからは、お父さんが御飯を作ることになるから、悦子もお手伝いしないと駄目だよ。」
竜也は、駐車場のタウンカーに戻る途中に悦子に言った。
「うん!」
悦子は元気良く答えて車のほうに走り出した。竜也には何故か悦子が快活になったように思われた。こんな明るい返事はアメリカに来てからというもの聞いたことがなかった。皮肉なことだが、梢が倒れたことで悦子と梢の諍いに幕が下ろされた結果になった。
その日の午後、竜也は悦子を連れて再びセントジョセフ病院を訪ねた。今回は直接ICUに進んでいった。部屋の前で消毒を済ませ、息を呑んで部屋に入った。奥のベッドに梢がうっすらと目を開けて横たわっていた。
「梢、分るか。」
竜也は梢の左手を強く握り締めた。かすかにではあるが、その手は握り返してきた。
「そうか。分るのか。」
梢の目は少し大きく開かれて僅かに微笑んだように思えた。竜也の目から思わず涙がこぼれ落ちた。竜也はハンカチを取り出すのも惜しく、梢の左手を握り締めていた。悦子も泣いていた。
会社、家事、介護。竜也の3K生活が始まった。朝、会社に出勤し、夕方には病院に行く。帰りにスーパーで買い物をして、夜、翌日1日分の食事を作るといったパターンだ。
会社には日本人社員が竜也以外に15人ほど居た。社長の竜也の下に副社長が2人。1人は河田でもう1人はホイール販売の古川。古川の下にセールスマンの星田。星田は高校時代からボクシングをやっており、今でもデトロイトの「クランク・ジム」に通っていた。
機械部門は、副社長の河田の下に、セールスマネジャーの木谷、ダイカスト・マシン担当の米野。サービス部門ではマネジャーの糸川、その下に田口、中原。他にもサービス会社からの駐在が数名。
また、経理・庶務部門には新婚ホヤホヤの新島が居た。新島は高知の寒村・北川村の出身。そのことで、夜の席では皆にからかわれるのだが、本人は「四国の軽井沢のようなところです。」と澄ましていた。
殆どの日本人社員が夫人同伴だったので、奥さん方が気遣って、最初の2週間ほど交代で食事を届けてくれた。毎日御馳走ばかりで、流石に竜也は負担に感じて食事の提供を断わった。
梢の方は、3日目からはベッドから下りてリハビリの訓練に入った。リハビリのスタートは早ければ早いほど良い。梢の場合は、左脳摘出なので右半身は完全に麻痺しているが、左半身の機能を早く復活させることが、今後のQOL(クオリティ・オブ・ライフ)即ち、生活の質に大きく影響する。痛くても、辛くても、早く始めることが勝負の分かれ目になる。梢は、元来頑張り屋なのでリハビリには懸命の努力をした。
1日数時間の機能訓練が如何に大切かを本能的に理解していたようだ。1週間もすると、鼻から流動食用のチューブをぶら下げたまま、歩行具の助けを借りて数歩だが歩けるようになった。だが、言葉は全く喋れなかった。梢は竜也が用意した紙に左手でマルや四角の模様を書いて見せた。
梢が最初に書いた文字は、どういうわけか、漢字の『野』であった。後に分ったことだが、言語機能を失うと、文字記号と音声とを結ぶ糸がぷっつり切れた状態になり、表音文字の片カナや平カナは全く理解できない。表意文字の漢字なら音声を媒介せずに意味が理解できるようだ。数字も形自体が音を介さずに意味を持つので何とか理解できるようで、梢は竜也に算数の式を書いて見せた。
15―8=-7
マイナスの表示は変だが、引き算自体は正しい。
「梢は元気なときでも引き算は苦手だったのに、これだけ出来れば立派なもんだよ。」
竜也が言うと、梢はにっこり微笑んだ。魅力的な笑顔だった。梢は喋ることは出来なくても、聴くことは出来るようだった。何故そうなのかは竜也には分らなかった。
2週間後、梢は本格的なリハビリを受けるため、家の近くにあるサリーン市民病院のリハビリ病棟に転院することになった。サリーン病院は医療施設の面では劣るが、リハビリのセラピスト(療法士)は優秀なメンバーがそろっていた。
リハビリには、PT(理学療法)、OT(作業療法)、ST(言語療法)の3種類があり、それぞれに専門のセラピストが、毎日1時間程度の特訓を行う。梢は3つのセラピーを熱心に受けた。
竜也は、梢のリハビリ訓練を何度か見るうちにPTとOTの区別が漸く分ってきた。PTは歩行が中心で、OTは手の動きが主体だった。恐らく、手の機能を回復させて職業訓練を行うのでOT(Occupational Therapy)と名付けたようだ。
3つのセラピーの中で、最も困難なのはSTだった。梢の場合、基本言語は日本語だから英語でセラピーを受けること自体があまり意味をもたないのだ。PTについては、多点杖と呼ばれる4本脚の杖を左手に持ち、何とか自力で10歩程度歩けるまでに回復した。
OTの方も左手1本で時間をかければ衣服の着脱が自分1人で出来るようになった。だが、STだけは殆ど進歩がなかった。
サリーン病院での梢は、当初は、セラピーに復活の願いを賭けたように意欲的だったが、やがて徐々に元気が無くなっていった。食事は軟らかいものを口から食べるようになったが、5月には病院の食事を一切受付けなくなった。看護婦が差し出しても食事には見向きもせず、ベッドに横たわったまま天井の一点をじっと睨んでいた。時々、妄想に駆られたように大声をあげたかと思うと、全身を痙攣させた後、ぐったりと気を失ってしまう。
医者はトニック・シージャー(痙性発作)だと説明したが、竜也には梢が生きる勇気を失ったように思われた。現に、竜也に家族の写真をベッドの横に持ってこさせて、梢は自分の顔の部分を左手で覆い、静かに首を横に振った。自分はもう居なくていいのだ、とでも言いたげな、悲しい表情を見せることがしばしばあった。
竜也は、梢の衰弱は主治医と関係があるかもしれないと考えた。今の男性主治医は如何にも気弱そうで、信頼性に欠けていた。梢が痙性発作を起こすと医師自身が慌ててしまう。発作後梢が失神すると急いで瞳孔を懐中電灯でチェックする有様で、竜也は側で見ていてもどかしかった。
梢がうめき声を立てると、自分は日本語が分らない、何と言っているのだ、と竜也に通訳を要求する始末で、失語症の患者を診ているという自覚もない。思い余った竜也は、ディレクターのキース・カースに相談した。
アメリカでは患者の人権は完全に尊重されるので、こういうときには主治医の交代を要求できる。竜也は女医のデボラ・ペリー医師を指名した。
カースの理解ある計らいで、主治医がペリー医師に代わってから梢は見る見る元気になった。再びリハビリに励むように梢をみて、竜也は救われたように感じた。
7月になると、サリーン病院のスピーチ・セラピストのキャシーが、遂に弱音を吐いた。
「梢は熱心にセラピーを続けるのに、殆ど進歩が見られないわ。やはり、英語が母国語じゃないので無理なのかもしれないわね。一度、日本の病院で徹底的にSTを訓練すれば、少しは良くなるかもしれないわ。」
この時点で、梢の喋れる日本語は数えるほどしかなかった。
「ありがとう」「すみません」「ちがう」「いたい」「いやいや」「すげーな(すごいな)」「ほんと」
この程度のボキャブラリーで、梢は自分の意思を伝えようとした。しかし、これらの単語の間には意味不明の「モチカ、モチカ」とか「アプティ、アプティ」といった呪文のようなことを喋るので、聴く方は日本人でも竜也以外は殆ど聞き取れなかった。
竜也は日本で徹底的に言語療法を受けさせることを決心した。早速、東京の本社にファックスを入れて、日本のリハビリ病院を調査してもらうことにした。日本からの連絡によると、郷里の神戸に「しあわせの村」という施設があり、そこに立派な神戸市立のリハビリ病院があるという。
竜也は、直ちに高校の時のクラスメートで今は神戸市の幹部になっている山口省二のことを思い出した。山口とは2年間同じクラスで、一緒に野球をしたり、麻雀をしたりした仲だ。竜也の家にも何度かきたことがある。それに、彼の奥さんの和歌子も同じクラスメートで、クラスでトップを争う才女だった。
竜也は、ある時期和歌子に憧れていて盛んにアプローチを図ったこともあるが、結局は山口が和歌子を射止めた。それでも、和歌子とはずっと年賀状のやり取りを続けている。但し、山口との結婚後は和歌子だけに宛てるのは何となく気が引けるので、年賀状の宛名としては、山口省二様、和歌子様と併記していた。
竜也は神戸市の企画調整局長の山口省二にファックスを入れた。『一度お会いして相談したいことがある。』との内容だったが、竜也には突然電話するよりも文書でこちらの意思を先ず伝えることの方が自然なように思われた。
折り返し、山口の秘書から返事のファックスが来て、そこに複数の日程が示されていた。竜也は、早速山口との面談を最優先に一時帰国のスケジュールを作り、会社には1週間の休暇届けを出した。
8月に入ったばかりの日本は、既に猛暑が到来していた。竜也は、新しくできた神戸市役所の高層ビルの18階でエレベーターを降りた。秘書に名前を告げると直ぐに案内され、クーラーの効いた局長室で山口と向かい合った。
「卒業してから35年か。早いもんだよね。」
竜也は、すっかり貫禄のついた山口に気後れすることのないよう、変わりばえのしない挨拶から切り出した。
「そんなことより、君んとこ、奥さんが大変だったらしいな。今は、食事なんかどうしているんだ。」
山口は多忙なのだろう。早く本件に入って用件を済ませたかったようだ。
「まあ、何とかやってるよ。実は、今日はそのことでお願いがあるんだが。」
竜也も山口の事情を察して思い出話を抜きにいきなり用件に入った。
「しあわせの村の話か。」
「そうなんだ。アメリカでいくらリハビリをやっても、言葉のリハビリだけはどうにもならないんだ。向こうのセラピストからも、日本でスピーチ・セラピーを受けることを勧められていてね。」
「君が来ると聞いてちょっと調べておいたんだがね。あそこのリハビリ病院は人気が高くてなかなか空きがでないんだが、10月からなら何とかなりそうだよ。但し、あまり長期は無理だがね。」
「流石は将来の市長候補。早く市長になって下さいよ。」
「何を言うとるんや。君の方も体に気をつけてな。」
市庁舎を出て花時計の辺りまで来たとき、竜也は何か大きな忘れ物をしたような気がした。和歌子のことを訊くのを忘れていたのだ。
新幹線の新神戸駅から竜也は東京に向かった。今回の一時帰国で、もう1つプライベートな用件を片付けなければならない。
それは、3女の亜希子をアメリカに呼び寄せるための手配だった。亜希子はR大の2回生で彼女なりの学生生活をエンジョイしていた。が、母親が倒れたことへの心配と父親の手助けをしなければいけないとの配慮から、R大を中退してミシガンに行く決心をほぼ固めていた。
また、亜希子なりの計算としては、アメリカ留学という錦の御旗を手に入れる心積もりもあって、名門ミシガン大学への編入手続きを既に進めていた。竜也としては、亜希子の入学先は2の次で、亜希子をアメリカに駐在員の家族として呼び寄せるために、本社人事部の説得とアメリカ大使館からのビザの取得が優先事項だった。
これらの手配を一応終えて、竜也は埼玉県の朝霞に向かった。亜希子は、朝霞駅の近くにアパートを借り、次女の美佐子と2人で暮らしていた。そこに、猫のビビも同居していた。4年前に迷い込んできた真っ白な仔猫を梢が拾い上げて飼い始めたものだが、ビビは忽ち家族のアイドル的存在となった。今は便宜的に朝霞の狭いアパートに閉じ込めているが、亜希子がアメリカに来るならビビも一緒に連れてくることになっていた。
その夜、竜也は朝霞のアパートに泊まることにして、2DK全体がミシガンの家の一部屋に納まりそうな居住空間に窮屈な思いで床についた。だが、日本特有の真夏の湿気と、これからの生活を考えると、なかなか眠りにつけなかった。
![]()
「介護日記ーその後」にもどる
![]()
「白い闇」第28章に進む
![]()
トップページへ戻る