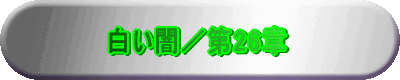
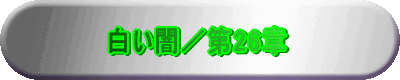
アメリカへの赴任について、仕事の面では全く不安はなかったが、問題は家族をどうするかにあった。
長女の恵子はW大を卒業し、外資系の運輸会社に勤めていた。次女の美佐子はD大の4回生だったが、教育産業に就職が決まっていた。3女の亜希子はR大の2回生で、オーケストラに所属してビオラを弾いていた。この3人は日本に置いていくほかはなかった。
末娘の悦子は14歳という多感な年頃で、これまでに何度も転向を余儀なくされ、精神的には不安定な状態であった。
ドイツで生れの悦子は、幼稚園だけでもドイツ、藤代、小平と3個所に通った。特に、ドイツの幼稚園から日本の田舎の幼稚園に移ってきたときのカルチャーショックは子供心に大きかったようだ。
帰国して1ヶ月もするとドイツ語を全く喋らなくなった。帰国直後は日本語よりもドイツ語が先に出てくるほどだったが、そのことが災いした。藤代の幼稚園では「変な言葉を喋る子」と、徹底的にイジメにあったらしく、早くドイツ語を忘れることが彼女にとっては仲間に入れてもらうための第一条件だったようだ。
親としては、折角喋れるようになったドイツ語を身につけさせておきたいという願望もあり、梢はしばしば悦子にドイツ語で話しかけたが、「それは悪魔の言葉!」と悦子は断固としてドイツ語を拒否した。
やがて、悦子は友達に異常なまでの気遣いをするようになっていった。小学校、中学校でも何度か転校があったためか、新しい友達をつくることに不自然なまでの努力を重ねていた。一旦できた友達には決して離すまいとする執着心が極めて強かった。
子供たちの間でポピュラーだった誕生プレゼントの交換でも、悦子は友人の気に入るプレゼントを買うために1時間でも2時間でも店の前で考え込んだ。
悦子の友人中心の価値観は、自我の芽生えとともに母親から心が離れていく結果となった。中学に入る頃には、必要なこと以外は梢とは話さなくなった。
だが、悦子は何故か父親の竜也にはなついていた。竜也は、悦子の態度を思春期に一時的にみられるエレクトラ・コンプレックスだろうとタカをくくっていたが、その傾向は時とともに拡大していった。
「貴方が悦子を可愛がりすぎて甘えかしたのがいけないのよ。」
梢は時として竜也をなじった。竜也は実際その通りだと思ったが、梢にそう言われると何故か腹立たしく感じた。
梢と悦子の間に揉めごとがあると、何時も悦子の味方をした。梢は徐々に孤立化していき、竜也との夫婦仲も徐々に冷え込んでいった。
梢は、小さな子供が大好きで、母親として子育てを最優先に考えていた。しかし、4人の娘が親離れし、夫の竜也も会社中心の生活を続ける状況からは、自分の存在を家族以外に求めるしかなかった。
梢は結婚前から和裁に熱中していたが、子育ての間は殆ど時間を割けなかった。梢は気分転換の意味もあってK着物学園に通うことにした。元々和裁の腕は相当進んでいたので、たちまち学園でも師範格に昇進し、助教授の免状を得た。
着付けの発表会には嫌がる竜也を無理やり会場に呼んでビデオを撮らせた。梢はビデオを何度も見て、自分の着物姿でのポーズや歩き方を研究した。努力の甲斐あって遂に教授の内看板を得ることができた。梢は外の世界で活躍することに喜びを感じるようになった。
梢は有田焼の絵皿の仕事にも手を出した。竜也から資金を借りて有限会社を設立し、自らが社長となり『代表取締役』と肩書きのある名詞をバッグに入れて関係先を歩き回った。
当時は女性の社会的地位の向上がもてはやされた時期で、梢の積極的な営業姿勢は評判を呼んだ。ある雑誌の企画で、政界の有力者A氏との対談記事が写真入で大きく掲載されたことがあった。
竜也は、この雑誌を見せられたとき、記事の大きさに内心驚いたが、中身には興味がなかった。A氏は、当時、若手議員として注目されかけていたが、竜也には九州のセメント会社のオヤジというイメージが強かった。
まさか、A氏が将来日本を背負う立場になろうとは夢にも思わなかった。20年後、A氏が自民党の総裁選挙で総裁就任が決まったとき、竜也は慌てて梢の残した荷物の中を調べたが、この雑誌は見つからずホゾを噛むことになる。
絵皿の事業は失敗だった。竜也から借り入れした数百万円は返済の目処が立たなかった。梢は自分の力の限界を感じた。片意地を張らずに竜也についていきたいと思うようになった。
しかし、竜也に面と向かうと、どうしてもしおらしい台詞が言えなかった。梢は何とか竜也との間を以前のように復活したいと思い、しばしば竜也に手紙を書いた。竜也が会社から戻ると、梢は既に寝ていて、テーブルに手紙が置いてある。
梢の手紙には、何時の場合もある種の思い込みが見られたので、竜也はその部分に赤線を引きそれが何故思い込みであるかについて丁寧な説明を付加えた。
翌日になると、梢はすっかり機嫌が直っていた。自分の手紙に加えられた朱筆のメモ書きを竜也の誠意と受け取った。その日の夜には、竜也のベッドにもぐりこんできた。竜也は可愛いと感じて梢を抱きしめるのだが、数日するとまたぞろ不定愁訴が高まって、鬱の様相を呈した。
今度は、竜也が手紙を書く番だった。あるときは、『思いこみの心理』という単行本を梢の枕もとに置いた。梢の良いところは、竜也のそうした説得を素直に受け容れることであった。
反面、梢と悦子の関係修復はそれほど簡単ではなかった。梢が口に出して説明しても最後まで聞かないので、竜也にやったように手紙で意図を伝えようとすると、翌日にはビリビリに引き裂いた梢の手紙が返事となって返ってきた。
竜也も流石に悦子の味方ばかりしていられなくなり、時には悦子をきつく叱ることがあった。悦子はふくれ面に涙をためてドアをピシャンと締めて部屋を出ていった。
悦子の3人の姉は、それぞれ自分の生活を謳歌していて、悦子のレベルに下りてきて慰めてやる余裕はなかった。結局、悦子は自分の理解者を友人に求めることになった。
竜也は梢と悦子の関係を何とか修復させたいと願っていた。そうすることが、梢との間の立て直しにもつながる。
その矢先に、アメリカ駐在の話が出てきたのだ。転勤の話を梢に伝えると、梢は「あなた一人で行ったらどう。」と冷ややかに答えた。竜也も内心ではその返事を期待していた。
面倒な家族との関係から解放されて、自由を楽しめるとの思惑があった。だが、一方では残された悦子と梢はどうなるのかとの心配が残った。梢は「なるようになるわよ。」と竜也の単身赴任を促したが、竜也には梢の発言は無責任だとしか思えなかった。同時に、竜也が単身で赴任するのは、それ以上に無責任のように思えた。
竜也は姉たちより先に、悦子にも話してみた。悦子の答えは「お父さんと一緒に行く。」だった。竜也の赴任地のアンナーバーには日本人学校はなく、80㎞ほど離れたデトロイト北部に日本人の補習校があるだけだった。英語もろくに喋れず、人見知りの激しい悦子がアメリカの現地校で上手くやって行けるとはとても考えられなかった。
しかし、竜也の下した結論は、梢と悦子を帯同することだった。梢を連れて行くことは、上司の新田専務からも強く勧められていた。新田は以前ニューヨークに単身赴任した経験があり、その時の侘しさを竜也に語り聞かせ、是非奥さんを連れて行くよう、強く進言していた。
竜也が梢に一緒に行って欲しいと懇願すると、梢の顔は、一瞬、明るくなった。梢は学生時代からアメリカの大地に憧れていた。特に、高校時代に愛読したマーガレット・ミッチェルの『風とともに去りぬ』は、ビビアン・リーの名演技に増幅されて、梢の心の奥底に燃える青春の血として長い間温存されてきた。そのアメリカの大地に足を踏み入れることは、梢には自分の理想像だったスカーレット・オハラに一歩近づくことのように思えた。
竜也の決心は固まったが、アメリカでの就業ビザの取得には時間がかかった。12月の初めになって漸くビザがおり、出発予定も固まったので、竜也は梢を連れて新田専務の自宅に挨拶に出かけた。
新田の家は聖跡桜ヶ丘にある。竜也一家は、帰国後、広い家を求めて転々とし、今は新百合丘の借り上げ社宅にいた。そこから聖跡桜ヶ丘は山越えすれば遠くはない。竜也は久し振りに着物姿の梢を助手席に乗せ、多摩の丘陵を越えて川崎街道を走った。
竜也夫婦を迎え入れた新田は上機嫌だった。狭い庭や趣味の鉢植えを梢に見せて、自宅を建てたときの経緯を説明した。梢は、新田との会話の受け答えを実に見事にこなした。
着物姿の自分を魅力的に見せる応対を知っていた。
新田は「奥さん一杯いきましょう。」と梢にビールを勧め、梢が一気に飲み干すと、「奥さんは亭主よりよっぽど話がわかるなあ。」と自分も些か酩酊気味で相好を崩した。竜也は久しく忘れていたデュッセルドルフ時代を思い出していた。
その年の12月29日、3人はデトロイト空港に降り立った。河田が迎えに来ていた。その日は、河田がアレンジしてくれたアンナーバーのホテルに泊まった。住居は予め決めてあった。会社はアンナーバーにあったが、竜也の家は郊外のサリーンという小さな町にあった。敷地2000坪、建坪50坪の大邸宅だった。しかし、家賃は東京での小さな借り上げ社宅よりはるかに安かった。
「中野さんは社長ですから社有車はタウンカーにしました。ホテルの駐車場にあります。鍵はここに置きます。」
河田はそれだけ言うと、さっさと帰っていった。翌朝、竜也はホテルから自分の新居まで必死の思いでタウンカーを運転した。何しろ、日本で乗っていたホンダのビガーに較べると、車幅は広く、車長は倍ほどもある。それに、左ハンドルなので、方向指示器を出そうとするとワイパーの水がフロントガラスに勢いよく飛び出してくる。道順は大体知っているとはいえ、全く初めてのアメリカでの運転だ。交通標識も理解できなかった。
やっとのことで我家にたどり着いたもののガレージの扉の開け方が分らない。だが、悦子は初めて見る豪邸の我家に思わず息をのみ、車のドアを開けて雪の中に飛び出した。
ミシガンの12月は日本の真冬以上に寒い。暖房は既に入れてあったので助かったが、家具は未だ届いていなかった。結局、ベットが届くまでの最初の数日間は、カーテンに包まって絨毯の上に寝る羽目になった。
翌朝、竜也は梢と悦子を連れて近くのサリーン中・高等学校を訪れた。アメリカの公立学校は、小学校が5年だが、中・高等学校が合計で7年ある。悦子は日本では中学2年の2学期を終えたばかりだったが、9月から新学期の始まるアメリカでは中学2年の前期からの入学となった。
アメリカの学校では、特に担任教師はなく、ソーシャルワーカーと呼ばれるスペシャリストが全学年を通じて、事務的な手続きから家庭の相談まで面倒をみてくれる。
ミセス・ファウラーがその人だった。長身のファウラーさんは、悦子のこれまでの生立ちを竜也から聴き、学校の規則を丁寧に説明した。竜也にとって最大の関心事はサリーン校に日本人生徒が居るかどうかにあった。ファウラーさんの説明によると、悦子の学年には男子生徒が1人、1年下には女子生徒が1人居るとのことだった。
だが、2人ともかなりの英語力があり、アメリカ人生徒の中に溶け込んでいる様子で、引っ込み思案の悦子の友人になれるとは思えなかった。
竜也の不安は的中した。悦子は2日目から学校に行くのを嫌がった。毎朝、黄色のスクールバスが竜也の家の近くまで迎えに来るのだが、悦子はバスに乗ることさえ嫌がった。アメリカ人生徒たちから白い目でみられるように感じていたのだ。悦子は人の視線を強く意識する性格で、他人から見つめられるのを極端に嫌がった。
仕方なく、竜也は毎朝悦子を学校まで送って行くことにした。悦子の当面の課題は英語のレベルアップにあったが、それ以前に教科書の内容がまるで理解できていないので、これを理解させる必要があった。
河田の紹介で、ミシガン大学の大学院に留学している安達美香に家庭教師を頼んだ。ミシガン大学は全米でも十指に入る優良校で、アンナーバーの中心部にあった。大学は、ゴルフコースまである広い敷地を有し、学舎も荘重な建物だった。また、ミシガン大学は市内に10万人収容の全米最大のフットボールスタヂアムを所有しており、アンナーバーは大学町としての名声を博していた。
徳島出身の美香は、ほっそりした、色白のチャーミングなお嬢さんで、美しい声で話した。竜也は東京オリンピック通訳時代の厚子のことを思い出していた。
悦子は、安達美香のことを無条件に受け容れたようだった。アメリカの学校のこと、アンナーバーの街の様子、自分の今後の進路などについて話すことが山ほどあり、日本人の相談相手が欲しかったのだ。
安達美香は大学の学生寮に住んでいて、車をもたなかったので、毎週2回の送迎は梢の仕事となった。竜也は社有車のタウンカーを使い、梢には当時ベストセラーカーのフォード・トーラスを買った。中型車だが排気量は3000㏄あった。
引越しの荷物の整理がつかない内に新しい年を迎えた。会社の日本人駐在員たちは、大半が家族とフロリダやメキシコの暖かい地方で冬休みを過ごしていた。竜也たちには、当然ながらそうした余裕はなく、アンナーバーに残って荷物整理やショッピングの場所を覚えたりするのに忙しかった。
竜也の家はアンナーバーの郊外にあったので、何処に出かけるのも車だった。公共の交通手段はタクシー以外にはなく、悦子がちょっとした買い物をするにも車に乗せていかなければならなかった。悦子は梢の車には乗りたがらないので、竜也の休日は殆ど悦子の買い物の付き合いで潰れてしまった。
梢と悦子の不仲は一層ひどくなっていた。夕食の食卓を囲んでも、悦子はもっぱら竜也に話しかけた。梢が口をはさもうとすると、「お母さんと話してない!」と会話の扉を閉ざしてしまう。典型的な反抗期の態度であった。
悦子は自分の母親に対して、まるで、イバラの鎧で身を固めているように、竜也には思われた。その矢先、1月14日に梢は倒れた。
![]()
「介護日記ーその後」にもどる
![]()
「白い闇」第27章に進む
![]()
トップページへ戻る