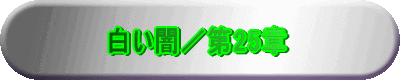
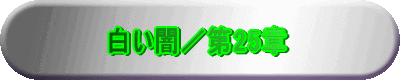
4年間勤めたプラント事業部の仕事に愛着を感じていた竜也は、割り切れない気持ちで機械事業部に帰ってきた。
新しい仕事は、機械の主力製品である射出成形機や押出しプレス、それに製鉄機械の販売であった。殆どの機種は既に経験済みだったので、竜也は直ぐに仕事に入ることができた。
一旦、機械の仕事に手を染めると、不思議なものでプラントへの執着は徐々に薄れていった。
時は正にバブル景気への入口で、1985年のプラザ合意以降急速に進んだ円高により、国内の金利が下がり、客先の各社は設備投資に意欲的であった。
特に、アルミサッシ業界では、各社が競って大型押出しプレスの新設に踏み切る設備投資競争の様子を呈していた。
従来、アルミサッシ業界では、大型押出し品の過当競争を防ぐため、各社共同で、「軽金属押出開発」という会社を設立。そこに超大型7500トンの押出しプレスを共同で設置し、大型押出し品はすべてこの設備を共同使用することがルール化されていた。従って、各社は4000トン以上の大型機を自社に設置しないことを申し合わせていた。
しかし、油圧機械の能力は、単位当たりの圧力と油圧シリンダーの直径で決まる。例えば、1 cm2当たりの圧力が210㎏で4000トンの能力があれば、単位圧力を350㎏に上げると6700トンの能力になる。業界では単位圧力を規定していないので、この申し合わせは実際にはザル同様であった。
各社はこぞって3950トンの押出しプレスを設置することにしたが、どれも単位圧力を350㎏まで上げることができる構造になっており、実力は7000トン級のプレスであった。
この背景には、トラックの大型化がある。従来、トラックの荷台には鉄か鉄と木を組合わせた側壁(あおり)が使われていた。しかし、大型化と軽量化のために、あおりがアルミ押出し製品に代わったのだ。大型トラックのあおりを作るには大型押出しプレスがどうしても必要だった。
また、バブル景気に入ると、ビルやマンションの建設ラッシュが始まり、大型アルミサッシの需要が一挙に伸びてきた。山口工業は大型機が得意だったので、ほぼ独占的に大型プロジェクトを受注していった。
竜也は部下の広田と組んで、サッシ業界の大手各社を精力的に回った。注文はドンドン入り、現場は悲鳴を上げた。竜也の配下の押出しプレスグループは少ない人間で莫大な売上と利益を上げた。
製鉄業界も同じような傾向にあった。製鉄機械グループでは、自動車のボディなどに使う、圧延コイルの最終仕上げ用テンパー・ミルを扱っていたが、こちらも海外中心に大きく伸びた。
しかし、射出成形機については、様子が違った。2000億円足らずのマーケットに10社以上が参入する完全な過当競争の結果、自動車会社や家電メーカーに買い叩かれて、安値競争が激化していた。各社は活路をアメリカ向け輸出に見出した。
射出成形機の製造はヨーロッパと日本が主力で、アメリカには大手メーカーはミラクロン社1社しかなかった。まるで、アメリカ市場を狙い撃ちするかのように、各社はアメリカ向けに力を注いだ。
竜也のところでも、ベテランのセールスマンだった河田と木谷をデトロイトにある販売会社に駐在員として派遣した。更に、サービス体制を充実するために工場から糸川を引き抜いて現地に派遣した。
射出成形機メーカーが日本人スタッフを現地に送り込んだ裏には、日本の自動車およびその関連メーカーのアメリカ進出があった。自動車各社は工場をアメリカに建設し、日本と同じものを作ったので『トランスプラント』と呼ばれた。トランスプラントのキーマンはすべて日本人で占められていたため、彼らも勝手の分らないアメリカ製の設備よりも使い慣れた日本製のものを好んだのである。
また、ビッグスリーと言われるアメリカの3大自動車メーカーでも、日本車の品質を見直す段階に入っていた。彼らの研究では、日本車の品質は廉価で優秀な部品に頼るところが大きいことが分かった。その結果、効率的に品質のよい部品を製造するために、進んで日本製の設備を購入した。
こうした背景から、射出成形機の対米輸出は集中豪雨的に増えていった。やがて、日本メーカーはしっぺ返しを受けることになる。米国側からのダンピング提訴と特許違反提訴であった。
特許違反については、レメルソンなる街の発明家の基本特許を日本各社が侵害しているとするものだった。レメルソン特許は、日本ならおよそ特許として成立しない内容だが、実に広い範囲をカバーしていた。
しかし、この特許には先行文献があり、無効確認訴訟で十分対抗できると思われた。事実、提訴に対抗するために業界は結束した。
当時の通産省の下部機関である産業機械工業会の射出成形機部会で、竜也は輸出問題検討会の座長を務めた。この部会に、各社の営業マンと特許マンを集めてレメルソン特許への対抗手段を協議した。
各社とも最初は打倒レメルソンに満々たる意欲を見せた。しかし、レメルソン側の弁護士から脅迫とも思える訴訟の警告状が各社に届いた途端、腰砕けとなってしまった。
警告状には、露骨にも次のような文面があったからだ。
『賢明なる日本各社は既に御存知と思うが、アメリカの裁判は陪審員による裁判である。陪審員は、機械の専門知識を持たない、いわば素人の集まりで、彼らにとっての関心事は日本製の機械がレメルソン特許を侵害しているか否かではない。
彼等は、アメリカ経済に打撃を与える日本の大企業に対抗する、”無力で善良な米国の一発明家の挑戦”という構図で全体を捉えるであろう。
我々の弁護団も、強者対弱者の構図を浮き彫りにして陪審員に訴える積りだ。その場合の判決がどちらの側に有利となるかは、技術論争以前の問題といえる。この事実を無視して、無謀にも我々に法廷での闘争を選んだK社は、結局敗訴して、1億ドル近い罰金を払う結果になったことを付記しておく。』
警告状は最後に和解の場合の金額を示唆していた。その金額は組合加盟の11社で割れば1社当たりの金額は捻出できない額ではなかった。各社は一斉に和解の方向に動いた。
「皆さん、これは和解ではなく恐喝です。こういうことを許すから日本はアメリカになめられるのです。全社が結束して対抗しようではありませんか。」
竜也は、N社、S社とともに最後まで徹底抗戦の構えを崩さなかった。しかし、財閥系のS社が和解に傾いたことで、遂に矛先を納めるべき状況となった。
竜也は上司の新田に相談した。常務で営業本部長の新田は、ひと通り竜也の説明を聞いてから静かに言った。
「確かに、日本で裁判するなら勝てるだろう。だが、陪審員の下で勝てる確証はない。負ければ、汚名と莫大な損失を被る危険がある。今の当社にはそんなリスクを犯すことはできない。キミの正義感だけで会社にリスクを負わせるわけにはいかない。」
竜也は涙を呑んだ。後日、射出成形機各社が米国の発明家との特許係争で和解した、と新聞各紙が短く報道した。
1989年7月、竜也は重機営業部長に昇進した。重機営業部は50人の大部隊で、その営業部長は機械事業部では最大の要職であった。従来の機種に加え、ダイカスト・マシンや減速機が営業品目に加わった。更に、その年の10月にはアルミホイールの販売をも竜也がみることになった。
上司の新田からこの相談を受けたとき、田辺をリーダーに抜擢してくれることを条件としてつけた。田辺はデュッセルドルフでは、竜也の手足として実によくやってくれた。だが、帰国後の処遇は余り恵まれていなかった。竜也は成長性の高いホイールビジネスを田辺に任せたいと考えたのである。
アルミホイールの販売まで竜也がカバーすることになったお陰で、再び、久保田との接点ができた。射出成形機とホイールの最大の顧客は自動車メーカーで、ホイールについてもアメリカ生産を伸張させることが緊急課題となった。
オハイオ州のメイソンという片田舎に山口工業のホイール工場があった。久保田は頻繁にメイソンに出かけていた。
ある時、出張を目前に控えた久保田に驚くべき事態が起こった。あの鉄人久保田が交通事故で即死したのだ。
メイソンの近くにはジャック・ニクラウスの設計による名門ゴルフコースがあり、メイソンへの出張では休日に此処でプレーするのが出張者の楽しみとなっていた。久保田は出張の前日に自宅近くの練習場でコンディションを調整した。練習場への送り迎えは奥さんの仕事で、その日も練習の後、奥さんの運転で自宅に戻る途中であった。
自宅近くの信号で、横から出てきた自転車を避けようとして、奥さんがブレーキとアクセルを間違えたらしい。クルマはコンクリート塀に激突し夫妻ともに即死だったという。
敦賀では電車と衝突しても死なず、アルジェリアの拘置所では囚人たちを怒鳴りつけたという偉丈夫が、いとも簡単に自宅近くの事故で死亡したことは、竜也にとって大きな衝撃だった。
しかし、竜也よりも大きなショックを受けた人物がいる。他でもない、社長の塩川だった。塩川は、以前患った狭心症に加え、すい臓にガンが見つかり、体調は既に悪化していた。久保田急逝のニュースは塩川の体調悪化に拍車をかけ、久保田の後を追うかのように病死する。
塩川は自分の残りの寿命が短いことに気づいていたようで、自ら社長の座を化学出身の東山専務に譲り、自分は会長に就任した。
この社長交代には、種々の憶測が流れた。というのは、東山専務が子会社の社長に転出するという新聞辞令が先に発表されたからだ。現実に、新社長には研究開発出身の名村専務が内定していたらしい。
名村は仕事はよくできたが地味な存在で、果たして社長の器に相応しいか、疑問があった。この内定に猛然と反対したのは、中田道夫だった。
当時、副社長に昇格していた中田道夫は、故・中田会長の長男で、外見は父親譲りだが中身はまるで違っていた。豪放磊落という点では共通するものがあったが、父親が仕事の虫であったのに対して、道夫の方は仕事にはあまり熱心でなかった。
道夫の興味は勤務時間が終わった後のアフターファイブにあったようだ。海外出張に出かけても、昼間は半分居眠りしていたかと思うと、夜になると目が輝き、深夜2時、3時まで付き合わされるため、駐在員は一様に中田道夫のアテンドにはてこずったものだ。
しかし、中田道夫には経営者としての自信があった。毎朝1時間、父親から帝王学の講義を受けてきただけに、トップは斯くあるべしについて一家言もっていた。本来は自分が塩川の後継者となるべき筈だが、名村が指名された。中田道夫はこの社長人事に猛然と反対し、対抗馬として4歳年上の東山専務を推した。
東山は、バランスのとれた人格者で、従業員からの信頼も厚く、カリスマ性という面では名村よりも数段優れていた。社長職に求められるカリスマ性を議論の前面に出した中田道夫の熱心な説得により、他の役員たちも中田の意見に傾いていった。
役員諸侯の雰囲気から塩川も名村の社長就任を断念せざるを得なくなり、急遽、東山の子会社への転出が取り消された。
新体制は塩川会長、中田副会長、東山社長のトロイカ体制に落ち着いた。しかし、中田道夫は実権のない副会長という新しいポジションに違和感を覚えた。会長と社長の狭間に追い込まれたような代表権のない副会長というポジションは、従来山口工業にはなかった役職で、中田道夫のために便宜的に用意されたような印象を受けた。ポスト東山の次期社長候補と自負していた中田道夫にはまことに居心地のよくないポジションであった。
しかし、他の役員たちは、お行儀のよくない中田が会社の代表取締役に就任することには抵抗があり、中田の副会長は『はまり役』だと感じていた。塩川の死後、中田は一時的に会長職につくが、この時にも代表権はなかった。
重機営業部長としての竜也の仕事は多忙を極めた。新しく守備範囲となったアルミホイールは丁度成長期にあり、日本のT社と米国のGM社が主要カストマーだった。
工場側では量産によるコストダウンを実現しようと、年産2百万個体制を敷き、2社以外にも新規顧客の開拓が急務となっていた。その矢先に久保田が急逝したために、中心を失ったホイール部隊は混乱した。
ホイール会社の会長の藤本は、好機到来とばかりに再び自らの勢力挽回を図り、新社長の東山を説得してホイール会社の社長兼会長に返り咲いた。
オハイオの工場では、久保田の死後本部からのコントロールが効かなくなり、現地では全米自動車労組(UAW)が組合化の動きを見せていた。
一般に、トランスプラントと呼ばれる日本企業の米国工場では、UAWが入り込まないよう万全の対策を講じている。UAWは強大な組織力をもっており、労使交渉が決裂すると、1ヶ月でも2ヶ月でもストを続けることができる。生産に追われた会社側は止む無くUAWの要求を呑み、待遇改善を約束する。
こうして、米国の自動車会社はコスト高と品質の低下という慢性的な病気に取り付かれ、次第に競争力を失ってしまった。ただ、クライスラー社だけは、伝統的に主要部品を自社で生産しておらず、外部から購入する外注比率が高かった。このためコストの安い日本のトランスプラントから主要部品を購入することで、コストダウンと高品質を同時に達成できた。
1980年フォード社から身を転じたアイアコッカがクライスラー社の会長に就任するが、彼は自社製の部品を日本メーカーからの購入に切替えて成功した。90年代に入り、一時的にではあるが、クライスラーはビッグスリーの中で最大の成長を遂げることになる。
山口工業のオハイオ工場も組合対策には万全を期していた。ウィスキー工場から引き抜いた辣腕のダグ・レイノルズを総務部長に据え、UAWの入り込む隙はないようにおもわれた。しかし、その当時からUAWによるメイソンの従業員囲い込みの動きは徐々にではあるが、密かに始まっていた。
重機の主力製品である射出成形機とダイカストマシンについても、米国のビッグスリーがメインのお客であった。竜也が重機営業部長になったときには、既にGM・サターン社向けに大型射出成形機の大量注文が決まっていた。
GMが大衆車・サターンを世に出すにあたり、従来の鉄製のボディパネルを樹脂に替え軽量化を図ったのだ。主力工場のスプリングフィールドでは、トランスファープレスではなくプラスチック成形機のラインが設置されることになった。これは、プレス業界では極めてショッキングなニュースで、当時は大きな話題を呼んだ。
一方、フォード社もバンパーの大型化を進めており、大型成形機に定評のある山口工業への大量発注を決めていた。
また、ダイカストマシンについてもGM・パワートレイン社では、全く新しいタイプのシリンダーブロックをDJ社と共同開発し、そのための超大型の3600トン/ダイカストマシンを山口工業に発注していた。この商談では、竜也がキーマンとなった。
竜也はGM本社のあるミシガン州のサギノウとDJ社のあるオハイオ州トレドを何度も往復した。
クローズド・デッキと呼ばれるシリンダーブロックの新技術は日本の自動車メーカーからも熱い視線を受けていた。特に、T社はこれの導入に非常に乗り気で、竜也はDJ社の技術者を連れて、名古屋の奥にあるT社の第4生技部を幾度となく訪れた。
一度は、後に副社長になるT社のJ重役とベテラン技術者のM氏を帯同して、DJ社の技術を確認するために、アメリカを駆け回った。
このようなアメリカ市場への傾注は、やがて自分を新しい任務に導く導火線になるのではないか、と竜也は内心では薄々感じていた。
1992年10月、竜也は専務に昇格した新田に呼ばれ、アメリカ行きの転勤内示を受けた。デトロイトの販売会社の社長の椅子が用意されていた。竜也は一応驚いて見せたが、こうなるだろうことは既に覚悟していた。
![]()
「介護日記ーその後」にもどる
![]()
「白い闇」第26章に進む
![]()
トップページへ戻る