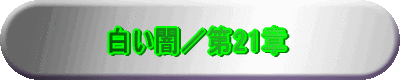
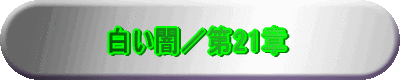
竜也の所属するプラント営業第3部は新しく作られた部署であった。1975年に、山口工業の第5の事業部としてプラント事業部ができたが、営業品目が増えるに従って部の数も増え、竜也の帰国を機に営業3部体制がとられた。
営業第1部長、第2部長とも竜也より7歳も年上で、43歳の第3部長は異例の昇進だといえる。しかし、竜也の新しい上司になる中山は竜也以上の抜擢であった。
シドニーの小さなオフィスで石炭の輸入をしていた中山は、竜也と同時期に帰国辞令を受けたが、中山のポジションは取締役・プラント営業本部長だった。46歳の中山は、以前から竜也に対してある種のライバル意識をもっていたようで、着任早々竜也を夕食に誘い、その席で竜也に対して宣言した。
「サラリーマン社会では、役員と部長の間には大きな段差がある。この段差は決定的なもので、キミはオレを裏切ることはできない。また、オレの命令にはキミは絶対服従しなければならない。このことを肝に銘じてほしい。」
竜也は中山の勝利宣言のような台詞を聴きながら内心苦々しく思った。だが、中山が上司となった以上この男に仕えるのはサラリーマンとして当然だ。けれども、豪州で石炭を買っていた男にプラントビジネスは到底無理だろうと感じた。中山自身も仕事のやり方については、竜也に一目置かざるを得ない筈だ。竜也としては、中山とは一定の距離を保ちながら、無抵抗不服従を通すほかはなかった。
営業第3部の業務は、化学、セメント以外のプラントを販売することにあった。プラントとは、特定の製品を作るための工場を設計(エンジニアリング)し、必要な設備機器を調達し、生産できる状態にして、工場1式を客先に引き渡すビジネス。従って、工場の設計には生産技術がどうしても必要であった。
化学とセメントは山口工業の主力製品だから、社内に技術の蓄積も豊富にある。それらの技術をベースにエンジニアリングを展開するのは常道と思われた。
しかし、それ以外となると山口工業には技術の蓄積がなかった。唯一あるとすれば、機械事業部の主力製品を核にプラントを設計することだが、その場合も機械のユーザーで、生産技術をもった会社の協力が不可欠である。営業第3部としては、先ず、海外にプラントを販売してくれそうな、生産技術をもった会社と協力関係を打ち立てることから入っていくことが必要だった。
優れた生産技術をもつ会社には、例え中小企業でも、竜也は熱心に足を運んだ。そんな中で、ふとしたきっかけから娯楽機械メーカーのT社と知り合ったことが、極めてユニークなソ連向けのプラント商談に結実することになる。
83年の夏も終わりかけた頃、新しいビジネスチャンスを求めて、竜也は新宿で開催されていた「日本娯楽機械展」にぶらりと立ち寄った。特に目的があったわけではないが、当時、ニュービジネスのABCの「A」に「アミューズメント」と「エージング」があげられていたことが心の底にあった。
たくさんの遊器具が並べられていた中で、ジェットコースター・レールの三次元CADによる展示に何故か惹かれるものを感じた。早速、メーカーのT社に依頼して各種の技術データを取り寄せ、それをもとにジェットコースターの英文カタログを作成した。
イメージキャラクター「アヒルの水兵さん」を大きく取り入れた、楽しいカタログを社内に回覧したところ、上司や同僚から一斉に冷たい笑いを浴びた。
「山口工業の体質に合わない。」
「遊んでいて仕事ができるはずがない。」
予想していたとはいえ、各所からのブーイング。だが、竜也には漠とした確信に近いものがあった。
アヒルの水兵さんを社外にばらまいて暫く経った頃、一つの小さな当たりがあった。日本商事からソ連に紹介したいと言ってきたのだ。
当時のソ連はゴルバチョフの出現とともにペレストロイカが叫ばれ、陰湿な秘密政治から市民を解放し、夢と喜びを市民に与える政策に重点が置かれていた。資本主義諸国の市民の娯楽の中で、最もポピュラーなものの一つにジェットコースターがあった。ソ連にもカターリニエ・ゴールキ(滑る山)と呼ばれるローラーコースターがあったが、旧式のもので、スリルに富んだ日本のものに較べると極端に見劣りして市民も殆ど利用していなかった。
アヒルの水兵さんを日本商事経由でソ連のライセンス公団に配ってから暫くして、ジェットコースターを製作する設備(プラント)の引合が寄せられた。竜也は久し振りにロシア語を使えるチャンスが来たことを喜ぶと同時に、直感的にこの商談はものになると判断した。そこで、部内でも最も粘り強い性格の福井にこの商談の担当を命じた。
福井は、大学では化学を専攻したエンジニアで、水処理や化学プラントにこそ自分の本領が発揮できるものと信じていた。ジェットコースターの担当を命ぜられた福井は、一瞬、顔を引きつらせて抵抗した。
「自分は化学屋です。こんな仕事は言っちゃ悪いですが、誰にでもできます。他の誰かにやらせて下さい。」
「確かに、君は化学屋だが、化学屋が娯楽機械を売ってはいかんというものでもあるまい。それに、君の幅を広げるためにもいいチャンスになるだろう。とに角、文句を言わずに一度だけモスクワの商談に参加してほしい。その上で、どうしても嫌なら他のメンバーを考えよう。」
竜也はなだめすかすようにして、福井をモスクワでの第1回のネゴに送り出した。福井なら辛抱強くソ連との商談に耐えるだろうと考えたからだった。“案ずるより産むが易し”とはよくいったもので、福井は喜々としてモスクワから帰国した。
第2回、第3回のネゴには福井は自ら進んで参加した。また、メーカーのT社や商社の日本商事との調整についても、持ち前の粘り腰でこちらの要求を通していった。
ネゴが進んでくると、福井はモスクワにアパートを借りて、そこに寝泊りするようになった。片言のロシア語も憶えた。20のボキャブラリーでモスクワ中を歩けると豪語した。
第10回目のネゴで、漸く商談がまとまった。
84年11月、竜也は日本商事の部長とともに調印式に赴いた。シェレメーチェボ空港には福井が出迎えたが、竜也は最初それに気がつかなかった。長身の福井が毛皮の帽子を目深に被っていたためロシア人と区別がつかなかったのだ。
福井は、竜也が社内きってのソ連通であることを忘れたのか、竜也にモスクワ市内のガイドをしてくれた。ホテル付属のアパートの一室では福井と日本商事の内川の手料理を御馳走になった。
翌日の調印式の夜のパーティーの席で、竜也は何年振りだろうか、ロシア語で挨拶した。前夜、ベットの中で少し練習した所為もあって思いのほか上手く喋ることが出来た。
「ガスパヂン・ナカノのロシア語の復活のために!」
乾杯好きのロシア人がウォッカのグラスを上げた。竜也はなみなみと注がれたグラスを少し舐めただけでテーブルに置いた。
ジェットコースターの商談に成功したことがきっかけとなって、ライセンス公団向けに次々に追加商談が決まった。C社のカメラのシャッターを作るプラント、同じくC社のマイクロモーター・プラント、更には、Z社の魔法瓶プラントなども成約に漕ぎつけた。社内では、竜也の営業第3部がソ連向けに次から次へと注文を取ってくるのを魔法使いの魔法を見るような眼差しで見ていた。
しかし、反対意見もあった。特に、事業部長の安井専務は、赤ら顔を引きつらせて皮肉混じりに竜也にクレームをつけた。
「君は何でも注文を取ればいいと思っているのかも知れないが、ワシはこういう仕事は、ウチの会社がやるべき仕事だとは思わない。第一、当社にない技術を売って利益を稼ぐこと自体理解できない。仮に利益がでるとすれば、それは商社の口銭と同じではないか。プラント事業部は商社ではない。」
「そうは仰言いますが、専務。」
竜也は反論した。
「第3部の営業品目は、元々化学とセメント以外のその他ということになっています。その他の技術はウチにない。だから他人のフンドシを借りるのです。」
「日本には優れた技術をもった中小企業が沢山あります。彼らはプラント輸出しようにも、それだけの人材がいない。英文の技術仕様書のひとつも書けません。それを我々が協力してエンジニアリングパッケージに仕立てあげるのです。専務は、ウチは商社ではないと言われますが、私は技術商社としての立場を尊重したいと思っています。」
安井は竜也がこれほど粘り強く抵抗してくるとは予想していなかった。高潮した顔には、明らかに、焦りの色が見られた。
「それなら訊くが、ウチの利益は何処から出てくるのかね。商社と同じようにマージンで稼ぐしか方法がないはずだが。」
「技術商社は専務が考えておられる以上に有利なのです。というのは、プラント事業の最大のコストは固定費です。プラントの受注には山谷がありますが、谷の部分の注文の少ない時でも、山の部分を想定した技術陣を抱えておく必要があります。その固定費をカバーしきれないのです。」
竜也は、勝ち誇ったように続けた。
「つまり、谷の部分で被った損失を山の部分で取り返せない、そのリスクがプラント事業にはついて回るのです。一方、技術商社ならどうでしょうか。オールラウンドの技術屋を少数抱えていればよいのです。山の部分をこなすだけの技術陣は他社が準備してくれているわけです。つまり、固定費は極端に低い。だから儲かるのです。」
「ワシには君の考え方が分らん。」
安井はケッケッと笑うと竜也に下がるように手で合図した。
竜也が自分の席に戻ると、営業本部長の中山が心配顔で竜也のところにやってきた。
「専務がああいっておられるが、君は考え直す必要があるんじゃないのか。」
「その必要はありません。優秀な企業と密に付き合っていれば、この仕事は幾らでも伸ばせるのです。第1部、第2部の稼ぐ利益と比較してみて下さい。第3部が利益面で見劣りがするというなら考え直します。」
竜也は大見得を切ったが、この時は第3部の利益を根底から覆すような事件が発生しようとは夢にも思っていなかった。
![]()
「介護日記ーその後」にもどる
![]()
「白い闇」第22章に進む
![]()
トップページへ戻る