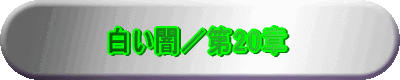
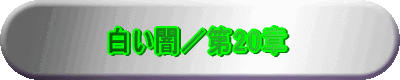
辞令が出ると2週間以内に新しい職場に赴任するのがサラリーマンのルール。8月初旬、竜也は帰国準備に手間取っている家族を残して一足先に東京に帰った。とはいえ、住居は都心から遠く離れた茨城県北相馬郡藤代町の志村邸である。
取りあえず、スーツケース1つで藤代の家に入ってみて驚いた。家の中は散らかり放題。部屋には洗濯物がぶら下がってまま。本棚には志村の書物がビッシリ並んでいる。冷蔵庫を開けてみると、干からびたご飯の入った茶碗や半分飲みかけのビールなどが雑然と入っていた。
まるで空き巣に入ったような感覚にとらわれて、竜也はタンスの引出しを開けてみた。そこには、空の香典袋がギッシリと詰まっていた。前年、志村の母が亡くなったときの香典らしい。
2階は2人の姉妹の部屋。こちらも階下と同じようなものだった。床に放り出された無名塾の卒業証書に目が留まり、竜也はそれを拾い上げて暫く眺めていたが丁寧に机の引き出しにしまい込んだ。
役に立ちそうな家具は置いていく、と恩着せがましく言っていた志村の顔を思い出しながら、竜也は何度も舌打ちした。
「これじゃ、ウチの荷物を入れるところがないよ。」
自分でも驚くほどの大声で独り言をいった後、竜也は額の汗をぬぐった。やけに暑かった。窓を閉め切ったままの2階は、真夏の太陽の火照りでサウナ風呂に入ったようだった。
竜也は、リビングに下り、クーラーのスイッチを入れてみた。ガタガタと音を立てながらモーターが回り始め、暫く経って少し冷たい風が頬をなでた。
「無いよりマシか。」
小声で口に出し、マットレスを畳んだだけのソファに腰を下ろすと、ポケットからタバコを取り出して火をつけた。冷蔵庫の上にあった汚れた小鉢をを灰皿代わりにして、吸い込んだ煙を天井に向けてゆっくり吐いた。
「梢が見たらパニックになるかもしれないな。」
今度は声には出さず心の中でつぶやいて、これからどうすればよいか考えをまとめることにした。志村一家は時間が無くて慌てて出て行ったのかもしれないが、これではまるで夜逃げ同然。いくら先輩とはいえ少しひど過ぎると思う。直ぐに掃除をせずに、このままの状態を会社の人事に見せておく必要がある。この家は志村の家だが、契約は竜也と会社の人事で結んだもので、家賃も会社に支払うことになっている。
翌朝、2時間近くかけて出社した竜也は、自分の部署に行く前に人事部に立ち寄った。
「昨日、志村さんの家に入ってみたのですが、家の中は散らかり放題でしたよ。志村さんの家とはいっても、借り上げ社宅ですからキチンと入居できる状態にしておくのスジではないですか。一度、見に来てください。」
「中野さんが入居されるというので、前日に下見に行きました。ドアを開けて中に入ってみると、未だ、どなたかが住んでいるのではないかと思いました。」
20代半ばと見られる男の係員が、申し訳なさそうに小声で答えた。
「人事としては、そんなことでいいのですか。ドイツでは、妻が明日にも荷物を発送すると思います。私どもの家財はどこにしまうのですか。書棚やタンスは置きっ放し。中にはモノが詰まっているじゃないですか。あなた、冷蔵庫の中を覗いてみましたか。」
「いいえ、そこまでは・・・」
担当者の声は更に小さくなった。
「このことを課長には報告されましたか。」
小心者の係員ではラチが開かないと判断した竜也は課長に直談判しようとした。だが、すがるような眼で担当者が振り向いたデスクには誰もいなかった。
昼前になって、竜也はニューヨークの志村に電話をかけることにした。時差は13時間。今頃は家に帰っているはずだ。志村はホワイト・プレーンに豪邸を借りたと聞く。人事で教えられた番号を回した。
「おう、お帰り。藤代の住み心地はどうだ。」
受話器から志村の張りのある声がした。
「住み心地もどうもないですよ。家の中は志村さんの荷物がいっぱい残っているじゃないですか。」
「ほう、オレは先に出てきたから良く知らないんだ。どんなものが残ってる?」
「先ず、本棚には志村さんの本がギッシリ。冷蔵庫にはビールや食べかけのご飯が残っています。」
「そうか。こちらは日本の書物がなくて困っているんだ。すまんが送ってくれるかな。ビールは飲んでいいよ。」
「また、そういう調子だから! いくら先輩といっても、今度のことは腹に据えかねていますから・・・」
竜也は少しきつい表現で胸のつかえを吐き出して、電話を切った。
藤代は田舎町ではあるが、東京のベッドタウンとして発展しつつあった。たくさんの戸建て建売住宅が完成していて、殆どが東京へ通うサラリーマンが住んでいた。家の近くにはスーパーやレストランなどもあって、生活自体に不自由を感じることはなかった。だが、週末に竜也は藤代に来て初めてのカルチャー・ショックというべきものを経験することになる。
8月末には家族が帰国し、子供たちは2学期の9月から地元の学校に通い始める。転校の手続きは既に終えたが、学校の制服をそろえる必要があった。長女の恵子は中学3年、次女の美佐子は1年。藤代中学指定の近所の洋服屋を訪ねた。
「藤代中学の制服が欲しいのですが。」
すると、店頭に立った竜也を快く迎え入れたオヤジさんが出し抜けに言った。
「イロ・イモ・イスがあっだべ?」
語尾を上げて言っているので、明らかに竜也に対する質問なのだ。意味がよくわからなかったが、こういう時には会話を進めることで判断するのが竜也のやり方だ。
「色は紺色と聞いています。芋や椅子ではなく、制服だけ買いたいのですが。」
「んだども、イロ・イモ・イスがあっだべ。」今度はやや語尾が下がって苛立ちをこめた語気に思えた。
「はぁ?」
いぶかしげな表情の竜也を見て、オヤジさんは物分りの悪いヤツだといわんばかりに、ウィンドーから制服を一着取り出して、襟の裏を指差した。
そこには「M」と書いてあった。
「そ、そうです。Mがほしいのです。」
竜也は、その時はじめて、イロ=L、イモ=M、イス=Sであることに気がついた。
![]()
「介護日記ーその後」にもどる
![]()
「白い闇」第21章に進む
![]()
トップページへ戻る