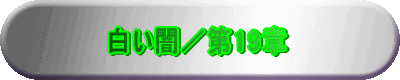
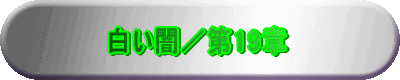
1983年7月、竜也に帰国辞令が出た。新しい部署は「プラント事業部・営業第3部長」とあった。
竜也は新しい職務に満足したが、実はこの人事の裏には複雑な人間関係が潜んでいた。
その年の4月、山口工業本社では大きな人事異動があった。社長の水沼が1期で退任。後任の新社長にプラント事業部長の塩川専務が抜擢された。この人事を決めたのは会長の中田だが、塩川は必ずしも本命視されていなかった。
中田の意中の人物は筆頭専務の藤本ではないかと噂されていた。藤本は40代で専務に昇格した若手のバリバリで機械事業部を任されていた。だが、藤本がとんとん拍子で出世していったのは、同期入社の中田道夫との関係からではないかと言われていた。
中田道夫は中田会長の長男で、セメント事業部を任されていた。中田会長の本音としては、自分の長男を早くトップに上げたいが強引にやるのは憚られる。だから、同期の藤本を先に引き上げて道夫をその後から昇格させるという目立たない方法を選んだというのがもっぱらの噂であった。
事実、それまでの藤本と中田道夫の昇格のタイミングは、藤本が先ず先行し、少し遅れて中田道夫が上がるというように社内スズメの推測と一致していた。しかし、社長人事ではそうはいかない。藤本を社長にすると中田道夫のチャンスは無くなるかもしれない。だから、リリーフ的に塩川を抜擢したのではないかとの観測が流れた。塩川は大正5年生まれの辰。道夫は昭和3年の辰年で塩川とは丁度一回り違う。
塩川が社長に内定したことにより、後任のプラント事業部長には安井が昇格した。安井は化学部門で長く労務を担当してきた労務屋で、工場の合理化にらつ腕を揮い“人切り安井”と言われていた。
後年、機械部門の営業担当常務に転ずるが、化学部門から機械部門に役員が異動するのは極めて稀な人事であった。
機械の営業には、安井の下に5人の部長がいた。中でも、油圧機械を担当していた志村は、山口工業では異色の人物。竜也の先輩に当たるH大の出身だが、機械工学に明るく、仕事面でも非常に積極的で、戦略的な営業を展開した。
志村は、新製品を売り込むに際して、最初は大手のユーザーを避けて、中小企業へ足繁く通う。これを“末端誘導作戦”と名付けた。その後、中小のユーザーでブランドが認識されてくると、大手企業に突撃をかける。これを“拠点重点作戦”と呼んだ。
拠点重点作戦では、志村自らが乗り込み、客先のトップと直接面談する。この時の事前準備が凄い。志村の自宅には、業界紙や専門誌のスクラップをファイリングする書庫があり、最近2年以内の業界の動向が分野別に整然とファイルされている。この作業には、志村夫人が動員された。
N自動車の川崎社長との面談では、事前に“自動車”のファイルを徹底的に読破し、自動車業界の動向を頭に入れた上で面談に向かう。
普通、初対面の挨拶は、名刺交換した後、当たり障りのない話題で終るのだが、志村の場合は違っていた。冒頭から日本の自動車業界の現状と課題を理路整然とまくし立てる。志村の指摘が正鵠を射るものであるため、N自動車の川崎社長といえども忽ち志村のファンになってしまう。
このようにして、志村は自動車や住宅の分野で業界に顔を売っていった。竜也から見ると、まさにプロの営業マン。何時か志村のようになりたい、と憧れを抱く存在であった。
しかし、日本のサラリーマン社会では、社外では優秀でも社内では評価されるとは限らない。志村の場合も例外ではなかった。
事業部長の藤本専務からは全幅の信頼を得ていたものの、直属の上司である安井常務には徹底的に嫌われた。
安井の感覚では、N自動車の川崎社長のような大物に面談するのは、営業部長の志村では役不足。当然、常務の安井を伴って面談に赴くのがスジであった。ところが、志村は安井には一言の相談もなく単独で出かけて、話をまとめてくる。これでは、安井の存在価値がない。
安井は、志村の社外営業での手腕を認めながらも、決して志村を評価することはなかった。
その年の6月、最初の日曜日に竜也は新社長の塩川から、突然、自宅に国際電話をもらった。簡単な挨拶に続いて、塩川の張りのある声が電話口で響いた。
「キミには御苦労だが、今度はニューヨークに行ってもらいたい。あちらは、中田英雄クンが帰ってから所長は空席になっている。後任はキミしか居ない。これは中田会長のお考えでもある。奥さんとよく相談して1週間以内に返事がほしい。」
中田英雄は中田会長の次男で、ニューヨーク事務所の所長の職にあったが、4月に帰国し石油化学の営業部長をしていた。中田会長は人事問題を決めるときには、長男の道夫ではなく次男の英雄に相談することが多かった。
中田英雄は何度かドイツに出張してきたことがある。最近も、ポリエチレンのジョイント・カバーの商談で訪れた。ジョイント・カバーは大口径のパイプラインに使う防食材料で、竜也はこの売込みにもイタリア人のザネリとともに積極的に活動していた。恐らく、竜也の英語力や仕事振りが中田英雄に認められたのであろう。父親の中田会長にニューヨーク事務所長の後任として竜也を推薦したものと思われる。
竜也は、早速、梢に相談した。梢の返事は一も二もなくYESであった。短大時代に修得し、N社勤務で実践に使ってきた得意の英語が役立つだけではない。梢は中学時代から荒涼たるアメリカの大地に憧れていた。マーガレット・ミッチェルの「風とともに去りぬ」を読んでからは、スカーレット・オハラのイメージを何となく自分の理想像に重ね合わせていた。
梢はいいとして、後は娘たちのことが気がかりだった。長女の恵子は中学3年になっていた。アメリカに連れて行くには学校のことが心配だ。
翌日、竜也はリーと一緒にフィンランドに出張に出かけた。フィンランドは白夜の季節で殆んど夜がなかった。仕事の後も、リーの計らいで湖の小島で2日ほど休養を取ることになった。
リーはアメリカ人だが、生まれたのはウクライナ。小学校時代はフィンランドで過ごした。そのため、ヘルシンキには幼馴染が少なくない。その一人の別荘のコテージを借りた。
驚いたことに、小島全体がリーの友人の所有になっていて、島には1軒の母屋と10軒ほどの小屋が湖の畔に建っている。来客には1人1軒の小屋が割り当てられた。竜也のコテージにはサウナと寝室があり、来客はサウナを楽しんだ後、部屋から、直接、湖に飛び込んで泳げるようになっていた。
竜也とリーはこの島で、2日間、フィッシングやバーベキューをしたり、白夜のボートを楽しんだり、十分リフレッシュすることができた。
竜也がフィンランドから帰ってみると、梢が驚くべき報せをもって待っていた。竜也の留守の間に、本社の塩川新社長から電話があって、「先日の話はなかったことにしてほしい。」と言われたという。梢は先日の話が何のことかよく分かっていたので、背景を聞こうとしたが、塩川はそれだけ言って電話を切ったらしい。
竜也は一体何が起こったのか、見当がつかなかった。会社の人事は辞令を貰うまでは分からないということは十分承知していたが、今回は会社のトップである中田会長と塩川社長が決めた話だ。それが、突然、ひっくり返されるのはとても信じられなかった。
翌日、オフィスに出勤した竜也に機械営業の志村部長から電話があったとき、今回の人事に関係があるな、と竜也は直感した。果たして、志村は前置き抜きに人事の話から切り出した。
「大変だったな。そんな馬鹿な人事はないよな。6年も7年も外に出しておいて、そのまま今度はアメリカなんて、全く迷惑な話だよな。子供さんの学校のこともあるし、奥さんは困っておられただろう。」
竜也が反論する間を与えず、志村は続けた。
「オレが藤本専務に頼んで、あの話は潰したからな。キミの代わりにオレがニューヨークに行くことにするよ。その代わり、プラント事業部・営業第3部長をキミに譲るからな。」
竜也には、漸く、おぼろげながら“馬鹿な人事”の背景が見えてきた。どうやら、今回の人事を覆したのは藤本専務らしい。中田会長に覚えの良い藤本が、7年も外地勤務をした中野クンをそのままアメリカにやるのは、どう考えても人道上無理がある、と中田に直訴したようだ。
そうさせたのは、勿論、志村だろう。ということは、志村にはプラント営業第3部長に就きたくない背景があるに違いない。
新しい本社の組織と新人事を調べて、竜也には事態が更に明確になった。機械部門では、志村は対外的には大きな評価を得たが、社内では上司の安井に嫌われていた。今度、プラント部門に異動することで、漸く、安井のクビキから離れることができると期待したが、そこには、また、安井が居た。
しかも、それだけではなかった。自分の上に、新しくシドニーから帰国することになった中山が来るらしい。中山は志村より7歳年下で、自尊心が滅法強く、荒削りな男である。志村から見れば営業のことは全く分かっていないが、上下関係には極めて厳しい。その中山が取締役・営業本部長として自分の上に来る。さらに、その上には苦手の安井が居る。このような新職場の構図に志村は耐えられないと考えたに違いない。
そこで、懇意の藤本専務を使ってアメリカへの脱出を図ったようだ。
竜也は、凡その事情は理解できたが、果たして自分はどうでるべきか、決心がつかなかった。志村は尊敬する先輩だし、プラントの営業第3部長の椅子も悪くない。竜也の年齢にしては異例の出世かもしれない。今さら自分はアメリカに行きたいと言い出しても波紋を広げるだけだろう。
竜也には、生来、自分の我を通すよりも全体の調和を重んじるところがあった。梢を説得して、日本に帰国するのが自分の選択すべき道だろうと、心が決まった。
数日後、今度は中田英雄から電話があった。
「キミはアメリカ行きを断ったというじゃないか。」
「いえ、断ったわけではなく、本部の方で勝手に筋書きを替えられたのです。」
「子供の教育の関係でアメリカには行きたくないと言った、と聞いているぞ。」
「それは、藤本専務の作り話だと思いますよ。私は、当初、アメリカ行きを受ける積もりでいたのですから・・・」
「詳しいことは知らないが、会長は御立腹だよ。帰ったら、会長に何と説明するかよく考えておいた方がいいぞ。」
そうは言われても、竜也には被害者意識の方が強かった。自分は志村のゴリ押しに身を引いただけだ、と言いたかった。が、それも、また、新たな波紋を広げることになるだろう。
竜也は複雑な気持ちで、プラント営業第3部長のポストを受けることにした。
日本に帰国するとなると、東京の住居も決まっていないし、子供の学校も手配する必要がある。竜也は7月の終わりに一時帰国した。
真夏の東京はドイツ帰りの竜也には厳しかった。東京本社に出社して、先ず、塩川社長に挨拶した。中田会長は幸いにも不在だった。次にプラント部門の安井専務を訪問した。最後に機械部門に行き、志村に挨拶した。
志村は、まるで自分が人助けをしたような口ぶりで、エラの張った顔を竜也に向けた。
「とに角、無茶な人事だったよ。オレと藤本専務で何とか阻止したから良かったよ。」
「そうは言われても、ニューヨークは私にとっても魅力でしたが・・・」
「そんなことをしたら大変だよ。子供さんの学校の問題もあるしな。」
「それは、志村さんが勝手に推測されただけではないですか。私に相談もなく・・・」竜也は言いかけて言葉を呑んだ。
更に、志村は驚くべき提案をしてきた。
「オレも急にアメリカに行くことになったから、まだ何も準備ができていない。先ず、家のことが心配でな。キミは東京での家はどうするんだ。」
「はあ、借上げ社宅をお願いすることになると思いますが・・・」
「良かったらウチの家に入ってくれないか。女房と娘を連れて行くことにしたんで、今の家が空いてしまうんだよ。」
「志村さんの家って、取手のまだ先ですよね。」
「常磐線の沿線は今から開けるんだよ。筑波に学園都市もできるし・・・」
その夜、竜也は強引に志村の家に連れて行かれた。志村は、以前、東久留米の借上げ社宅に居たが、数年前、常磐線の藤代に建売住宅を買って移り住んでいた。住所も茨城県北相馬郡藤代町とあり、通勤時間は片道2時間はかかると思われた。
志村は竜也に軽く夕食を御馳走した後、上野駅から青色の常磐線・取手行きに乗った。この電車は、取手止りで藤代までは行かない。果たして通勤時間を短く見せるためか、藤代からはタクシーを使った。竜也は慎重に時間を測っていたが、1時間半ほどで藤代の志村邸に着いた。
「1時間半なら東京では普通だよ。」
志村は竜也の心配を見透かしたように言った。
志村には奥さんと2人の娘がいる。姉妹はどちらも美人で、姉は見本市会場などのコンパニオン、妹は「無名塾」を卒業して俳優の卵だった。当時、NHKの朝の連ドラ「ハイカラさん」に準主役の津田梅子役で出演していたことが、志村の自慢でもあった。
その夜、竜也は志村家で歓待を受けた。女優の娘さんから飲めないビールの酌を受けて、悪い気分ではなかった。家の中を一部屋ずつ案内された。ついでに、志村自慢のファイリングも見せてもらった。部屋数は2階に3間あり、4人娘が帰ってきても何とかなりそうだった。帰りも遅くなったので、東京のホテルまでタクシーを手配してもらった。
「子供さんが少々汚しても構わないからな。」
帰りがけに、志村は竜也がこの家に決めたのが既定の事実であるような口ぶりで言った。
翌日、竜也は会社の人事部に行き、借上げ社宅の相談をした。
「中野さんところは子供さんが多いので、なかなか適当な家は見つかりませんよ。志村さんがそう仰ってくれるなら、そちらがいいかもしれません。」
人事担当者は家探しが面倒なのか、あっさり志村の提案に賛同した。竜也自身も7月の暑い最中、東京の町を家探しに歩くのが面倒になって、志村の家を借りることに決めた。
結局、今回の人事異動では、配属先の部署から住む家まですべて志村の思い通りに運んでしまったことに竜也は抵抗を感じたが、反面、志村の強引さに舌を巻いて、内心で呟いていた。
「やっぱり、凄い営業マンだよ。志村さんは。」
![]()
「介護日記ーその後」にもどる
![]()
「白い闇」第20章に進む
![]()
トップページへ戻る