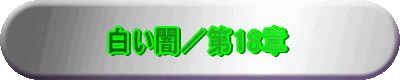
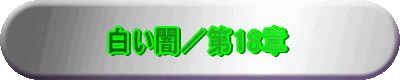
中田は、このことがあってから翌年の株主総会で社長職を副社長の水沼に譲り、自分は会長におさまった。だが、誰の目にも中田が会社の実権を握っていることは明らかだった。
83歳の中田からバトンを受けた後任社長の水沼は、既に80に手が届く年齢で、80代の世代交代に『山口工業は老人天国』とマスコミに揶揄されたこともある。
水沼は中田とは違って、仕事にはそれほど興味はなく、専ら見聞を広めるためにヨーロッパに出張することが多かった。水沼には死ぬまでに達成したい3つの目標があった。
1つは、1900年生れの自分が2001年まで長生きして3世紀にまたがる人生を送ること。2つ目は、中学生のときに見て感動を覚えたハレー彗星を76年後にもう一度この目でみること。そして、3つ目は、究極のエネルギーとされる核融合技術の開発を見届けることであった。
水沼のヨーロッパ出張は毎年4月上旬のタイミングに行なわれた。4月1日の新入社員の入社式で挨拶し、3月末の決算の見通しを立てると、その後に空白の期間ができるからとの理由だったが、実は今ひとつの背景があった。
水沼の誕生日は4月11日で、この日を海外で迎えたいという漠然とした願望があった。社長就任後の初めての海外出張では、80歳の誕生日を中東のドバイで迎えた。この時は、日本商事の計らいでアラビア湾で獲れるタイに似た白身の魚の刺身で誕生を祝った。
81歳の誕生日は、デュッセルドルフの竜也の自宅でパーティーを開いた。この時は妻の梢が大活躍した。
梢の手料理にえらく御満悦の水沼は、揮毫するからといって筆と硯を求めた。梢は、慌てて娘が日本人学校の習字の時間に使っている筆をもってきた。
「こんな筆じゃあ上手く書けるかな。」
水沼は梢の用意した紙にもクレームをつけ、それでも上機嫌で長い文章を書いた。達筆な漢文で、『観草木以養目』という書き出しで始まっていた。説明を聴くと、以下のような内容だった。
『草木を見て目を養い、鳥の鳴き声を聴いて耳を養い、芳草を嗅いで鼻を養い、甘いものや美味しいものを食べて口を養い、時には筆を取って腕を養い、庭を逍遥して脚を養う。これらを節度をもってやることが長生きの秘訣である。』
流石は81歳社長の揮毫だと皆が感心したところで、水沼は竜也に向かって口を開いた。
「ところで、キミはボクの半分になったかな。」
41歳の竜也がそのことを告げると、水沼は目を細めて嬉しそうに言った。
「そうか、そうか。半分を過ぎたか。」
その後、梢の手作りケーキにロウソクを立て、娘たちがピアノを弾いてハッピーバースデーを合唱すると、水沼は更に目を細めて何度もうなずいた。
竜也は、何故か末娘の絵本『花咲じじい』の1ページを連想していた。
4月のドイツの夜は明るい。10時近くでも外の景色が見える。水沼は竜也の家の庭を眺めながら、羨ましそうに言った。
「中野クン、キミは幸せだよ。世の中で一番美しい音は白樺の葉擦れの音と鳥の鳴き声だ。キミはその両方を毎日聞いている。」
竜也は、その時初めて庭の片隅にある木が白樺だったことを思い出した。
竜也のヨーロッパでの仕事は充実していた。仕事と同様、プライベートな面でも竜也は梢と3人の娘、それに生まれたばかりの末娘の悦子を連れて精力的に旅行にでかけた。
一家6人が車で出かけるとなると、梢のVWパサートには乗り切れない。竜也は職権を活かして社有車のベンツ280SEをプライベート旅行に大いに利用した。竜也の感覚では、その程度の公私混同があっても、会社に対しては未だ十分に貸しがあると自負していた。
ベンツでの家族旅行の一番の想い出は、スイスのマッターホルンに出かけたことだろう。
8月の夏休みだったが、スイスの山道は雪が積もっていた。通行止めの標識を無視して、フルカパスという峠に危険を覚悟で入り込んだものの周囲は一面真っ白で何も見えない。しかも、道路は狭く、左には山肌が迫り、右は断崖絶壁で、一つハンドル操作を誤れば忽ち谷底に転落するのは確実だった。
竜也は極端にスピードを落とし、這うようにしてベンツを前進させ、峠を登り始めた。娘どもも後部の席で心配そうに竜也を眺めて、「お父さん、頑張ってね。」というのがやっとだった。
漸く下り坂に来て緑の樹木が見えてきたとき、竜也たちはサバイバルしたことを自覚した。
冒険旅行の末にたどり着いたマッターホルンは雲に隠れて見えなかった。しかし、翌朝再び山に向うと、みるみるうちに霧が晴れ上がり、紺碧の空を背景に真っ白なマッターホルンが目の前に浮かび上がった。
娘たちは思わず歓声をあげた。日本から来たという登山客は、2週間滞在して漸く山の全貌をみることができたと感激していた。幸運にも竜也たちはその勇姿を簡単に目の当たりにしたのだ。しかし、1時間もするとマッターホルンは再び霧に隠れてしまった。
この旅行では、子供たちのたっての希望で、スイスからオーストリーに入ったところにあるマイエンフェルドまで足を伸ばした。言わずと知れた「アルプスの少女ハイジ」の里である。
しかし、現地は何の変哲もない山上の野原で、小さなレストランが1軒あるだけだった。よく見ると、レストランの看板には「Heidi」 という文字が小さく書かれていた。娘たちはハイジやペーターの面影を探そうとしたが何もみつからなかった。
竜也はトルコのハンニバルの墓を思い出した。日本と違って、彼らは自然の景色を観光対象として重んじるが、物語や伝説上の場所にはあまり重きを置かないとみえる。
そういえば、ベルギー・フランダース地方を訪問したときも、地元に人たちにパトラッシュという名犬の話をしても誰も知らなかった。日本人は、自然の景色よりも物語やテーマを大切にしすぎる傾向があるようだ、と竜也は思う。
梢も積極的に動いた。悦子が未だ腹の中に居るとき、予定していた南仏旅行に竜也が社用で行けなくなったことを知ると、幼い娘3人の手を引いて、単身ニース、カンヌを旅行したことがある。
梢はVHSでドイツ語を習得した自信から、何処に出かけてもドイツ語と英語のチャンポン(ジングリッシュ)で話した。イタリアのお巡りさんであれ、パリの街頭絵描きであれ、相手構わず身振り手振りを加えて得意のジングリッシュで意思を伝えた。
ドイツのように自分の意思をはっきりと伝える必要のある国では、梢の積極的社交性は水を得た魚のようだった。竜也は、梢の社交性に救われたことが少なくなかった。
日本からの訪問客があっても、竜也がアテンドするまでもなく、梢に任せておけば愛車のVWパサートを駆って観光案内程度なら問題なく引受けてくれた。
また、梢は和服の着付けが得意だったので、ドイツ人の奥さん連中を家に招待すると、必ず着物を着せてやることにしていた。
帯をきつく締め上げられた御婦人たちは、苦しそうに喘ぎながらも梢の弾く琴の音に聴き入って、生の日本文化に触れたことに御満悦だった。
竜也たちの住む家の近くにクレフェルドという中都市がある。目抜き通りの写真館のウィンドーには、紋付姿の両親の横で赤、青、黄、紫の着物で着飾った4人娘の写真が飾ってあった。
竜也一家が正月に記念写真を撮ったときのものだが、写真店がどうしても飾りたいと、竜也の許可を得てウィンドーに掛けてあった。竜也は気恥ずかしい想いだったが、梢は大自慢で日本からの客をクルマに乗せてクレフェルドの写真館の前に案内することもあった。
近所でも、梢の人気は高く、お祭り好きのドイツ人に盆踊りを教え、日本館から借用した提灯にローソクの火を灯し、子供たちも一緒に盆踊り大会を催すこともあった。
梢と4人の娘は浴衣姿で、輪に加わった。そんな時には、近所の世話役が事前に警察に連絡し、通り全体を通行止めにした。
通りの名前が『ドレスデン通り』だったことから、この催しはドレスドナー・フェストと名付けられ、ドレスデン通りの夏のイベントの一つとなった。
![]()
「介護日記ーその後」にもどる
![]()
「白い闇」第19章に進む
![]()
トップページへ戻る