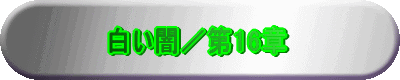
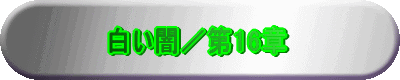
丂丂拞搶偐傜儓乕儘僢僷偵巇帠偺僥儕僩儕乕傪堏偟偨棾栫偼丄栆楏偵巇帠偵懪偪崬傫偩丅
丂晪擟捈屻偺僨儏僢僙儖僪儖僼帠柋強偼丄棤捠傝偺屆偄彫偝側價儖偺係奒偵偁偭偨偑丅偦偙偵偼僄儗儀乕僞乕偺愝旛偡傜側偔丄弌挘幰偑廳偄僗乕僣働乕僗傪帩偭偰奒抜傪搊傞偺偼憐憸埲忋偺廳楯摥偱偁偭偨丅
丂摉帪偺帠柋強偺婡擻偼媄弍忣曬偺傾儞僥僫偺傛偆側傕偺偱丄墷廈偺柺敀偦偆側媄弍傪杮幮偵徯夘偟丄杮幮偑嫽枴傪帵偣偽媄弍採実偺嫶搉偟傪偡傞偲偄偭偨丄暥帤捠傝楢棈帠柋強偱偟偐側偐偭偨丅
丂梻擭丄帠柋強挿偵徃奿偟偨棾栫偼丄愭偢僆僼傿僗傪楢棈帠柋強偐傜價僕僱僗偺嫆揰偵扙旂偡傋偔戝偒側曄妚偵庢傝慻傫偩丅
丂庤巒傔偵丄帠柋強傪挰偺拞怱晹偺婡擻揑側價儖偵堏揮偟偨丅摨帪偵帠柋強奐愝摉弶偐傜20擭嬤偔嬑柋偟偰偄偨擭攝偺僪僀僣恖旈彂傪夝屬偟偨丅
丂斵彈偺柤慜偼儔僀儞僗僴乕僎儞丅擭楊偼60偵嬤偔丄懢偭偨恎懱偵娵偄婄丅壗張偐偍偲偓榖偺杺朄巊偄傪巚傢偣傞戝偒側娽傪傕偭偰偄偨丅帠柋張棟擻椡偼偁傞偑丄巇帠偺傗傝曽偑儅僀儁乕僗偱丄婃屌丅帪偵偼棾栫偺尵偆偙偲偵傕恀偭岦偐傜斀懳偟偨丅
丂20擭慜偼丄弶傔偰晪擟偡傞擔杮恖挀嵼堳偵丄夛幮偱偺僪僀僣岅夛榖偺庤傎偳偒偵巒傑傝丄巹惗妶柺偱偼栶強傊偺揮擖庤懕偒傗揹婥丄悈摴偺奐愝庤懕偒偵帄傞傑偱柺搢傪傒偰偄偨偲偄偆丅傗偑偰丄挀嵼堳偨偪偼儔僀儞僗僴乕僎儞敳偒偱偼壗傕偱偒側偔側傝丄斵彈偼僆僼傿僗偺庡偲偟偰孨椪偟巒傔偨傛偆偩丅
丂斵彈偼屵慜拞偼弌幮偣偢丄屵屻偵傗偭偰偒偰丄棴傑偭偰偄傞僥儗僢僋僗傪懪偮偺偑儊僀儞偺巇帠偩偭偨丅屵慜拞弌幮偟側偄棟桼偼丄偙偺僆僼傿僗偺巇帠検側傜屵屻偩偗偱廫暘偙側偣傞偲偄偆偺偑斵彈偺尵偄暘偩偭偨偑丄幚偼屵慜拞偼懠強偱摥偄偰偄傞傛偆偩偭偨丅
丂夝屬傪怽偟搉偟偨偲偒丄斵彈偼栆慠偲棾栫偵怘偭偰偐偐偭偨丅偙傟傑偱丄擭攝偺強挿傪庤側偯偗偰偒偨偺偵丄偙傫側庒憿側傫偐偵傗傜傟偰偨傑傞偐丄偲偄偆暤埻婥偑偁傝偁傝偲擿偊偨丅嫇嬪偺壥偰偵丄帺暘偑嵨傪庢偭偰偄傞偐傜庒偔偰鉟楉側彈惈偺曽偑偄偄偺偩傠偆偲媰偒弌偡巒枛丅嵟屻偼丄楯摥嵸敾強偵晄摉夝屬傪慽偊傞偲偺嫼偟傕偁偭偨偑丄壗偲偐墌枮戅幮偄偨偩偄偨丅
丂儔僀儞僗僴乕僎儞偺梊尵偑摉偨偭偨偺偐丄戙傢傝偵嵦梡偟偨旈彂偺傾儞僕僃儔偼塸崙恖偱僗僞僀儖偺偄偄旤恖偩偭偨丅
丂傾儞僕僃儔偺嵦梡傪寛傔偨偲偒丄摨椈偺揷曈偑乽偙傝傖偁丄壗偐栤戣傪婲偙偟偦偆偠傖偺偆丅乿偲嶳岥曎偱偮傇傗偄偨偺傪棾栫偼挿偄娫婰壇偟偰偄偨丅
丂棾栫偑強挿偵徃奿偟偨偲偒丄僨儏僢僙儖僪儖僼帠柋強偵偼丄棾栫偺懠偵俁恖偺擔杮恖偑嫃偨丅棾栫偲摨惄偺拞栰丄揷曈丄偦傟偵墶揷偩偑丄墶揷偼僾儔儞僩偺挷払愱擟偱丄僆僼傿僗偺幚嵺偺巇帠偼棾栫丄拞栰丄揷曈偺俁恖偑愗傝惙傝偟偨丅
丂拞栰傕揷曈傕棾栫傛傝俁嵨擭壓偱丄拞栰偼壔妛弌恎丄揷曈偼婡夿弌恎偩偭偨丅椉恖偲傕嶳岥導偺惗傑傟偱丄俁恖偺嫟捠岅偼嶳岥曎偲側偭偨丅
丂摿偵揷曈偼抂惓側梕巔偵帡崌傢偢丄挐傞偲鎍傝偑傂偳偐偭偨丅棾栫偼嶳岥偱俆擭娫惗妶偟偨偺偱嶳岥曎偵偼掞峈偑側偔丄帺傜傕愊嬌揑偵嶳岥鎍傝傪庢傝擖傟偨丅棾栫偺姶妎偐傜偼丄偙偺偙偲偼俁恖偺寢懇傪崅傔傞忋偱嬌傔偰廳梫側億僀儞僩偱偁偭偨丅
丂棾栫偼儓乕儘僢僷偱偺價僕僱僗偼丄擔杮恖偩偗偑搘椡偟偰傕娙扨偵惉岟偟側偄偙偲傪捈姶揑偵屽偭偨偺偱丄愊嬌揑偵儘乕僇儖僗僞僢僼傪嵦梡偟偨丅偟偐偟丄捈愙廬嬈堳偵偡傞偲丄媼椏傕崅偔丄慜偺旈彂偺傛偆偵帿傔偰傕傜偆偺偑戝曄側偺偱丄宊栺儀乕僗偺儕僥乕僫乕偲偟偰嵦梡偟偨丅崱棳偵偄偊偽丄傾僂僩僜乕僔儞僌偱偁傞丅
丂價僕僱僗慡懱偺傾僪僶僀僗偲擄偟偄嬊柺偺僱僑傪扴摉偡傞偺偵傾儊儕僇恖偺傾儗僢僋僗丒儕乕傪屬偭偨丅
丂儕乕偼丄傾儊儕僇偺戝庤壔妛儊乕僇乕偺墷廈夛幮丒幮挿偺宱楌傪傕偮戝暔偱丄壔妛嬈奅偵婄偑峀偐偭偨丅
丂婡夿偺娭學偱偼丄摉弶偐傜帺摦幵夛幮岦偗偺僟僀僇僗僩儅僔儞偺攧崬傒偵揑傪峣偭偰偄偨偺偱丄摨嬈懠幮偐傜僙乕儖僗寭僒乕價僗儅儞偲偟偰丄僪僀僣恖偺儘乕儔儞僪丒儗儀僟傪僗僇僂僩偟偨丅
丂峏偵丄摿掕暘栰偺價僕僱僗愱梡偵丄僀僞儕傾恖偺僷僆儘丒僓僱儕傪嵦梡偟偨丅
丂偙傟偵旈彂偺傾儞僕僃儔傪壛偊傞偲丄暷丄塸丄撈丄埳偲偄偆悽奅偺楍嫮偐傜擔杮恖僗僞僢僼偺彆恖偑抷偣嶲偠偨妴岲偲側偭偨丅
丂摿偵丄儕乕偼丄挿擭偺墷廈偱偺宱尡偵棤懪偪偝傟偨僕僆僌儔僼傿僇儖丒價僕僱僗偲偄偆傕偺傪係恖偺擔杮恖偵愢偄偰暦偐偣偨丅儕乕偵傛傟偽丄堦岥偵儓乕儘僢僷偲偄偭偰傕崙傗抧曽偵傛偭偰恖乆偺峫偊曽偑堎側傞丅抧堟偺摿惈傪峫椂偵擖傟偰價僕僱僗傪揥奐偟偰偄偔昁梫偑偁偭偨丅
丂儕乕偺峫偊曽偼棾栫偵傕戝偒側塭嬁傪梌偊偨丅儕乕偼偳傫側擄偟偄巇帠偱傕丄寛偟偰偁偒傜傔側偄丅揮傫偱傕扅偱偼婲偒側偄偲偙傠偑偁偭偨丅
丂偁傞帪丄墶揷偵棅傑傟偰僪僀僣嵟戝偺壔妛夛幮丒俛俙俽俥幮偐傜峸擖偡傞怗攠偺抣抜傪壓偘偰傕傜偆岎徛偵弌偐偗偨丅
丂僪僀僣恖偼堄枴傕側偔抣抜傪壓偘側偄恖庬偺揟宆偲偄偭偰傕傛偄丅僩儖僐偐傜捈愙僪僀僣偵晪擟偟偨棾栫偵偼丄偙偺揰偑戝偒側僇儖僠儍乕僔儑僢僋偱傕偁偭偨丅
丂拝擟憗乆偵棾栫偼斕懀梡偺幮柤擖傝儃乕儖儁儞傪嬈幰偵敪拲偟偨丅侾杮10儅儖僋偺昳暔傪50杮拲暥偡傞偺偱壙奿傪晧偗偝偣傛偆偲偟偨偙偲偑偁傞丅
丂棾栫偑50杮傑偲傔偰攦偆偺偱丄450儅儖僋偵偟偰傎偟偄偲尵偆偲丄愭曽偼丄偟偘偟偘偲棾栫偺婄傪尒偰丄擔杮恖偼寁嶼偵庛偄偺偱偼側偄偐偲怱攝偦偆側婄傪偟偰摎偊偨傕偺偩丅
乽扷撨偝傫丄侾杮偑10儅儖僋偩偐傜50杮偩偲500儅儖僋偵寛傑偭偰傑偝偀丅巹偳傕偵偼偦傟偩偗偺嵼屔偑側偄偐傜丄550儅儖僋捀懻偟偨偄偱偡側丅乿
丂棾栫偼憡庤偺弌曽偵傛偭偰偼100杮敪拲偡傞偙偲傕摢偵抲偄偰偄偨偑丄偙偺戜帉傪暦偄偰僪僀僣恖偵偼擔杮揑側峫偊曽偼捠梡偟側偄偙偲傪巚偄抦傜偝傟偨丅
丂儖乕僪償傿僢僋僗丒僴乕僼僃儞偺俛俙俽俥杮幮偺彫婏楉側墳愙幒偱丄儕乕偲棾栫偼愭曽偺塩嬈晹挿傪憡庤偵擄偟偄岎徛傪擲傝嫮偔懕偗偰偄偨丅偟傃傟傪愗傜偟偨塩嬈晹挿偑岎徛偺懪偪愗傝傪愰尵偡傞偐偺傛偆偵惡傪峳偘偨丅
乽愭傎偳偐傜尵偭偰偄傞偱偟傚偆丅僂僠偼壗張偺媞愭偵懳偟偰傕摨偠壙奿偱擺擖偡傞丅偍戭偩偗壓偘傟偽懠幮偐傜暥嬪偑弌傑偡丅戞堦丄壓偘傞棟桼傕側偄偺偵偳偆偟偰抣抜傪堷偐側偗傟偽側傜側偄偺偱偡偐丅崱擔偺偲偙傠偼偍堷庢傝婅偄傑偡丅乿
丂儕乕偼丄偍傕傓傠偵億働僢僩偐傜僔僈儕儘傪庢傝弌偟丄崟偄僟儞僸儖偺儔僀僞乕偱備偭偔傝偲壩傪偮偗丄攛偺墱怺偔媧偄崬傫偩墝傪惷偐偵揤堜偵岦偗偰偼偒弌偟偨丅弖娫丄怱抧傛偄崄傝偑幒撪偵昚偭偨丅偦偺崄傝偑敪尵偺崌恾偱偁偭偨偐偺傛偆偵丄挘傝偺偁傞惡偱備偭偔傝偲榖偟巒傔偨丅
乽偁側偨偼塩嬈晹挿偝傫偲偟偰丄棫攈側宱尡傪偍帩偪偺傛偆偩偑丄堦偮尒棊偲偟偰偍傜傟傞偙偲偑偁傞傛偆偱偡丅偦傟偼丄擔杮偲偄偆僇僗僩儅乕偵偮偄偰偺偙偲偱偡丅乿
乽擔杮恖偺峫偊曽偼嬌傔偰夋堦揑偱偡丅儌僲傪攦偆応崌偵偼丄帺暘偺夛幮偑摿偵桪嬾偝傟偰偄傞偐偳偆偐偑敾抐偺億僀儞僩偵側傞丅偁側偨偺傛偆偵懠幮偲摨堦忦審偩偐傜偲偄偆偙偲偱偼擺摼偟側偄偺偱偡丅崱丄変乆偑峸擖偟傛偆偲偟偰偄傞怗攠偼偍戭偺傕偺偑嵟崅偺昳幙偱偁傞偙偲偼廫暘彸抦偟偰偄傑偡丅偩偐傜丄変乆偼挿婜偵傢偨偭偰峸擖偟偨偄偺偱偡丅乿
乽儈僗僞乕丒僫僇僲偼搶嫗偺杮幮偐傜10亾偺抣堷偒傪埶棅偝傟偰崯張偵棃偰偄傞偺偱偡丅崱丄偁側偨偺敪尵傪偦偺傑傑杮幮偵揱偊偨傜丄儈僗僞乕丒僫僇僲偺婄偼傑傞捵傟偲側傞偱偟傚偆丅偦偆側傞偲丄変乆偼懡彮昳幙偑楎偭偰傕懠幮偐傜峸擖偡傞偙偲傪峫偊偞傞傪偊側偄丅乿
乽抣堷偺棟桼偑側偄偲嬄尵傞偑丄抣堷偼桭岲偺徹偟側偺偱偡丅偁側偨偑変乆偲挿婜偺桭岲娭學傪朷傫偱偍傜傟傞側傜丄俆亾偺抣堷偒偵摨堄偝傟傞偙偲傪採埬偟傑偡丅偦傟偱傕丄杮幮偼擺摼偟側偄偱偟傚偆丅偟偐偟丄変乆偼恎懱傪挘偭偰俆亾偺抣堷偒偑嵟戝偺傕偺偱偁傞偲杮幮傪愢摼偡傞偙偲傪栺懇偟傑偡丅儃乕儖偼偁側偨偺僐乕僩偵堏傝傑偟偨丅偁側偨偺寛抐傂偲偮偱丄変乆偺桭岲娭學偑惉棫偟傑偡丅俆亾抣堷偒傪庴偗梕傟傞偐斲偐丅摎偊偼僀僄僗偐僲乕偱偍婅偄偟傑偡丅乿
丂儕乕偼堦婥偵偙偙傑偱挐傞偲丄嵞傃僔僈儕儘傪壛偊丄戝偒偔媧偄崬傫偩丅
丂棾栫偼懅傪偺傫偱憡庤偺尵梩傪懸偭偨丅儕乕偺揻偄偨僔僈儕儘偺墝偺岦偙偆偱丄塩嬈晹挿偼婄傪偟偐傔偰峫偊偰偄傞條巕偩偭偨丅懡暘丄斵帺恎偺拞偱抣堷偒傪惓摉壔偡傞偙偲偵嬯偟傫偱偄傞偺偩傠偆丅
丂儕乕偑師偺堦暈傪妝偟傓偨傔偵僔僈儕儘傪岥偵帩偭偰偄偒偐偗偨偲偒丄塩嬈晹挿偼惷偐偵岥傪奐偄偨丅
丂棳挩側塸岅偱偼側偔丄僪僀僣岅偱億僣儕偲傂偲尵丄乽傾儗僗丒僋儔乕乮傛偔暘偐傝傑偟偨乯丅乿偲偮傇傗偄偨丅
丂偦偺栭丄儕乕偲棾栫偼廽攖傪嫇偘偨偑丄儕乕偺梊崘偟偨捠傝丄杮幮偼俆亾抣堷偒偵偼枮懌偟側偐偭偨丅嵞搙10亾抣堷偒偵挧愴偟偰傎偟偄偲偺僥儗僢僋僗偑撏偄偨丅
丂棾栫偼搶嫗偵揹榖傪偐偗丄偙傟埲忋偺抣堷偒偼扤偑傗偭偰傕柍棟偱偁傞偙丅俆亾偺抣堷偒傕椺奜揑偵擣傔傜傟偨傕偺偱偁傞偙偲傪椡愢偟偨偑丄杮幮偼偦傟偱傕擺摼偟側偐偭偨丅
丂挷払晹挿帺傜偑弌岦偄偰偔傞偺偱丄嵞搙俛俙俽俥幮傪朘栤偟偨偄偲嫮峝偩偭偨丅
乽彑庤偵偟偰壓偝偄丅乿偲棾栫偼揹榖傪偒偭偨偑丄屻擔僨儏僢僙儖僪儖僼偵挷払晹挿偺尨揷偑幚嵺偵尰傢傟偨偺偵偼彮側偐傜偢嬃偄偨丅
丂尨揷偵摨峴傪嫮偔媮傔傜傟偨偑丄棾栫偼庱傪怳偭偰嫅斲偟偨丅儕乕傕乽僨傿僓僗僞儔僗乮柍拑嬯拑偩乯丅乿偲尵偭偰摨峴傪嫅斲偟偨丅
丂巇曽側偔丄尨揷偼墶揷傪楢傟偰俛俙俽俥傪嵞搙朘栤偟偨丅寢壥偼棾栫偺怱攝偟偨捠傝偵側偭偨丅
丂扴摉偺塩嬈晹挿偐傜偟偭傌曉偟傪庴偗偨偺偩丅偁偺帪丄峴偒偑偐傝偐傜俆亾偺抣堷偒偵摨堄偟偨偑丄杮幮偑偦傟傪庴偗側偄偲偄偆偺偼栺懇偑堘偆丅俆亾偺榖傕側偐偭偨偙偲偵偟偨偄偲丄寢嬊丄抣堷偒偼揚夞偝傟偰偟傑偭偨丅
丂墶揷偐傜曬崘傪暦偄偨棾栫偼丄崅偄弌挘椃旓傪偐偗偰僪僀僣傑偱傗偭偰偒偨尨揷偺嬸峴傪旕擄偟偨偑丄摨帪偵僪僀僣恖塩嬈晹挿偺婃屌偝偵偁傞庬偺嫟姶傪妎偊偨丅傑偨丄儕乕偺榖弍偵傕夵傔偰姶暈偝偣傜傟偨丅
丂儕乕偼婡夿偺價僕僱僗偱傕戝偄偵岎徛椡傪敪婗偟偨丅倁倂幮傊偺僟僀僇僗僩儅僔儞偺攧崬傒偵丄棾栫偼儕乕傪婲梡偟偨偺偩丅
丂僟僀僇僗僩儅僔儞偼丄帺摦幵偺僄儞僕儞丒僽儘僢僋側偳偺庡梫晹昳傪惢憿偡傞偺偵昁梫側拻憿婡夿偱丄偙偺儅僔儞傪儓乕儘僢僷偵攧崬傓偙偲偼杮晹偵偲偭偰傕挿擭偺柌偱偁偭偨丅
丂擔杮偺庡梫側帺摦幵夛幮偵偼偡傋偰嵦梡偝傟丄暷崙偺僼僅乕僪幮偵傕戝曄側搘椡偺枛偵攧崬傒偵惉岟偟偨儅僔儞傪丄惀旕儓乕儘僢僷偺帺摦幵墹崙丒僪僀僣偵弌偟偨偄偲偄偆偺偼丄杮晹偩偗偱側偔棾栫傕揷曈傕摨偠婥帩偪偩偭偨丅
丂儓乕儘僢僷偱偼丄僪僀僣惢丄僗僀僗惢丄僀僞儕傾惢偺儅僔儞偑庡棳偱丄偦傟埲奜偺儅僔儞偼慡偔巊傢傟偰偄側偐偭偨丅
丂棾栫偲揷曈偼丄働儖儞偵偁傞僪僀僣丒僼僅乕僪幮傪朘栤偟丄僼僅乕僪偺傾儊儕僇杮幮偑嶳岥岺嬈偺僟僀僇僗僩儅僔儞傪嵦梡偟偨偙偲傪婌乆偲偟偰揱偊偨偙偲偑偁傞丅
丂偟偐偟丄僪僀僣恖偺庡擟媄巘偐傜偼丄
乽傾儊儕僇恖偼僟僀僇僗僩儅僔儞偺巊偄曽傪抦傜側偄丅乿偲椻偨偔偁偟傜傢傟偨丅
乽擄媀偠傖偺偆丅偙偄偮傜偼丅乿摨峴偺揷曈偑彫惡偱愩懪偪偟偨丅
丂儓乕儘僢僷偱偼儊僢僙偲偄偆尒杮巗偱彜攧傪惉棫偝偣傞偙偲偑懡偄丅摿偵丄僨儏僢僙儖僪儖僼偱偼拻憿娭學偺 GIFA 偲偄偆儊僢僙偑俁擭偵侾搙偁傝丄偙偺婜娫偼悽奅拞偐傜拻憿暘栰偺娭學幰偑廤傑傞丅
丂巗撪偺儂僥儖偼偳偙傕枮幒偩偭偨丅偦傟傕偦偺偼偢丄斵傜偼 GIFA 偵棃傞偲丄俁擭愭丄師夞偺 GIFA 婜娫偺儂僥儖傪梊栺偟偰婣傞偺偩丅偩偐傜丄僪僀僣偺儂僥儖偼儊僢僙偲廳側傞偲壗擭傕慜偐傜枮幒偲側偭偰偟傑偆丅
丂 棾栫偼 GIFA 偵儅僔儞傪弌揥偡傞偙偲傪峫偊偨偑丄幚嵺偵儅僔儞傪擔杮偐傜塣傫偱偔傞偲側傞偲壄扨埵偺宱旓偑偐偐傞丅壛偊偰丄傕偟儅僔儞偑攧傟側偗傟偽崅壙側嵼屔傪書偊偰偟傑偆儕僗僋傕偁傞丅嬥傪偐偗偢偵儅僔儞傪俹俼偡傞昁梫偑偁偭偨丅
丂 偁傞擔丄旈彂偺傾儞僕僃儔偑柺敀偄怴暦峀崘傪尒偮偗偨丅僗僀僗偺僶乕僛儖偱奐嵜梊掕偺僟僀僇僗僩儅僔儞尒杮巗偱丄捈慜偵側偭偰40噓偺彫娫偑堦偮僉儍儞僙儖偝傟偨偲偄偆偺偩丅庡嵜幰偼攋奿偺抣抜偱彫娫傪攧傝弌偟偰偄偨丅 奐嵜傑偱俀廡娫偟偐側偐偭偨丅儅僔儞偺愝塩婜娫傪峫偊傞偲丄偲偰傕庁傝庤偼尒晅偐傜側偄偲巚傢傟偨丅
丂棾栫偵偼傾僀僨傾偑慚傔偄偨丅傾儞僕僃儔偵奿埨偱庁傝傞傛偆巜帵傪弌偟丄揷曈偲儕乕偵棾栫偺傾僀僨傾傪榖偟偨丅
丂摉帪偼枹偩價僨僆偲偄偆傕偺偑側偔丄棾栫偼僀僗僞儞僽乕儖挀嵼帪戙偵偼丄16噊塮幨婡偱媞愭偵儅僔儞傪 PR 偟偰偄偨偑丄偦偺16mm僼傿儖儉偑巆偭偰偄傞丅偦傟傪棙梡偟傛偆偲偄偆偺偩丅
丂僟僀僇僗僩儅僔儞偺 PR僼傿儖儉偼側偐側偐傛偔弌棃偰偄偰丄30暘懌傜偢偺忋塮帪娫偺拞偱丄嬥宆岎姺偑帺摦壔偝傟偰偄傞條巕偑忋庤偔徯夘偝傟偰偄偨丅
丂僪僀僣偱偼嬥宆岎姺偵俈乣俉帪娫傕偐偗偰偄傞偑丄PR僼傿儖儉偱偼15暘偱弌棃傞偲徯夘偝傟偰偄偨丅偙偺嬥宆帺摦岎姺偑僪僀僣恖偵戝偒側僀儞僷僋僩傪梌偊傞偺偱偼側偄偐丄偲棾栫偼峫偊偨偺偩丅
丂偦偺栭丄拞栰偲墶揷傕壛偊丄係恖偱壗搙傕孞傝曉偟16噊僼傿儖儉傪塮幨偟偰傒偨丅俁恖偼丄壗偲側偔峴偗偦偆側暤埻婥傪姶偠偨丅
丂偩偑丄旂擏壆偺拞栰偩偗偼丄忕択傑偠傝偵椻傗傗偐偵抐掕偟偨丅
乽擔杮偺傾僯儊傪棳偟偨曽偑恖偼廤傑傞偠傖傠偆傛丅乿
丂棾栫偺崋椷堦壓丄弌揥偺弨旛偑巒傑偭偨丅僾儗僛儞僞乕偲偟偰偼傾儞僕僃儔傪婲梡丄斵彈偺枺椡偵埶懚偡傞偙偲偵偟偨丅
丂傾儞僕僃儔偼帺暘偺栶妱傪暦偔偲戝婌傃偟偨丅16噊僼傿儖儉傪壗搙傕尒偰丄撪梕偼慡偔棟夝偱偒側偄偑丄媄弍揑側戜帉傪娵埫婰偟偰偟傑偭偨丅
丂尒杮巗偺巒傑傞俁擔慜偵丄棾栫丄揷曈丄傾儞僕僃儔偺俁恖偑僶乕僛儖偵岦偐偭偨丅儀儞僣280俽俤偵塮幨婡傗惢昳僒儞僾儖傪戝検偵愊傒崬傫偱丄揷曈偺塣揮偱幵偼傾僂僩僶乕儞俁崋慄傪堦楬撿偵岦偐偭偨丅
丂偙偺摴楬偼儓乕儘僢僷僴僀僂僃乕俤35偵崌棳偟丄僶乕僛儖偲偺娫傪600噏懌傜偢偱寢傫偱偄傞丅
丂幵撪偼傾儞僕僃儔偺堖憰偑懡偔丄屻傠偺惾偼杦偳嵗傞僗儁乕僗偑側偐偭偨偑丄棾栫偼僶僢僌傪墴偟傗偭偰慟偔嵗傞応強傪妋曐偟偨丅
丂傾儞僕僃儔偼彆庤惾偱偼偟傖偄偱偄偨丅
丂揷曈偼丄乽僂儖僒僀両乿偲偄偆戙傢傝偵儀儞僣偺傾僋僙儖傪摜傒崬傫偩丅傒傞傒傞丄僗僺乕僪儊乕僞乕偼200噏傪挻偊丄恓偑傎傏悈暯偵側偭偨丅240噏嬤偄丅棳愇偵傾儞僕僃儔偼柍岥偵側傝丄怱攝偦偆偵奜偺宨怓傪尒偰偄偨丅
丂係帪娫懌傜偢偱僗僀僗偺僶乕僛儖偵拝偄偨丅偦偺栭偼儂僥儖偵攽傑傝丄梻挬俁恖偼尒杮巗夛応偵弌偐偗偨丅
丂拲暥偟偨彫娫偵峴偔偲丄學姱偑嬱偗偮偗偰丄偍戭偺婡夿偑摓拝偟偰偄側偄丅懠幮偼杦偳愝抲傪廔偊偰偄傞偺偵崱偐傜偱偼娫偵崌傢側偄丄偲岥妏朅傪偲偽偟偰僋儗乕儉傪偮偗偨丅
丂傾儞僕僃儔偑偵偭偙傝徫偭偰丄乽僂僠偼僷僱儖偱埻傫偱傕傜偊偽偄偄偩偗傛丅乿偲墳偠傞偲丄學姱偼僉儑僩儞偲偟偨婄偮偒偵側偭偨丅
丂尒杮巗夛応偱偼丄懠幮偼僨儌婡傪愝抲偟偰丄幚嵺偵儅僔儞傪嬻塣揮偟偰傒偣傞偺偩偑丄棾栫偨偪偺彫娫偼堦晽曄傢偭偰偄偨丅
丂僷僱儖偱埻傫偩偩偗偺丄偵傢偐嶌傝偺彫寑応丅偦傟傕丄傾儞僕僃儔偑怓乆偲岺晇偟偰抝惈偑廤傑傝偦偆側忺傝晅偗傪巤偟偨丅
丂撪晹偵偼丄30媟傎偳偺堉巕偲戝偒側僗僋儕乕儞偑偁傞偩偗偩偭偨丅偟偐偟丄廃埻偵偼幚嵺偵拻憿偟偨昳暔偺僒儞僾儖傪婔偮偐暲傋偨丅偦傟傜偑側偗傟偽丄壥偨偟偰壗偺尒杮巗側偺偐尒摉傕偮偐側偐偭偨丅
丂奐嵜偺慜擔偵偼丄拞栰偲墶揷偑儕乕傪敽偭偰傗偭偰偒偨丅憤摦堳偱嵟屻偺巇忋偘偵偐偐偭偨偑丄梉怘傑偱偵偼廔傢傜側偐偭偨丅
丂憗偔價乕儖傪堸傒偵峴偙偆偲桿偆儕乕傪捛偄弌偟偰丄擔杮恖係恖偲傾儞僕僃儔偱嶌嬈傪懕偗偨丅搑拞丄儕乕偑嵎偟擖傟偨僒儞僪僀僢僠傪偐偠傝側偑傜丄摉擔偺枹柧傑偱偐偐偭偰慟偔忺傝晅偗傪廔偊偨丅
丂奐嵜摉擔偺挬丄俇恖慡堳偑嬞挘偟偨昞忣偱摿愝塮夋娰偵廤傑偭偨丅
丂壥偨偟偰丄偙傫側偲偙傠偵棃偰偔傟傞偩傠偆偐丄棾栫傕撪怱怱攝偩偭偨丅
丂儕乕偩偗偼丄乽僀僢僣丒僴乕丒僕儑僽丅乿偲傾儞僕僃儔傪巜嵎偟偰丄怱攝側偄偲尵偆丅
丂帠幚丄夛応偑僆乕僾儞偡傞偲丄傾儞僕僃儔偺媞堷偒偑岟傪憈偟偨偺偐丄摿愝塮夋娰偼崥偪戝擖傝枮堳偲側偭偨丅拞偵偼丄傕偆堦搙忋塮傪傒偨偄偲惾傪摦偐側偄楢拞傕偄偨丅
丂侾擔10夞掱搙忋塮偟偨偑丄壗帪傕枮堳偵側偭偨丅嫞崌愭偺懠幮偺彫娫偐傜傕揋忬帇嶡偵壗恖偐偑擿偒偵偒偰偄偨丅
丂俀働擔栚偺挬丄棾栫偼妴暆偺傛偄僪僀僣恖偐傜柺夛傪媮傔傜傟偨丅柤巋傪傒傞偲丄倁倂丒僇僢僙儖岺応挿偲側偭偰偄傞丅倁倂偺僇僢僙儖岺応偲偄偊偽丄儓乕儘僢僷嵟戝偺拻憿岺応偩丅棾栫偼婌傫偱榖傪挳偔偙偲偵偟偨丅
丂岺応挿偺儈儏僢働巵偼塸岅偑杦偳挐傟偢丄棾栫偼敿暘儕乕偵捠栿偟偰傕傜偭偨丅
丂偦傟偵傛傞偲丄儈儏僢働巵偺埶棅偼丄偙偺僼傿儖儉傪僇僢僙儖岺応偺媄弍幰偨偪偺慜偱忋塮偟偰栣偊側偄偐偲偄偆丅棾栫偼擇偮曉帠偱俷俲偟偨丅壗婥側偟偵悅傟偨娖偵戝暔偺嫑偺摉偨傝傪姶偠偨丅
丂俁擔娫偺摿愝塮夋娰偱偺忋塮偼戝惉岟偩偭偨丅1,000恖嬤偄棃朘幰偑偁偭偨姩掕偩丅杦偳偑戝庤帺摦幵夛幮偺楢拞偱丄倁倂埲奜偵傕俛俵倂傗儖僲乕幮偐傜傕擬怱側幙栤偑婑偣傜傟偨丅
丂崱夞偺庡栶偼傾儞僕僃儔偩偭偨丅棾栫偼夵傔偰傾儞僕僃儔傪嵦梡偟偨偙偲偵帺怣傪怺傔偨丅
丂僶乕僛儖嵟屻偺栭偼丄儕乕偺傾儗儞僕偱懪偪忋偘偺戝僷乕僥傿乕偲側偭偨丅偙偺僷乕僥傿乕偱傕傾儞僕僃儔偑庡栶偩偭偨丅寢嬊丄崱夞偺尒杮巗偱偼偙偺僷乕僥傿乕旓梡偑嵟戝偺宱旓偲側偭偨丅
丂侾廡娫屻丄棾栫偼儕乕偲俀恖偱倁倂偺僇僢僙儖岺応偵偱偐偗偨丅
丂倁倂偺杮幮偼丄傕偆彮偟杒偺僂僅儖僼僗僽儖僌偵偁傞偑丄偙偺僇僢僙儖偺拻憿岺応偺寶暔偼杮幮埲忋偵埿梕傪曻偭偰偄偨丅
丂嫄戝側楖姠憿傝偺墶挿偺價儖偼丄惓柺偐傜尒傞偲椉抂偑帇栰偵擖傜側偄丅嫲傜偔丄侾噏偼偁傞偩傠偆偐丅棾栫偵偼嫄戝側孯娡偺傛偆偵尒偊偨丅
丂尯娭偵偼丄儈儏僢働岺応挿偑弌寎偊偰偔傟丄棾栫偲儕乕偼嫵幒偺傛偆側晹壆偵捠偝傟偨丅憢偵偼崟偄僇乕僥儞偑妡偗傜傟丄塮幨偺弨旛偑偱偒偰偄偨丅
丂棾栫偼丄憗懍丄僶乕僛儖偱梡偄偨16噊僼傿儖儉偺忋塮傪僗僞乕僩偝偣偨丅
丂40恖傎偳偺僄儞僕僯傾偨偪偑丄偪傚偆偳惗搆偑庼嬈傪挳偔傛偆側僗僞僀儖偱塮夋傪尒偨丅摿偵丄嬥宆偑帺摦岎姺偝傟傞晹暘偼壗搙傕孞傝曉偡傛偆梫惪偑偁偭偨丅
丂忋塮偑廔傢傞偲丄慡堳偐傜偨傔懅偑塳傟偨丅
丂僇僢僙儖岺応偱偼丄僟僀僇僗僩儅僔儞偺嬥宆岎姺偵俉帪娫傕偐偗偰偄傞偲偺偙偲偩偭偨丅偦傟偑15暘偱偱偒傞偲僼傿儖儉偱偼愢柧偟偰偄傞丅
乽壖偵丄30暘偐偐偭偨偲偟偰傕乿偲丄儈儏僢働巵偑慡堳傪戙昞偟偰姶憐傪弎傋偨丅
乽偙偺儅僔儞偼僇僢僙儖岺応偺擻棪岦忋偵惀旕偲傕昁梫偩丅捈偖偵尒愊彂傪峸攦晹埗偵採弌偟偰傎偟偄丅乿
丂1250僩儞偺墷廈岦偗侾崋婡偺彜択偑寛傑傞傑偱偵帪娫偼偐偐傜側偄丄偲棾栫偼恎懱偺墱偐傜偙傒忋偘偰偔傞嫽暠傪梷偊傞偺偵昁巰偩偭偨丅
丂僨儏僢僙儖僪儖僼偵栠偭偨棾栫偼丄憗懍杮晹偵儗億乕僩傪彂偄偨丅庴拲偑妋幚偱偁傞偙偲傪嫮挷偡傞偨傔偵憓奊傪昤偄偨丅
丂悈偺拞偵戝偒側僞儌栐偑昤偐傟偰偄偰丄偦偺捈偖忋傪戝嫑偑塲偄偱偄傞丅僞儌傪忋偘傟偽丄妋幚偵嫑傪偲傞偙偲偑偱偒傞丅偙偺憓奊偼杮晹偱戝昡敾偵側偭偨丅
丂媄弍杮晹挿偺愳忋偼丄倁倂偑儅僔儞傪攦偆偲偼怣偠傜傟側偐偭偨丅僼僅乕僪岦偗偵侾崋婡傪攧崬傓偨傔偵丄愳忋偼11夞傕僨傿傾儃儞偺僼僅乕僪杮幮偵弌挘偟偨偺偩偭偨丅杮晹偐傜扤傕弌岦偄偰偄側偄偺偵丄挀嵼堳偑庤帩偪偺 PR 僼傿儖儉偩偗偱丄倁倂偺傛偆側戝嫑傪掁傝忋偘傞偲偼丄愳忋偺忢幆偱偼峫偊傜傟側偐偭偨丅
敪拲偵嵺偟偰倁倂偑嵟傕婥偵偟偨偺偼傾僼僞乕僒乕價僗丅妋偐偵丄墦偄擔杮偐傜傗偭偰偒偨儅僔儞偑屘忈偟偨偲偒偵偼廋棟偺曽朄偑側偄丅擔杮偐傜恖傪屇傇偩偗偱俀擔偼偐偐傞丅偦偺娫偼惗嶻傪拞巭偟側偗傟偽側傜側偄丅
倁倂偺梫媮偵墳偊傞偨傔偵丄棾栫偼嫞崌愭偺僀僞儕傾偺俬俹幮偐傜僪僀僣恖偺僗儁僔儍儕僗僩傪僗僇僂僩偟偨丅偦傟偑儗儀僟偩偭偨丅
儗儀僟偼僔儏僣僢僩僈儖僩偵嫃傪峔偊偰偄偨偑丄帺壠梡偺僙僗僫婡傪傕偭偰偄偨丅
偙傟偩偲丄僇僢僙儖傑偱偼俀帪娫偱摓拝偱偒傞丅儗儀僟偵嶳岥岺嬈偺儅僔儞傪曌嫮偝偣傟偽丄倁倂偺傾僼僞乕僒乕價僗偺梫媮偵墳偊傞偙偲偑偱偒傞丅棾栫偼12帪娫埲撪偺僒乕價僗傪儈儏僢働岺応挿偵栺懇偟偨丅偙傟偑丄倁倂岦偗僟僀僇僗僩儅僔儞侾崋婡惉栺偺寛傔庤偵側偭偨丅
丂
擔杮惢偺婡夿傪奜崙偵斕攧偡傞偲偒丄嵟戝偺栤戣偼儅僔儞偺儊儞僥僫儞僗偵偁傞丅棾栫偼丄偙偺偙偲傪埲慜偺墴弌偟僾儗僗斕攧偺宱尡傪捠偠偰廫暘偵巚偄抦傜偝傟偰偄偨丅
侾擭慜丄僀僞儕傾偺僆儖僫僑偵偁傞傾儖僉儍儞幮岦偗偵杦偳惉栺傑偱憜偓偮偗偨彜択傪嵟屻偺搚抎応偱丄僀僞儕傾偺抧尦儊乕僇乕偵扗傢傟偨嬯偄宱尡偑偁傞丅
偦偺帪丄傾儖僉儍儞墷廈偺媄弍愑擟幰偱偁傞塸崙恆巑偺儀僱僢僩巵偼丄戝偒偔乽僨傿僗僞儞僗乿偲塸岅偱庤彂偒偟偨巻傪棾栫偵帵偟偨丅
偮傑傝丄擔杮偲墷廈娫偺嫍棧偺強堊偱嵟屻偺寛抐偑偱偒側偐偭偨丄偲儀僱僢僩巵偼棾栫偵揱偊偨偺偩丅
墦偔棧傟偨擔杮偐傜偺婡夿偱偼丄偳偆偟偰傕屭媞偼傾僼僞乕僒乕價僗偵晄埨傪姶偠傞丅僒乕價僗偺廳梫惈偵偮偄偰偼丄屻偵棾栫偑傾儊儕僇嬑柋偲側偭偨偲偒偵傕丄嵟弶偵夝寛偡傋偒廳梫壽戣偲偟偰庢傝忋偘傞偙偲偵側傞丅
![]()
乽夘岇擔婰乕偦偺屻乿偵傕偳傞
![]()
乽敀偄埮乿戞17復偵恑傓
![]()
僩僢僾儁乕僕傊栠傞