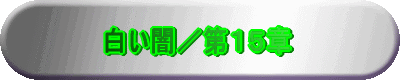
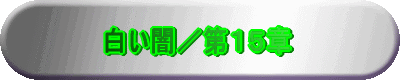
翌年の8月、竜也は梢と3人の娘を連れてデュッセルドルフに赴任した。
梢は初めての海外生活にいささか興奮気味だったが、それでも事前にドイツ語の即席学習を済ませたらしく、着任したときは竜也よりも上手にドイツ語を喋った。
竜也は梢の希望もあって、日本人が多く住んでいる地区を避け、町外れのメアブッシュ第3区に家を借りることにした。周囲には殆ど日本人は居らず、ドイツ人たちの真っ只中に敢えて居を構えた。
梢は、早速、近所のVHS(フォルクス・ホッホ・シューレ)という成人学校でドイツ語の学習に取りかかった。竜也は、当面トルコが勤務地なのでドイツ語の必要もなく、むしろ独学でトルコ語に磨きをかけた。
デュッセルドルフには立派な日本人学校があり、上の娘2人はそこに入れた。3女の亜希子は現地のドイツ人幼稚園に通うことになった。
そこでは、日本人園児は初めてということで、登園の初日に亜希子のために盛大な歓迎パーティーを開いてくれた。竜也は梢とともに亜紀子に付き添った。
亜希子は浴衣に下駄履きというスタイルで、カラン・コロンと音を立てて無邪気に木の床を駆け回り、梢は勇敢にもドイツ人の奥さんたちに身振り手振りで話しかけていた。
竜也はドイツ語がさっぱり理解できずに、自分が場違いなところに居る焦りを感じながら腕時計ばかりみて時間の経つのが遅いことに苛立っていた。精々、写真を撮るくらいが自分の存在価値を周囲に理解させる唯一の仕事だった。
後に、アルバム整理をしていて、竜也は亜希子の幼稚園の写真がやけに多いのに苦笑したことを覚えている。
イスタンブール勤務の竜也は、トルコ中心に中近東で仕事をして、月末にデュッセルドルフに帰るという通い夫の生活が始まった。
イスタンブール駐在員として、竜也の毎日は多忙だった。テリトリーはトルコだけでなく、中近東をカバーすることになっていたので、隣国のイラン、イラク、ギリシャは勿論のこと、アラビア半島や北アフリカの各地まで足を伸ばした。
これらの諸国は、ギリシャを除いて殆どがイスラム教の国だったので、竜也はイスラム思想の根底にある独善性を嫌というほど経験することになった。
地元のイスタンブールでは、ある時、日本人の感覚からはどうにも理解し難い事件に遭遇した。
ワンマン駐在員の竜也は、イスタンブールのホテルに事務所兼宿舎の部屋を借りていたが、その日は久し振りにヤリムジャを訪問し、タクシーでホテルに帰る途中の出来事である。
トルコのタクシーは、当時はメーターというものがなく、すべて事前の交渉で料金を決めていた。これはトルコに限らず、当時の中東諸国では極めて一般的であった。だから、目的地までの距離と料金の相場を知らなければ、雲助運転手に高くふっかけられても仕方ない。
竜也は、最初から自慢のトルコ語で料金を値切ったので、トルコ人の相場とほぼ同じ料金でタクシーを利用していた。
その日の運転手とも、ヤリムジャからイスタンブールのホテルまで約100㎞を500リラ(当時で約1万円)で契約した。
おんぼろのシボレーは見た目より快調に走り、1時間余りでボスポラス海峡の吊り橋にさしかかった。
この橋は長さ1100m余りあって、当時世界で11番目に長い橋として2年前に完成した。コントラクターはオーストリアのフェースト社だが、当初は日本の IH 社の受注が最有力であった。円借款も準備されていたが、最終的な入札でフェースト社が1番札を取った。竜也たちのラクタムプラントは、この IH 社敗退で宙に浮いた円借款を使って成約した経緯がある。
余談だが、このボスポラス橋に1ヶ月遅れて、日本の関門大橋が完成した。その完成祈念のパンフレットには世界で11番目の橋と印刷されたが、ボスポラス橋が先に完成したため、11の上からゴム印で12番目と訂正された。竜也は、後日、下関でこの訂正印を見たとき、日本人の几帳面さが表れているようで微笑ましく感じた。
竜也は、おんぼろタクシーの窓から、ぼんやりとボスポラス海峡の雄大な景色を見下ろしていた。
突然、鋭いブレーキ音とともに車が大きく右に傾き、竜也は激しい衝撃を感じた。瞬間、橋から落ちると直感した。しかし、車は橋の欄干に激突して停まった。昔のアメリカ車はボディだけは頑丈にできているので助かった。
運転手が何か叫んだ。「大丈夫か」と訊いていると思い、竜也が身体を起こそうとしたとき、運転手は運転席のドアを開けて外に出るや、車道を走り出した。
竜也は、一瞬爆発するのかと身を伏せたが、次第に状況が分ってきた。おんぼろタクシーの右前の車輪が走行中に突然外れたのだ。だから、車はバランスを失って欄干に激突した。で、運転手の方は、外れた車輪を拾いに走ったらしい。
日本のタクシーなら、どんな運転手でも先ず乗客の安否を気遣ったに違いない。しかし、このトルコの運転手は、は乗客の安否より車輪の確保を優先したのだった。
竜也は次第に腹が立ってきた。何という運チャンだ。炎天下、額から汗をたらしながら車輪を抱えて車に帰ってきた運転手を怒鳴りつけた。しかし、件の運チャンには一向に悪びれた風はない。御免なさいのひと言もないのだ。逆に、口角泡をとばして竜也のことを非難している。
何故、自分が悪いのか。悪いのはお前だろう、と竜也は断固抗議して料金を払わないと決めた。
ところが、運チャンの台詞は竜也を唖然とさせた。
「この車のタイヤは手に入らない。もう少しでタイヤを失くすところだった。車の方も前部を壊してしまって修理に大変な金がかかる。アンタを乗せていなければこんなことにはならなかった。車の修理費の一部をアンタに負担してもらいたい。だから、2,000リラ払ってほしい。」
「お前との約束は500リラでイスタンブールのホテルまで行くことだ。お前はその約束を破ったのだ。だから、料金は払わない。」
竜也の執拗な抗議に対して、運チャンは顎を上げで舌を小さくチッと鳴らした。
この仕草は、トルコ人特有のもので相手のいうことを拒絶するジェスチャーだ。運チャンは、再び彼のロジックを繰り返した。
「この事故はアンタを乗せたから起こったのだ。アンタの所為で、オレは今日大変な損をしたのだ。」
「冗談じゃない。タクシーの義務は客を目的地まで運ぶことにあるのだ。途中で義務を放棄しておいて金をよこせというのは間違っている。警察を呼ぼう。」
ボスポラス橋の上での押し問答は暫く続いた。通り過ぎる車の何台かは、速度を落として日本人らしき乗客とタクシー運転手の激論を珍しそうに見物していった。
やがて、運転手側が折れた。1,000リラにまけるという。竜也にはどう考えても契約料金の倍も払うだけの根拠が見付からなかった。
今度は、竜也が顎を上げて舌打ちする番だった。最後は500リラで手を打った。一時は本気で警察を呼んでもらおうかとも思ったが、ポリスが運転手の味方をしないとう保証はない。500リラを払って次のタクシーを拾うべく、走ってくる車の群れに向かって手を挙げた。
トルコは未だよかった。アラブの国々では、もっと理解を超える事件が頻繁に起こった。
イラクのバスラ空港での事件は、竜也が被害者ではなかったが、更に生々しかった。
アラブ諸国の航空会社では、オーバーブックは日常茶飯事で、フライトの確認を取っていても席のないことがある。
こんなときは、エキストラの金を払うと席を呉れるのだが、この日も、竜也はバスラからバグダッドに向かうイラク航空にエキストラ料金を払って席を確保した。
国内便には指定席はない。前方の席は込み合うので、竜也はできるだけ後方の窓側の席を確保した。通路側では、折角席を確保しても訳のわからない理由で立ち退きを要求される危険があるからだ。
その日も機内は満席だった。全部のシートが乗客で埋まっているのに、飛行機は出発する気配がない。前方には未だ数人の乗客が立っていた。彼らには席がないのだ。
すると、彼らのうちの1人がパーサーに耳もとで何か囁いた。明らかに取引しているのだ。やがて、パーサーが乗客の航空券をチェックするとアナウンスした。
竜也は窓側の席で救われたと感じた。見渡したところ、数人の外国人が居るが、彼らは全員窓側の席にいるようだ。
通路側には白装束のアラブ人たちか居た。パーサーは何人かのアラブ人たちを通路側の席から退去させた。航空券をチェックして何か屁理屈をつけているようだ。意外にも、退去を要求されたアラブ人たちは大人しく飛行機から降りていった。
更に、パーサーが後方に進んできて竜也の横で立ち止まった。竜也は窓の外を眺めながら、言葉が分からない振りをしていた。実際に、パーサーは殆ど英語を喋らなかったので、竜也には何を言っているのかは理解できなかった。
竜也の隣では、大きなズダ袋を持って乗り込んできたアラブ人が航空券のチェックを受けた。パーサーが大声のアラブ語で何か叫んだ。ズダ袋の白装束が必至に抵抗している。
竜也はその様子を盗み見ていたが、ズダ袋が動いているように見えた。
パーサーが強権を発動して白装束の襟首を掴んで引きずり下ろそうとした。
その途端、袋の口がゆるんで、中から、何と! ニワトリが飛び出したのだ。ニワトリはけたたましい声をあげ、羽をばたつかせて機内を飛んだ。白い羽毛がパッと舞い上がった。
ニワトリを捕まえようと立ち上がった白装束はそのまま退去させられ、代わりに前方にいた別の白装束が座った。
竜也の隣人だった男はニワトリを片手にすごすごと機外に去った。羽毛だけが竜也の膝の上一面に残った。飛行機は何事もなかったように、定刻1時間遅れでバスラを飛び立った。
竜也には、このパーサーの挙動もボスポラスの運転手の発想も同根のように思えた。要するに、他人の事情は全く無視して、自分のことしか考えないのだ。
竜也の仕事は思いのほか順調に進んだ。
イランではアルミ精錬会社向けに天井クレーンの大型商談をまとめた。また、ペイカンという自動車会社向けのダイカストマシンの商談にも参加した。
山口工業の本社では、その年に、新しくプラント事業部を発足させたが、竜也はトルコで中型のプラント案件を2件まとめた。更に、プラント事業部の最初の大型成約となったアラブ首長国連邦向けのセメントプラント商談にも参加した。
当時のプラント事業部長の塩川専務は、プラント事業部はイスタンブールに駐在員を置いていると発表した。竜也の本籍は知らぬ間に機械事業部からプラント事業部に移されていたようだ。
1978年、恒常的なインフレと輸出の不振からトルコの外貨保有高は底をつき、遂に対外債務の支払い不能を意味するモラトリアムを宣言することになった。
一国が対外債務を支払えなくなると、債権国がパリに集まってその国の債務の支払いを繰り延べするための協議を始める。これをパリ倶楽部によるリスケジューリングと呼ぶが、業界では簡単にリスケと呼んでいた。
モラトリアム宣言後、トルコもリスケ国の仲間入りをしたが、こうなると当時の通産省の保険課では輸出代金保険を認めず、トルコでいくら商談が成立しても支払いが保証されない。
竜也はイスタンブールの事務所を閉鎖し、デュッセルドルフに引揚げてきた。同時に、竜也の通い夫の生活にも終止符が打たれた。
また、この年に第4女の悦子がデュッセルドルフで出生し、竜也は妻の梢と4人娘に囲まれた新しい生活をドイツで始めることになった。
![]()
「介護日記ーその後」にもどる
![]()
「白い闇」第16章に進む
![]()
トップページへ戻る