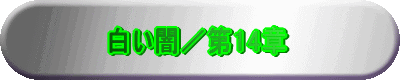
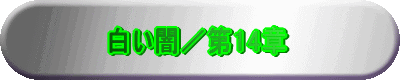
メインイベントの竣工式が成功裡に終了し、ラクタムプラントの運転が安定してくると、竜也にはサイトでの仕事が殆どなくなった。ギュルセルも現地事務所から本部の建物に移っていった。
竜也は、この機会に以前担当した押出しプレスをトルコに売込むことを考えた。早速、トルコ人の運転手を雇い、毎日、アルミ工場を探して歩いた。
イスタンブールの一郭にカラキョイと呼ばれる地区がある。日本でいえば戦後の闇市のようなところで、鉄やアルミ製品の小規模の卸問屋が集中していた。
カラキョイにある、間口一間ほどの小さな店の2階に竜也は居た。埃だらけの通りは、人と車、さらにはロバの引く荷車でごった返していた。車はどれもスクラップ寸前のオンボロばかり。けたたましくクラクションを鳴らして、通行人を追い散らしている。
車と車の僅かな隙間を縫うようにして、金属製の丸いお盆を手に下げた少年が走り回っている。少年はお茶売りで、お盆にはお茶の入った小さなグラスがたくさん載っている。トルコ・コーヒーのカップも幾つか見える。車の向こうでは、鋼材を積んだ荷車を薄汚れたロバが排気ガスに顔をそむけながらノロノロと引いている。
「コーヒー、紅茶、どちらにする。」
デミルサッシと書かれた看板の卸問屋の主人、メーメット・ガジオールが竜也に問う。
「コーヒーをお願いします。サーデ(砂糖なし)を。」
竜也が答えると、メーメットは窓から通りの方に身を乗り出して、指を口に当て、ピーッと鳴らす。すると、通りの向こうにいた少年が振り返る。メーメットが手でひしゃくから水を注ぐような仕草をする。これで、コーヒーの注文が成立するのだ。
直ぐに、車の列をかき分けて、少年が店の階段を登ってきた。少年は代金を受け取ると、、デミタスカップに入ったコーヒーを傷だらけのデスクに置いた。
「ところで、押出しプレスだが、1800㌧の設備を買えば、月にどのくらいのサッシを生産できるのかね。」
「それは、生産するサッシのタイプによって大きく変わります。通常の住宅用サッシで百㌧前後ではないでしょうか。」
「そんなにできるのかね。それで、設備一式の値段はどのくらいするの。」
「付帯設備によって、これも大きく変わりますが、標準の設備でプレス本体が大体70万ドル程度です。」
「70万ドル? 単位が違うんじゃないかね。7万ドルならキャッシュで買うよ。」
「我々のプレスは世界でも一級品です。トルコ製の機械と較べてもらっては困ります。70万ドルから1割程度なら何とかなりますが、それ以上は無理です。」
「分かった。明日、見積書と図面を持って自宅の方へ来てくれないか。関係者を集めておくから。」
翌日、メーメットは真っ白のベンツの新車で竜也のホテルに迎えに来た。昨日、カラキョイの店の前に停めてあったトルコ製のムラットとは大違いだ。服装も、白の上下に銀色のネクタイを締めている。昨日は、確かジーパンにTシャツだったはずだ。
トルコの国民所得は低いが、一握りの富裕層は大変な金持ちで、通常、スイスに外貨預金をもっている。住宅も、イスタンブールのヨーロッパ側に日本流にいうマンションをもち、アジア側に一戸建てのサマーハウスを所有している。だから、イスタンブールの上流階級の間では、5月に入ると、「お宅では何時からサマーハウスに移られるのですか。」というのが時候の挨拶となる。
この日、メーメットが案内したのも海辺に立つ彼のサマーハウスだった。瀟洒な門をくぐるとアメリカ映画のスクリーンから抜け出たような金髪の女性が竜也を出迎えた。妻のインジェだと紹介された。
竜也が通された部屋は、窓一杯に海の広がる30畳もあろうかと思えるリビング。中央に螺鈿細工の施されたロココ調の大テーブルがあった。椅子もすべてロココ調の高級品で、壁にはトルコ磁器の一流品であるスメルバンク製の大皿がバランスよくかけてある。
昨日カラキョイの闇市で訪れた、屋根の落ちそうなデミルサッシの事務所とからは、とても想像できない豪華な暮らしぶりに、竜也は思わずため息をついてしまった。
竜也の疑問をすばやく感じとったのか、メーメットが説明した。
「我々は会社では1リラの金も節約するが、プライベートではできる限りエンジョイするのだよ。」
「それにしても立派なお宅ですね。それに奥様もまるでアメリカ映画のスターのようですね。」
竜也はお世辞ではなく感じたままをいったのだが、メーメットは夫人にわざわざ通訳した。夫人は顔を赤らめて、竜也にドイツ語で話しかけた。
「ドイツ語はお喋りになるのかしら。」
「少しは喋りますが、トルコ語の方がベターです。」
竜也は持てる知識を総動員してドイツ語で答えた。
トルコ語を喋るときいて、夫人は一気にトルコ語でまくしたてたが、竜也には半分も理解できなかった。
ほどなく、プロジェクトの関係者の3人が現れた。全員メーメットの弟だった。末弟のユスフは未だ丸坊主の高校生だ。メーメットの説明によると、彼等は何をするにも兄弟4人が話し合って決めるのだという。
チャイ(紅茶)とサクランボがテーブルに運ばれ、いよいよ会議が始まった。冒頭に、メーメットが兄弟を代表して趣旨説明をした。
「我々は、鋼材の卸売りで成功して金を作った。次にアルミサッシに進出したいと計画している。トルコには大手のサッシメーカーはなく、中小のメーカーが5社ほどある。彼らは殆どがトルコ製のプレスを使っていて生産効率は極めて悪い。
我々は、最新の日本製プレスを導入してトルコのトップメーカーになりたいと思っている。」
途中で一息いれると、テーブルからチャイのグラスを取り上げ、一口、口に含むと、グラスを置いて口ひげに手をやった。
「だが、我々には技術のバックグラウンドがない。貴社が技術と設備を供給してくれれば、我々はトルコのトップメーカーになることができる。貴殿は我々の計画に協力してくれる意志があるか。もしあれば、貴殿を我々の5番目のブラザーとして尊敬したい。」
冒頭から大袈裟な趣旨説明に竜也は少し面食らった。だが、押出しプレスを売る目的は達成できそうだと直感して、喜んで兄弟に加えてもらうと答えた。途端に、他の3人の兄弟から握手と頬擦りの挨拶を頂戴し、嫌々ながらそれに応じた。
トルコ人は親しみの表現として頬擦りをするのが一般的で、竜也は最初は抵抗があったが、次第に慣れていった。
このことがあってから、実に半年の間、技術資料の提出や生産性の説明、更にはオペレーターの訓練方法まで、根掘り葉掘りの質問攻めに遭い、おまけに値段の方も執拗な値下げ要求を受けた。
商談がまとまったときには、当初70万ドルだったはずのプレスは、仕様変更に次ぐ変更で、30万ドルまで値切られていた。それも、ブレトンウッズ体制崩壊のタイミングで、1ドル360円が308円に大幅な円切り上げの最中に漸く決まったのである。
山口工業の本部では、竜也の活躍振りが話題になっていた。期待していなかった中東向け押出しプレスの1号機が決まったことが大きく評価された。矢張り、客先密着型の営業が功を奏するのだという結論になった。
ヤリムジャのラクタムプラントの仕事は殆ど終わっていた。しかし、押出しプレスの受注が影響したのか、竜也には1年間イスタンブールに留まって機械の商売をするよう指令が来た。
そうなると、竜也は日本に残した梢と3人の娘のことが流石に気がかりになった。そこで、竜也は一計を案じて、人事担当の佐伯に手紙を書いた。佐伯は既に専務に昇格していた。
『佐伯専務殿。憶えておられるでしょうか。私は専務殿に2度裏切られました。』という書き出しで、妻と3人の娘が心配であること、イスタンブールは日本人学校もなく子供の教育には不向きであること、トルコとドイツは非常に近い関係にありドイツに家族をおいて自分はイスタンブールに単身赴任できること、月に1度はドイツへの出張を認めてほしいこと、等々を誠心誠意書き連ね、最後に、
『今度こそ、3度目の正直で私の希望が叶うことを念じてやみません。』と締めくくった。
1ヵ月後、竜也は前例にないタイトルの辞令を受け取った。
【デュッセルドルフ駐在員事務所付きイスタンブール駐在員を命ス】
竜也は、山口工業に入社して初めて自分の思惑どおりに人事が実現したことに、内心で快哉を叫んだ。入試以来憧れであったヨーロッパ駐在員の椅子を射とめたのだ。
![]()
「介護日記ーその後」にもどる
![]()
「白い闇」第15章に進む
![]()
トップページへ戻る