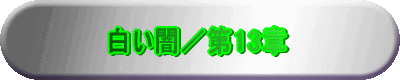
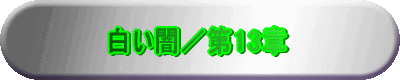
1976年1月、竜也は単身でトルコのプラントサイトに向かった。期間は1年という約束だったが、結果からすると、帰国したのは8年後であった。
プラントサイトは、イスタンブールから南へ100㎞ほど下った、イズミット郊外のヤリムジャという村だった。この地は、元々サクランボ畑だったところへ国営の石油化学公社であるペトキム社が国策として小規模の石油化学コンビナートを建設。ラクタムプラントは、そのコンビナートの一部として新設されることになっていた。
隣村のキラズリヤールと並んでヤリムジャはトルコでは有数のサクランボの産地。大きく甘い果肉はとても新鮮だった。サクランボはトルコ語でキラーズというが、隣村のキラズリヤールは、その名の通り「サクランボ村」であった。
石油化学コンビナートは、既に世界的に大型化の時代に入っていて、代表的なポリエチレンでは商業規模は最低でも年産5万トンといわれていたが、ヤリムジャ工場のポリエチレンは1万トンという規模の小さなもの。完成してもコスト競争力がないのは誰の目にも明らかだった。
案の定、ペトキム社は創業当初から赤字を余儀なくされ、幹部の1人は、「ペトキム社の最大の失敗はこの土地でサクランボの生産をしなかったことだ。」と嘆いた。
トルコのサクランボについて、後日、竜也はあるドイツ人のユーモアに接することになるのだが、これは秀逸のジョークとして竜也には忘れがたい。
ドイツ/クルップ本社のエッセンで、同社の営業部長と昼食をともにした時のこと。デザートに出された小さなサクランボの粒を見て、竜也は思わず自慢した。
「ドイツの果物はすべてが小振りだけど、トルコのサクランボはこんなに大きいよ。」
竜也は右手の親指と人差し指で輪を作ってみせた。相手の営業部長は、しげしげと竜也の作った指の輪を覗き込んで、おもむろに断定した。
「ハハァ、その大きさのものは、ドイツではリンゴと呼ばれているよ。」
プラントの建設現場での竜也の仕事は、大きく3つに分けられた。
1つは、対客先との折衝。プラント建設中に発生したペンディング事項をすべて議事録に残しておき、客先との定期会合で協議することになっていた。
議事録の作成について、従来のやり方は客先が作成した議事録の原案を日本側でチェックして必要な修正をした後にサインするのだが、竜也は議事録の原案をすべて自分で作成した。その方が、自社に不利なことを省略し、有利なことを強調することができるからだ。
トルコ側の現地の渉外担当はギュルセル・イルドゥリムという女性だった。
ギュルセルと最初に出会ったとき、竜也は胸のときめきを憶えた。素晴らしい美人だった。年齢は竜也より3歳下。トルコ人は欧米人に較べて小柄だが、ギュルセルはトルコ人の中でも背の低い方で、小柄な竜也と並んでもバランスが取れた。
浅黒い肌が美しく、切れ長の目と高い鼻が面長な顔に理想的に配置されていた。低音の声がまた素晴らしかった。アンカラにある中近東大学の化学科を卒業し、アメリカに留学経験をもつギュルセルはアメリカ人よりも美しい英語を喋った。
事実、彼女が一気に喋ると、美しいイントネーションに聞き惚れ、魅力的な表情の変化に見惚れて、話の内容を全く理解していないこともあった。
日本人技術者やスイスから来た技師たちは、彼女をミセス・イルドゥリム、と苗字で呼んでいたが、竜也は、彼女のファーストネームに親しみを表す「ハネム」という接尾語をつけて、ギュルセル・ハネムと呼んだ。
ギュルセルには、頭の禿げた亭主と2人の子供がいた。彼女の家は工場に付随した社宅の1軒だが、欧米の規格に合わせて建てられた社宅は日本のウサギ小屋とは比較にならず、広いリビングに海岸に突き出たテラスが隣接していた。
竜也は何度か自宅に招待されたが、夏の夕べ、テラスでの食事は優雅そのものだった。ワイングラスを片手にもち、少し鼻にかかった低音で綺麗な英語を喋るギュルセルの背中には、水平線に没しようとする赤く大きな太陽が、最後の輝きで海面を照らす。
ダーク・ブラウンの髪が夕陽に浮かび上がり、物憂げな表情のギュルセルがゆっくりとグラスのワインを揺らす。竜也はまるでクレオパトラと話しているような気分になった。
竜也の第2の仕事は、日本人技術者たちのお世話だった。現地に派遣されている技術者は、スーパーバイザー(略称SV)と呼ばれ、1人・1日当たり300ドル(当時の換算レートで約10万円)の対価を貰って、建設指導に当たる。この対価は、アブセンス・フィーとして、直接、山口工業に送金される。それとは別に、現地手当てとして1日数千円のトルコリラが支払われたが、これは、全額、SVを代表して竜也が現金で受け取ることになっていた。
SVは、日本から滞在費としてドルを持ってきているので、そのドルを現地通貨に交換するのも竜也の仕事となる。この滞在費の管理がなかなか面倒だった。
当時、中近東諸国はどこでも、外貨の交換には公定レートと闇レートがあり、闇レートが2割程度ドル高となっていた。トルコでも同様で、竜也はこのレート差を利用して、SVに公定レートでトルコリラを支払い、集めたドルを闇レートでトルコリラに交換した。こうした作業を繰り返すと、現地通貨は確実に増えていく。だが、日本には増えた部分を報告できないので、これをSVたちの厚生費に当て、休日に、ソフトボール大会をやったり、バスを借り切って近くに観光に出かけたりした。
トルコは観光資源に恵まれていて、オリエントの歴史を少し勉強すると、日本人には涎の出そうな名所旧跡が無数にある。
トルコの西海岸にはギリシャ時代の遺跡が数多く残っている。ヤリムジャに近いイズニックという町は、ギリシャ時代にはニコメディアと呼ばれ、宗教会議のメッカであった。
キリスト教が普及し始めた頃、父と子と聖霊という3つの神が存在し、その内容をめぐって多くの議論がなされたが、最後はニコメディア(ニケーア)の宗教会議で、3者は同じものだとする三位一体説が成立したのである。
また、ヤリムジャから車で30分ばかり北に行くと、ゲブゼという小さな町がある。
マルマラ海に面した高台の美しい町だが、偶々訪問した先で、竜也は興味あるものを見つけた。紺碧の海を眼下に見下ろす小高い丘に、杉の木が大きく円を描くよう並んで立っている。円の中は何の変哲もない牧草地だが、中央に半分土に埋もれた石碑のようなものが見える。
此処に来る入口のところに、何かの案内のような小さな看板があったのを思い出し、引き返して半分倒れかかった看板に近づいてみた。看板の文字はペンキが剥がれて消えかかっていたが「アンニヴァル・・・」と、どうにか読めた。
地元の人に確かめると、何と此処がカルタゴの英雄ハンニバルの墓だという。歴史書によれば、山から象に乗ってローマを攻め、名将スキピオの軍を襲撃し見事にこれを破ったカルタゴの英雄の末路は悲しい。フェニキアの地に追われて、山の上から身を投げたとある。
だとすれば、このゲブゼの丘がハンニバルの最後の地ということだろう。
竜也は、暫くの間、杉木立の円の周囲を歩き、岸壁に近づいて、はるか眼下のマルマラの海を見下ろした。3000年前、此処に立ったハンニバルは、恐らく無念と絶望に打ちひしがれて、この海を眺めたのであろう。そこには、当時と同じ岸壁に打ち寄せ、砕け散る波の姿があった。
また、ある時は、バスと船を使い、マルマラ海の先端にあるチャナカレーの町に出かけた。
町の外れにトゥルバと呼ばれる場所があり、これはギリシャ語ではトロイのことで、大きな木馬に兵士を隠して敵を撃退したことで知られている。
遺跡の方は、ドイツ人の考古学者シュリーマンが発掘し、目ぼしいものはすべてドイツに持ち帰ったので、何も残っていない。ただ、不器用なトルコの大工さんが作ったと思われる粗末な巨大木馬が不自然に置かれている。
子供の工作としか思えない木馬の顔は所在なげに観光客を見下ろしていた。
ハンニバルの墓にしても、トロイの遺跡にしても、観光地という雰囲気がまるでない。
日本なら、時代の背景が丁寧に説明され、近くには、ハンニバル饅頭とか、トロイ・クッキーの店が並ぶところだが、トルコの観光資源は無造作に放り出されている。このことは、有名なエフェスの遺跡を訪問したときにも感じた。
エフェスは、遺跡の規模といい、神殿の大きさといい、アテネのパルテノンを凌駕するものがあるが、監視員は誰も居ない。観光客が石のかけらを拾い上げてもとがめられることはない。パルテノンでは、石の柱を触っただけで監視員が飛んできて注意するところだ。が、トルコでは監視員を置くだけの余裕がないのか、遺跡の価値を高く評価していないのか、恐らくその両方からだろうが、観光客が遺跡に触れることも、石のかけらを拾うことも全く自由であった。但し、帰国時には空港でチェックがあり、万一遺跡の一部でも持ち出そうとするのが見付かると、相当ひどい罰則を受けると、竜也は聞いたことがある。
イスタンブールのグランドバザールは有名だが、トルコ語では此処を「カッパル・チャルシィ」(覆われた市場)と呼ぶ。英語ではこれを直訳してカバード・バザールとしている。
此処には、4000軒もの小さな店が並び、大勢の人でごった返していて、まるで上野のアメ横を大きくした感じだ。
この店の1軒で、竜也は金メダルの製作を頼んだ。
ラクタムプラントの竣工式のときに関係者に配る記念品で、竜也たちが自分でデザインした5㎝大の14金製のメダルだ。トルコと日本の国旗を交差させ、竣工を祝う簡単な言葉を英語で刻んだメダルだが、下絵の制作に当たった藤川は真剣に取組んだ。藤川は、その後、若くして病死したので、これが彼を偲ぶ記念メダルともなった。
インフレ率の高いトルコでは金は貯金代わりで、とても喜ばれる。200個のメダルを値切りに値切って発注したが、それでも200万円近くかかった。SVには実費として5000円相当で販売したが、客先にはお土産として配った。この費用もすべて両替の差益から捻出することができた。
竜也の第3の仕事は、日本で船積みされた貨物をデリンジェ港で受入れ、通関の立会いと員数チェックすることだった。しかし、とてもそこまでは手が回らず、実務は取扱商社である日本商事の派遣員に一任した。
主要貨物は7船に分けて出荷されたが、その中の1船、ユーゴ船籍のオパティヤ号がインド洋上で火災を起こし、積荷の電気品や計装品はすべて焼失してしまった。
積荷には保険がかけられていたが、運悪くオイルショックで物価が3倍に跳ね上がった時期と重なったため、保険求償しても尚且つ前回の2倍の費用をかけて同じものを調達せざるをえなかった。
この請求書を客先のペトキム社に回したことで、猛反発を喰らった。偶々、オパティヤ号には高価な部品が多く積まれており、再調達品の総額は20億円を超える金額となった。一方、保険会社から受け取る全損保険金は8億円程度しかなく、差額の12億円を客先に請求したためである。
交渉の過程で、あるトルコ政府の高官は声を荒げて怒り出した。
「山口工業という会社は何とエゲツナイ会社だ。トルコ人の月給に相当する金額をSVが1日でふんだくり、今度は船に火をつけて、倍の金額を責任のない我々から騙し取ろうというのか。」
確かに、トルコ側からすれば、身に覚えのない請求書だろう。
かといって、FOB契約の趣旨からすると船積みされた貨物の責任は売主にはない。至難と思われた交渉が比較的簡単にまとまった裏には、ギュルセルの冷静な分析と社内説得に向けての頑張りがあった。
竜也は、この点でもギュルセルの協力に頭の下がる思いであった。
1976年の夏、ラクタムプラントは竣工式を迎えた。山口工業の本社からは、機械事業部長の浅田専務が出席した。
トルコ側の主賓は通産大臣だった。両の拳を振り上げ、聴衆に訴えかける、堂々たる演説は、マイクを通して快晴のヤリムジャの空に響き渡った。トルコ語の中身は、流石に竜也の理解を超えていたが、ギュルセルの通訳で大体のところは把握できた。
トルコ語と日本語は同じアルタイ語系の言語だが、抑揚に乏しく、演説には不向きな日本語に較べて、トルコ語の方は何故これほど迫力があるのか、竜也は不思議に感じた。
日本側の主賓は、後に航空機疑惑で国会喚問を受けることになる、日本商事の副社長・海野五郎だった。
海野は殆ど原稿を見ずに英語で格調の高い祝辞を述べた。
実は、海野の祝辞には裏話がある。竣工式の前日、日本商事と山口工業が合同で、客先の要人を多数招待して、ペトキム社のゲストハウスで前夜祭のパーティーを開いた。
この席では、先ず、山口工業の浅田専務が日本語でスピーチし、竜也が英語に通訳した。日本語の原稿自体は竜也が準備したが、それには竜也なりの工夫が加えてあった。
こうした席でのスピーチは、通常、日本語の美辞麗句が並べられて、英語に翻訳しにくいものだが、竜也は先ず英語で原稿を書き、それをもとに日本語原稿を作成した。だから、英語に通訳すると、流れの良い美しい響きのスピーチとなった。
しかも、竜也は中身を諳んじていたので、原稿を見ることなく聴衆に向って訴えるように話しかけた。浅田のスピーチが終わると、大きな拍手が響いた。
次は、海野の順番だが、海野は明らかに焦っていた。カラオケで、自分の前の人が玄人はだしに歌うと、次が歌いにくいのと同じ心境だ。
パーティーが終わると、案の定、日本商事の責任者を呼びつけて、海野の脂ぎった口元から怒声が響いた。
「明日の原稿は俺が作る。」という海野のダミ声がはっきりと聞こえた。
翌朝、浅田と海野が同じデーブルで朝食を取っているのを見て、竜也は近くの席に座った。
海野は、浅田に昨夜のパーティーのことを話し、通訳をした竜也のことを訊いているようだった。浅田は竜也にも聞こえるように言った。
「海野さんはよその会社からスカウトするのがお好きのようだが、あの男は出しませんよ。」
浅田は言い終わると、竜也に手を振って自分たちのテーブルに招いた。
竜也にとっては、海野のような有名人と親しく話ができるのは光栄であった。
このことがあったからかどうか、竣工式本番のスピーチを海野は原稿を見ずに上手に話した。相当の時間をかけて練習したのだろうと、竜也は勝手に想像した。
竣工式が終わり、浅田はイスタンブールから帰国の途についた。ヤリムジャからイスタンブール空港に行く途中、竜也は浅田をハンニバルの墓に案内し、ボスポラス海峡の奥にあるリゾート海岸・タラビヤに連れて行った。
海岸沿いに魚のレストランが軒を並べていて、炭火焼の新鮮な魚はとても美味しかった。竜也は鞄から醤油を取り出して浅田に勧めた。浅田は明らかに竜也のアテンドに満足していた。
山口工業のように従業員が1万人を超える大きな会社では、竜也クラスの入社10年そこそこの平社員が会社のトップと接するチャンスは殆どない。海外での1対1のアテンドが、自分の売込みには絶好の機会であることを竜也は十分理解していた。
浅田をイスタンブール空港で見送って、竜也は自分が大きな仕事をやってのけたことを誇らしく感じていた。
![]()
「介護日記ーその後」にもどる
![]()
「白い闇」第14章に進む
![]()
トップページへ戻る