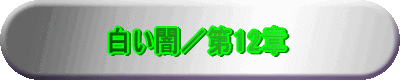
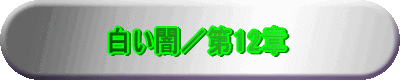
竜也は入社2年目の3月9日に、神戸で梢との結婚式をあげた。
梢の誕生日は3月8日。1日の違いで26歳になってしまった梢は、25歳までに結婚できなかったことを真剣に嘆いた。
新婚旅行は、神戸港から船で九州に渡り、九州の主だったところを周った。九州最南端の指宿では、新婚記念植樹として熱帯植物のワシントニアの苗木を2人で植えた。梢は新調の黄色いコートの裾が土まみれになるのも構わず鍬を振るった。
苗木が立派に成長したら2人で見に来ようと、梢が提案した。竜也は軽い気持ちで頷いたが、まさか35年後に実際にこの地を訪れることになるとは、その時は想像もしなかった。
1週間の新婚旅行から、2人はそのままU市に入った。新居は炭住と呼ばれる炭鉱住宅の空き家があてがわれた。
山口工業は竜也が入社する昭和41年まで海底炭鉱を一部操業していた。新入社員教育の一環で、竜也はゲートル巻に地下足袋、頭にはライト付きのヘルメットという炭鉱夫姿で坑内に入ったことがある。
驚いたことに、海底にエレベーターで降りてみると、そこには複線のレールが敷かれていた。U市から国東半島に向けて5㎞程の海底トンネルを構内電車で走る。電車を降りると徒歩で“切り羽”と呼ばれる炭層まで歩いた。海の底というよりも洞窟の中を歩くようだった。海水の重量を支えるために至るところに大きな門型の坑木が設置されていた。貴重な体験だったが、地上に上がったときは、流石に安堵した。
炭鉱が次々に閉山され、鉱夫たちの住宅も空き家になっていった。その空き家の中でも、程度のよい一軒をスイートホームとして提供されたのだ。
梢は珍しそうに家の中を見て廻った。特に、五右衛門風呂には関心を示し、ゲス板と呼ばれる円形の板を風呂釜に装着する方法について何度も竜也に質問した。
炭住の新居を梢は大した抵抗もなく受けいれた。それでも、竜也が独身寮を案内し、カーテンを開けて東洋のレマン湖を見せたときには、狭くてもこちらの方がいいと駄々をこねた。
竜也と梢は新居をできるだけ快適にするために、一室を洋風に改造した。畳にベージュの絨毯を敷き、壁と襖が隠れるように天井から黄色いカーテンをかけただけだが、そこに赤い布張りの小型応接セットを置くと、立派な客間ができあがった。
この客間が自慢で友人や近隣を次々に招いた。神戸から来た若奥さんは、忽ち炭住の人気者になった。
だが、楽しかった炭住での新婚生活は長くは続かなかった。
翌年、竜也は東京本社への転勤辞令を受けたのだ。梢は、この時最初の子を身ごもっていたので、東京に出るのを怖がった。が、竜也は嬉しかった。東京には無限の可能性が秘められていた。
東京への転居は惨めだった。出産を間近に控えた梢は神戸の実家に帰り、竜也ひとりが引越しに立ち会った。
東京郊外の国立にある借上げ社宅は、文字通りウサギ小屋。炭住にあった家財道具はとても納まりきらず、運送会社もあきらめて大半の梱包を道端に置き去りにしたまま帰ってしまった。
隣の松原さんも山口工業の社員で、奥さんが片付けを親身になって手伝ってくれた。しかし、最後には、荷物が多すぎますわ、とギブアップ宣言され、1人残された竜也は途方にくれた。
その夜は寝る場所もなく、竜也は押入れの空間に潜りこんで寝た。翌日、大家さんに不要不急の家財を処分してもらうことにして、何とか納まりをつけた。赤い応接セットだけは捨てる気にはなれず、無理して2階の片隅に押し込んだが、竜也の勉強机や梢の三面鏡は、残念ながら救出できずに涙を飲んだ。
東京での職場は機械営業輸出課というところで、山口工業の産業機械を海外に売込む仕事だった。だが、海外に売れるような製品は少なかった。主力製品の多くが技術提携品で、販売権は日本国内しかなかったからだ。
竜也は、入社1年後に研修テーマの一環として職場の問題点を作文にまとめて提出していた。『機械事業部の問題点』と題する、大学ノート1冊にまとめられた論文には、オリジナル製品がないことや見積価格の積算がずさんであることなどが、実例とともに詳細に検討されていた。この論文は、問題点を鋭く指摘したものだったが、上司の部長止まりで人事部には回らなかった。
係長の説明では、非常によく書けているが、だからこそ人事部には回せないということだった。竜也としては、この論文を佐伯重役に読んでもらい、希望の職場に就けなかった竜也が機械事業部をフレッシュな眼で見直す努力をしていることを知って欲しかった。それだけに、折角の論文が途中でもみ消されてしまうことに軽い憤りさえ覚えた。
オリジナル製品が少ない中で、唯一海外で売れている機械製品が押出しプレスであった。
押出しプレスは、加熱したアルミや銅を、ダイスと呼ぶ金型からトコロテン式に押出すことによって、金型の断面と同じ形状のプロファイル(型材)を生産する機械。主として、ビルや住宅の窓枠・アルミサッシの製造に使われる。
山口工業の押出しプレスの特長は、機械全体の構造が堅固で、押出し速度を制御する油圧コントロールが優れていることにあった。
この押出しプレスも、元はといえばアメリカのL社からの技術導入だった。が、技術提携直後にL社が倒産したため、自社開発を余儀なくされ、今ではオリジナル製品として業界では評判が良かった。
竜也の初仕事は、台湾向けの1250㌧アルミ用押出しプレスで、当初は1億円近くで見積提出したものが、厳しいネゴの結果、受注したときには5000万円を切っていた。こんな大幅な値引きが許されるのかと驚いたが、係長の末村は「注文とらにゃ赤字も出んわ。」と澄まし顔だった。
中国向けの押出しプレスでは、強烈なクレームを経験した。当時、中国は文化大革命の最中で、毛沢東語録という赤い小さな本が中国側のバイブルとなっていた。
毛思想によると、「完全なる全体は完全なる個から成る」とされていて、機械製品についてもこの思想が適用された。
中国側は、港に到着した押出しプレスをその場で解体し、個々の部品を検査したのだ。その結果、100項目を超える個々の部品の欠陥と称するものがリストにまとめられた。中には、分解されたモーターの巻線やローターの錆を指摘する項目も含まれていた。
1台の押出しプレスは数千点の部品から出来ていて、これらの部品を1品ずつ検査するということは、常識では考えられなかった。一般家庭を例にとるなら、一流メーカーの電気洗濯機を購入して、配達されたとたんに、バラバラに分解して部品をチェックするようなものだ。
このクレームの解決には1年以上を要した。竜也の仕事は現地に派遣された技術者との連絡担当だった。当時、中国との連絡手段は、電話とテレックスしかなく、図面や技術資料を伝えるには写真電報に頼るしかなかった。ところが、写真電報は大手町にあるKDD本社でなければ送信できない。竜也は、連日、夜中近くにKDD本社に行くのが日課となった。
時には、日本側の技術部隊の対応が不十分で、竜也は自分で技術調査を引き受けた。中国側から提案された“斜角探傷”という検査方法に本部の技術陣も知見がない。専門家が集まる、日本非破壊検査協会の202小委員会に竜也自身が出席して、この技術の詳細を調査したこともあった。
竜也は押出しプレスのビジネスを通じて多くを学んだ。特に、海外向けビジネスには、現地に派遣されたピッチャーの球を国内でちゃんと受け止めてやるキャッチャーの役割が如何に重要か身を持って体験した。
また、日本の商社とも積極的に付き合った。S商事の連中とも仕事をしたが、正直なところ、商社に入らなくて良かったと思った。機械のビジネスに関していえば、完全にメーカー主導で、商社はヘルパーに過ぎなかった。商社マンはメーカーの御機嫌をとりながら自社に商売をつけてもらうことに懸命で、竜也のような若造でも一流商社の部課長を相手に恩着せがましい話を堂々と展開することができた。
輸出課での仕事に必要な外国語はロシア語ではなく、英語だった。竜也は英語も得意だったが、近年はロシア語に力を入れすぎて英語の学習を怠っていた。輸出課に配属となってから竜也は猛然と英語の勉強をした。
会社への行き帰りの時間を有効利用するため、電車の中でも歩きながらでも、頭の中で一度日本語の文章を作り、それを英語にする訓練を繰り返した。
語学の学習は、才能という要素も少しはあるだろうが、大半の部分はその学習に費やした時間の総和で決まる、と竜也は考えていた。だから、往復3時間近い通勤時間は語学学習に集中できる、理想的な時間帯であった。竜也は会社から派遣されて、英会話セミナーにも出席した。
竜也が最も残念に思ったのは、貿易大学への派遣であった。貿易大学は企業戦士を1年間富士の裾野に集めて、英語と貿易実務を徹底して訓練する日本には珍しい実務教育機関で、1970年に発足した。竜也は貿易大学の第1期生に山口工業からただ1人選ばれた。いや、選ばれたと思った。
ある日、営業部長の森田が竜也の机の傍に来て、話があるという。別室で森田の話を聴いてみると、竜也を貿易大学の第1期生に推薦するので、1年間単身でやれるか、奥さんと相談しほしいという。相談するも何も、願ってもないチャンスで、竜也は梢に話す前からこの話を受けることに決めていた。梢に話したときも梢は反対しなかった。子育ては私に任せて頂戴と胸を張った。
翌朝、早速森田に決心のほどを伝えたところ、森田も大いに喜んでくれた。
ところが、3日後に森田が神妙な顔で竜也のところに来て、あの話はなかったことにしてくれ、と詫びた。トップの裁量で話がひっくり返ったという。
竜也は、既に人事担当の常務に昇格していた佐伯の狡猾な顔つきを思い浮かべた。ラクタム営業に続いてまたしても佐伯に一杯食わされたと思った。人事というものは、内定したといっても、辞令を貰うまで、信用できないことを再度思い知らされたのだ。
そのことが、逆に、反骨精神を掻き立てたのか、竜也の英語学習に拍車がかかった。お陰で、2年後には竜也は社内でも5本の指に入るほどの英語の使い手として認識されるようになった。
東京に出て3年目に、トルコ向け大型商談がまとまった。カプロラクタムプラントの成約である。
これは、1件の商談で72億円という破格の規模で、所謂プラント輸出のはしりであった。商談の内容は、山口工業が自社で生産しているラクタムと同じものをトルコで作るために必要な設備1式を設計し、機器を調達し、トルコ現地で工場を建設するというもので、EPC契約(Engineering, Procurement and Construction Contract)と呼ばれていた。
会社始まって以来の大型商談に、社内にプロジェクトチームが組織された。トルコラクタムプラント部(略称TL部)と称するチームがU市の機械工場の事務所に置かれた。
竜也はこのチームのアドミ(事務まとめ役)の任を受けて、再びU市に戻ることになった。
1973年、竜也がU市に再赴任したときには、梢との間に2人の娘をもうけていた。U市での新居は2DKのアパートだったが、75年に3女が誕生し、どうにも手狭になった。
3姉妹の誕生に喜んだ梢の実家からは、立派なお雛様のセットが送られてきたが、それを飾ると寝る場所もない。竜也は雛人形の下に潜って寝ることになったが、雛壇の架台はブリキを曲げただけの支えなので、寝相の悪い竜也は顔や手にスリ傷が絶えなかった。
自分たちもマイホームがほしいと梢がいうので、休日には、近くの建売住宅を見学に行った。ある日のこと、気に入った建売を見つけた。1350万円と表示された2階家を、梢と2人で入念に観察していると、セールスマンが近づいてきて、この家は明日には10万円値上げする予定だという。
当時は第1次オイルショックの最中で、確かに物価は連日高騰していた。竜也と梢の貯金を合わせても100万円に満たなかったが、思い切って25年ローンで買うことにした。衝動買いに近かった。
給料は毎年1割以上のベースアップがあり、ローンは何とかなると考えたのだが、これが甘かった。翌年から昇給がストップしたのだ。
竜也と梢は生活の足しにと、近所の高校生に英語を教えることにした。竜也は、それとは別に会社の同僚に頼まれて、娘さんの受験英語の家庭教師をも引き受けた。
サラリーマン社会では、家を新築すると転勤になるといわれているが、竜也の場合も新居に半年暮らしただけでトルコの建設現場勤務となった。
![]()
「介護日記ーその後」にもどる
![]()
「白い闇」第13章に進む
![]()
トップページへ戻る