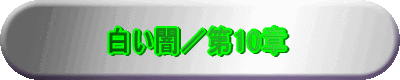
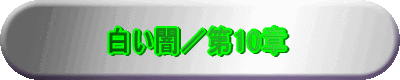
そのことがあって2ヶ月間、竜也は悩んだ。自分は梢のことをどう思っているのか、自分の内なる声を聴きだそうと苦しんだ。
梢に対する自分の本心は何処にあるのか。必要なのか、そうではないのか。内なる自分と対峙して外から眺める経験を京都の山奥の修行でつんだはずだったが、この時ばかりは内なる声は聞こえてこなかった。
森元との間はどうなるのか、これも竜也には予測がつかなかった。竜也は心の内に潜む本当の自分を見定めるには、机の上で考えるのではなく、何か特別な舞台設定が必要なのではないか、と思いついた。
東京の喧騒の中では自分の本心は分からない。誰もいない人里はなれた場所で自分を問い詰めたい。
竜也は大学時代に友人と旅行したことのある能登半島の景色を想いうかべていた。日本海の荒波を受けて節くれだった岩。そうだ、曽々木海岸だ。岸辺から大きく日本海に伸び出し、中央に穴のあいた巨岩のある風景を思い出した。
曽々木海岸では、何枚もの写真を撮り、作品として何度か展示したこともあった。あそこへ行こう。竜也は、更に想像を飛躍させ、梢をその場所に誘いだすことを考えた。熟慮の末、梢に手紙を書いた。
『先日、貴女が帰ってから数日後、森元が訪ねてきました。彼は大きなショックを受けていました。事態がこうなった以上、最善の道は僕が梢と一緒になることだ、と森元はいいます。本当にそうなのか、僕には答えがありません。
この答えを出すべきなのは、僕の本心というか、内なる心なのですが、その内なる心の叫びが聞こえてこないのです。だから、その声を聴くために、あるところに旅行したいと思います。
場所は能登半島の曽々木海岸。同封の写真の場所です。ここで、僕は僕の本心を聴く。更にいえば、梢と一緒になるべきだという本当の声を聴きに行く。もし、そこに貴女が現われたなら、その声は必ず聞こえると思います。
12月X日の正午に写真の場所に来て下さい。貴女が来なくても僕は行きます。一人で内なる声を聴いてきます。随分芝居がかったことをやると思われるかもしれませんが、そうでもしないと自分の本当の心が分らないのです。
これは、1つの賭けですが、僕は曽々木海岸に貴女が来るか来ないかを賭けることにしました。勿論、諸般の御都合もあるでしょう。だけど、日程をずらすとか、場所を変更するような提案をしないで下さい。僕の関心事は、今や、この日のこの時間に貴女が来るかどうか、また、仮に貴女が来なくても自分の本心が聞こえるか、それだけです。その他のことはすべて2の次なのです。』
手紙を投函するとき、梢は来ないのではないかと思った。若い娘が勤めをさぼって能登の辺境まで行くのは簡単なことではない。逆に、だからこそ効果があるのだと勝手に決め付けたて、祈るような気持ちで投函した。
決行の日は1週間後だった。が、2日前になって梢の父親から電話がかかってきた。電話は大家さんの居間にあり、普通は電話の取次ぎは出来ないことになっているのだが、緊急ということで大家の奥さんが部屋に呼びに来た。
階段を降りながら、竜也は不味いことになったと思った。折角のシナリオが没になるかもしれない。
案の定、梢の父は、娘ひとりであんな場所には出せない。本人は行くというが自分は反対だ、といって電話を切った。「それでも私は行きます。」と伝えるのが竜也にできる唯一の抵抗だった。
決行の日、竜也は金沢行きの夜行に乗った。曽々木海岸は能登半島の先端に近く、鉄道はない。金沢から七尾線で輪島まで行き、そこからバスに乗るしかない。
目的地には翌日の昼前についた。12月の初めともなると、小雪の舞う海岸には観光客の姿はなかった。
竜也は荒波に向かって立った。目の前にはイメージした通りの奇岩が、波の向こうに横たわっていた。
水しぶきを受けて立つ巨岩の中央にはポッカリと穴が開いていて、地元では窓岩と呼ばれている。源義経が矢を射って空けたとの伝説もある。
元々、この地は平清盛の義弟の時忠が流されてきて住み着いたとされている。源平にはゆかりの地らしい。
竜也はコートの襟を立て、雪混じりの寒風に耐えながら、しばらく巨岩を見つめた。
正午を過ぎたが、辺りに人影はない。先ほどから内なる声に聞き耳を立てているが何も聞こえてこない。当然ながら梢の姿もない。
殺伐とした自然の懐で、今、梢がくればいいのに、と竜也は勝手な想像を巡らせた。だが、風が強くなってきて、竜也は帰途についた。吹雪になると、地元の人たちは騒いでいた。
中途半端な気持ちで、再び夜行列車に乗った。真直ぐ帰りたくはなかった。翌朝、東京についた竜也は、わけもなく繁華街を歩き回った。日の暮れる頃、下宿に帰り着いた竜也は、仰向けに寝転がって天井の蛍光灯を眺めた。取り替えたばかりのランプが、竜也の心とは裏腹に、狭い下宿部屋を煌々と照らしていた。
翌日、突然、梢の来訪を受けた。厚手のコートを脱ぎもしないで、梢は机の上に黙って何かを置いた。見ると、それは小石と切符だった。
切符は曽々木海岸行きのバスのもので、小石には日付と「曽々木海岸」という字が鉛筆で書かれていた。
梢はあの翌日、吹雪の中をあの場所まで行ったのだ。何ということだ。そこまでするなら、何故もう1日早く来てくれなかったのか。竜也は同情と叱責の入り混じった複雑な気持ちで梢を見た。
梢はにっこり笑って、
「能登から直接来たの。凄いところだわね。これから神戸に帰るわ。今日はこれを渡しに来たの。」
それだけ言うと、梢はさっさと帰ってしまった。
机の上には切符と小石が残されていた。小石を手にすると冷たい能登の海の感触が伝わってきた。
竜也は自分の心に区切りがついたのを感じた。よし、梢と一緒になろう。
そう心に決めたとき、不意に竜也はレニングラードで出会ったジプシーの老婆を思い出した。あのハンカチは何処に行ったのだろう。竜也は旅行に持っていったボストンバッグを押入れから引っ張り出して中を覗いた。底の方に、白いハンカチが両端を結ばれたまま入っていた。
![]()
「介護日記ーその後」にもどる
![]()
「白い闇」第11章に進む
![]()
トップページへ戻る