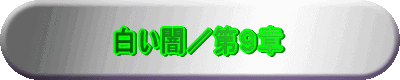
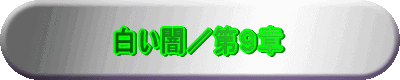
バイカル号が横浜に到着し、竜也は2ヶ月振りに日本の土を踏んだ。
予想した通り、北野が迎えにきていた。後ろに、若い女性の姿があった。また厚子を誘ってきたのだろう。通関の手続きの間を利用して、お土産の万年筆と刺繍のハンカチを取り出した。車の中で渡そうと考えたのだ。
ところが、税関を出て顔を合わせると、驚いたことに、その女性は梢だった。梢と北野は一面識もないはずだ。竜也は一瞬頭が混乱して、どういうわけでそうなったのか、猛烈な速さで推理を巡らせたが、とても結論は出なかった。
竜也の狼狽を見透かしたように、北野の第一声は「お帰り。」ではなく、
「おヌシ、ワケが分からなくなってるな。これは愉快だ。」と、本気で声を出して笑った。
「梢、一体どういうことなんだ。」
「私にも分からないの。こういうことになってしまって。」
「お2人の話は後でゆっくりしてもらうとして、さあ、乗った、乗った。」
北野は狐につままれたような竜也と何故か妙にはしゃいだ様子の梢を小型車に詰め込むと、クラッチを入れアクセルを踏んだ。車はブルブルと震えた音を立てて勢いよく走り出した。
「旅行、楽しかった?」
2ヶ月前と同じ方向から、厚子ではなく梢の声が飛んできた。
「まあね。」
竜也は生半かに答えた。
「この先生、事態が飲み込めずにうろたえているんだよ。」
北野が言い、梢が笑った。
「梢さん、事情説明は帰ってからにしようよ。今は、竜也君の土産話を聞かなきゃあ。」
竜也はからかわれているようで不愉快になったが、その気持ちとは裏腹に、手に持っていたベルギー刺繍を後ろめたい気分で、そっとショルダーにしまいこんだ。
帰りは新しくできた高速道路を利用したお陰か、1時間余りで高井戸の下宿についた。道中、竜也は質問攻めに遭い、自分が質問する余裕を与えられなかった。
北野は荷物を降ろすと、「じゃやな。」と帰ってしまった。万年筆を渡す間もなかった。
竜也は梢を下宿部屋に招きいれ、自分は荷物の上に腰を下ろし、梢には椅子を勧めた。梢は畳の上に直に座った。
「どういうことなの。北野とは何時から付き合っているの。森元とはどうなったの。」
竜也は矢継ぎ早に疑問を梢にぶっつけた。梢は何から話そうかと迷った表情を見せながら、少しずつ話しだした。
「貴方を驚かせて御免なさい。私、相談する人がいなくて北野さんに相談したの。だって、肝心の貴方はいないでしょ。」
竜也は旅行に出る前に、万一のときの連絡先として友人の住所と電話番号のメモを母に渡していた。どうやら梢はそのメモを母から手に入れて北野に連絡をとったらしい。
「私、森元さんと一緒になれないと決めたの。だって、森元さんは貴方の親友でしょ。私が森元さんと結婚したら、貴方と森元さんの間が変になってしまうんじゃないの。森元さんはいい人だし、夫として不足は何もないわ。だけど、私のために森元さんと貴方の友情が壊れてしまうのには耐えられないの。」
「どうして僕と森元の間がそうなると思うの。」
「森元さんが言ってたわ。自分は竜也くんを捨てても君をとるって。」
「それは単なる愛情表現じゃないのか。」
「私も最初はそう思ったわ。だけど、このことは森元さん自身がいい出したの。君と結婚すれば竜也くんとは別れなければならないって。」
「・・・・・」
竜也は森元らしいと思った。
「それで、梢はどうするんだ。」
「今まで通りの関係を続けられないかしら。それが一番いいと思うの。北野さんは私と竜也さんが一緒になるべきだっていうけど。」
梢はそれだけいうと、今日は遅いからといって宿舎へ帰っていった。竜也はお土産の琥珀のブローチのことなどすっかり忘れていた。
梢は東京に出てくるときは、いつも梢の父の会社の寮に宿泊する。それは赤坂にあった。
梢が帰った後、竜也は畳に仰向けになって、蛍光灯のランプを眺めながら自分なりに考えをまとめようとした。が、何もまとまらないまま、旅行の疲れからか、そのまま眠ってしまった。
数日後、竜也が旅行の整理をしていると、夜中近くになって、突然、ノックとともに青ざめた顔の森元が入ってきた。
「何処かに酒があったな。」
森元は、本棚にあるウィスキーを自分で取り出し、グラスになみなみと注ぐと一気に飲み干した。
森元も竜也も酒は飲めない方で、以前一緒に袋田温泉に旅行したとき、旅館の夕食に出されたビール1本を2人で漸く空けた程度だった。
下戸の竜也にはウィスキーは苦手だ。実家の父が寝酒にといってくれたものを本棚に飾っていたが、殆ど口をつけていなかった。
森元は決心したように2杯目を空け、3杯目に口をつけると漸く座り込んで、泣き出した。
竜也は森元の勢いに押されて黙って見ているほかはなかった。やがて、森元は嗚咽から搾り出すような声でいった。
「君が梢さんと結婚してくれ。それが、彼女にとって一番幸せなんだ。」
「どうして、そんなことになってしまったんだい。」
「俺は彼女に気に入られようと一所懸命つくしたよ。だけど、俺がつくせばつくすほど彼女の気持ちは君の方に近づいていくように思う。結局、俺は君たちをくっつける猿回しの猿だったんだよ。」
森元は残っていたグラスを一気に空けて、再び泣き出した。竜也は自分のいない2ヶ月の間に大変なことが起こってしまったように感じて、口をつぐんだ。
「君は梢さんと一緒になるべきだ。これが親友としての最後の忠告だ。矢張り、蓼科で君にジャンケンで負けた時、勝負はついていたんだ。君とはしばらく会わない。」
森元はいうことだけいうと、しっかりした足取りで帰っていった。
竜也は数日前と同じように、畳に仰向けに寝転んで、蛍光灯のランプを見上げた。
ランプの両端が黒ずんでいた。このランプはもう直ぐ寿命だなと思った。
![]()
「介護日記ーその後」にもどる
![]()
「白い闇」第10章に進む
![]()
トップページへ戻る