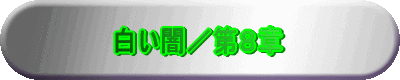
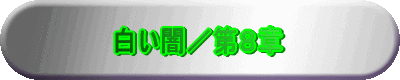
レニングラードは元の名をペテルブルグ、また後に改名されてザンクトぺテルブルグと呼ばれるように、ピョートル大帝の都だ。
ピョートル大帝は大変な権威者で、当時モスクワからぺテルブルグに遷都するときに、地図の上に定規で真っ直ぐ1本の線を引き、この線の通りに鉄道の幹線を建設するよう命じたといわれる。
お陰で、モスクワーレニングラード間の鉄道は今もカーブが殆んどない。
レニングラードの魅力は、何をさておいても、ネバ川と冬宮だ。
冬宮に対して、ピョートル夏の離宮(ペテルゴフ)が郊外にあるが、ここは離宮というより噴水公園とでもいうべき施設。ポンプなどは一切使わず、水位だけを利用して壮大な敷地の中に様々な仕掛けの噴水を設置している。
冬宮では、エカテリーナ女帝が世界の各地から集めた秘蔵のコレクションが、エルミタージュ美術館に納められている。中でも、圧巻はラファエロの回廊と呼ばれる、ルネッサンス・イタリアの再現ともいうべき広間。
壁には、ルネッサンスの特徴であるグロッタ模様が描かれている。グロッタとは意味不明の画のことだが、「グロテスク」は「グロッタ風」から来た言葉だと知った。
冬宮の前をネバ川が悠々と流れている。モスクワ河、テムズ河、セーヌ、ドナウ、ラインと大きな川を見て周った竜也の不満は水の汚いことだったが、ネバ川に来て初めて川の水を美しいと感じた。
最後の目的地レニングラードで竜也はある経験をした。それは、ピョートル夏の離宮を訪れた時のことだった。
数々の趣向を凝らした噴水を見て廻って、竜也は疲れた身体をベンチに休めていた。何処からともなく1人の老婆がやってきて隣に腰を下ろした。
服装はみすぼらしく、顔は半分汚れたネッカチーフで覆っていたが、目鼻立ちにはある種の気品が漂っていた。
老婆は少し身体をずらせて竜也の方に近づくと、
「何をしているの。」と話しかけてきた。
ソ連では年配者はすべて年金生活者。受け取る年金は少ないが、ヒマをもてあましているのだろう、見知らぬ外国人に話しかけてくることも少なくなかった。
「休んでいます。」と竜也は答えて、話が長くなりそうだから立ち去ろうとした。
老婆はチョット待つよう手で合図すると、自分はツィガーン(ジプシー)だと名乗った。
ジプシーは、元々コーカサス系人種でハンガリーに多く住んでいるが、ロシアにもいるようだ。
老婆は、竜也に悩みがあるだろうと一方的にいうと、今日は特別に占ってあげようと切り出した。
ややこしくなる前に立ち去ろうとしたが、それができなかったのは、老婆の姿が何故かマカロヴァさんと重なったからだ。
マカロヴァさんは、竜也の神戸時代、ロシア語の先生で、ポーランド生れの白系ロシア人。貴族の娘で白軍の高官と結婚したが、ほどなくロシア革命が起こり、ご主人とは離れ離れとなって日本に逃げてきた。
日本での生活は苦しく、兵庫県警の外事課から出る僅かな補助金で暮らしていた。ステータスは無国籍白系ロシア人とされ、日本の生活保障からも見放されていた。
神戸にはこうしたロシア人が多く居住していて、一部にはチョコレートを作って成功した例もあるが、大半はナイトクラブのドアボーイなどの職を求めて、つましい生活を余儀なくされていた。
神戸の山本通りの一郭に白系露国人組合という古い建物があり、その物置にマカロヴァさんは暮らしていた。竜也はロシア語会話の勉強に此処を訪れて、マカロヴァさんと出会った。高齢の彼女は殆ど寝たきりで、ボランティアの日本人が身の回りの世話をしていた。
山本通りは梢の短大からも近く、梢も時々顔を出して掃除の手伝いなどをしていたようだ。
貧しくても気位の高いマカロヴァさんに竜也は同情に近いものを感じていたが、同時に何処となく惹かれるものがあった。
ジプシーの老婆にマカロヴァさんとの共通点を見たように思って、竜也はしばらく老婆の話を聴くことにした。
老婆は口の中でブツブツ何やら念仏をとなえながら、竜也にハンカチを出せと言った。
竜也が白いハンカチを渡すと、再び念仏をとなえ、竜也の名前と恋人の名前を言えという。竜也は自分の名前は即座に教えたが、恋人の名前を言う段になると逡巡した。
老婆の「スカレー(早く!)」という鋭い声に急かされて、思わず「コズエ」と口に出した。
老婆は「タツヤ・コズエ」を繰り返しながら、器用な手つきでハンカチの両端を結んだ。
「あなた方はこれで結ばれる。今度コズエに会うまでにこの結び目を解くようなことがあれば2人の恋は破れる。このハンカチの結び目が解けないようにしっかりと守って帰りなさい。今日の占いは大切な内容なので、お代は20ルーブルです。」
竜也は、高いといって半分の10ルーブル紙幣を差し出した。老婆は黙ってそれを受け取ると、立ち上がって「スパシーボ(有り難う)」と言うと、そそくさと去って行った。
竜也は昔のおとぎ話の世界に入ったような自分に苦笑したが、それでも念のために結び目のついたハンカチをそっとカバンにしまった。
竜也が学生時代のクライマックスと位置づけた大旅行も、終わってみると早かった。
帰りのバイカル号で、各地の記念の品をベッドに広げてみた。お土産も忘れずに買った。梢にはソ連の琥珀のブローチ、森元にはスイスのネクタイ、北野にはドイツの万年筆、厚子にはベルギーの刺繍を買った。
森元のネクタイには後日談がある。
竜也がスイスのジュネーブでレマン湖遊覧をしたとき、一回だけだからよかろうと思い、記念写真の前に買ったばかりのネクタイを締めたのだ。帰国後、たくさんの写真の中から森元は1枚の写真を目ざとく見つけ、「これ、俺のネクタイに似ている。」と、大発見をしたように叫んだのである。
![]()
「介護日記ーその後」にもどる
![]()
「白い闇」第9章に進む
![]()
トップページへ戻る