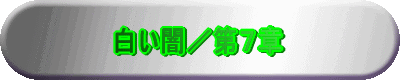
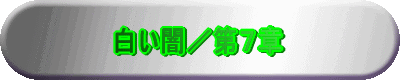
横浜を出て3日目の午後、バイカル号はナホトカに入港した。遠くに大陸が見え、それが段々と近づいてくる様子は、流石に感動的だった。
ナホトカに上陸すると、直ぐに待合室で待たされた。聞いてはいたが、社会主義のビュロクラシーは相当なもので、今なにをしているのか、何時になったら手続きが終わるのか、全く知らされないまま全員が待たされた。乗客の殆どが日本人客で、あちらこちらで、官僚主義の悪口をいい始めた。
竜也は、もの珍しそうに周囲の掲示を見ていた。書かれているロシア語をどの程度理解できるか、自分で試していたのだ。殆どの掲示は理解できたので、何とはなく自信が湧いてくるように感じた。
船で同室だった先生の1人が、この場の状況を係員に訊いてほしいと頼んできたので、竜也は「インツーリスト」と書かれたオフィスのドアを叩いた。オリンピックの後、至難とされた通訳案内業の国家試験にも合格し、ロシア語会話には自信をもっていた。
「あなた方は、何の説明もなく皆を待たせているが、日本人は気が短い。事情を説明した方がよいと思う。」
竜也は応対に出た太めの中年女性に頭の中で事前に準備したロシア語をぶっつけた。
「まあ、上手にロシア語を喋るわね。」
お褒めの言葉を頂戴した後、状況の説明を聴いた。
早口のロシア語で全部は理解できなかったが、要は、ハバロフスク行きの列車の出発まで時間潰しをしているようだった。ナホトカの街はは外国人が自由に立ち入れない地区になっているので、待合室から外に出られないのだという。
「何時まで待つのだ。」と訊いたが、相手は肩をすくめるだけだった。
待合室で3時間も待たされただろうか、漸く、案内があり、バスで鉄道の駅に向かった。ナホトカはシペリア鉄道最南端の駅で、ここから夜行列車でハバロフスクに向かう。
ナホトカの隣にウラジオストックという小さな町がある。此処は日本海に通じる軍港で、外国人にはオフリミット。日本では、この町の名前をウラジオ・ストックと分割し、省略して「ウラジオ」と言ったりするが、正確には「ウラヂー」と「ヴォストーク」の合成語。「東方を占領せよ」という意味になる。原語の意味を知ると、その昔、日本侵略の拠点として名付けられたように思う。
シベリア鉄道は広軌で、レールも長いものを使っているので乗り心地は悪くない。竜也の車両は、日本でいう3等車でロシア語では「ジョーストキー・ワゴン」と名付けられている。これは、「硬い車」という意味だが、アクセントを間違えて「ジェストーキー」と発音すると「残酷な車」という意味になるので、ロシア語を少しかじった人は辞書をみて慌てる。硬車に対して軟車があるが、こちらは料金が高い。
竜也たちの乗りこんだ硬車は、コンパートメント式の寝台車。バイカル号で同室だった4人が同じ部屋を割当てられた。
日本の3等寝台に較べるとはるかに快適で、列車はシベリアの平原を一路ハバロフスクに向かった。
20時間近くかけてハバロフスクに着くと、乗客は漸く解放され、ツーリストたちは三々五々それぞれの目的地に向かうことになる。
竜也は同室の3人と再会を約して別れを告げ、1人でハバロフスクの街に出てみた。子供たちの服装は聞いていた通り粗末で、裸足の子供もいた。話しかけると、人懐っこく集まってきたが、子供の話す早口のロシア語は竜也には理解できなかった。
しばらく歩くとアムール川の岸辺にでた。中国語で黒龍江といわれるように、まるで瀬戸内海の水を黒くしたような印象だった。初めて踏むロシアの大地に些か興奮しながら、竜也はカメラを片手に貪欲に歩きまわった。
その日の夜は、インツーリストの手配したホテルで一泊し、翌朝アエロフロートでイルクーツクに向かった。
ハバロフスク空港を飛び立つと、眼下にアムール川が、まさに、黒い龍が躍動しているかのように横たわっている。絶好の構図に思わず、カメラを出しシャッターを切った。
「ダヴァイチェ!」と女の声がした。
見ると、何処にいたのか、スチュアーデスが手を出して睨んでいる。ガイドブックの撮影禁止場所に空港と並んで俯瞰撮影というのがあったのを思い出した。いわば、ダブル違反だ。
一瞬、恐怖感が走り、鹿児島での通関を思い出した。恐る恐る差し出したカメラをスチュアーデスは無造作に受け取って、頭上の棚に置いた。フィルムを抜かれるかと覚悟を決めていたが、その心配はなさそうだ。
カメラを取り上げられてからというものは、何となくバツが悪く、竜也はずっと窓の外を眺めていた。何もない荒涼としたツンドラや大密林のタイガを過ぎて、ツポレフ機は夕方になってイルクーツクに降りた。当然ながら、カメラはそのまま返されてきた。
イルクーツクはシベリアに抑留された日本人捕虜が建設した町といわれているが、建物はどれも古びていた。この町での竜也の目的はバイカル湖であった。
翌朝、インツーリストのガイドの案内で、バイカル湖見学に出かけた。客は竜也1人だけだったが、リュバと名乗るモンゴル系の若い女性のガイドがついた。
最初、中学生が教科書を読むような英語で話しかけてきたので、「ガバリム・パルースキ」(ロシア語で話しましょう)というと、ニッコリ笑って、立て板に水を流すように喋り出した。日本人そっくりのリュバが流暢なロシア語を喋るのが何となく不思議に思えた。
客1人にガイド1人ではとても引き合うまいと思うが、ガイドは監視の役目も帯びているようで、1日中竜也に付き合ってくれた。
竜也とリュバを乗せた車は白樺の林の中を猛スピードで走った。車は2000ccクラスのヴォルガ。年輩の運転手は舗装のない道をガタガタと音を立てて飛ばした。
数時間して、車はバイカル湖のほとりで停車し、竜也たちは外に出た。運転手もついてきた。竜也は湖の傍まで歩き、思い切り息を吸い込んだ。
『これがバイカル湖か!』
バイカル湖は、巨大な淡水湖で琵琶湖の46倍、透明度では世界一を誇る。湖には330の川が流れ込んでいるが、流れ出るのはアンガラ川1本だけなので、とてつもない水量となる。これを利用するために、いくつもの水力発電所がアンガラ川沿いに作られているという。
バイカル湖は、まるで海だった。対岸も見えない岸辺に立って、竜也はロシア民謡「バイカル湖のほとり」を口ずさんだ。
リュバはその歌を知らなかった。横で聞いていた運転手が「随分古い歌だ。」と言った。
3人は岸辺に腰をおろして、暫く休むことにした。見渡す限り水と白樺林で人気は全くなかった。岸辺に打ち寄せる波が一定のリズムを与えていた。
竜也はリュバの生立ちを訊いた。リュバは問われるまま、素直に話した。
根っからのイルクーツク娘で殆ど町から出たことがないという。途中で、運転手が質問を引き継ぎ、最後は2人のロシア人の世間話になってしまった。
竜也は運転手にカメラを渡し、リュバと並んで記念写真を撮った。日本で見せたら北海道かどこかの海で撮った、日本人のツーショットに間違われるだろうと思った。
帰りは、来た道を更にスピードを上げて戻った。リュバは運転手との話しに夢中で、竜也は後部座席に放っておかれた。運転手が前方ではなく、リュバの顔を見ながら運転するのが気になって、竜也は景色を楽しむどころではなかった。
イルクーツクはバイカル湖だけがお目当てだったので、1日の滞在でモスクワに向かった。
モスクワは、流石に大都会で訪問する個所が多い。
先ず、高い場所から街を見下ろすことにして、タクシーでレーニン丘にあるモスクワ大学を見に行った。スターリン時代の豪華建築の代表として、モスクワ大学とウクライナホテルは広く紹介されていた。
現地についた途端、建物の壮大さに肝をぬかれた。当時、日本で唯一の高層建築だった霞ヶ関ビルに驚いたほどだから、その数倍規模のモスクワ大学の威容はすさまじい迫力で竜也を圧倒した。
また、モスクワ大学を背にして、丘の上から見るモスクワ全景は、なだらかなUの字にカーブしたモスクワ川のアクセントに引き立てられて素晴らしいものがあった。竜也はモスクワに居ることを実感した。
モスクワ滞在の2週間足らずの間に、クレムリン、赤の広場、ボリショイ劇場、プーシキン美術館など、竜也は名のあるところをすべて見てまわった。
その中で、「ベデンハー」と呼ばれる常設の博覧会を訪れたとき、竜也は意外なものを見つけた。
ガガーリンの乗ったスプートニクがその展示場の目玉であったが、片隅に世界各国の企業がソ連に輸出している、商品展示コーナーがあった。
日本からの輸出品の中に、竜也は山口工業の「カプロラクタム」というものを見つけたのだ。
それは、ポリエチレンと並んで文字で表示されていただけだが、カプロラクタムとは、一体どんなものだろうかという疑問と興味が旅行中ついてまわった。
モスクワでたっぷりと異国情緒を味わって、空路ロンドンに向かった。
竜也は旅行に出かける前にソ連通の友人からある忠告を受けていた。
それは、東から周るとモスクワは感激するが、西から周るとガッカリするというものだったが、ロンドンに着いてみて、その言葉の意味が判った。
確かに、ロンドンを見た後でモスクワを訪問したのでは、ただの田舎町としか映らないのではないか。赤の広場にあるワシリー寺院の原色のネギ坊主やモスクワ大学の威容はもちろん迫力はあるのだが、ロンドンの整然とした都市の美しさには勝てないと思った。
特に、テムズ河から臨む議事堂やハイドパークなど、自然を取り入れた都市の美しさは竜也を魅了した。
郊外に出ると、端正な家々が同じような造りではあるが、それぞれに工夫を凝らして整然と立ち並ぶ様子には気品すら感じる。
こういうところに住む人たちが日本のチマチマした住宅を見ると、ウサギ小屋にみえるのも無理はない。竜也は住宅の広さと質の両面から決定的な落差を痛感した。
ロンドンの街は素晴らしいが、郊外はもっと素晴らしい、と竜也は日記に書き残した。
ヨーロッパの魅力は、更にフランス、スイス、ベルギー、ドイツ、オランダと周って行く中で増幅されこそすれ決して飽きることはなかった。
歴史の重みと芸術の香り、水と緑を豊富に取り入れた都市美とバロック建築の伸びやかな美しさ、更にはどこをとっても画になるような郊外の素朴な味。ヨーロッパの各都市に竜也は完全に魅了された。
確かにヨーロッパは素晴らしい。最後の目的地であるレニングラードに向かう飛行機の中で、ソ連の第2の都市に敢えて期待しないよう自分にいい聞かせた。
![]()
「介護日記ーその後」にもどる
![]()
「白い闇」第8章に進む
![]()
トップページへ戻る