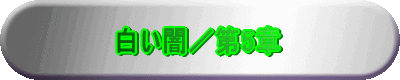
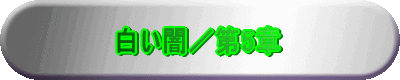
神戸を離れてからも、竜也と梢の交際は続いていた。交換日記のような手紙のやり取りがあったし、たまに神戸に帰省したときには必ずデートした。梢は、N社という外資系の会社に勤めていた。
短大時代から英語が好きで、独学で勉強した英文速記(ステノグラフ)を活用できる職場に、梢はとても満足していた。加えて、外資系は給与が高い。学生時代に較べると、服装もぐっと洗練され、高級OLに変身していた。
だが、梢はN社に長く勤める気はなかった。女は適齢期になれば結婚するものと決めていた。梢の常識では適齢期とは25歳までであった。高校時代に肺結核で1年遅れた梢はN社に入ったときには、既に21歳で、適齢期までに余裕はなかった。
N社では、梢の容姿に声をかける男も少なくなかったが、特定の交際相手といえば竜也以外になかった。しかし、竜也の方は、学生生活の延長を楽しんでいる様子で、結婚について真剣に考える風ではなかった。だから、竜也とたまにデートしても何の進展もなくマンネリ感を抱きはじめていた。
ある日、新しく完成した神戸ポートタワーの展望台から神戸港に停泊しているたくさんの外国船を見下ろしながら、梢は竜也の沖縄旅行での失敗談を聞いていた。
竜也の話に一応の区切りがついたとき、梢は出し抜けに質問した。
「あなた、結婚についてはどう考えているの。」
不意をつかれた竜也はどう答えるべきか十分考える間を与えられずに、咄嗟に逃げを打った。
「先のことだと思っている。未だ勉強もしないといけないからね。」
「山口工業の就職試験、受かるといいわね。父に聞いたらとてもいい会社だと言っていたわよ。」
「お父さんは山口工業のこと知っているの。」
「ゴルフボールのゴムを共同開発するそうよ。」
竜也は山口工業がゴムを作っているとは知らなかった。
梢の父はD社に勤務し、企画畑の仕事をしていた。高校卒業後、工員として採用された苦労人で、働きながら夜間大学を卒業した。梢は長女で下3人は男だったので、一人娘の梢をとても可愛がっていた。梢の方も親思いで、竜也に親をもっと大切にしなければいけないと、姉さんぶった忠告を何度もしていた。
「私、今年24でしょ。親も心配するし、お見合いしようかと思うの。」
「・・・・」
竜也は言葉につまった。折角、結婚の話題から離れたと思った矢先のことで、何と答えてよいか判断がつかなかった。
「どうぞ。梢がそう思うのなら仕方ないよね。」
そう言いながら、竜也は自己嫌悪を感じた。何と下手な台詞だ。相手の質問には何も答えていないし、自分の気持ちも正直に表現できていない。
事実、竜也は自分の気持ちが何処にあるのか、自分でも掴みかねていた。梢のことを愛しいと思う気持ちはあったが、将来の妻として考えたことはなかった。竜也には、結婚相手は年下の女性が自然だという漠然とした常識が働いていた。梢は年下ではあるが、同級生だ。その点からすれば、竜也が一方的に淡い想いを抱いている雅子が理想の相手だった。
雅子とは芦屋の海水浴場で偶然知り合った。彼女はS女子高の3年生で、竜也の家の近くに住んでいた。時折、バスの中で出会って口を聞く程度で、雅子から見れば竜也は特別の存在でも何でもなかった。一人っ子の竜也は、兄と妹が欲しかった。だから、自分の妻としては、可愛い妹のような相手を頭に描いていた。そのイメージが雅子と重なるように思えた。
一方、竜也には現時点で将来の妻を選ぶのは損だという打算があった。自分の周囲の女性は限られている。一生の伴侶は、もっと広い選択肢の中から選ぶ方が良い相手が見つかるかもしれない。
この日、竜也は梢と別れて東京に帰ったが、数日して梢から手紙を受け取った。飯島某という男と見合いしたと書かれていた。竜也は梢が自分の手許から離れていくのが惜しいと感じた。
1週間後、大学時代の親友の森元が竜也の下宿に訪ねてきた。森元はC商事に就職していて、ソ連貿易の最先端で働いていた。森元は三鷹の独身寮に居たが、料理がお粗末だと不満を洩らしていた。
竜也は、以前、森元に下宿で調理したビフテキを御馳走したことがある。森元はそれをとても気に入って、それから時々竜也の下宿にやってくるようになった。
この日は、自分でビフテキ肉を2枚買ってきて、それを焼いてほしいと言う。狭い下宿部屋でビフテキを食べながら、互いの近況報告に移った。竜也が梢のことを森元に話したところ、森元は意外な反応を示した。
「そんな男にやるなら、俺に紹介してほしい。」
森元と梢は、以前、竜也の父が招待したパーティーで顔を合わせたことがあった。その時から森元は梢の容姿に惹かれていたようだ。森元と梢が結婚すれば、梢を手放すことにはならない。竜也は勝手な想像を思いついた。
また、1週間が過ぎた。その間に、竜也は山口工業からの内定通知を受け取った。それほど大きな喜びを感じなかったが、心置きなく旅行に出かけることができるのは嬉しかった。
旅行の出発が10日後に迫ったある日、竜也が大学から帰ると下宿の奥さんが、綺麗な方が訪ねてこられたので部屋にお通ししたと伝えた。急いで自分の部屋に上がってみると、驚いたことに、部屋の片隅には梢が正座してた。
「どうして! よく此処が判ったね。」
「地図で調べてきたから。突然お邪魔して御免なさい。でも、どうしても貴方に聞いてほしかったの。」
竜也は梢を近くの養老院の庭に案内した。そこは、浴風苑という古くからある老人ホームで、広大な庭があり一般の人も散歩がてらに来ていた。
梅雨が終わり、夏の太陽が庭の芝生に照りつけていたが、木陰のベンチは涼しかった。足もとには、名も知らぬ黄色の花が咲き乱れていた。
梢は薄いピンクのワンピースに頭には白い布を巻いて、遠くに見える老人たちの姿を珍しそうに眺めていた。浴風苑の緑のバックによく調和して、竜也はしばらく見ないうちにまた洗練されたと思った。
梢は竜也の方に向き直って少し目を細めて微笑んだ。
「飯島さんって、ちょっと変なの。」
梢は見合いの相手の男について不信感をあらわにした。
梢の説明によると、結婚を前提に見合いした2人の間は、表面的には順調に進んでいったが、梢自身は心の中でついていけないものを感じていたという。飯島は何でも勝手に決めてしまい、梢の意見を無視するようだ。梢がこれ以上進んでは危険だと感じたのは、婚約指輪の選定に関して意見の衝突があったときらしい。
梢の話には竜也も十分理解できないところがあったが、どうやら、自動車のセールスマンをしている飯島というのは相当に独断的な男らしい。竜也は森元のことを頭に浮かべて、思い切って自分のアイデアを切り出した。
「そんな男はスッパリあきらめて、僕がいい人を紹介しようか。」
全く予期しなかった竜也の言葉に梢は訝しげに竜也の次の言葉を待った。
「一度、パーティーの席で梢にもあったことがある森元君。いい男だよ。C商事に勤めているから、車のセールスマンなんかよりよっぽど収入は安定しているし。先方は梢のことを気に入っているみたいなんだ。」
「あの時のパーティーでは男の人が大勢いたから、森元さんがどの人か分からないわ。」
「一度、会ってみるか。損はないと思うけど。」
「会ってどうするのよ。貴方、私がその人と結婚するのを望んでいるの。」
「そうなればいいと思う。そうなれば何時でも梢とあえるからね。」
「変な理屈ね。」
正に、変な理屈だと竜也も思う。しかし、その変な理屈が竜也にも意外なほど進展し、次の週末に3人で旅行に行くことに決まった。場所は信州の美ヶ原高原である。
竜也は、前年、母を連れて蓼科から美ヶ原を旅行した。若いカップルや若者グループの登山客に混じって、母親と2人で旅行することに抵抗はあったが、山好きの母に対するせめてもの親孝行と決心したのだ。
50を超えたばかりの母は、蓼科から美ヶ原に通じる険しい山道を黙々と歩いた。あたり一面、高山植物の花々に覆われ、特にニッコウキスゲのオレンジの色が美しかった。
「素晴らしいところやね。」
母は同じ台詞を連発した。確かに素晴らしかった。もう一度行ってみたいと、竜也は思った。
ヨーロッパ旅行を3日後に控えていたが、竜也は森元と梢をつれて信州の高原を歩いていた。高山植物は昨年と変わらない美しさで3人を迎えた。
梢は初めてみるジーンズ姿で子供のようにはしゃいでいた。時折、道が一段高くなったところにさしかかると、「森元さーん。」と、甘え声で森元に手を差し出して助けを求めた。
最初は少し緊張気味だった森元も次第に打ち解けて、楽しさを素直に表した。まるで、竜也のシナリオ通りに梢が演技しているようだった。
ところが、白樺湖の近くにきたとき、小さな事件が起こった。梢が上諏訪駅の茶店に自分の荷物を忘れてきたと言い出したのだ。竜也は帰りにとりに行けばよいといったが、梢は着替えが入っているので、今夜どうしても要ると主張した。
竜也は、自分が取りに行くので、森元と梢はボートにでも乗って待っていてほしいと提案した。その方が竜也のシナリオは進展するし、ひょっとすると荷物を忘れたこと自体も梢の演技かもしれないと思った。
しかし、森元は竜也の提案を聞き入れず、竜也と森元がジャンケンをして負けた方が取りに行くことを主張した。多分、森元もコトが上手く運びすぎていると直感したのだろう。ジャンケンで決めることで、より自然な決着を求めようとしている、と竜也は判断した。
結局、2人がジャンケンをすることになり、竜也は負けることを念じてグーをだした。普通、ジャンケンをするとき、何となくパーをだす人が多いからだ。ところが、皮肉なことに、森元は竜也と同じ発想をしながら、勝つことを念じてチョキをだしてしまった。
実は、このジャンケンが3人の将来を決めることになろうとは、その時、誰もが想像しなかった。
森元が梢の荷物を取って帰る2時間あまりの間、竜也は梢を誘って白樺湖にボートを浮かべた。透き通るような湖面には、白樺林からの木洩れ陽が細波に輝いていた。名も知らぬ鳥の声が聞こえ、頬をなでる微風が汗ばんだ肌に心地よかった。
竜也は、先ほどから最も気になっていた質問から入った。
「森元のこと、どう思う。」
「良さそうな方ね。でも、此処で2人きりで少しお話しがしたかったわ。」
「だから、わざと荷物を茶店に置いてきたんだね。」
「当然、貴方が取りに行くと思ったわ。」
「そこが、森元のいいところなんだ。悪い役目は自分が引き受けようとする。」
「でも、何だか皮肉ね。折角、貴方の筋書き通りに運んでいたのに。」
「まあね。」
確かに、皮肉な話だった。3人の思惑が一致していたにも拘らず、事態が別の方向に進んでいくように、竜也には思われた。
梢は紺のジーンズに白いブラウスで頭には赤と白のネッカチーフをつけていた。シンプルな装いは梢の魅力をかきたてるようだった。
「その恰好、よく似合うよ。」
「有り難う。でも、貴方、本当に私が森元さんと一緒になっても構わないの。」
「仕方ないよ。僕と一緒になろうと思うと梢の適齢期をとっくに過ぎてしまうよ。」
竜也は、一瞬、余計なことを言ってしまったと後悔した。梢は「そうね」と答えただけだったが、内心では心のざわめきを覚えた。適齢期を過ぎても竜也を待つ、という新たなシナリオが瞬間的に頭をよぎったのだ。
その夜、白樺湖の旅館で、3人は竜也を中に挟んで同じ部屋に寝た。梢は疲れたのか、横になると直ぐ寝息を立てはじめた。竜也は明け方まで寝つけなかった。森元も起きていたようだが、梢に遠慮したのか、ひと言も喋らなかった。
翌朝、旅館の豪華な朝食を済ませ、3人は松本市に向かった。この日は市内を見学して東京に帰るだけなので、梢は淡い緑のワンピースにハイヒールを履き、頭には白い帽子を被っていた。一夜にして都会の令嬢に変身した姿に竜也も森元も素直にみとれた。
松本城は日曜日とあって東京や関西からの観光客で混雑していた。若い女性も多かったが、梢の洗練された魅力には誰も敵わなかった。
3人は松本から名古屋に出た。完成したばかりの新幹線で梢は大阪へ帰っていった。
森元と竜也は梢を見送った後、東京行きの列車を待った。生憎、列車は満員で、2人はデッキに並んでしゃがみこんだ。
「君は、本当に僕が梢さんと一緒になっても後悔しないのか。」
森元はたまりかねたように口火を切った。
「最初からその積もりで君に紹介したが・・・」
「僕が荷物を取りに行った間、君らは何を話したんだ。」
「別に・・・」
「正直いって、梢さんのこと、とても気に入った。魅力的な人だと思う。だけど、何だか友達のものを横取りするようで、そこがどうも引っかかるんだが。」
「遠慮することはないって。僕も君たちが結婚してくれるとハッピーなんだから。頑張れよ。」
「もう一度訊くが、君は絶対に後悔しないんだな。」
「後悔しないって、言ってるだろう。」
そう言いながら、竜也は後悔に似た後ろめたさを感じた。東京駅で2人は別れた。
竜也は2日後に控えた旅行の準備に頭を切り替えた。
![]()
「介護日記ーその後」にもどる
![]()
「白い闇」第6章に進む
![]()
トップページへ戻る