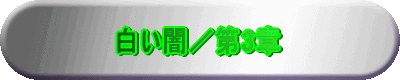
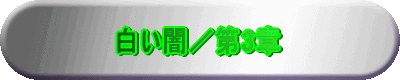
東京オリンピックは、経済的な面でも竜也の懐に大きな幸運をもたらした。当時の流行歌にフランク永井の「1万3千800円」というのがあったが、大学卒の初任給が2万円にも満たない時代に、竜也は60日間の選手村勤務で残業代も含め、破格の30万円近い大金を手にしたのである。この資金を元手に長年の夢であったソ連・ヨーロッパへの旅行を計画することになる。
当時、海外旅行は未だ珍しく、1ドル360円。外貨管理制度が敷かれ、海外旅行に持ち出せる外貨は500ドルに厳しく制限されていた。一方、竜也の計画では、ソ連とヨーロッパをつぶさに見てまわるには2ヶ月程度必要で、とても500ドル(18万円)では足りなかった。竜也は一計を案じた。
当時、沖縄では通貨としてドルが使われており、沖縄への渡航も外国扱い。申請すれば500ドルの外貨を手に入れることができた。先ず、沖縄に行こう。そして、ドルを使わずに持ち帰ろう。そうすれば、正規に両替する分と併せて、2ヶ月は何とかなる。
竜也は、早速、同じアパートに住む沖縄からの留学生の牧原に事情を話し、彼の実家に2週間投宿する快諾を得た。
翌年の春休み、竜也は初めて手にした米ドルの札束を手に沖縄旅行に出かけた。初めて訪問する牧原家では思わぬ歓待を受けた。特に、牧原の妹の恵美子は高校生だったが、竜也に好感を抱いて、沖縄口(ウチナワグチ)といわれる沖縄の方言を教えた。お返しに、竜也はロシア語の手ほどきをしたのだが、驚いたことに恵美子は1週間足らずの間に主要な単語を暗記し、あの複雑なロシア文字もすべて正確に憶えてしまった。
竜也の沖縄滞在は恵美子がいたお陰で瞬く間に過ぎ、帰京の時がきた。
竜也は牧原家の全員に丁寧にお礼を述べ、恵美子には、是非、内地の大学に進むようにアドバイスした。恵美子のような可憐な女子大生がロシア語を学ぶのは、とても素晴らしいことのように思えた。
那覇港から鹿児島行きの船に乗り込んだが、折からの荒天で海は大シケ。船は前後左右にあるときは大きく、またあるときは小刻みに揺れた。気分が悪くなった竜也は、その夜、何度も3等船室のトイレに駆け込んだ。お陰で、殆ど眠れないまま、翌日、鹿児島港に着いた。
早速、長崎税関の2人の入国審査官が船に乗り込んできて、入国審査と通関事務を始めた。竜也は気分がすぐれないまま係官の前に進んだ。パスポートのチェックがあった後、年輩の係官がおもむろに尋ねた。
「沖縄滞在中に買ったみやげ物を見せて下さい。」
「特にありません。」
「持ち出し外貨の残高に記入がありませんが、全部使ったということですか。」
「はい、そうです。」
「一体、何に使ったのですか。」
「飲み食いと宿泊費です。」
「それでは、ホテルの領収書を見せて下さい。」
「捨てました。」
「何というホテルに泊まったのですか。」
「・・・・・・」
うかつにも、竜也は通関について何も事前準備していなかった。一応、牧原には簡単に聞いてはいたが、牧原の場合は内地への留学生扱いなので、殆ど無検査ですんでいるようだった。
虚をつかれて、竜也は言葉に詰った。ベテラン審査官はとっくに竜也が外貨を残していると睨んでいた。
「時間は十分あげるから、何に使ったのか、明細を思い出す限り全部かきあげなさい。領収書のあるものは出しておきなさい。」
審査官の自信に満ちた声が、うつろに響いた。竜也は全員が下船するまで控え室で待たされた。乗客は次々に下船し、竜也以外は誰もいなくなった。しかし、竜也の目の前に置かれたザラ半紙は白いままだ。竜也の頭の中では、どうすればこの場を逃れられるか、ありとあらゆるシナリオが非常な速さで渦巻いていた。
いくら考えても名案はなかった。どうにでもなれ、という気になった。同時に、「此処は鹿児島港なのに、どうして長崎税関なのだろう。」 どうでもいい疑問がぼんやりと頭に浮んでいた。
「思い出さないのなら、今から身体検査をさせてもらうが、よろしいですか。」
審査官の重みのある声が、竜也に衝撃を与えた。
胸の内ポケットには、殆ど手つかずのままの500ドル近い紙幣が入っている。もしこれがみつかるとどうなるのか。竜也は自分の計画がいかに軽率であったか、思い切り後悔したが、もう遅かった。竜也のろうばい振りを察した年配の審査官は、がらりと口調を変えた。
「学生の分際で500ドルもの大金を使ってしまったは、ないだろう。身体検査で宝石でもみつかれば、君は密輸現行犯だ。ドル紙幣なら、外国為替管理法違反ということになる。いずれにしても、我々の管轄外だから、今から警察を呼ぶ。それまで此処で待ってもらう。」
竜也は自分の中で、折角積み重ねた計画がガラガラと音を立てて崩れ落ちるのを感じた。何故か、不意にバベルの塔のことを思い出した。
人間が力を合わせて天まで届く高い搭を築いたとき、神がそれを見て怒り、それまでは単一の言語だったものを多くの違った言葉に変えてしまった。お陰で、コミュニケーションを失った人間どもは力を合わせることができずに、バベルの塔は崩れてしまう。
この物語には尾ひれがついていて、搭が崩れたときに言葉のベースとなる文字がバラバラに落ちてきた。中には裏向きになってしまった文字も多かったが、それらを拾い集めて作ったのがロシア文字だというのだ。
「申し訳ありませんでした。実は、外貨を残していました。」
正直に白状して、竜也は頭を机の上に伏せた。ここは泣きの一手だと判断した。東京の中央線でキセルをして捕まったときのことを思い出したのだ。
勝ち誇った顔の審査官は、警察に引渡すとか、君は前科一犯だとか、竜也を攻撃したが、殊勝に詫びの言葉を繰り返す竜也に見切りをつけたのか、最後に好意あふれる台詞で竜也の審査を打ち切った。
「君もH大学の大学院生といえば前途ある身だ。今回だけは大目にみるから、今すぐこのドルを円貨に両替してきなさい。」
国鉄のキセルで3倍の罰金を取られたことを思い出し、心の中で、18x3=54と暗算して50万円もの罰金をどうして作るか、絶望に近い気持ちでいた竜也は、思わず大声をあげた。
「有り難う御座います。」
千円札ではちきれそうになった封筒を鞄に詰めこんだ竜也は、鹿児島から東京行きの特急に乗った。目的は達せられなかったが、気分は晴れやかだった。恵美子と知り合えたことだけでも収穫だと思った。
![]()
「介護日記ーその後」にもどる
![]()
「白い闇」第4章に進む
![]()
トップページへ戻る