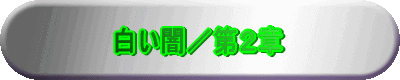
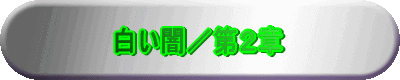
竜也と梢は幼馴染というか、郷里神戸の小学校の同級生だった。しかし、その頃から互いに意識していたわけではなく、竜也は小学校時代の梢にそれほど強い印象をもっていなかった。ただ、毎朝、学校に早く来て皆の机を雑巾で拭いていることがよくあったので、掃除好きのお下げの子という印象は記憶の片隅にあった。
確か、高校二年の夏休みだったか、小学校の同窓会があり、竜也は大して気が進まなかったが、友達に誘われるまま、出席した。
その当時、梢は竜也の高校の近くにある女子高に通っていたのだが、同窓会には、その女子高の白いセーラー服ではなく、空色の浴衣に赤い帯を締め、塗りの下駄履きで登場したので、皆の注目を集めた。
竜也も「可愛い」と思ったが、その時は何事もなく別れた。しかし、この同窓会でうすれかけていた掃除好きのお下げの子についての記憶が再び蘇ったのは間違いない。
その後、竜也は地元の外国語大学に進み、梢も神戸の街中にある短大に進学した。大学からの帰りに時々電車で見かけることがあったが、とても声をかける勇気はなかった。
竜也は、高校時代から写真が得意で、大学に入っても写真部に所属していた。初めての学芸祭が近づいたとき、竜也は、自分の作品を異性にも見てもらいたいという漠然とした願望を感じていた。だが、特に誰に見せたいと決めたわけではなかった。
ある日のこと、梢の姿を電車の中で見かけ、何故か不意に、浴衣の彼女に自分の作品を見てもらいたいという強い衝動を覚えた。竜也の方から声をかけ、今度の日曜日に学芸祭に来て欲しいと頼んだ。できれば浴衣姿で来て欲しいと、勇気を出してこちらの意向を伝えた。梢の返事は「行けたら、行くわ。」という曖昧なものだったが、竜也には十分だった。
学芸祭当日、紺色のワンピース姿で、大学に通じる坂道を上がってくる梢を見つけたときの胸の高鳴りを竜也は決して忘れていない。
その日から2人の交際が始まった。竜也の4年間の大学生活は瞬く間に過ぎたが、専門のロシア語学習に加えて、ゼミで少しかじり始めた経営学についても更なる学習の必要性を感じていた。
当時の世の中の状況は、1957年からの鍋底景気が終わると、64年からは証券不況と呼ばれる短期不況が始まる。竜也の卒業した63年はちょうど不況の狭間での景気沈滞期で、新卒者に潤沢な職場が準備されているわけではなかった。
更に、竜也には、就職よりも進学を選ぶ上での隠れた理由があった。それは、1964年の東京オリンピック。
当時、ソ連はアメリカと並んでオリンピックには最大の選手団を派遣するが、その一方で、日本人のロシア語学習者は限られていた。選手村でのロシア語通訳の確保がオリンピック準備委員会の課題の一つとされていた。竜也には、これまで学習した自分のロシア語を実地で試すには絶好のチャンスと映った。
東京に出たい。自分が生まれ育った神戸の街に誇りと愛着を感じてはいたが、この時ほど日本の中心で勝負したいというチャレンジ精神をかき立てられたことはなかった。
大学4年の夏休みには、竜也は所属していた水泳部の合宿をさぼって、1人、京都の山奥にある親戚のお寺にこもって受験勉強に精を出した。この2ヶ月間を竜也は自分で修行と呼んでいたが、1人子の竜也にとっては、長期に親元を離れる初めての機会でもあった。
友人との会話もなく、テレビや新聞とは無縁の修行期間は、竜也にとって全く新しい体験となった。竜也はこの時初めて、自分を外から眺めること、つまり外なる自分と内なる自分が対峙することを経験した。
2ヶ月間の修行が効いたのか、竜也は難関といわれたH大学・大学院修士課程の試験に合格し、晴れて東京に出ることになった。
東京での新生活は、竜也にとって充実そのものであった。念願のオリンピックの通訳試験にも合格し、竜也は60日間八王子にある選手村に勤務した。竜也が相手をする選手団は、ソ連はもとより、モンゴル、ブルガリア、ポーランドといったロシア語圏の選手たちで、総勢50人を超えていた。
八王子選手村では竜也が唯一のロシア語の通訳だったので、連日、選手の相談にのったり、取材のための記者会見に応じたりで多忙を極めた。が、竜也にとって、自分が必要とされていることを実感するのは大きな喜びであった。
1964年10月10日、東京オリンピックの開会式を迎えた。当日の早朝まで雨模様だった空がまるで手品のように晴れ上がり、代々木の大会場では選手団の入場式が行われた。
八王子選手村からは3人の通訳が招待されたが、竜也はその1人だった。通訳の制服である黒のブレザーの胸にロシア語を示す「P(エル)」の文字と、その日はH大学のマーキュリーのバッジをつけて、会場に臨んだ。選手入場に先立ち、轟音とともに5機の航空自衛隊のジェット戦闘機が飛来して、紺碧の空に大きく5色の輪を描いた。耳をつんざくような戦闘機の飛来音を聞きながら、竜也の満足感は頂点に達していた。
![]()
「介護日記ーその後」にもどる
![]()
「白い闇」第3章に進む
![]()
トップページへ戻る