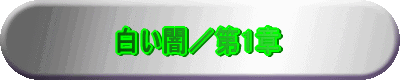
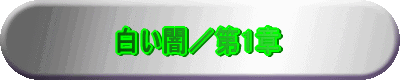
1993年1月14日夜、3人を乗せたリンカーン・タウンカーは猛吹雪の23号ハイウエーを、一路、南に向かっていた。
フォード社の重要なお客との夕食をデトロイトで済ませ、3人はアンナーバーにあるオフィスに戻るところであった。漆黒の闇からフロントガラスめがけて飛んでくる無数の白い粉を蹴散らしながら、車はアンナーバーへと急いでいた。
運転しているのは木谷。鳥目だから夜は見えないという割には、先ほどからスピードメーターは80マイルを指している。タウンカーの走行スピードはデジタル表示されるので、後ろの席からでも竜也にはよくみえた。
助手席の河田は、ディナーのワインが効いたのか、だらしない恰好でなかば眠っていた。それでも、時々、眼を閉じたまま口を開いて、皮肉とも冗談ともつかぬ口調で今夜のパーティに出てきたフォード社の面々の人物批評をした。
窓の外では、水銀灯に照らされた、乾いた粉雪がまるでワルツを踊ってるかのように、風に煽られて下から上へと舞い上がっていくのがみえた。広いハイウエーには他の車は殆ど見当たらず、白い闇は不思議な静寂に閉ざされていた。3人を乗せた車だけが、静寂に呑み込まれまいと抵抗しているようだった。
中野竜也は、1ヶ月前に妻の梢と4女の悦子を伴いミシガンに赴任してきたばかりだった。東京の本社では、竜也は機械部門の営業部長の要職にあり、主として自動車メーカー向けの機械を販売していた。
山口工業は新聞の株式欄では化学メーカーだが、他にもセメントや機械を手がけており、以前は多角経営の典型として成長会社の中にランクされていた。山口工業の機械部門は万年赤字で、社内ではお荷物扱いされていたが、同社の製作する自動車向けの機械は業界では相当に名前が売れており、フォードやGMでは、山口工業は日本の優れた機械メーカーだと思っていたほどだ。
特に、デトロイトのビッグ・スリーから高い評価を得ていたのは、射出成形機と呼ばれる、特殊プラスチックを一度に成形して、バンパーやインパネ(計器盤)をつくる機械で、大型機の分野では、山口工業の製品は世界でもトップシェアを占めていた。射出成形機を手がけるメーカーは日本でも10社以上あったが、山口工業の技術が優れているのは機械製作の面よりも、むしろ樹脂技術に関するものであった。この点が、化学メーカーの強みで、自身が製造するプラスチック原料の特性をレベルアップするために、CAEと呼ばれる最先端の技術を米国のコーネル大学と共同で開発していた。
CAEとはコンピューターの助けを借りて、誰にも見えるはずのない金型内部での成形中の樹脂の流れをモニター画面上で手に取るように見せるもので、この技術のお陰で自動車メーカーは部品試作の手間を大幅に短縮することができた。
竜也が東京本社の他部門から機械の営業部長に移ってきたときには、河田や木谷はベテラン・セールスマンとして、射出成形機を内外に売込んでいた。だが、更なる拡販を目指して、最大の顧客であるビッグ・スリーのお膝元であるデトロイトに、2年前、販売会社を作り、河田と木谷をそこに派遣したのである。
竜也は軌道に乗り始めた販売会社の社長としてアメリカに派遣されたわけだが、竜也の最大の目標はこの会社を早期に黒字化することにあった。販売会社といっても、アフターサービスのための米人技術者を多数抱え、セールスマンなどを含めると総勢50人近く、マシンや部品の在庫費用も加えると、年間の固定費は20億円を超えており、これを黒字にするのは簡単ではないと思われた。
しかし、入社以来30年近く営業畑を歩いてきた竜也には、売上増によって利益を出すことに漠然とした自信があった。そのためには、河田や木谷にセールスマネジャーとして存分に活躍してもらわなければならない、と考えていた。
機械のビジネスでは技術的な知識が不可欠で、大学の工学部を卒業した技術屋がセールスを担当することがよくあるが、河田も木谷も、それに竜也自身もれっきとした事務屋だった。しかし、3人とも機械については技術面の勉強も積み、経験も重ねていたので、ビッグスリーのエンジニアと技術ディスカッションする程度の技術的なバックグラウンドを備えていた。
サラリーマンを事務屋と技術屋に分けるのは明らかに間違いだと竜也は考えていた。確かに、学校を出た時点では、そのような分類は可能だろう。だが、入社後10年もすれば、実地教育が学校での学習を凌駕し、事務屋・技術屋の分類は意味をもたなくなる。
欧米では、確かに、技術系の学校を出たものはエンジニアとしての道を進み、銀行マンや証券マンとは軌道を異にするが、それは彼等の思考の不器用さからくるものだ、と竜也は考える。日本人のように柔軟な思考能力を備えていれば、事務屋が画期的な技術発明をすることも、あるいは技術屋が一流の銀行マンになることも、決して、不思議ではない。
現実に、松下幸之助や本田宗一郎のように技術面で大きな仕事をした偉大なる先輩は、特に学校で技術教育を受けたわけではない。逆にいえば、自分は事務系の教育しか受けなかったから技術は分らなくてもよいと決めこんでしまった技術音痴こそが、狭義の事務屋であり、通常、メーカーでは、サラリーマンの出世競争から脱落してしまうのだと思う。
また、技術屋・事務屋の分類以上に竜也が抵抗を感じるのは高卒・学卒の区別である。たかだか4年間のハンディを何十年という会社生活の中で追いつけないはずがない。高卒の事務屋が会社での長年の実地経験に基づいて、技術開発部長の役職についたとしても何の不思議もない、と竜也は思う。むしろ、その新任開発部長の努力に対して快哉を叫びたいくらいだ。
3人を乗せたタウンカーは、雪道を滑りながらも漸くアンナーバーのオフィスにたどりついた。
突然、ヘッドライトに照らされた真っ白な世界に一人の日本人女性が浮かび上がった。木谷の奥さんだった。この夜更けに雪の中を、何故、会社まで出てきたのか。急いで開けた窓から彼女の叫び声が飛び込んできた。
「奥さんが倒れました。」
瞬間、竜也は河田の妻の愛嬌ある丸顔を頭に浮かべ、河田の方をみた。河田は例によって特に表情を変えることもなく、木谷夫人の次の言葉を待っているようだった。
「中野さんの奥さんが脳出血で倒れて、セントジョセフ病院にヘリで運ばれました・・」
木谷夫人の言葉を聞きながら、竜也は、まるで頭の中が雪に侵されるように、真っ白になっていくのを感じた。
粉雪を伴った寒風が、ヒーターの効いた車内に吹き込んでいるのに漸く気がついて、木谷夫人にお礼を言おうとした。が、喉が渇ききっていて言葉にならなかった。
着任早々の竜也には、病院の名前すらおぼつかない。河田が案内するというので、彼のビュックで病院に向かった。
セントジョセフ病院はアンナーバーの東隣のイプシランテにあり、この地方ではミシガン大学病院と並ぶ権威ある病院とされている。河田が運転しながら説明したが、竜也の意識は全く別の方に向かっていた。
これまで、企業戦士として家庭のことを妻に任せきりにしていた自分に問題はなかったのか。妻の健康管理をもう少し真剣に考えるべきではなかったのか。木谷夫人の話では、梢は全く意識がないという。助かるだろうか。アメリカの医師は信頼できるのだろうか。
河田は、竜也が彼の話を全く聴いていないのを察知して話すのを止めた。静まり返った車内には、ワイパーがフロントガラスを忙しく往復する音だけが残った。車は、一向に弱まる気配のない粉雪を突いて、どこまでも走り続けた。竜也は、このまま白い闇の中に吸い込まれてしまえばいい、と密かに願っていた。
待合室には、悦子と悦子の家庭教師でミシガン大学大学院生の安達美香が青い顔で立っていた。2人は慌てて駆けつけたらしく、やけに薄着だった。安達美香の白いうなじが何故か周囲の状況とは不釣合いに映った。
安達美香の説明によると、その夜、8時半ごろ悦子の部屋で勉強していたところ、突如、階下でパニックのクラクションが鳴ったという。オートメ化の進んだアメリカでは、大抵の車のキーにはドア開閉、トランク開閉ボタンと並んで、パニックと表示されたボタンがついている。これを押すと車のクラクションが断続的に鳴り出し何か異常が生じたことを知らせる。アメリカ人は防犯用にこのボタンを使用しているらしく、自分の車が物取りに遭っている現場などでは、近づくと危険なのでパニックボタンで暴漢を追い払うのに便利だと、後に聞いたことがある。
しかし、トランク開閉ボタンと隣接しているため、間違って押すことがよくある。その夜もパニックのクラクションが鳴っても、慌てもののお母さんがまた間違えた、と悦子が説明したために、暫く放っておいたという。だが、いくら経っても鳴り止まないため下におりてみて、ガレージの前で梢が雪の中に倒れているのを見つけたらしい。
慌てて救急車を呼び、近くのサリーン病院に運んだが、そこでは始末におえないとのことで、急遽、ヘリでセントジョセフに移動することになった。安達美香は、日頃のおっとりした口調からは想像できないほどの早口で一挙に話した。
だが、アメリカといえども、夜更けにヘリが直ぐに手配できるわけではなく、安達美香と悦子の車が先に着き、ヘリの到着を待っているところであった。
事態の全貌が漸く理解できたので、河田には帰ってもらい、悦子と安達美香と竜也の3人がヘリの到着をまった。
11時ごろになって漸くヘリが到着した。梢は担架の上で毛布に包まれ、エマージェンシーと書かれた入り口から病室に消えた。3人は、中には入れてもらえず待合室に残されたままで、何の説明もなかった。
事故の状況をひと通り聞き終えた竜也には、安達美香への次の質問も見つからず、梢の病状をあれこれと推測しながら待合室のベンチに黙って座りこんだ。閑散とした部屋は、暖房が入っているのに殊のほか寒く感じられた。
ミシガンの冬は非常に厳しく、時として、屋外では零下40℃まで下がる。アメリカでは華氏を使用しているが、日本人には馴染みが薄く、華氏と摂氏の両方を示す寒暖計を窓の外につけている。これが、華氏・摂氏ともに同じ値を指すことが、長い冬には何度かある。その時がほぼ零下40℃になる。
その夜も-40℃近辺まで下がっていた。梢は、厳寒の中、自宅のガレージへの近接道の氷を割っていたらしい。安達美香を送って帰るのに車がスリップするのを心配したようだ。
生来、梢は高血圧で、体調の悪いときには上が200を超えることがあり、日本では病院通いをしていた。だが、アメリカに来て間もなく、引越しの片付けや雑事に追われて病院を探すのは二の次になっていた。転居の疲労と新しい環境での緊張に、厳寒と力仕事が加わり脳溢血を起こしたものだろうと、容易に推察できた。
2時間も経過しただろうか。突然、待合室のドアが大きく開かれ、白衣を着けた医師とみられる大柄な男と2人の看護婦が部屋に入ってきた。男は真っ直ぐに竜也に近づいた。
慌てて立ち上がった竜也に無言で手を差し伸べ、握手をすると同時に短く自分の名前を言った。竜也には聞き取れなかったが、後で聞くと、この男はストラックナー医師で、当病院では腕利きの脳外科医とのことだった。
ストラックナー医師は全員を待合室の片隅に集めると、検査を終えたばかりのMRI断層写真や脳波の記録紙を脇の小机の上に広げて、病状の説明を始めた。
冒頭に、はっきりした口調で、状況はベリー・シアリアス・コンディションであると前置きした。
竜也はアメリカの前に8年間欧州にも駐在経験があり、英語力にはかなりの自信があったが、専門外の医学用語は殆ど理解できず、隣の安達美香のヒアリング能力に期待した。が、こちらの方も竜也と大差はなかった。
2人の理解しえた範囲を寄せ集め整理すると、ストラックナー医師の難解な説明の7割程度が理解できた。それによると、梢は左脳に約5㎝の脳出血を起こしており、非常に危険な状態にある。手術をして血塊を除去する必要がある。しかし手術の成功率は50%。手術をしなければ、80%以上の可能性で死ぬだろう。手術が仮に成功しても後遺症は残る。手術するかどうかを決めるのは貴方だ、というのが説明の骨子だった。
竜也の頭には、ストラックナー医師の言った2つの言葉がこびりついていた。
「シー・メイ・ダーイ。」(ダメかもしれない)、
「ディシジョン・イズ・ヨアーズ。」(決めるのはあなただ。)
手術をするかとの問いに「イエス・プリーズ。」と答えるのがやっとだった。選択の余地はなかった。
竜也の答えを確認すると、今までひと言も発言しなかった傍らの看護婦が、手際よく何通かの書類を取り出し、そこにサインを求めた。訴訟社会のアメリカでは後のトラブルを避けるために、こうした手術の前には用心を重ねた確認をとっておく必要があるのだろう。竜也は指示された個所に何度もサインしながら、果たしてアメリカ人はこんな時にはちゃんと文章を読むのだろうかとぼんやり考えていた。
一般に脳卒中といわれるものには、脳出血と脳軟化症の2種類がある。脳出血は、更に高血圧性脳出血とクモ膜下出血に分類される。一方、脳軟化症も脳血栓と脳栓塞とに分けられる。梢のケースは典型的な高血圧性脳出血で、先ず出血した血塊を除去する必要がある。それには、開頭術とよばれる大掛かりな外科手術により、頭蓋骨を切断して内部の血塊を慎重に摘出するのだが、この時に、いかにして内部の健全な脳細胞を傷つけずに血塊を取り出すかが開頭術成功のポイントとなる。
脳は身体全体を支配し、コントロールする中枢なので少しの傷を与えても致命的な後遺症が残ることになる。梢の出血は左脳部分なので、後遺症としては右半身の麻痺と言語障害が心配された。
ストラックナー医師の執刀による開頭術は真夜中の12時半から朝の6時まで、6時間近くかけて行われた。
竜也は安達美香を帰宅させ、悦子と2人で病院に残ることにした。一旦帰宅してはどうかといわれたが、どうせ家に帰っても眠れないだろうから、病院の待合室で夜を過ごすことにした。梢が手術室に入る直前に、病院側の計らいで数十秒間ではあるが、家族との面接が許された。
ひょっとすると最後になるかもしれない梢の顔を正面から眺めて2人で名前を呼んだ。移動ベッドの上に横たえられた梢の顔は、数時間前に車の窓から眺めた雪の世界を思い出させるほど白く見えた。眼は硬く閉じられていたが、口元は少しゆるんでみえた。
竜也は、内心、美しいと思った。竜也はこれまで自分の妻の顔を人並み以上だとは思っていたが、美しいというイメージはなかった。梢のチャームポイントは眼にあり、特ににっこり微笑んだ眼には独特の魅力があった。しかし、その眼は固く閉ざされていたにも拘らず、美しいと感じると同時に「失いたくない」という気持ちが胸中に突き上げてきて、思わず「梢、待っている。」と、看護婦が驚くほどの大声で叫んでしまった。
![]()
「介護日記ーその後」にもどる
![]()
「白い闇」第2章に進む
![]()
トップページへ戻る