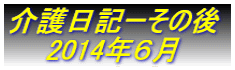
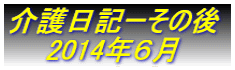
ソチ・オリンピックが終わった。日本勢は若い選手の活躍で8個のメダルを獲得した。大会を終えて成田に帰国したメダリストたちは、歓迎のフラッシュライトを浴びて高らかに胸のメダルを掲げて見せた。その陰に隠れるように、そっと唇を噛んだ選手がいる。高梨沙羅、あどけなさの残る17歳。
事前の下馬評では金メダル候補の一番手だった。ロシアの新聞でさえも女子ジャンプの優勝候補に彼女を挙げていた。そりゃそうだろう。オリンピックに先立つ10回の世界選手権で、高梨は8度の優勝、2度の準優勝を収め、圧倒的な強さを発揮していた。その高梨がソチの大舞台では4位の結果に終わった。風の向きが彼女に味方しなかった、雪の質が合わなかった、等々、さまざまなエクスキューズが飛び交った。だが、高梨の真の敗因は、17歳の少女の肩に圧し掛かったプレッシャー以外には考えられない。

直後の産経新聞に、同じような重圧に押しつぶされた長崎宏子さんのことが紹介された。
1984年、当時16歳の長崎宏子は水泳ニッポン復活の期待を一身に背負って、ロスアンゼルス五輪・女子200m平泳ぎに出場、4位に終わった。
「私は生きていていいですか、競技を続けてもいいですか、再びがっかりさせるかもしれませんよー。」 そのときの思いを長崎はこう語っている。また、高梨についても
「世界の頂点を目指すアスリートに大人も子供もないと言いたいですが、このシチュエーションだけは違います。大人なら、うまくスルーできる。逆境に打ち勝つ強さを身につけていますから。でも、17歳は繊細な年齢です。」
30年前の自分の心境と重ね合わせて次のように結んだ。
「4位を乗り越えるには五輪メダリストになる以外に道はありません。将来ある彼女に言葉をかけるとしたら『大丈夫だから』かな。そして強く、しっかり抱き締めてあげたい。」
仮に、高梨が事前にこの記事を読んでいたとしたら、帰国した彼女は、報道陣のマイクを避けて、真っ先に長崎の胸に飛び込んで思いのたけ泣きたかったであろう。高梨の気持ちが分かるのは日本中で長崎宏子以外にはなかったはずだ。
その17歳の少女は、ソチ五輪の余韻も醒めやらぬ3月の初め、ルーマニアに飛んで世界選手権の第14戦、15戦に連続優勝して、日本のファンに気丈さをみせつけた。
それでも、彼女の胸のつかえはとれないだろう。残るは、4年後、韓国・平昌(ピョンチャン)で開催される冬季五輪での優勝しかない。 平昌の大空を鳥のように飛んで、日本嫌いの韓国人観衆の眼前に日の丸を高々と掲げてほしい。想像するだけで4年後が待ち遠しい。