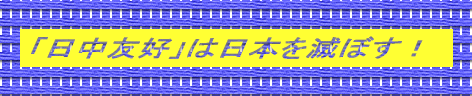
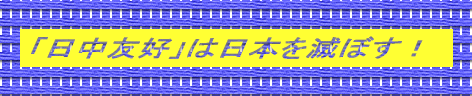
�@�����h���I�ȃ^�C�g���̖{�����A���҂͒����l�̃C���e���A�Ε����B���̖{��2005�N�ɏ����ꂽ���̂ŁA�Ε����͂��̌���{�ɋA�������B�@�Ε����̓��{���́u�Z�L�E�w�C�v�A�������́u�V�[�E�s���v�B1962�N�����l��Ȃ̐��܂�A1984�N�k����w�N�w�ȑ��ƁA1988�N�ɗ������A�_�ˑ�w��w�@�E���w�Ȃ̔��m�ے����C���B���Ԃ̌������Ζ����o�āA���M�����ɓ������B2007�N���ɂ͓��{�ɋA�����Ă���B
�@���҂͖L�x�ȗ��j������g���āA���j�I�Ȏ��_��������W���l�@���Ă����B�v�����[�O�ŁA�u�����ɋ߂Â��ƕK���w�������x���{�j�̖@���v���Љ�邪�A���̎��_�͋����[���B���{�j��ʂ��āA�����Ȏ����i���j�ƍ������i���j�������I�Ɍ���邪�A����ɂ͉��炩�̖@����������̂ł͂Ȃ����A�ƒ��҂͖���N����B
�@�����Ԃ̌𗬂Ɋւ���ŏ��̗��j���́A�����E�O������̗��j���u�����v�́u�n���u�v�ɏo�Ă��邭����ł���B
�u�C�̌������ɘ`�l�i�킶��j���Z��ł���A�S�]���ɂ킩��Ă��āA����I�ɍv���������Ă���v�Ƃ���悤�ɁA�I���O�P���I�A���{�͖퐶����ł������B�����̓��{�ɂ͊e�n�ɏ����ȑ��̏W�܂�Ƃ��Ắu�N�j�v�����݂��A�݂��ɍR�����đS���I�ȓ��ꐭ���͎�������Ă��Ȃ������B

�@�P���I��́u�㊿���v�́u���Γ`�i�Ƃ����ł�j�v�ł́A���̂悤�ȋL�q������B
�u�`���i�킱���j�̃N�j�̂P�ł���z���i�ʂ����j�����v���Ă��āA���̌�����i�����ԂĂ��j�������i����j���������v
�@���̂��Ƃ́A�]�ˎ���ɔ����p�ŌÂ�����������A����ɂ́u���`�z�����v�ƍ��܂�Ă������Ƃ���j���Ƃ��ďؖ����ꂽ�B
�@�܂�A���̎���ɂ����Ă����{�ɂ͓��ꐭ���͂Ȃ��A���ꂼ��̏����������ɑ��čv��������u�W�i�����ق������j�v���������𒆐S�Ƃ��Ď��ӂɓ��{���܂މ��ʂ̍��X���W�܂�W�ɂ������B
�@�R���I�ɏ����ꂽ�u鰎u�`�l�`�i�����킶��ł�j�v�ɏ��߂ē��{�̓��ꍑ�Ƃ̒����Ƃ��āu�הn�䍑�i��܂��������j�v���o�ꂷ��B����ɂ��ƁA�הn�䍑�̏����E�ږ�āi�Ђ݂��j�́A�g����h������鰂̉����ɒ��v���A鰉�����u�e鰘`���v�̏̍����������Ƃ����B�����A�הn�䍑�����{�ꂵ���킯�ł͂Ȃ��A鰂̈Ќ�����Č��͂��ێ����悤�Ƃ����B
�@�T���I�ɓ���ƁA�����̗��j���ɂ́u�`�̂T���v���o�ꂷ��B�]�A���A�ρA���A���Ƒ����T�l�̉������A���̎���͑�a�����̈����O�ŁA���ꐭ�����ł��钼�O�ł������B�����A�����Ƃ̊W�͖����̐��̒��ɂ������B
�@���̌�A�b�������W�͓r�₦��̂����A6���I�̌㔼�A���Ái�������j�V�c�̎���ɁA�ې��̐������q������A�����W�͐V���ȓW�J��������B�����ł��@�����̎����600�N�A�������q�͑�P��̌��@�g�𑗂�B�X�ɁA�Q��ڂ̌��@�g�ɍۂ��đ�a���삪�@�����̍c�鈶�ɓ͂������̂��L���ȍ����ŁA���̂悤�ȏ����o���Ŏn�܂�B
�u���o�i���j����Ƃ���̓V�q�A������v����Ƃ���̓V�q�ɒv���A���i���j�Ȃ���v

�@���̎���̒��������̐��E�ςƂ́A�܂��A���E�̏�ɂ́u�V�v�Ƃ������̂�����A�V�邪�F���̐X�����ۂ��x�z���Ă���B����A�u�V���v���Ȃ킿�V�̉��̐��E�ł́A�V��̎q�ł���u�V�q�v���V�����ėB��̓����҂ƂȂ�B���ؒ���̍c�邱�����V�������V�q�ł���A���̐��E�̒��_�ɗ��B��̎x�z�҂ł���A�Ƃ������̂ł������B
�@�������q�̍������@�����̍c����u���v���鍑�̓V�q�v�Ə̂��A��a����̐��Ï�����u���o���鍑�̓V�q�v�ƌĂԁB�܂�A�����炪�V�q�Ȃ炱������V�q���A�ƒ��ؐ��E�̓ƑP�I�C�f�I���M�[�ɒ�����@���������ƂɂȂ�B
�u�V���v��Ɛ肷�鑶�݂ł��钆�؍c��ȊO�ɁA�����P�l�́u�V�q�v����翂ȓ������痧���オ��A�Γ��W���咣���Ă���B���ؒ鍑�ɂƂ��ẮA�̐����m�����Ĉȗ��̓��A�W�A�̒��������{����Ђ�����Ԃ��A�܂��ɋ��V���n�̏o�����ł������B
�@�������q�͓Ɨ��錾�Ƃ������ׂ�����������Ȃ�ؗE���瑗������̂ł͂Ȃ��B�����ɁA���N�����ɑ���R���s�����J�n�����B�u���{���I�v�ɂ��ƁA�����Ę`���̎x�z���ɂ��������N�����암�̔C�߁i�݂܂ȁj��D�҂��邽�߁A�P���]�̑�R��V���i���炬�j�ɑ���A�V�������~���������B�@�����ɑ��ĊԐړI�ɑ�a����̎��͂����������̂ł���B
�@�������q�̍�킪����t�����̂��A�@�̍c�邩�瓚��g�Ƃ��ĊO���������{�ɔh������A��a����Ƃ̍����ĊJ�ɉ�����|�̕ԓ����Ȃ��ꂽ�B���̂��Ƃɂ��A���{�͒����c��ƑΓ��̊W�����V�c�_�Ƃ���A���X����Ɨ����ƂƂ��ăA�W�A�̒��ɒa�����邱�ƂɂȂ����B
�@
�@���{�ɂ����鍑�Â���́A�̐��𒆎��Ƃ��钆�ؑ̐�����̓Ɨ��Ƃ����`�Ői�߂�ꂽ���A����ł͓��{���������ؐ��E����l�X�ȕ������w�сA�����̂��̂������ꂽ�B�U�`�W���I�̔���ɒ�������w�S�̑�\�I�Ȃ��̂́A�A�����A�����A���ߐ��ł��낤�B
�@�͓����̒��������̒��S�I�C�f�I���M�[�ł��������A���ꂪ���{�Ɏ������ꂽ�̂́A�T���I�ɕS�ρi������j���痈�n�������m�i��Ɂj���u�_��v�������炵���̂����̎n�܂�Ƃ����B�v�z�͑�a����̈א��ҁA�m���l�̊ԂōL��������A�������q�́u���@�\�����v�ɂ��p���o�T����̈��p�������݂���B
�@����ɑ��ĕ����͏����x��āA�U���I�̔��A�S�ς̐������i�����߂������j����a����ɕ��T�ƕ��������̂��ŏ��Ƃ�����B�������A���{�ɂ͊��Ɏ��`�����Ă������ߍ������������B�U���I���ɂ́A�r���h�̕����i���ׁ̂̂j���Ɛ����h�̑h��i�����j���̊ԂōR�����N����A���������ł���āA�����̎���ɂ��Ă̑����Ɍ����������B
�@�]�䎁�̈���i�����j�Ƃ��Ď�����R���ɉ�������������q�����Ò��̐ې��ƂȂ�ƁA�����U�������͂ɐ����i�߂�ꂽ�B��g�i�Ȃɂ�j�Ɏl�V�������A�X�ɑ�a����̒��S�n�E�ɂ͖@�������������ĕ������y�̋��_�Ƃ����B�u���@�\�����v�̑�Q���ɂ́u�Ă��i�����j�O����h���v�Ƃ��邪�A���̎O��Ƃ͕��E�@�E�m�̂��Ƃł���B

�u�Čh�O��i�Ƃ���������ڂ��j�v�̖��̉��ɁA�����͔���̒��S�I�v�z�ɂȂ邪�A�ޗǎ���ɂȂ�ƑS�ʊJ�Ԃ̂Ƃ����}����B�ޗǂ̓s�ɂ͐��E�ő�̕������@�ł��铌�厛�Ƒ啧������������A�S���ɍ����������Ă�ꂽ�B
�@�����ŁA���҂͐ݖ�𓊂�������B���ؕ�����ϋɓI�Ɏ�����č��Â�����n�߂����{���A�����×��̃C�f�I���M�[�ł���ł͂Ȃ��A�C���h���̐��E�@�����镧�����d�������͉̂��̂��B���҂͂��̓������a����̊O��헪�ɋ��߂�B
�@��a���삪���Â���ƕ���ł����P�̑傫�ȉۑ�Ƃ��Ă����̂́A�����嗤�̋���鍑�Ƃ̊O���W�ł���Ƃ���B�����A���{�͂ǂ�����Β����Ƃ̊ԂőΓ��ȊO���W��ۂ������邱�Ƃ��ł���̂��B���҂͉s���l�@��W�J����B
�@�������q�̑Β����p�����ł������ɕ\�킵�Ă���̂��u���o����̍��c�v����n�܂鍑�������A���͂��̍������g�����@������K�˂Ă����g�߂́A�`���̈��A�Ƃ��ĂP�̌�����q�ׂĂ������Ƃ��L�^����Ă���B
�u�@���v�́u���Γ`�i�Ƃ����ł�j�`�����v�̋L�q�ɂ��ƁA�g�߂̌���Ƃ��āu�C���̕�F�V�q�d�˂ĕ��@�������ƕ����B�̂Ɏg�������킵�Ē��q�����߂��B���˂č���\�l������ĕ��@���w�ԁv�Ƃ���B
�@���̑O����̃L�[���[�h�͂Q�B�P�́u�C���́v�ł���A�����P�́u���@�������ƕ����v�ł���B�u�C���v�͂���ɓ��{���猩�Ē������C�̐����ɂ���Ƃ������P�[�V�����������w�����̂ł͂Ȃ��B���������̐��E�ςɊ�Â��A�~�̒��S�ɒ��؉���������A���̑��̏����i�؈̍��X�j�͓��S�~��ɍL����~�̒��ɂ���B�����ɂ͐��������Ȃ��B����̂́u���S�v�Ɓu���Ӂv�̊W�����ł���͂����B
�@�܂�A���{�̎g�߂��������u�C���́v�Ƃ������t�́A���ؒ���𒆐S�Ƃ��鐢�E�ς̔ے�ł���A���ӂ��猩�������ւ̔��������߂��Ă���B
�@�����P�̃L�[���[�h�u���@�������ƕ����v�́A���ɑ����u�̂ɁA�g�������킵�Ē��q�����߂��v�ƌĉ����āA���̎g�߂��@������K�˂��ړI���q�ׂĂ���B�{���Ȃ�؈̏������璆�؉����Ɏg�߂𑗂�ړI�͂����P�B���؉����Ȃ�тɒ��ؓV�q�́u���v�����āA���ؕ����́u�����v�����߂Ă���̂��B
�@�Ƃ��낪�A���o���鍑���痈���g�߂͖K��̖ړI���u���@�v�ɋ��߂�B�܂�A�@�����̓V�q���܂��u���@�v�𐒌h���A����������̂ɔM�S���ƕ����Ă��邩�炱���K�˂Ă����̂��Ƃ��Ă���B
�@�M�ҁi�����j�̒����ł́A���@�̑O�ɂ͒��؉�������a����������ł���A����̓L���X�g���������u�l�͐_�̑O�ł͂��ׂĕ����v�Ƃ����l�����Ɏ������̂�����B
�@�����͒��ؕ������琶�ݏo���ꂽ���`�ł͂Ȃ��B���x�ȕ������E�������������ꂴ������Ȃ������O���@���Ȃ̂��B�������A���̕����͒������璩�N�������o�R���ē��{�ɓ`����Ă����B���ؕ����́u�v�����A�͂邩�ɕ��ՓI�ȉ��l�������E�@���ł���B�����Ƃ������E�@���̒��ɐg���������ƂŁA���{�ׂ͗̒��ؒ鍑�ƑΓ��ȗ���ɗ����Ƃ��ł�B���ꂱ�����A��a����̈Ӑ}�ł͂Ȃ������̂��A�ƒ��҂͎咣����B
�@���������̓L���X�g�����S�̕����Ƃ��ĉh���A�����������𒆐S�ɑg�ݗ��Ă�ꂽ�̂Ɠ��l�A���{�̕����͕����𒆐S�ɑg�ݗ��Ă��Ă����B�����āA���̌������Ƃ��Ă̏ے����ޗǂ̕��鋞�̒����ɒz���ꂽ���厛�Ɛ��E�ő�̑啧���ł��낤�B

�@���{�͔���ɒ����ƔZ���ȊW�����̂����A�����̐���͈��肵�Ȃ��B622�N�A����̐��������Ă����������q�����������B�������q�̎��ɂ��卋���h�䎁��}����҂����Ȃ��Ȃ����B�h�䎁�̐ꉡ�͎���Ɍ������Ȃ�A���̌����͓V�c�Ƃ𗽂��قǂɂȂ����B�������A645�N�A�h������͒���Z�c�q�i�Ȃ��̂������̂������F��̓V�q�V�c�j��ɈÎE�����B�u�����i�������j�̕ρv�ł���B������_�@�Ƃ��āu�剻�̉��V�v���N����A���{�͌����̎�����}����B
�@�V�q�i�Ăj�V�c�̌䐢�͒��������Ȃ��B���N�����ŋN�������u�����]�i�͂��������j�̐킢�v�ɑ�s�B�����āA�Ñ�ő�̓����Ƃ�����u�p�\�i����j�̗��v���N����B
�@�����̎��オ�I���A�ߓn���̓ޗǎ�����o�āA���{�͑Q������̎�����}����B�����ʂ�u��������v�ł���B���̎���́A�u������i������̂܂����ǁj�̗��v�ȂNjǒn�I�Ȕ����͂��������̂́A���S�̂Ƃ��Ă͉��₩�ȁh�����̍Ό��h���������B�����āA�������ケ���������Ƃ͍ł����������������ł������B�����́A����܂ł̊��s�Ɋ�Â��f���I�Ɍ����g������ꂽ���A����ŏI���A894�N�ɐ����ɔp�~���ꂽ�B�Ȍ�A�����Ƃ�200�N�߂��ɂ킽��v���ƂȂ�B�܂��ɁA�u���y�v���牓�������āu�����v����A�ƂȂ����B
�@��������̒����u���v�̎���́u�ی��E�����̗��v�ɂ���ďI�~�����ł����B�����̕���Ɋ����������i������̂������j�́A���������̂��Ƃ�`�Ŏj�㏉�̕��Ɛ�����������B
�@�����͓��{�����̍`�����C���Ē����E��v�Ƃ̖f�Ղ�ɂ����B�����g�̒�~�ȗ����f���Ă��������Ƃ̌𗬂��Ăюn�܂����B�����ĕ��Ɛ����͈��Ŗłт�Z�������ƂȂ����B
�@���Ƃ̂��Ƃ��p�������q���{�́A�����嗤�Ƃ̊W�͔��������ł������B�嗤�Ƃ̗B��̐ړ_�́A�������犙�q�̒n�ɑT�m�������đT�@���L�߂����x�B���̏��ׂ��A���q���{�͕S���\�N�ɂ킽�萭�����ێ����邱�Ƃ��ł����B�����A���́u���v�͐���������Ă����B�����i�����j�̏P���ł���B���{�̕��m�K���͒c�����đR���A��������ނ����B�������A�푈�̌��ʁA���{�͎�̉����A���q���{�̕���Ɏ���B
�@���̌�̓��{�j���u���v�Ɓu���v���z����̂����A�ߖڂɂ͉��̂������嗤�Ƃ̊֗^���݂���B���q�����ɑ������������{�ł͕����̎���͒Z�������B�������������R�E�ɂ��Ĉȍ~���u��k���̑����v�͑����A�R�㏫�R�`���̂ɂ��Q����k�����ꂪ��������B
�@�`���͒����Ƃ̊ԂɁu�����f�Ձv���J���B����́A�����̖������ɍv���������o���u���v�f�Ձv�̌`���Ƃ�B�`���͋��ׂ��̂��߂ɐi��Ŗ����̍̐��ɓ��荞�̂ł���B�����āu���m�̗��v���N����퍑����ɓ���B
�@�퍑������삯�������D�c�A�L�b�A����̂R�l�̕��������A���̒��ŖL�b�G�g�́A�����Ƃ̊W�ő�Ώ������B�����𐪕�����Ƃ����]�ɔR���Ē��N�ɏo���A��s���i�����B

�@�L�b�����ɑ����ēV������������쐭���́A�G�g�̎��s�Ɋw�̂��A�O�ꂵ���u��������v���Ƃ�B���A�ŁA����300�N�͓��{�̗��j�̒��ōł������u���a�ƈ���̎���v�ł������B�o�ςƕ������Ƃ��ɔɉh���A�]�˂̓A�W�A�ŗB��̕S���s�s�Ƃ��ĉh�����̂ł���B
�@�߁E����ɓ����Ă��A���̕s�v�c�ȏz�͑����B�����ېV�ȍ~�A���{���ڎw�����ߑ㉻�̎��ɂ́A����@�g�ɑ�\�����u�E���_�v�̎v�z������ɂ������B�A�W�A�Ȃ���̂�ے肵�A�u�����J�ԁ��������v�������Ƃ����B����@�g�͎��̂悤�ɏq�ׂĂ���B
�u�c����A���̎x�M�l�Ɍ��Ă͑��̊J�Ԃ�]�ނׂ��炸�A�V��F�Ƃ�������_�㗘���鏊�Ȃ��c�v
�@�������{�̊O���͓O�ꂵ���u�E�������v�ł������B�ĉp�����Ƌٖ��ȊO���W�����сA���̒����Ƃ͋�����u�����B���̊O��H���̂��A�ŁA���{�͒����Ƃ̃g���u���Ɋ������܂�邱�Ƃ��Ȃ��A�ߑ㉻�ɏW�����邱�Ƃ��ł����B�����āA���̂��Ƃ͗���ׂ����V�A�Ƃ̐킢�ɔ������u�x�������v�ւƂȂ����Ă����B
�@�������{�����̃N���C�}�b�N�X�͖���38�N�i1905�N�j�̓��I�푈�̏I���ł������B�����ŋ��̌R�����ւ郍�V�A�ɓ��{�������������ƂŁA���������A�ߑ㍑�Ƃ̌��݂Ƃ����������Ƃ��ۂ����Ă������j�I�g�����B�����ꂽ�B
�@���a������T�ς��Ă݂�ƁA���a�U�N����20�N�܂ł�14�N�ԁA���{�͖��B���ς��Ђ��N�����Ē����嗤�ɖ{�i�I�ɐi�o���A�����Ƃ̑S�ʐ푈�ɓ˓�����B���{�������ɂ���قǐ[���肵���̂͏��߂Ă̂��Ƃł������B�����āA����14�N�Ԃ̍ł����ɖ������u�����̎���v���o�����A�����m�푈�̔s��Ƃ����ň��̌��ʂɂȂ������B
�@���a20�N����47�N�i1972�N�j�́u���������v�܂ł�27�N�ԁA���{�͍Ăђ����嗤�Ɗu�����ꂽ�W�ɂ������B�����āA���̊��ԁA���{�͋��ٓI�ȍ��x�o�ϐ����𐬂������A���̔ɉh�Ɣ��W��z���グ��u�����̎���v�ƂȂ����B
�@1972�N�ɂȂ�A�c���p�h�̖K���ɂ������̍��𐳏퉻�̋@�^�����܂�A1978�N�W���ɂ́u�������a�F�D���v�����ꂽ�B10���ɂ́A���̍ō��w���ҁE���������������A�������i�߂�u���v�E�J������v�ւ̋��͂��Ăт������B���N�ɂ́A���{�̑啽���K�����A�~�؊����܂߂��Β��o�ϋ��͂̎��{�\�B���{�͒����Ƃ̊W��[�߂Ă����B
�@1982�N����̒��]�������ł͒����Ƃ̊W���[�݂ɂ܂œ��荞�B�h������������h�̎n�܂�ł���B1983�N11���A�ӗs�M�i���悤�ق��j�����L�������A���]���Ƃ̊ԂŁu���a�F�D�A�����b�A��������A���ݐM���v�̂S���������ӁB���̌ӑ����L�̖K��ɍۂ��ẮA���]���͊��@���̃v���C�x�[�g�E�]�[���ɏ����A����̉Ƒ��ƈꏏ�ɐH���������B��������A���]�����k����K�₵���ہA�ӑ����L�͎���ɒ��]��������������Ƒ��ƂƂ��ɐH���������B��̏��҂̕ԗ�ł���B
�@�����̃g�b�v���Ƒ�����݂̕t������������̂́A���������Ԃ̗��j��ŏ��ɂ��āi���炭�j�Ō�ł���B
�@�ӗs�M�Ƃ́h�����h�����o�������ŁA���]���́u��㐭���̑����Z�v���f���A1985�N�W��15���A���{���Ƃ��ď��߂Ė����_�Ђ����Q�q�������B�������A���̂��Ƃ��������{�̈ꕔ�Ŕ������ĂсA���N�X��18���́u9.18���ρv�i���B���ρj�L�O���ɁA�k����w�̊w����ɂ��R�c�f�����N����B���̐����^�����A��̓V���厖���ɂȂ����Ă������ƂƂȂ�B���������ł͔����̋@�^�����܂�������n�߁A�e���̌ӗs�M�̐�����Ղ���邬�����B
�@���]���͗��N�ɂ͖����Q�q��f�O���邪�A���ތ�ɏo�ł����w�V�n�L��E50�N�̐�㐭�������x�̒��ŁA���̗��R���ȉ��̂悤�ɏq�ׂĂ���B
�u���������Q�q�����߂��̂́A�ӗs�M�����̖����Q�q�Œe�N�����Ƃ����댯��������������ł��v
�@���x�Ȑ������f���A����Ƃ����m�̏���炩�A���]���́u��㐭���̑����Z�v�̃X�^�[�g�Ƃ��Ďn�߂������_�ЎQ�q���P��Ŏ��߂Ă��܂��B�����A���ʓI�Ɍӗs�M���~�����Ƃ͂ł��Ȃ������B
�@1987�N�A���剻�����߂�f�����S���ɔg�y�������ŁA�ӗs�M���ӔC��Njy����A�e�N����Ă��܂��B���̌��ʁA���{�ł́u��㐭���̑����Z�v�͍��܂��A�����ł́A�ӗs�M�̎��r�������ƂȂ��� 1989�N�ɓV���厖�����u���A�����̖��剻�v���Z�X�����f����Ă��܂��B
�@���̕�����n�����ꎁ�́u���{�̗��j�[���сv����q���g�āi�M�҂��j�⑫����ƁA�V���厖���͖����`�̒e���ł���ƁA�����w�����͊e������̔��ō��ۓI�ɌǗ������A�����ł͖��剻���͂̍U���̖�ʂɗ������ꂽ�B���̃s���`���~�����̂��A���{�ł������B
�@���̊�@��E���邽�߂ɁA�����̎w�����͓��{�̓V�c�������A�������O���̓˔j���ɂ��悤�ƍl�����B�����āA���{���{�͓V�c�É��ɖK�����Ē������Ƃ����߂Ă��܂����̂ł���B����͒������{�ɂƂ��ē�d�̈Ӗ��ő傫�ȃv���X�ƂȂ����B�ΊO�I�ɂ́A���{�̓V�c���K���������ƂŊO������̑Β����ᔻ����܂����B�����ł͓��{����̒��v���ĊJ���ꂽ���Ƃ������ɂ݂����邱�ƂŁA���Y�}�w�����ɂɑ���U���̖�������킵���̂ł���B
�@���{�̌������̌����\�h�K�₵���̂͗��j�㏉�߂Ă̏o�����ł��������A���̓V�c�K���Ƃ��������I�s�ׂ����߂��̂́A�����̋{�V���ł���B���[�����͉����h�ꎁ�������B
�@������@�ɁA���������ł͔����v�z�ɔ��Ԃ�������B���ɁA�]��Ȃ͗��j�����������A��������ɂ����Ă��c�Ȃ������j����҂ɋ����A���{�����z�G�������ɂ܂ʼn��������Ă��܂��B
�@���łȂ���A�M�҂����̐������������Ȃ�A����������������̐��ʂ́A2005�N�̓��{��g�ُP�������Ȃǔ������Љ^���ɓW�J���Ă����B�����������������A2009�N�ɂ͓��{�ɐ�����オ�N����A���R�������a���������ƂŎ���͍X�ɕ��G�������B
�@�V�����́A�u���A�W�A�����́v�u�����F�D�̊C�v�Ȃǂ̃X���[�K�����f���Ē����ɂ�����p�����������B���ɉA�̍ō����͎҂ƌ���ꂽ��������600�l���̐��s���A�Ӌџ���Ȃ�K�₷��B�܂��A�����̎����w���҂Ɩڂ����K�ߕ�����{�ɏ����A���[���ᔽ�̓V�c�Ƃ̉�܂ŃA�����W���Ă��܂��B�܂��ɁA���{�̒��v�p�����̂��̂̓������������̂ł���B
�@����ŁA���R�����͕��V�Ԋ�n�ڐݖ��Ŗ����ɖ������d�ˁA�X�����Ŏ��E�B�������������͔��R�����̊O���P����B���̖��A��t���Œ������D�ƊC��ۈ����̒����Փˎ������u���B�������͎��������ւɎ��߂悤�Ƃ��邪�A���X�ɂق���т��o�āA���E�����Ȃ��Ȃ茻�݂ɓ����Ă���B


�@�P�j��₷�ׂ��A�P�����M���̒����i�o�u�[��
�@1990�N��̊J���E���v����Ƌ}���Ȍo�ϔ��W���āA�����嗤�ւ̐i�o�͓��{�o�ϊE�̈��u�[���ƂȂ����B�����Ė��s���ȘJ���͂����߂āA14���l�̑�s��Ƃ����������߂āA���Ƃ����ł͂Ȃ��������Ƃ܂ł������Ē����i�o�����B�����A�ނ�̖��͖{���Ɋ����̂��낤���B�����s��ɎЉ^��q�������Ƃ́A���̒n�Ŋ��H�����o����̂��낤���B
�@���{��Ǝ��g�̓w�͂����邱�ƂȂ���A�����̂��ׂĂ͒����Ƃ�����������ǂ��Ȃ邩�ɂ������Ă���B��蒷���I�Ȏ��_���猩��A���{��Ƃ̒����i�o�̏��s�����߂�ő�̗v���́A��������̂��̂ł���B
�@�����͌��݂̂悤�ȍ��x�����𑱂��邱�Ƃ��ł���̂��낤���A�o�ς̎�����Љ�I�ȕs���̕��o�ɂ���Ĉ���������邱�Ƃ͂Ȃ����낤���A��p�C��������łْ̋������܂�A�푈��Ԃɓ˓�����\���͂Ȃ����낤���c
�@�������������̃��X�N�̂P�ł������̂��̂ƂȂ����Ƃ��A�����ɖ��Ɩ������������Ƃ͂ǂ��Ȃ�̂��낤�B��a����ȗ��A���������Ԃ̗��j�����Ă��A�����Ɛ[���ւ���������͖w�ǎ��s�����ł͂Ȃ����B��㐔�\�N�Ԃœ��{�͒����s��Ƃ̊W�Ȃ��ɐ��E��Q�̌o�ϑ卑��グ���ł͂Ȃ����B
�@�Q�j�\�z���ׂ��A���������������N�[���ȓ����W
�@1972�N�̓��������ȗ��A�����ł́u�����F�D�v�������炩�ɋ��ꂽ�B�ł́A���{�ƒ�����30�N�Ԃɂ킽��u�����F�D�v�̌䗘�v�͂ǂ����������B
�@�����ɂƂ��āA����30�N�]��̊��Ԃ́u�����̎���v�Ƃ������ׂ��P���鎞��ł������B�o�ς͖��\�L�̔��W�𐋂��A���͔͂���I�Ɍ��サ���B���ɁA1980�N�ȍ~�̒����͓��{���瑽���̂��̂Ă����B�o�ς̌��Ē����Ɍ��ߎ�ƂȂ�Z�p�Ǝ���������̂͗��̓��{�ł������B���ꂾ���ł͂Ȃ��B
�@1989�N�̓V���厖���ȍ~�A��������i������o�ϐ����č��ۓI�ɌǗ������Ƃ��A�^����ɏ����̎�������L�ׂ��͓̂��{�ł���B���{�Ƃ̊W�ɂ���āA�����͍��ێЉ�֕��A���鎅�������̂ł���B�����F�D�́A�����ɂƂ��Ă͗ǂ����ƂÂ��߂ł������B
�@�|���āA���{�͉������낤���B�ɒ[�ɂ����A�����������̂͂Ȃ������B�m���ɁA�����Ƃ̌o�ό𗬂��g�債�����Ƃ͓��{�ɂƂ��ă����b�g�������낤�B�������A����̓r�W�l�X���E�̘b�ŁA�u�F�D�v�Ƃ͊W���Ȃ��B�F�D�����ꂽ30�N�ԂŁA���{�͒����ɍD�����悤�ɂȂ������B�[�hNO�h�@�u�����F�D�v�ɐs�͂��A�N���푈�̉ߋ��������Ă������ʁA���{�͗��j���Ƃ����ߋ��̎�������J�����ꂽ���B������hNO�h�ł���B
�@�l���Ă݂�A�푈�I���� 60�N���o�����B���{�̗��j�ɒu�������Ă݂�ƍ]�˂̏I��肩�� 60�N�Ƃ����A���łɏ��a�ɓ����Ă���B�܂�A�����Ɠ��{���A���݁A���j���Ō��܂���Ƃ����̂́A���a����̓��{�l���]�ˎ���ɋN���������ɑ��āu�ӔC�����v�Ɣ����Ă���悤�Ȃ��̂��B�����A���ꂪ�����Ԃ̌����Ȃ̂��B
�@1980�N��ȍ~�A���{�͒����Ƃ͑ΏƓI�Ɉ����̎�����}����B�ŏ���10�N�ԁA���{�̓o�u���ɗx�炳��A�o�u�����͂�����Ɓu����ꂽ10�N�v�ƂȂ�B���{�̃o�u���������F�D�ƒ��ڊW������킯�ł͂Ȃ����A�����嗤�ɐڋ߂���Ɠ��{�������h�����ƍ����̎���h���}����Ƃ����A�s�v�c�ȗ��j���ۂ������ł��J��Ԃ��ꂽ�B
�@���{�͕��a���@�̌��O����A�����̈��S����Ĉ��ۏ��ɗ����Ă���B�����A�����̑䓪�ɂ��Ē��W�����������Ȃ�ƁA���{�͂ǂ�����̂��B�A�����J���̂ĂĒ����ɂ��̂��B����Ɏ^��������{�l�͐悸���Ȃ����낤�B���ǁA���{�͓��ē������ێ����Ă��������Ȃ��B�ł́A�A�����J�Ƃ̓������ێ������܂܁A���{�������ƘA�g���Ă������Ƃ͂ł���̂��B�����́hNO�h�ł���B
�@���������A�Ē��̑o���ƒ��ǂ����Ȃ���A�����Ƃ̘A�g�𗘗p���ăA�����J�ɂ��̂������A�A�����J�Ƃ̓����𗘗p���Ē�������������Ƃ����̂́A�^�ʖڂ�����蕿�̓��{�l�ɂ͂ł��Ȃ��|�����낤�B���������A�A�����J�Ƃ̐M���W�������A�����Ƃ̘A�g����肭�s���Ȃ��Ƃ����ň��̏ɂȂ�\�������Ȃ��Ȃ��B
�@�����W��\�킷���t�Ɂu����o�M�v�Ƃ����̂�����B�܂�A�����W���₦����ł��A�o�ό𗬂͔M���A����ł���A�Ƃ����Ӗ����B���{�ɂƂ��đΒ��W�́u����v�͕K�������悭�Ȃ����u���M�v�͍X�Ɉ������낤�B�Β��W�̐����ʂŖ]�܂��̂́A�u��v�ɗ����ꂸ��̃V�K���~�ɂ���������Ȃ��悤�ȁA���������ɑ������N�[���ȊW�ł͂Ȃ����B�܂�u�����v�ł���B�o�ϊW�ł́A���݂̂悤�ȉ��M�͏�����܂��������悢�̂ŁA�u�o���v���炢���K�����낤
�@����̓����W�Ɍ����Ē������L�[���[�h�́u�����o���v�ł���B
�@�R�j�x�����ׂ��u���A�W�A�����́v�̗��Ƃ���
�@�ߔN�u���A�W�A�����́v�\�z���r���𗁂тĂ���B�u���A�W�A�v�Ƃ́u����A�W�A�v�iASEAN�����j�Ɓu���k�A�W�A�v�i�����A���{�A�؍��j���܂ތď̂ł���B�����A���̂Q�̃A�W�A�͗��j�╶���A�`���̖ʂňقȂ��Ă��邾���łȂ��A���{�Ƃ̊W���قڐ����ɂ���ƌ����Ă��悢�B
�u���j���v�Ɋւ��āA��O�͓��{����N����������A�W�A�����ł́A���{�ɑ��āu���j���v�������Ԃ����Ƃ͖w�ǂȂ��B����́A�������Ƃ��邽�тɁu���j�J�[�h�v�������o���ē��{��@�����Ƃ��钆���A�؍��Ƃ͖��炩�ȑΔ���Ȃ��Ă���B�܂��A���{���ő�̊O���ۑ�Ƃ��Ă��鍑�A��C����������ɑ��Ă��AASEAN�͓��{�x����\�����Ă��邪�A�����Ɗ؍��͏��ɓI���A���̎p����ۂ��Ă���B����ɁA���{�� ASEAN�ɂ͖w�nj��Ď����͂Ȃ����A�����Ɠ��̊Ԃɂ́u�̓y���v�Ƃ����ł����Ȗ�������Ă���B
�@���ǁA�u���A�W�A�����́v�Ƃ����傫�ȁu�w���v�̒��ɂ́A���{�ɂƂ��Ắu���ǂ��O���[�v�v�Ɓu���ܔ���O���[�v�v�Ƃ����Q�̃O���[�v�����݂��Ă���B���������u���v�����āA�����̂���낤�Ƃ����̂͏��F�����Șb�Ȃ̂��B
�@�{���̍Ō�ɒ��҂͌��_�Ƃ��Ď��̂悤�Ɍ����B

�u���{�͍���A���A�W�A�����Ɨl�X�ȃ��x���Ō𗬂��Ȃ�����A�����܂Ő�����i���̈���Ƃ��āA���ē����W�𒆎��Ƃ��鐢�E�I����Ɋ�Â����O�𐭍�𐋍s���A�n���K�͂̎s��ƊW��z���グ�Ă����B�܂��Ɂw���E�̐�i�����{�x�Ƃ��Đ����Ă����ׂ��ł͂Ȃ����ƁA���҂͍l����B
�@���ꂱ�����A���{�Ɠ��{�l�ɕ��������Ō�̒Ȃ̂ł���B�v