

8月も終わりに近づいたある日、近くのスーパーで買物をしていると、胸元の携帯からメールの着信を知らせる振動が届いた。
「高3の受験生。推薦入学の小論文を指導できますか?」
私は数年前から近くの学習塾で英語を教えているのだが、メールはその塾の塾長からだ。
小論文の指導? 具体的イメージを掴めないまま返信した。
「多分大丈夫だと思いますが、一度体験授業をお願いします」
体験授業とは授業料負担なしに生徒が受ける講習で、その結果によって続けるかどうか生徒が判断するもの。
体験授業に先立って、大型書店に出向いた。受験参考書の棚から「小論文」と書かれた参考書を数冊取り出して立ち読みしてみた。
大体の傾向は、与えられた設問に対して、1,000字~2,000字で自分の考え方をまとめるもの。但し、例示されている設問のバラエティに些かたじろぎを覚えた。政治、経済に始まり、法律、科学、医学、文化、教育…。最近の社会問題に関する設問がズラリと紹介されている。
安請け合いだったか。かすかな後悔の念が頭をよぎったがもう遅い。度胸を決めて臨むことにした。
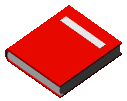
その日、やってきたI君は見上げるばかりの偉丈夫。恐らく
190㎝近い。
「よろしくお願いします!」元気な声を出すと一礼した。
「いい身体をしているね。何か運動でも?」
「ハイ。陸上競技です。短距離の選手です」
100mを
11秒台前半で走るという。運動で推薦して貰えばいいのにと思うが、自分は文武両道がモットーだと胸を張る。
将来は弁護士になりたいというI君の体験授業に入った。「武」については十分な実績を見せたが、「文」の方は今一つ。志望先もN大の法学部とあまり高くない。
推薦入学だから、N大なら面接だけで比較的簡単に入れるのではないかと思ったが、実情はそうでもないらしい。面接以外に英語と小論文の試験があり合格率は半分以下だという。
体験授業で、I君が出してきたN大の過去問は「尊厳死と終末医療の関係」を問うもの。私の得意分野でもある。妻の介護の実例を交えて、自説を展開した。
翌日、塾長からメールが入った。
「すごい迫力で、是非続けたいと希望しています」とある。
早速、I君への週2回の指導が始まった。私が設問を宿題として与え、次回の授業で、彼の作成した小論文を修正し、私の答案を例示するというやり方で授業を進めた。毎週2度、設問と答案を準備するのは私にとって負担となったが、I君には更にきつかったと思う。が、彼は毎回、苦心の跡が窺える答案を提示した。
![]()
1ヶ月ほど続けた頃、I君から意外な相談があった。
「実は、N大を受ける前に、予行演習のつもりで法政大学のキャリア・デザイン学部をダメモトで受けたいのですが…」
初めて聴く話だ。彼によると、東京の私大は、早慶に代表される一流校の次にランクされるのは「MARCH」と呼ばれる五校だという。それぞれのイニシャルから名付けられた呼び名で、明治、青山、立教、中央、法政の5校を指すと。中でも、法政のキャリア・デザイン学部は他校にない特徴をもった人気学部だという。競争率は五倍以上で、どうせダメだろうと諦めていたが、1ヶ月の特訓で少し自信がつき、高校からも推薦を貰ったとのこと。
一次試験が
10月27日。3週間しかない。しかも、その日までに志望理由書を
2,000字以内にまとめて提出しなければならない。その作成を指導してほしいというのだ。
綱渡りのチャレンジは、私も嫌いではない。急遽、目標を法政大学宛の志望理由書作成に切り替えた。時間を節約するため、先ず私が叩き台を作って、それを参考にI君の言葉で書いてもらうことにした。まずまずの合作が出来上がった。
ところが、それを担任の先生に見て貰ったところ、散々なコメントが返って来た。
「勘違いするな。中身がないのに表面的な文体で格好をつけるのは大学教員が最も嫌うパターンである。云々…」
最後には「これは小論文というよりまるでエッセイだ」とあったのには思わず苦笑してしまった。
担任の先生はI君と毎日接しているから「文が人を表さない」ことにストレスを感じたようだ。仰ることが分からないではない。先生のアドバイスを考慮に入れて、全面的に書き換えることにした。
苦節3週間。漸く3人の共同制作による志望理由書が完成。I君は意気揚々と一次試験に臨んだ。
次の日、塾で試験の報告を聞いた。小論文は何とかサマになったようだが、自信があったはずの英語にミスが目立った。これならもっと英語を指導すればよかったと思ったが、後の祭り。I君は手応えを感じていたようだが、私は半ば諦めの気分だった。
心機一転、N大法学部受験の準備を再開し始めた矢先に、法政の一次試験合格の報せが学校に届いた。
ヨッシャ! 後は11月10日の面接試験だけ。合格は即日発表となる。
![]()
当日の午後、I君から携帯にメールが届いた。
「私の名前がありました! 思わず眼がかすみました。親も大喜びです。先生には何とお礼を申し上げていいか…」
翌日、塾に現れたI君は大きな身体を二つに折って深々とお辞儀をした後、誇らしげに合格通知書を私に見せた。私も嬉しかった。固く握手をして彼の合格を祝った。
私の指導にどれほどの効果があったのかは定かではない。それよりもI君の陸上競技での実績が評価されたのではないだろうか。彼の最後の授業で私がそのことを伝えると、彼はとんでもないことを口にした。
「先生、7年間は元気にしていてください。2020の東京オリンピックでは、必ず
100m競争の代表選手になって先生を入場式に御招待します」
前回は通訳として、次回は応援席で、私は生涯に2度も、東京オリンピックの入場式を観ることができるかもしれない。
〔2013年12月 原稿用紙6.5枚〕